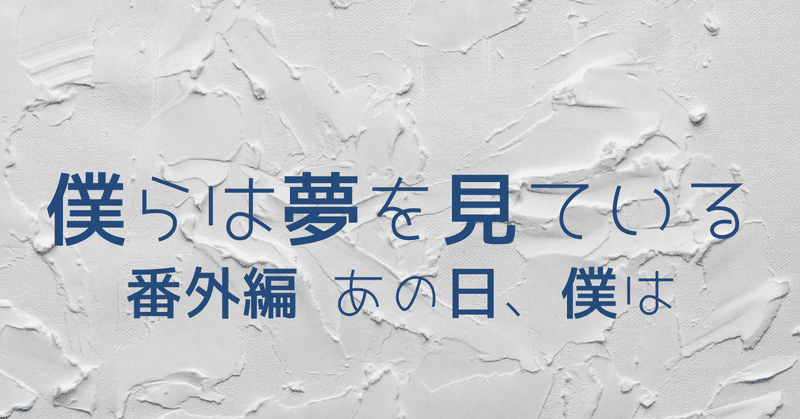
番外編 あの日、僕は (僕らは夢を見ている より)
17:39 中庭
なんてことない。一定間隔で流れる雲の筋。そのまま原色で塗りたくりましたと胸を張る青空。おまけと言わんばかりに、鳥のような影も規則的に頭上を舞う。そう、なんてことない。代り映えの無い、量産型の毎日だ。
意味も、描く気力も無いのに、いつもの定位置、とは違う場所に陣取った。少し建物からこっちの姿が見られるかもしれないが、特に問題は無いはずだ。現時点での僕の行動には。
夢がある。青空を見て、それを模写して、色を塗って、ほどほどな額縁に飾る。二十四時間。十二か月。時間も記録して、色も鮮やかに再現して、大きく描いてやる。楽しいだろう、きっと。この小さな狭いシェルターでのモノクロの毎日よりは。
そんな夢を見ながら、僕はその夢を人工的な青空に描く。
「呑気にお絵描きか、優等生」
どうやっても空の色を生み出せない。そんな時、声がした。やけに仰々しくて大きな、そんな声。ああ、彼は確か僕の幼馴染の中で断トツ一番の問題児じゃないか。ニイジマだ、先日、ちょっとやり合った。それで分かったのは、彼は問題行動を起こしてはいるものの、考えていることは中々に面白いものがある。
そう、この煮え滾った砂糖の檻から逃げ出したいと考える僕と、通じるものを感じるぐらいには。
「おいおい何だよ、返事ぐらいしろよな」
「君は、空の色を知っているか」
誰かに、それはもうずっと昔から聞きたかった質問。教師とか、教科書とか、図鑑とか、シスターや牧師に。彼らには聞けなかったが、彼には聞きたくなって、思わず言った。
顔に出やすい性分なのは、悪い事では無いと思う。正気を疑っています、と顔面にでかでかと主張しているのが視界の隅に映った。音で察するに、彼は少し遠くに座ったようだ。
「青だ、そりゃ。流石の俺でも見りゃわかるっての」
「いいや、あの青じゃない。というかそもそも、時間によって空は色が変化する」
「あ?夜は黒、夕方はオレンジだろ」
「違う。そうだが、違う」
「おいおい勘弁してくれ、どういうことだよ」
ぐっと回り出しそうになる舌を必死に押さえつけて、空から視線を外す。ようやっと、先日ぶりに彼の顔を見た。ああ、本当にこの少年は分かりやすい。何が分からないのかが分からないって顔だね。正直すぎるのもどうかと思うがね。
「所詮あの空もデータだ。投影だか何だか知らないが、本物じゃない。本に載っている写真も、間接的な情報で、本物かどうか確かめる術は無い」
「同じだろ。写真もあの空も、本物の空も」
「違うに決まってる」
「じゃあその証拠はあんのか?」
「同じ証拠も無い」
同じことを証明することも、違うということを証明することもできない。似たような事例というか、例え話は、悪魔の証明だな。悪魔が実際に存在するということも、逆に存在しないということも、証明する手立ては無い。そう、この地下施設の中で生活している限り、絶対的に通常の空は青色だと証明することも、青色ではないと証明することも不可能なのだ。僕らが持っている知識や資料が本物だと断定するものだって存在しない。
真っ白な画用紙を指でなぞる。ざらざらな画用紙の音と、人工芝が揺れる感触。
「まあ、俺にとって空の色はそんな大事じゃねぇから」
「そうだろうね。君が絵を趣味で描くとは思えない」
「へぇへぇ、その通りですよって」
「じゃあ、地上に行きたいと思った事は?」
声は震えていなかっただろうか。ちゃんと、言葉は届いただろうか。
「……正気か、お前」
「空を見たい。二十四時間、どんな色をするのか、この目で確かめてみたいと、僕は思ってる」
「おいおい、おい。流石の優等生でもその発言は罰則部屋に直行だぜ」
「わかっている。でも君は、少なくともいい子枠ではないだろう。地上に興味は?」
教科書は教えてくれない。何故、突然、僕ら人類が地下シェルターに閉じこもることになったのか。
僕らはわかっていない。同年代の子どもたちが、この世に今、どれほどの人数、生きているのか。
僕は知らない。地上がどんなものなのか、今現在、どんな姿、色、匂い、感触をしているのか。
僕は、確かめたい。地上の世界を、色を。この目で、足で、手で。彼と共に。
「興味がないと言ったら、嘘になるぜ」
彼の喉が大きく動いた。いつもよりずっと早口な言葉に、僕は笑みを抑えられない。彼に倣って僕も立ち上がり、画材を地面に置いて、立ち上がる。
「嘘吐きは好きじゃなくてね」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
