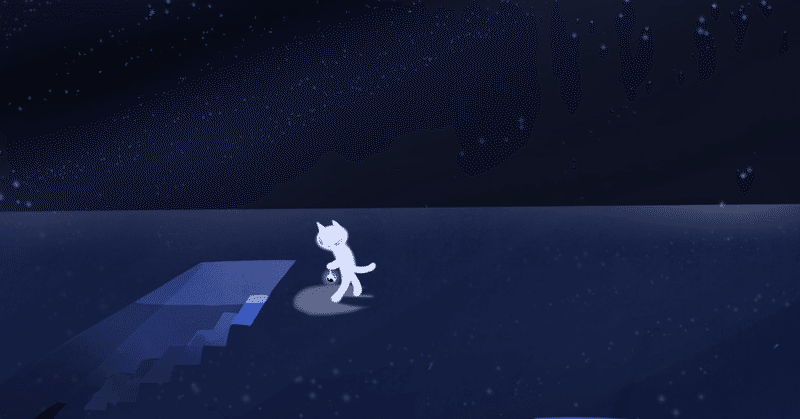
『万物の黎明』を読む。 #323
デヴィッド・グレーバーとデヴィッド・ウェングロウによる『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』を読んだ。本書は紙で708ページ、Kindle版で1097ページという大ボリュームであるため、大まかな論旨を追いつつも、個人的に気になった部分を中心に取り上げながら紹介していく。
『万物の黎明』で印象的だった部分
不平等は自然状態or文明病?
「どうすれば不平等を是正できるのか?」という問いを考えると、「なぜ不平等が発生したのか(平等だった時代や社会はあったのか)?」という問いも浮かぶ。その先駆者と言えばルソーとホッブズだ。
ルソー的な考え方をすれば、「昔は平和だったのに文明のせいで人類は不幸になっている(不平等になってきている)」となる。一方、ホッブズ的に考えれば、「昔は争いの絶えなかった人類は文明のおかげで平和な社会を構築してきた(不平等が解消されてきた)」となる。(ちなみに、二人が言う「自然状態」とはあくまでも思考実験における架空の状態であり、実在した原始の社会を指しているわけではないことに気をつけるべきらしい)
しかし、この両者の考え方は、あまりにも人類史を直線的で単純なものにしてしまう。よって、この本は両者のどちらが正しいのかという議論ではなく、どちらも誤りであるということを多様な考古学・人類学的な証拠から論じていく。
本書で乗り越えたいのは、この[ルソーかホッブズかの]二者択一なのだ。
ちなみに、本書では、ジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』やユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』、スティーブン・ピンカーの『暴力の人類史』などの著作を「ポップ人類史」として批判的に取り上げている。なぜなら、これらはルソーやホッブズ的な説明の再生産でしかなく、現在の世界へ至る経緯を単純化しすぎているからだ。
「対照実験」としてのアメリカ大陸
本書の特徴は、人類史がルソーやホッブズ(+「ポップ人類史」)的な説明ほど単純ではないことを論じるために、アメリカ人(いわゆる先住民・ネイティブアメリカンなどと呼ばれる人たち)に注目することから始める点である。
本書は、この問い(「社会的不平等の起源とはなにか?」)の歴史的ルーツを、十七世紀にヨーロッパの植民地とアメリカ先住民の知識人とのあいだで起きた一連の遭遇にたどり直すことから出発する。
たとえば、ウェンダット(族)と呼ばれる人々の中にいたカンディアロンクという政治家を取り上げ、彼が北アメリカ大陸に入植したフランス人を「論破」していく様を描く。ヨーロッパではこうした「新大陸」から持ち込まれた考え方を克服するための論理を構築しようと奮闘し、その結果が近代思想であるという。
本書でアメリカ人を取り上げた理由は、第12章「結論」で明かされる。つまりは、17世紀以前のアメリカの歴史はヨーロッパ視点からの人類史に対抗する「もう一つのあり得たかもしれない歴史」であり、ヨーロッパを最先端と見なす進歩史観を否定できる証拠なのだ。
イベリア半島人の侵略以前には、アメリカ大陸とユーラシア大陸とのあいだには、直接の交通も定期的な交通も存在しなかった。つまり、それらはけっして同一の「世界システム」に属してはいなかったのである。これは重要である。なぜならば、真に独立した比較対象のひとつ(北アメリカと南アメリカを別物とするならば、二つになるかもしれない)を、わたしたちは有していることになるからである。だとすれば、歴史は本当にある方向に進行する必然性をもっているのか、と、問うことも可能になる。
一方、『銃・病原菌・鉄』ではユーラシア大陸がアメリカ大陸を「侵略」できた理由を、ユーラシア大陸が東西に長く同じ気候が広く存在することを究極の要因としている。つまり、農業技術の共有が容易であり、その結果人口が増加しやすく、イノベーションが起きる確率も高かったのがユーラシア大陸だったというのだ。
(地理の気候区分を学んだことがあれば)この説明も説得力はあるのだが、ヨーロッパの方が文明が早く「進んだ」という前提で話が進んでいることに注意が必要である。あたかもヨーロッパがアメリカ大陸を侵略したことに必然性があったかのようにも読み取れ、ヨーロッパの植民地支配を正当化することにつながりかねない。だから、こうした「ポップ人類史」に批判的なようだ。
自由とは何か?
「どうすれば不平等を是正できるか?」ではなく、「いつから不平等な社会になったのか?」でもなく、「いつから不平等が議論の的となったのか?」を問うていくと、前述のようにアメリカ人(先住民)とフランス人(入植者)の17世紀に起きた議論に遡る。お互いの文化や社会制度の違いを共有し合うことで、どちらが自由なのかという論争が起こり、次第にどちらが平等なのかという問いも生じたようだ。こうした議論の後に、ルソーが1754年に『人間不平等起源論』を書いた。
そのため、平等とは何かを考える前に自由とは何かを考えていく必要がありそうだ。また、「平等な社会」という理想的な状態を定義することも難しい。そこで、実際の社会がどうだったのかを見ていくと、季節ごとに社会体制やヒエラルキーが変化するような「自由な社会」の事例に出会う。
また、「農業革命」が文明を不可逆的に進めたという従来の歴史観や「小麦がホモサピエンスを奴隷にした」という『サピエンス全史』に対し、農業革命と言いながら3000年の移行期間があったことを指摘する。その間は、「遊戯農業」という狩猟採集と並行した農業が行われていたり、一度文明が「進んだ」としても意図的にその文明を放棄したりする例なども取り上げている。つまり、狩猟採集から農耕への移行は不可逆的でも必然でもなく、可逆的で恣意的だったというのだ。
このように、複数の社会体制をポートフォリオ的に有していたり、可逆的かつ恣意的に移行させていた事例が過去にあったにもかかわらず、近現代では社会体制が固定化されているという点に着目する。そして、「なぜわたしたちは閉塞してしまったのか?(How did we get stuck?)」を問うていく。なお、本書では、この閉塞の対義語とも言える自由を以下の三点で定義している。
1. じぶんの環境から離れたり、移動したりする自由
2. 他人の命令を無視したり、従わなかったりする自由
3. まったくあたらしい社会的現実を形成したり、異なる社会的現実のあいだを往来したりする自由
つまり、今いる環境(ヒエラルキー)が自分に合わない場合にはその環境から離れたりその命令を無視したり(ストライキ)できる、さらにはヒエラルキーを解体(革命権を行使)することもできることが基本的自由である。逆に、これらが損なわれている状態を閉塞と捉える。
ケアと暴力は表裏一体
自由が失われることがケアと暴力の両方につながるという話も書かれているが、これには私的所有という概念が補助線として必要になる。カンディアロンクなどのアメリカ人がヨーロッパ文化に自由がないと論じた根拠も、この私的所有にある。
つまり、私的所有の概念がある場合、所有者は所有物を自由にできる権利がある。逆に言えば、所有されている存在(物だけでなく人も含む)は所有者に自由を奪われている状態となる。この「自由でない=ある人が別の人を所有している」と言い換えられるならば、以下の所有の説明にゾッとすることだろう。
ローマ法では、占有possessionにかかわる三つの基本的な権利がある。usus(使用する権利)、fructus(所有物の産物を享受する権利)、abusus(損害を与えたり破壊したりする権利)である。最初の二つの権利しかもっていないばあい、これはusufruct[用益権、使用権]と呼ばれ、法に保護された真の占有とはみなされない。つまり、真に法に即した所有を規定する特徴は、人がそれをケアしない、あるいは意のままに破壊するという選択肢を有しているということなのだ。
こうした状況を訳者が「DVを彷彿とさせる(999ページ)」と表するように、ケアと暴力は私的所有というコインに記された裏表なのかもしれない。絆という一見するとポジティブな言葉も、実は呪縛・束縛というネガティブな意味に由来することなども思い出させる。このケアと暴力の「混濁」に気づくことで、自由な社会・人間関係をデザインできるようになるのかもしれない。
ケアと支配のこの結合――というよりもおそらく混濁――は、たがいに関係し合う方法を自由に再創造することによってみずからを再創造するという能力を、人類がどうして喪失したのかというより大きな問題にとってもきわめて重要であるとおもわれる。
著者の一人であるデヴィッド・ウェングロウが『ガーディアン紙』に寄せたエッセイが巻末で紹介されているが、たしかにこのエッセイの締めの文章には前述の自由にまつわる主張とあるべきケアの姿が端的に書かれている。基本的自由の三条件が確保されてこそ真のケアと相互扶助と言えるのだ。
古代の奴隷所有者が教えてくれたような、毒々しい自由(他人の捕縛や苦痛からもたらされる合法的自由、勝者と敗者、生存者と犠牲者をつくる自由)ではない。ケアと相互扶助に裏打ちされた自由である。これは、わたしたちがみずからはまった最悪の罠を回避した(しかし、その運命がわたしたち自身の運命としっかりむすびついている)グローバル・サウスに住む人びとにとっては、古くからなじみのものだ。目的地で歓待されることを前提として、いまの環境から逃れ去る自由。恣意的な命令に逆らったとしても、追放されることはない自由。このような自由をもとに、わたしたちの社会、そして地球との関係をあたらしいかたちで再構築していくことができるのだ。
未来は変えられる?
さて、『万物の黎明』が提示する人類史から何が学べるのだろうか? 一言でまとめるならば、「人類史を進歩史観的に捉えないことが、他の可能性を選ぶ自由を思い出させる」となるだろうか。
人類史のなかで、なにかひどくまちがっていたとしたら――そして現在の世界の状況を考えるならば、そうでないとみなすのはむずかしいのだが――、おそらくそのまちがいは、人びとが異なる諸形態の社会のありようを想像したり実現したりする自由を失いはじめたときからはじまったのではないか。こうしてついに、この種の自由など人類の歴史上ほとんど存在しなかった、とか、ほとんど行使されたためしはないと考える人も出現するにいたるのだ。
本書の論の進め方は、今の社会構造や常識は過去における人為的な取り決めによって始まった偶然の産物なのだから、今の私たちが人為的にやめることができるということを歴史を遡ることで証明するという流れだった。進歩史観的・決定論的なポップ人類史を批判することで、今の閉塞した社会が続くという運命論を克服しようとしたのだ。
これは、ニーチェの系譜学的、フーコーの考古学的な手法と似ている。著者の一人であるデヴィッド・グレーバーはアナーキズムを支持しているらしく、現在の国民国家に対して系譜学的・考古学的なアプローチを試みたとも解釈できるだろう。
人間社会とはどのようなものかについて、わたしたちはまったく異なる考えのもとで生活していたこともありえたということなのだから。
ただし、「歴史を振り返ると現在の社会は必然であるように思えるが、実は様々な可能性から偶然選ばれたにすぎない」と分かったとしても、現状を変えるのは難しい。身近な例で言えば、キーボードのQWERTY配列のようにゼロから考えれば再設計した方が良さそうであっても、既存のシステムとしての慣性が働くため、リセットしてデザインし直すことは難しいという現象(経路依存症)がある。
そのため、本書のように「今の社会制度は複数の選択肢の一つだから、不満があるなら他の選択肢を選んでもいいんですよ」と説明されたとしても、今を生きる我々からすれば「選び直すのは大変だから、今のままでいいよ」となりやすいのである。「変えられる可能性があること」と「実際に変わること」には大きな隔たりがあるということだろう。
まとめ
題名に「万物の黎明」と名付けるだけあって、農業や都市、民主主義、国家など様々な歴史を辿っているのだが、この記事では本書の主張部分を中心に追った。論旨をピックアップしてまとめることも「ポップ『万物の黎明』」として批判されるのかもしれないが、あくまでも私個人が本書を理解するために必要なプロセスとしてご容赦願いたい。
『銃・病原菌・鉄』や『サピエンス全史』を人類史として鵜呑みにしていたが、これも「勝者の歴史」「勝てば官軍」的な人類史だったのかもしれないと思い直すきっかけとなった。本書でも取り上げられているジェームズ・C・スコットによる『ゾミア: 脱国家の世界史』のように、反近代国家的な視点から人類史を見ることも必要であることを再確認した。
デザイナーという立場からすれば、「変容は人為的に起こせるのか? それとも偶然の産物なのか?」という問いも浮かんできた。西洋近代から生まれたデザインは、デザイナーの意志・意図でプロダクトやサービス、ひいては社会をも良くできるという前提に基づいているが、現代はこの「コントロール幻想」を疑う時代なのだろう。だからといって、何もしないで偶然の奇跡を祈ればいいというわけでもない。意図と偶然、自由意志と決定論といった二者択一を乗り越えられるデザインがあるはずだ。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
