
小津安二郎と、山田洋次
Eテレの「小津安二郎は生きている」を見たが、小津の戦争体験に注目していたようだった。例えば映画監督で戦場に召集されたが、映画監督として広く知られていたので、新聞記事にもなり、さらにそれを小津の母親がスクラップ・ブックにまとめている姿を紹介されていた。その小津は徐州作戦に送り込まれたが、入隊早々、訓練なんか即席だと思うが、それで激戦地に放り込むなんて無茶だと思ったが、いずれにせよ、そのことが『麦秋』に現れていると番組は言う。
『麦秋』は原節子が「紀子」という名前で出てくる「紀子三部作」の一つで、映画には出てこないけれど、中国で戦死した兄の省二の高校時代の同級生、矢部(二本柳寛)と、レストランでデート(矢部はバツイチで子持ちだが、母親のタミ(杉村春子)が、紀子と結婚することを望んでいる)している時、紀子が死んだ省二の思い出を話すと、矢部は、省二くんから軍事郵便で麦の穂を送ってきたと言って、丁度、その時、徐州作戦のことを描いた火野葦平の『麦と兵隊』を読んでいたので云々……と、矢部が答える。


そのデートの後、紀子は矢部の母親のたみ(杉村春子)に、「もし、私でいいのなら」と答え、「ほんとう? ほんとうにしてもいいのね!」と大喜びして、当時、紀子の勤める会社の上司(佐野周二)から紹介されていた縁談を断り、矢部と結婚することになるわけだが、結婚にまで発展するのは不思議だ……と思っているところに平山周吉という「東京物語」の笠智衆の役名と同じ名前をペンネームにしている昭和史の研究者が登場、小津より少し年下の映画監督で、中国で戦病死した山中貞雄に対する小津の気持ちが込められていると言う。確かに中国で病死した紀子の兄と、山中貞雄のイメージはかぶるけれど、「結婚問題」はまた別で、ここは佐藤忠男が言うように、小津の「結婚願望」が矢部に込められていたと見るのが妥当なのではないか。要するに。何らかの偶然の後押しが必要だったが、私(小津)にはそれが乏しかった、と。

それは閑話休題として、平山周吉は『麦秋』の前の作品、『晩春』における「壺のカット」の「壺」が、山中貞雄の『丹下左膳・百万両の壺』の「壺」だというのは、ちょっと無理筋……。『丹下左膳・百万両の壺』はコメディだし……。小津安二郎の本質はコメディにあると私は思っているが、『晩春』の壺のカットは極めてシリアスなテーマを暗示しているのであって……。同じ『晩春』で、笠智衆が同年輩の親友(三島雅夫)と、龍安寺の石庭を見ながら「娘はつまらんよ、せっかく育てたのに……」と言うシーンは、平山周吉曰く、「石庭に空虚な心理を見たのではなく、隣の寺で若き山中貞雄がシナリオの勉強のために下宿していたことを重ねたのだ」とは無理筋すぎる……と私は言いたい。『晩春』は、戦争の記憶はほとんど触れていないので、平山氏は無理を承知で、と推測できないこともないけれど……。
でも新発見もいくつかあった。岡田茉莉子が撮影に入る前に出演者が台本を読む「本読み」で、普通は出演者が台本を読んで、それを監督がチェックするが、小津は、それを自分で読んで聞かせていたそうだ。役者よりうまい……とか。要するに、完璧に頭の中で出来上がっていて、それと寸分違わずつくる。普通はそんな映画は面白くないはずなのに、面白いのが謎だ。
それと関係があると思うのだが、小津映画の代名詞みたいな笠智衆が、青年になったり、中年になったり、老人になったり変幻自在のことだ。例えば『晩春』では紀子の父親で、京都の旅館で布団を並べて寝て、意味深な憶測

を呼んだ。ところが二年後の『麦秋』では、若返って紀子の兄の医者だ。

更に言えば、『晩春』の一年前の『風の中の雌鶏』では佐野周二の同僚のサラリーマンとして相談相手になっているが、三十そこそこで、当初、誰だかわからなかったが、多分、これが笠智衆の現実の姿であって、小津映画における笠智衆は、例外はあるが全て小津が造形したのだ……と思う。

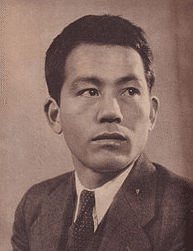

この年齢不詳、言い換えれば不死的なイメージをそっくりそのまま頂いたのが『男はつらいよ』の柴又の帝釈天の「御前さま」に違いない。

これは山田洋次に見る目があったということだが、山田洋次は「小津安二郎の助監督をしていたのに、小津監督の作品は古臭いと思っていました。でも八〇年代にヴィム・ヴェンダースが絶賛していることを知って、小津監督のすごさに気づきました」……と言っていたが、山田洋次は川島雄三と野村芳太郎の助監で、小津安二郎の助監督だったことはない……はずだが、そもそも映画のスタッフ表に「助監督」はないので「助監督」は、正式な役職ではないのだろう。私が気づいたところでは篠田正浩とか、今村昌平という意外な人が小津安二郎の助監督になっていた。
……というわけで、山田洋次が小津安二郎の助監督をしたことはないとは言い切れないが、小津の映画が「つまらなかった」というのは事実のようだ。ウィキには黒澤明が小津の映画が好きなことを知ってショックを受けたと書いてあった。要するに誰某の助監督だったということは映画監督のキャリアとしてはあまり重大な問題ではないのかもしれない。でも、それを承知で言うのだが、野村芳太郎の助監督時代に『拝啓天皇陛下様』でヒットした渥美清を川島雄三のセンスで換骨奪胎して「男はつらいよ」をつくり、そしてフーテンで危なっかしい寅さんを、常に見守る役として小津映画の笠智衆を「午前さま」として配置したのは見事だと思う。
ここで山田洋次のフィルモグラフィーを書いておくと、私が何となく記憶しているのは一九六三年の勝呂誉と倍賞千恵子の「下町の太陽」で、翌年一九六四年にハナ肇の「馬鹿シリーズ」が始まっている。クレージーが応援の形で出てくるという理由で、何本か見ている。私は大いに気に入ったが、その後、一九六九年に渥美清の「男はつらいよ」シリーズが始まり、その間に『幸福の黄色いハンカチ』、そして、小津映画を意識したと思われる『家族』や、『学校シリーズ』、『東京物語』へのオマージュ映画『東京家族』が挟まるというわけだ。私は全てまともに見ていないので……批評は差し控えるが、チラ見した限り……、いや、批評はさし控えたいが、一言だけ。
山田洋次は、自分が小津の魅力に気づかなかったことがコンプレックスになっていて、それを埋めるために映画をつくっている……のではないか。でも、本来、そうではなかった。
というわけで、以下、佐藤忠男の山田洋次の分析を紹介したい。
国際協力基金の仕事で、山田洋次と一緒に東南アジアの各地で『幸せの黄色いハンカチ』の上映会をした時、どこでも評判が良かったが、普段は温厚で真面目な高倉健が、妻が流産したという理由でふさいでいる時、酒場で人を殴り殺して、刑務所に入るわけだが、奥さんが流産したという理由で、凶暴になってしまうのがわからないと言われたそうだ。日本人だったら高倉健がどんな役を演じてきたか知っているから、突然、暴れだしても違和感はない。しかし、これは愛の表現が下手だということに原因があるので、この問題を何とかしなければならない。これが『下町の太陽』以来の山田洋次の映画のテーマになっていると佐藤忠男は言う。しかし、『下町の太陽』では、勝呂誉は、普通の日本の男性は決して言わない王な大仰なセリフで愛を訴えていた。これでは、ダメだ……というわけで、つくったのが、ハナ肇の「馬鹿丸出し」のシリーズと、「男はつらいよ」の二つのシリーズに続いている。



佐藤忠男曰く、『下町の太陽』のような「愛のために胸が痛い」というような直接的なセリフは、以後は影を潜め、『幸せの黄色いハンカチ』の高倉健のように、「言えないことは言わせないまま、その思いだけを濃密に浮き彫りにする描写力を山田洋次は身につけたが、そこで言おうとしていること、つまり「日本人は愛の表現が率直でないし、下手だから、これをどうにかしないといけない」という問題意識は変わらず、『下町の太陽』の次につくった「馬鹿シリーズ」のハナ肇演じる源五郎は下層社会の粗暴で図々しいが、根は途方もなく善良で女性に優しい。このハナ肇とのコンビのあと、渥美清とコンビになる。渥美清にはハナ肇のような粗暴な元気さの代わりに、巧緻な話術と絶妙な間の取り方を伴った芸の細かさがある。そして観客は、はっきり、渥美清の寅さんを選んだ。ハナ肇の時は、そこそこの観客しかいなかったが、渥美清になって爆発的なヒットになったのである。しかしそれを認めた上で、ハナ肇の決して自己卑下などしない爽快さも良かった。だからこそ、山田洋次の作品の主人公の常としての「愛情コミュニケーション不全症」に苦しみながら、最後は愛する女性を本当に幸せにすることができだ。あの至福感は「男はつらいよ」シリーズにはついにない。
……と、佐藤忠男は書いている。それが示す意味については何も書いていないけれど、私は暗澹とした気持ちにならざるを得ない。
山田洋次が小津安二郎に憧れたつくった諸作品については——大谷翔平じゃないけれど——「憧れるのは、やめましょう」と言いたい。
ところで番組には出てこなかったけれど、小津安二郎の『風の中の雌鶏』について少し書いておきたい。
夫の修一(佐野周二)が出征中、妻の時子(田中絹代)は貧しい中で生活をやりくりしていたが、息子が病気になって医者代がなく、身体を売ったことがあった。それを復員後に知った修一は、謝る時子を許すことができず、主婦売春が行われていた曖昧宿を訪ね、そこで主婦を指名して事情を聞き、主婦たちの内実を知り、時子を許す……というストーリー。
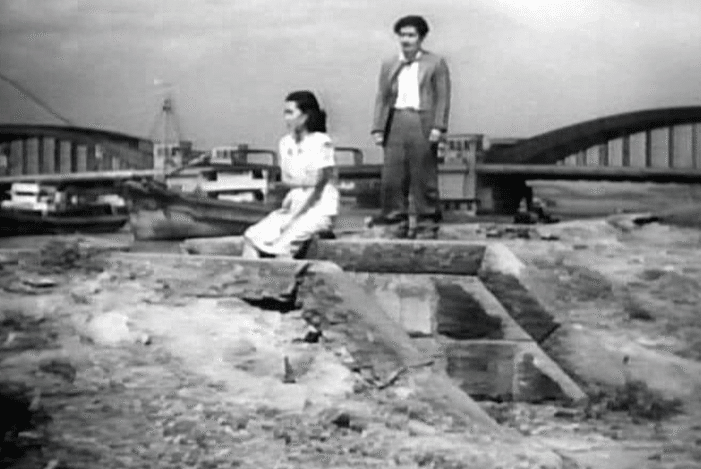

私は面白いと思ったけれど、当時の批評家、観客から「小津らしくない」と非難され、また野田高梧が「現象的な世間でしかない」と批判。その批判を受け入れた小津は、次につくった『晩春』をはじめ、全ての小津作品のシナリオを手がけることになった。という意味で、『風の中の雌鶏』はエポックメイキングな作品になったと言ってもいいと思う。小津自身は「失敗が自分のプラスになればいいが、そうはならなかった」と言ったそうだが、その野田高梧曰く「後期の小津安二郎の出発点になった」とは、うまい言い方だが、佐藤忠男は「戦時中に戦意高揚映画を作っていた映画人たちが終戦後に一転して民主主義啓蒙映画を作り出したことに食傷していた批評家が、そうした作品のひとつに分類してしまったこと」が小津の傷心を招いたという意見に賛成だ。この作品を批判した野田高梧、曰く、「後期の小津安二郎の出発点になった」と、批判しながら、それを反転させる形で言っているのは、なかなかうまい言い方だ……と、思う。
ちなみに平山周吉は『風の中の雌鶏』にも観察の目を怠ることはなく、『風の中の雌鶏』のテーマを示すものとして紙風船が飛んでいるが、これは山中貞雄の『人情紙風船』の紙風船だと言う。私は両方とも見ているけれど、紙風船のことは見逃したようだ。でもテーマ的にはなかなか説得力がある……ように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
