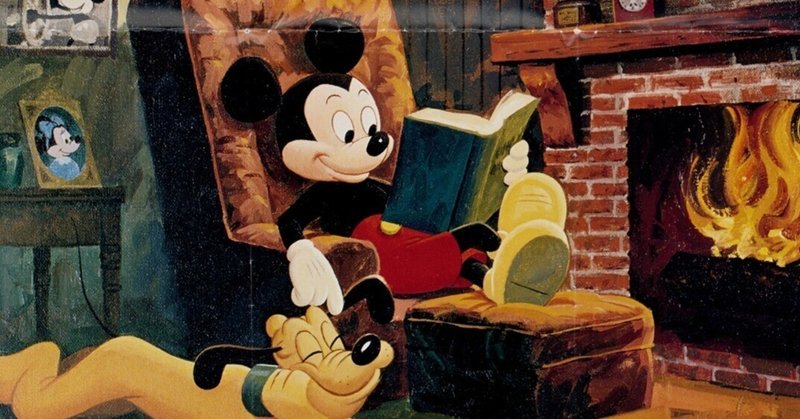
5月の読了
当記事のAmazonリンクはAmazonアソシエイトを使用しています。
影響力の武器-なぜ人は動かされるのか-
ずっと読みたかった「影響力の武器」。図書館で順番待ちをしていたのですが、ようやく手元に来ました。
「なぜ人は動かされるのか」という副題の通り、相手の要求に対してYesと言ってしまう、相手の望む行動をしてしまう、自分の意思が動かされ、誘導され、その通りの決定をしてしまうのはなぜか?ということを体系的にとてもわかりやすくまとめてある本です。
こう書くと難しく感じますが、現代生活は広告やSNSなど「影響力の武器を使う側」に囲まれた生活をしているのは自明。自分がこの武器を使うための指南書というよりもこの攻撃から身を守り、賢明に生きていくための防衛書だと感じました。この本の内容を知っていると知らないとではアンテナの張り方と精度がめちゃくちゃ変わるし、安易な決断をして後から後悔しないで済むようになると思う。
著者がいう”最も信頼性の高い、それゆえ最も多く使われる承認誘導の引き金”は、
①コミットメント
②お返しの機会
③類似した他者の承諾反応
④好意あるいは友愛の感情
⑤権威からの命令
⑥希少性に関する情報
の6つ。
私が特に印象的だったのは④好意の部分。
熱狂的なスポーツファン達が、応援しているチームの勝利後に「俺たち(we)が勝った!」と叫び自分とチームのつながりを緊密にアピールする一方、負けた時はweなぞ使わず「彼らは負けた」と都合よく使い分けることに対して辛辣にこう分析しています。
栄光の反映に浴したいとする気持ち(『栄光浴』)は誰にでも多かれ少なかれありますが、あまりにその傾向が強い人たちには、何か特別な理由があるように思われます。彼らは一体、どのような人たちなのでしょうか。私の推測が間違っていなければ、彼らは単なるスポーツ熱愛者ではなく、背後にパーソナリティの脆弱さが隠されている人たちです。つまり、否定的な自己概念を持っている人びとなのです。
こころの深層に、自分は価値が低い人間だと言う気持ちがあるため、自分自身の業績を高めて名声を得ようとしているのではなく、他者の業績の結びつきを形成し、それを強めることによって名声を得ようとしているのです。
私たちの文化の至るところにはびこるこの種の人間は、実に多種多様です。有名人を友達のように言う人たちは、その古典的な例です。
この「栄光浴」という言葉、グサっとくる・・・
誰しも有名人と友達だったり関係性があればそれを話したいし外部に知らせたい。
インフルエンサー同士が食事に行きお互いそれをInstagramにアップすれば、一方のファンは「この人と仲良いんだ!」ともう一方にも好意を持ったりするのもそう。
某朝の情報番組が、アイドルグループのメンバーの一人を隔週キャスターに起用したことをきっかけに必ず「”我らが”○○」と紹介するようになったり、日テレのアナウンサーがインタビューで意気投合した俳優さんを親友認定し、以後「私の親友○○」と敬称つけずに紹介するようになったのも、結びつきを外部へ発信したいという策略がある気がします。
私が時々利用する某ショップは、自分のお店がメンションされたストーリー投稿のうち、フォロワーが多い投稿者のものばかりを選んで紹介しているな〜という印象。あの人がいいと言うんだからいいと思わせる、本の中の言葉を使うなら『カチッ・サー』だな、と。(こういうことに気づきすぎるのも、生きづらい&自分の性格の悪さを感じてしまうのだけど。笑)
「推しの子」でも、”手っ取り早く登録者を増やす一番いい方法は有名Youtuberとコラボすること”と言っちゃってるし(笑)
広告主にとって重要なことは、とにかく結びつきを作り上げることです。論理的である必要はありません。ただ好ましい結びつきでありさえすればよいのです。
こう考えると、日常のあらゆる場面で狙われて心理を操作されているんだなあ(゚ω゚)と疑心暗鬼になってしまいそう。しかし周りには、損得など考えない本当に優しい人はたくさんいるし、そういった人たち全てを改めて「お返し目的か?返報性の原理使おうとされてるんか?」と闇雲に疑ってかかるのは悲しいし失礼。何より自分が疲弊してしまう。
著者も、大切なことは「相手の本心からの優しさ・好意と、搾取目的の行為を見極めること」と言っています。
私たちはこれらを見極められるくらいの人生経験は積んでいる、はず。
そしてこの本がその判断をするための強固な・頼もしいバックボーンになってくれると思います。
実践家がこのような引き金を使うこと自体は、必ずしも搾取的なこととは言えない。引き金がその状況のなかにもともとある自然なものではなく、実践家が埋造する場合が問題になるのである。
私が読んだのは第2版でしたが、現在は新訳の第3版が出ていてさらに読みやすくなっているようです。
英語日記BOY
英語学習を後押ししてくれた本。そもそも英語を勉強するとは?という話から、ひとりLINE、オンライン英会話など現代のツールを賢く使う方法が詳しく書いてあって、これならできそう!とモチベが上がります。
特になるほど!と思ったのはTwitterを例文検索として使う方法。
確かに思考を変えれば、Twitterは生きた日常フレーズが際限なく存在するプラットフォーム。「話題」タブはある程度拡散されていたり知名度がある人のTweetから見せてくるので、文章も下品すぎないはず。
私が実践した例で言えば、"make sense"というフレーズ。
相手の説明に対して「なるほど」という意味で"That's make sense."と言えるようにはなったけど、文章の間に挟んでサラッと使う用法がいまいち掴めない。そこで検索したら出てくる出てくる(笑)めっちゃ勉強になるう。

僕自身「言えない…悔しい」というおもいを何度も経験した。恥ずかしいおもいは、いま、ひとりでやってしまおう。そしていつか訪れる本番に備えるのだ。
著者の新井リオさんは「英語を話せるようになる」ことがゴールではなく、その先を叶えるための武器の一つとして捉えています。
本の最終章では「英語×○○」の幾つか掛け算が紹介されていて、それらの思考もとても為になる。
日本での英語話者は10%程度らしく、きっと生活のコミュニティ内では”自慢できる”スキルかもしれません。しかし、コンビニで働く外国人技能実習生が「日本語がある程度できること」を前提として働いているように、フィールドに立つ際には「英語が話せる」ことは前提でしかなくなります。
「身につけて何をしたいのか?」ということを常に思考に置いておくことで、勉強のモチベを保ち続けられる。
これは英語に限らず、あらゆるスキル習得や努力に通ずる考えだなと思いました。
「体重の数字を減らすためにダイエットするのではない、自分が好きな見た目になって服を着こなすためだ」みたいな。
人生は実験であり、アイデア次第でいくらでも楽しくなる。僕は本気で、そう信じている。
頂いたサポートは書籍購入費を中心に、発信に関わる使い方をさせていただきます!
