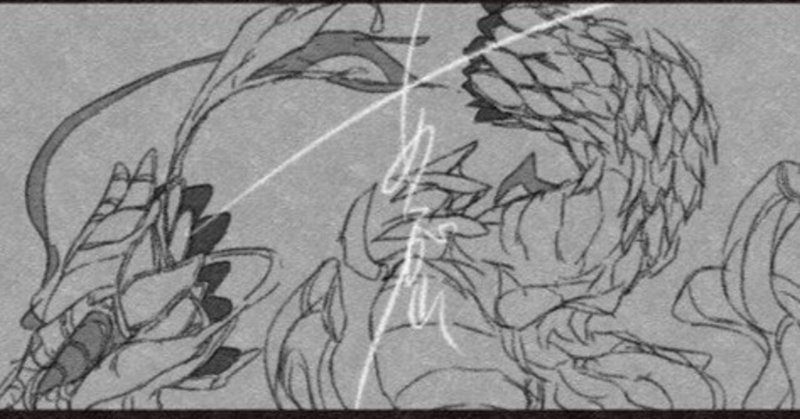
小説:出づるも あこがれ
※ホラー小説です

0
男が一人行方不明になった。
悪臭放つ家に住むおかしな男だった。
ヘラヘラニヤニヤと笑えば、今度はスッと表情が無くなる。優しい声で語りかけるくせに身なりは酷い有様だ、子供が近寄ればきっと連れて行かれるだろう、と誰もが思う。
そんな危ない男が突如行方不明になったのだ。安心こそするが、それでもどこかに彷徨い続けているのではないかという不安もあって、こうもウワサが流れている。
そんな男がある日、帰ってきた。
しかも、気が滅入る程に悪化して。
男は薄気味悪い声で言った。
「まぁ、満足だろうよ。俺も、コイツも」
1
「小鳥遊さんに憧れているのです」
いつも通り酒を飲んでふてくされている小鳥遊の前に一人の青年がやって来てそう言った。小鳥遊よりも身長は低いが、好青年であることには変わらない。
「小鳥遊さんのようになりたいのです」
不思議な男もいるもんだと、小鳥遊は思う。
てっきり書生としての小鳥遊に憧れているのかと思ったが、彼〔相(あい)川(かわ)〕が言うのはどこで知ったのか小鳥遊の副業についてのことだ。
小鳥遊にとって忌まわしい祓い屋の真似事は、しかし他の人間にとってかなりの需要があるようでそこそこに頼まれる事が多い。
「どういてあがな――……」
”怖い事”と言うのはプライドが許せなかったので「金にならんことを」と言い換える。
「格好良いではありませんか。凡人には無い秘めた力を持つなんて」
相川は興奮した面持ちで言う。
怖がりの小鳥遊にとってアレが何故「格好良い」と思えるのか到底理解が出来ない。
「何かやり方でもあるのでしょうか」
「やり方?」
「怪異に触れるやり方ですよ。狐の窓をご存じですか? 指をね、ほら。こうやって――……」
と、相川はまるで影絵遊びをするかのように自身の手で奇妙な形を作り出す。たしかに指と指の間には向こうを覗き込める小さな空間がある。
「これで怪異を見るのです」
そう得意気に披露されても、小鳥遊はそれが子供欺しにしか見えず反応に困る。
「小鳥遊さんの話を聞くに、毎回怪異があるようですが――……」
「好きでそうなった訳じゃない。おまさんが誰かは知らんが、自ら怪異に触れようなど思わん方がえい思う。そりゃ隙になる。なんちゃあ知らん人が狐に騙されて中に入り込まれる、なんてことをわしはいっぺんも二度も見ゆーき」
そこまで言ったのにも関わらず、相川はそれどころか「嗚呼、私も見てみたかったです。狐につけ込まれるだなんて。まるでカミソリ狐の話のようだ」などと嬉しそうに言っている。
「ね、ね。小鳥遊さん。今度副業をされる時是非声をかけてくださいよ」
「嫌に決まっちゅー。わしは、まずそういった事と縁を切りたくて仕方が無いとさえ思うちゅーのや」
嫌そうに答える小鳥遊に相川は「まあまあ」と猫撫で声のまま小鳥遊をその気にさせようとあの手この手で誘ってくる。
「ウワサは聞いているんです」
「誰から聞いた」
「それは言えません。とある情報筋からですよ」
どうせ書生仲間か垣谷先生なのだろう。と、小鳥遊は心の内で彼らに毒づく。前回の件で先生は暫くしおらしくしていたが、それでも一ヶ月も経てばいつもの調子に戻っていた。
「それとも、なにか? 小鳥遊さんは「嫌だ、嫌だ」と言う癖に、私のような求めている者を拒絶し、その気持ちを踏み躙りたいのですか?」
唾を飛ばし飛ばし言う男の姿に小鳥遊は呆れるやら腹が立つやらで言葉も出ない。
相川は次第に語気を荒げ「だったら、もういいです」と席を立った。その強い調子に周囲の客も従業員も驚き「何事か」と相川と小鳥遊に視線を送る。
「だったら、もう良いです! 隣町にもっと良い先生がいると聞きました」
相川は叩きつけるように机に金をばらまくと、釣りさえ受け取らず店を出て行った。
「面白い男じゃないですか」
その日、書生仲間の小岩井に愚痴ると、彼はのんびりそんなことを言うので、小鳥遊は「そがな事どうでもえい。折角の気分をわやにされた」とふてくされて布団に籠もることにした。
「でも、また会うと思いますよ」
「どいてそう思う?」
「そういう人間こそ執念深いんです」
2
小岩井の予想は二週間後に的中した。
いつも通り小鳥遊がふてくされながら酒を飲んでいると、再び相川が向かいに座った。
「他の席があいちゅーやろう?」
「いえ。小鳥遊さんを探していたので」
「おんしはわしの知り合いやか?」
「嫌だなあ。小鳥遊さん。相川ですよ」
相川はそう言いながら、自身の左手首に巻いた黒い珠々を撫でる。
「あの時、私は小鳥遊さんに酷いことを言われたでしょう? だから、とある先生の所へ行ったんです。その報告をして差し上げたくて。桜川さんと言うのですけれど――……」
頼んでも居ないのに相川は嬉しそうに言い始めた。
小鳥遊は聞く気など微塵も無かった。
眼を爛々と輝かせた彼が唾を飛ばし飛ばし説明するのを見るだけでも酒が不味くなると言うのに、彼の語る内容は更に不味さに拍車をかける。
要約するとこうだ。
桜川というのは、小鳥遊とは違い凡人には無い目には見えない力で妖怪を倒し、それを生業としているという。彼に力を授けたのは龍であり、それは神たる尊い位置である。
口にするのは雨水だけで、彼が出掛ける日は必ず雨が降る。
普段は弟子などとらないが、相川の力を見抜き特別にソレを許したのだという。
桜川の見てくれこそ老人であるが、身のこなしは軽く、力も相応に強い。哀れな誰かを救うため長距離を歩くなど苦では無い。
とのことだ。
(それを知ってわしゃ何の特になるがやろうか)
小鳥遊は思うが、ここで水を差せばそれこそ相川に何をされるか分からない。
未だ言葉を止めぬ相川は、さらに異常とも思える勢いを見せる。
「それで来週、師匠と仕事に行くんです。そこで力を得て、勿論その次の月だって音もします。先週は先生の力が強すぎて怪異に触れることなど出来ませんでしたが、きっと小鳥遊さんさえも驚かせることをしてきてみますよ」
「それはえいな」
適当に肯定しておけばすぐに解放してくれるだろう、とする小鳥遊の計画は成功した。相川はすっかり気分を良くし、小鳥遊のこれまでのツケの半分と今回の酒代を代わりに支払い「言ってくだされば小鳥遊さんの副業とやらも代行して差し上げますよ」とまで言ってのけた。
3
「小鳥遊さん。頼みがあるんです」
ある日の夕暮れ、いつも通り酒を煽っていると三度相川がやってきた。
「相川か?」
「覚えてくださったのですね」
そう言う相川の声は前回とはまるで違い気味の悪い程穏やかになっていた。
(だいぶ、やつれたな)
小鳥遊は酒を飲みながらそんなことを思う。
前回、前々回は異常とも言える程の勢いがあった。それが若気の至りかは分からないが、それは今やすっかり身を潜めている。
ねっとりとした言い方はそれもまた小鳥遊を不快にさせるのだが。
「頼む? おまんの師匠とやらがおるろう?」
「私の師に会ってほしいのです」
「どいて」
「師が貴方に逢いたいと」
「同業潰しなら無駄や。わしのは所詮副業で、おまんらの仕事を邪魔するつもりは微塵も無い」
「いいえ」
相川は静かに、けれど低い声でそういった。
「同業者としか話せない内容だと仰っていました」
「おまんがおるろう?」
「私は弟子なので。小鳥遊さん、既に私は小鳥遊さんがお住まいになっている所に向かい、むこう三ヶ月分の家賃を代わりに支払い差し入れもしてきたのです。垣谷さんは満足していましたよ」
そう言われてしまえば小鳥遊はぐうの音も出ない。
4
雨が降っている。
小鳥遊の赤い番傘がタントンタントンと雨に打たれて鳴いている。
「新しい着物でも買いましょうか?」
「いらん」
小鳥遊は、つっけんどんな態度のまま答える。
小鳥遊の副業の格好こそ目立つものだ。赤い着物、赤い番傘、一つに縛り腰まで伸びた黒い艶のある髪。後ろから見れば一見彼は女に見える。その格好を、相川は誰かのお下がり一式だと勘違いしたらしい。
「工面しますよ?」
「いらん」
その傲慢ぷりが小鳥遊を更に腹立たせた。
十六時だというのに空は暗く雨のせいで気持ちは落ちる。
「お邪魔するがは午前でもえいろう。おまんの師にこがな酒飲みを逢わせるのも失礼やろう」
と、打診した小鳥遊に相川は
「夕方が良いのです。それに、ちょうど今雨が降っている。師は龍神ですので特別に小鳥遊さんを歓迎しているのですよ。小鳥遊さんが酒を飲むのも良い。内から身を清めたのですから」
そう即答した。
その言葉を聞いた小鳥遊は眉を潜める。
以前の相川は、桜川と龍に関することを言っていた。だがそれは「桜川に力を授けたのは龍」と言っていただけで「桜川は龍神である」とまでは口にしていない。
身を清めたから良い。と、いうのもどうもおかしい。
(めくらになっちゅー)
相川の中で桜川は尊敬を越えて神格化されている。
元々相川は非日常への憧れが強く、それに一本気で単純そうな男であった。
今日は朝から雨が降ると誰もが思っていた。曇天が続いていたし、鳥は虫を求めて地面を撥ねていた。特別も何も無い。
(わしでも騙せそうな阿呆者だが、ここまで来て二体一というのも厄介か)
案内されたのは密集する家から少し離れ、川を向かいにした小さな家だった。
「人との境界線に成っているのです。川は龍の化身ですので」
説明する相川を無視し、小鳥遊は室内に入る。
廊下を歩き通された場所を見、少し寒気がした。
道場。
最初、小鳥遊が思ったのはそれだったがすぐに変更した。出来上がったばかりの家か、もしくは住人を探している家。そう例えてもまだ少し遠いかもしれない。
何も無いのだ。
広い部屋の中心に一人あぐらを掻いた男がいるだけで他にはなにも。
座布団さえ敷かれていない。
ただ梅雨のような、湿気と陰気に溢れた部屋であると思った。
「水を撒いているのですよ。龍と水は切れぬ関係ですので」
相川は濡れた床を見て言う。雨漏りのように床は濡れている。
重い雰囲気のまま相川は一礼して退室し、小鳥遊は廊下に一人取り残された。
「わざわざご足労頂きまして」
座ったままの男桜井が口にするのを聞き、相川の口調は彼を真似たのだろうと小鳥遊は直感した。
小鳥遊を気遣う言葉こそ丁寧だが、どこか雰囲気は重く窘められているかのようにさえ思える。
「わしに何のようや。おまんらあの仕事の邪魔をした覚えはないが?」
「勿論。そんな事思っておりませんよ。さあ、中に入ってくださいませんか? 私は肺がよくありませんで、声を張るのは得では無いのですよ」
小鳥遊は一歩進むが、足袋はすぐ床の水を吸い更に不快を誘う。
「それじゃあ、なんや? わしに屋根の修理でもさせるつもりか? こうも濡れては床が腐るろう?」
「いえいえ。そんなことありません。ああ、それと。どうかその傘を持ち込まないで頂けますか? 傘を盗もうなどと思う者はここには誰一人おりません」
「けんど」
「鉄の臭いがしますので」
有無を言わせぬ声に小鳥遊は眼を開く。相手は仕込み刀の存在を既に理解している。
「そうかよ。ほいたら、わしはここでえい」
小鳥遊は番傘を抱いてその場に座った。
着物が、袴が水を吸いさらに気分を悪くする。どうも臭い。
「これは雨水ではありません。日本酒です。場を清めるのに必要ですので」
穏やかな声で桜川は言う。
「それで? 場を清める事の出来るおまんが、どいて一介の書生であるわしに声をかける? わしゃ頼まれるほど、おまんらあと仲良うなった覚えはない。相川はおまんを信用しちゅー。そっちに頼んだらえい話や」
「あの子は私を尊敬しすぎているようなので」
「盲目的にな」
吐き捨てるように言う小鳥遊に桜川は頷く。
「あの子では資格がない。持っている者同士でなければ理解し合えない」
「持っちゅー物? わしにあるがは文才くらいか」
自身の顎を撫で小鳥遊は言うが、桜川はそれを鼻で笑い飛ばした。
笑顔だというのにそれがどうも恐ろしく思える。
「お前は私を知らないようだけれど、私はお前を知っているよ。怖がっておめおめ本島にまで来ている理由も、その刀が忌まわしいことも」
顎を撫でる手を止めて小鳥遊は桜川を睨んだ。
今や二人は演技をやめ、にらみ合っている。
「その番傘で私を斬るか?」
「どいて?」
「私は龍神だから。でなければ、お前の仕込み刀など知りもしないだろう?」
「わしに力なんて無い。霊も見んと、斬ることも出来ん。けんど、龍神は、龍は、こがな澱んだ水溜まりで満足される事は無いとわしゃ思うちゅーぜよ」
桜川は俯き、くっくっと笑う。それだけで、雰囲気がガラリと変わる。床にばらまかれた日本酒の、腐ったような嫌な臭いがむっと強くなる。
「わしは断りに来た。頼み事ちいうのも聞かん。それだけを言いに来た。ほいたら失礼します」
立ち上がり、背を向ける小鳥遊に桜川は先程とは打って変わって優しい声音で呼び止める。
――……相談させてくださいよ、小鳥遊さん
――……助けてくださいませんか?
――……認めて貰おうとは思わないのですか?
――……有名に慣れますよ
その猫撫で声の中でふと
「これは動かし難くてかなわんのですよ」
低い厭な声が聞こえたが、小鳥遊は振り返ることすらしなかった。
濡れた足袋がグチャグチャと鳴いて煩わしい。
玄関に出た際、詳細を聞きたくて仕方が無さそうな相川が待っていた。
「おんしに家族がおるならここを忘れてすぐに帰れ。おらんのやったら、相応に働きに出ろ。わしは言うたぞ」
相川の返事を待たず小鳥遊は外に出た。
月光美しい夜だ。
「何が歓迎しちゅー、だ。綺麗な月夜やないか」
小鳥遊はそう吐き捨てて番傘を開いた。
5
いつも通り店で飲んだくれている小鳥遊の前におかしな男が現れたのは九月の終わり頃だった。
全身黒い格好で、まるで喪に服しているような姿。だが、眼は悲しみに暮れることは鳴くギラギラと不気味に輝いている。
一目見ただけでどんな察しの悪い者でも、この男は異常だと分かるだろう。
「小鳥遊、小鳥遊」
男は低い声で言う。
「俺は成れたよ」
酒を飲んでいた小鳥遊はその言葉を、男を無視し勘定を済ませると、さっさと道へと向かう。
後ろではニタニタ笑う男がいるのを気にせず、人混みの中に入る。男はそれでも付いてきて、ニヤニヤニタニタと笑い続ける。
他の人間は彼に気がつかないのか、それとも存在も認めたくないのかいつも通りの日常を送っている。
それは小鳥遊はも同じ事で、まるで何事もないように裏路地へとまわり、ふと立ち止まる。
男に声をかけられた時から音が、日常に溢れかえる筈の音が消え去っていた。
それを異様・怪異と片づけるのはあまりにも簡単である。
騒ぐことも、あわてふためく事もすぐにできる。
鼻孔をつくのは水の腐ったような、けれど日本酒のような厭な臭いばかりだ。
後ろに付いてくる男も同じように立ち止まり、再度小鳥遊を呼ぶ。
かちん
かちん
小鳥遊はそれに答えずただ、二度だけ番傘に仕込んだ刀を鳴らした。
刀を少し出して音を出して仕舞う。たったそれだけの行為だ。それでも、そこでようやく振り返れば男はいなくなっている。
「だから、わしは言うたがよ」
男の立っていたであろう場所に汚く濁った水溜まりが出来ていた。
水溜まりに映る空はこうも青く、雲一つ無い。
サポート有難うございます。紙媒体やグッズ作成に使用したいと思います。
