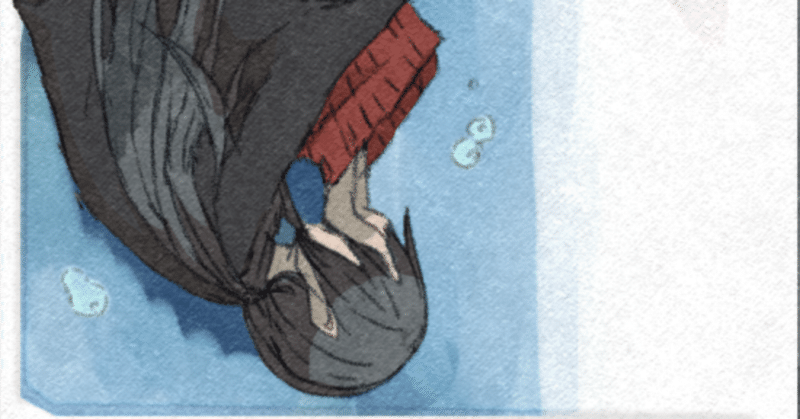
小説:出づるも ハンケチ
※ホラーです

0
あれだけの晴天は翳り、太陽は厚い雲で顔を隠す。
大粒の雨が地面を濡らし始め、ぱらぱらと降っていた雨は土砂降りに姿を変えている。
突然の大雨に慌てて家に帰る者、店に逃げ込む者がいた。
それは頼りない橋を渡るあの女も同じだった。
雨が降り注ぎ、川は暴れ、橋には川の水が溢れ出る。
水は足を滑らせ、足に絡み、足を攫い、しまいには――……。
1
大竹夫妻とその子供は祖父母を連れて街に出ていた。
「何を買おうかしらねえ」
穏やかに言う祖母に、孫は目を輝かせて図鑑をねだる。
「庭に虫がいたの。だけどねぇ、おじいちゃんも分からなかったんだよ」
孫の言葉に祖父は「参った、参った」と笑い、夫妻も微笑んだ。
誰もがその一家を見て幸せそうだと思うだろう。実際一家は幸せであり、喧嘩などといったものとは無縁だった。全員が穏やかというのもあるのだろう。
「おや」と、大竹正雄は立ち止まった。
「どうしたの、まささん」
「あの人、ハンケチを落としたよ」
見ると、地面には一枚のハンケチが落ちている。そのすぐ先には女が一人歩いている。
「渡してくるよ。少し待ってて」
正雄はそう言うと、軽い足取りで進みハンケチを拾った。その様子を、待っている家族みなが見ていた。
ハンケチを拾った時、一瞬だけ正雄は動きを止めた。彼は首を一度首を傾げ、それを絞るような仕草をする。そしてから、前方にいる女性の所へ駆けて行き、そして無事渡せたようだった。
戻ってきた正雄の様子は少しおかしかった。
「どうしたの?」
妻の大竹ハルが尋ねると、正雄は顔をしかめたまま、首を横に振った。
「なんでも無いよ」
けれど、その言葉は嘘だと誰もがすぐに分かった。
きっとハンケチのセンスが悪かったのか、とても汚れていたのだろう。と、それぞれ好き勝手に考えそれ以上の詮索はしなかった。
2
おかしな事が起きたのは、その翌日からだ。
友達を遊んでいた大竹夫妻の子供、正が泣きながら帰ってきた。
驚いた祖父が事情を聞くと、女に誘拐されかけたと言う。怒って現場に行こうとしたが、そこには誰も居ない。
不思議なことに雨が降ったかのように一箇所だけ大きな水溜まりがあった。
誘拐犯は逃亡し、おそらくまだ近くに居るだろう。そう考えた祖父は周囲を警戒しながら、正に自分の近くで遊ぶように言った。
その夕方。
今度は、買い物に出かけたハルが青い顔で家に戻ってきた。
事情を聞くと、一日中、誰かにつけられていたのだと言う。どうにかこうにか店を巡ってまいて来たが、怖くて堪らないと彼女は涙ながらに訴えた。
不安に思って玄関を見るが、そこには誰も居ない。ただ、玄関から一直線に水溜まりのあとが点々と続いていた。
そのようなことが、二日続いた。
三日目の夕方。
皆が揃って夕飯を取っていると、誰かが来たようだった。
「ただいまぁ」
玄関から言うので親戚でも来たのかとハルが玄関に向かい、そして悲鳴をあげた。その悲鳴に全員が慌てて玄関に向かった。
大竹の玄関は、一部摺りガラスになっている。ゆえに、客人の体格だけだが、把握出来る。
そこに居たのは、太っているわけでも、細いわけでも無い、四肢を歪ませた人の形であって人では無い”何か”が立っていた。
それはヨタヨタと両足を内側に折りながら、玄関前で数歩の前進と数歩の後退を忙しなく続けている。
「ただいまァ」
と、その何かは続けて言った。
誰もが恐怖に襲われ声が出ない。
黙っていると、ドンと戸を叩かれた。
「ただいまァ」
最初は平手で戸を叩かれる。
「開けて」
次は拳で戸が叩かれる。
「開けて。迎えに。迎えに」
次は、頭で戸が強く打ち付けられる。
「迎えに、ねぇ。あがりました」
誰もが恐怖に黙ったまま、涙を溢している。
額を戸に打ちつける際に見える顔は、死人のような色をし、目は左右逆にひん剥いている。
「ここは俺の家だ!」
それでも祖父がそう叫ぶと、その何かは頭を振り上げたまま動きを止めた。
「違う。違う声だ」
声はどこか悲しげに、どこか苛立たしげに呟いて、その姿を消した。
3
「ということなんです」
――……純喫茶。
大竹夫妻は、目の前に座る男に、この数日間の悪夢のような出来事を説明した。
あの後、正雄はすぐさま知人に助けを乞うた。その中で紹介されたのが目の前にいる小鳥遊 辰巳という男だった。
純喫茶に慣れていないのであろう青年は。震える手でどうにかカップを持ち、せめて下品な音を出さぬよう細心の注意を払ってコーヒーを啜っている。
思った以上に飲んだ物が苦かったのか、彼は一瞬だけ顔を歪めるとまだ震える手でカップを置いた。
頼りになるとは思えない。
正雄が彼、小鳥遊辰巳に抱いた第一印象だ。
体躯は大きいくせに、余程の小心者なのだろう。
先程からチラチラと動く視線が落ち着かない。純喫茶が初めてなのだろうか、世間知らずともいった具合が見て取れる。
場所も考えず持ってきた緋色の番傘を決して放そうとはしない。
「寺には行きましたか?」
「近くに寺はありませんで、こうしてお願いしているのです。あなたはこういったことに詳しいと聞きましたので」
「先生のご友人ですか?」
正雄は頷いた。
小鳥遊は書生だという。その先生の仲介でこうして彼は呼ばれている。
すると、小鳥遊は目を瞑って首を横に振った。そして何かブツブツと言っている。
「先生の話とあらぁ、仕方が無いきのう……。けんど……、どうしたもんか」
それは聞かせるつもりも、ましてや言葉にするつもりは無かったのだろう。会った時から抱いた敬語の出来なさに理解する。彼にはきつい訛りがみえる。
「えいけど……。いいですけれど、絶対解決は難しいです。努力はします」
小鳥遊はそう言って、上目遣いに夫妻を見た。
「謝礼は……。先生に渡さず、私にくださいませんか?」
「勿論です」
夫妻はそう言って、頷いた。
「先生には、仲介料を差し上げました」
すると、小鳥遊があからさまに不機嫌そうな顔で舌打ちをした。けれど、すぐにその表情を隠し、姿勢を正すと深々と頭を下げた。
「ほいたら、すぐにお宅に上がります」
「すぐに?」
「はい。つけられているなら、分かるかもしれませんで」
小鳥遊はそう言って、女給が持ってきたアイスクリームに目を輝かせた。
4
「おる」
帰り道、小鳥遊はふとそう言った。
夫婦は、その言葉にさえ怯えて立ち止まった。
「驚かさないでください」
「驚かせるつもりはない。けんど、奥方が言うた事は正しい。つけられちょる」
「誰か分かりますか?」
小鳥遊は黙ったまま、地面を睨んでいる。
そうして再度、歩き出した。その顔は緊張していて、すぐにここで立ち止まって話をしているのは危険だと理解する。
「ついてこられてる時、すぐに家に帰ったか?」
「いいえ」と、ハルが言う。
「怖くて一度お店に寄りました。それでまけるかと思ったんです」
「待っちょったじゃろ。今みたいに」
「今?」
「ずっと店におった」
小鳥遊の言葉に正雄は、店で彼が落ち着かない素振りをしていたのを思い出した。
「気付いていたんですか?」
「おん。あぁも視線がきつうてな。辿れば店のすぐ近くにおったがよ。けんど、中には入ってこん。ということは、「入れ」と言わない限り入れん輩ぜよ」
小鳥遊はそう言いながら、持ってきた和傘を強く握った。
「入れん輩いうことは、良い奴ではない。けんど、複数じゃないのが不幸中の幸いか」
夫妻は青い顔をしたままお互いの手を掴んだ。
「仲がえいな。籍をいれて、どれくらい経つ?」
「七年です」
「ほいで、祖父母とも良好かよ」
正雄は「有り難いことに」と緊張した面持ちでそう呟いた。
視線を感じたまま、三人は正雄の家についた。
庭には一人で遊んでいる正と、それを見守る祖父がいる。正は両親を見ると嬉しそうに駆け寄ってきた。
しかし、正は母に、父にしがみつこうとした姿勢のまま固まった。
みるみるうちに顔を青くし、目には涙を浮かべてヨロヨロと後退する。
縁側で座っていた祖父もすぐに顔を青くした。
「どうした?」
不審に思った正雄が己の後方を見、そして言葉を失った。
女が居る。
ずぶ濡れで、髪は顔に張り付き、ポタポタと水を滴らせている。
「居た」
小鳥遊が「ほたえなや」と叫び、不意にその番傘を開いた。鮮やかな赤が女と一家の間を遮るように広がる。
傘が顔に当たったのか、女はギャと声を上げると煙のように消えた。
「塩! 塩と酒じゃ! はよう! はよう持ってこんか!」
玄関から飛び出た祖父母に小鳥遊は叫ぶ。
二人は慌てて玄関に走った。
5
「俺は、ただハンケチを渡しただけなんだ」
大量に塩と酒をかけられた正雄はガックリと肩を落として言った。あそこにいた女はハンケチを落とした女そっくりだった。
「その時、変だとは思わなんかったか? なんでもえい、疑問に思ったことでも、覚えてることをなんでも話せ」
小鳥遊に言われて正雄は頷く。
「ハンケチが濡れていたんです。少しどころじゃない、それこそ持ち上げれば水が滴り落ちていました。だから絞って、渡したんです」
「女はどういた?」
「俯いていました。とても白い肌で、それが異様に恐ろしいと思ったんです。だから、すぐに渡して戻りました」
すると、小鳥遊は頷いた。
「そこで縁が出来たかよ」
「こんなことで?」
問いかけに小鳥遊は再度頷いた。
「目が合うだけでも縁は出来るき」
「拾わなければよかった」
「そがなこと思うな。それが、おまさんのええところやき」
「でも、どうして……。拾っただけで……」
「相手は道理なんぞ通じん。えいか。わしの話をちゃんと聞きとおせ。じゃないと、皆殺しよ」
「どうして、皆殺しなんて」
「言うた。道理が通じんとな。アレはおまさんを連れてくきよ。憎いんじゃない、優しくされて惚れたからだ。奥方なんて目にはいっちょらん。他は景色、花と変わらん。その花がしゃしゃり出るなら、選定するのが当然よ」
「花……。俺たちを、人だと思ってないのか?」
祖父の震える言葉に小鳥遊は頷いた。
「誰も責めちゃいかん。相手が悪かったがよ。喧嘩なぞしてくれるなよ。そうすれば相手の思う壺やき」
祖母の啜り泣きが居間に響く。
「ばあちゃんを泣かすな」
正が小鳥遊の背を叩く。
「そうじゃ。泣かすな」
小鳥遊はそう言って、叩こうとした正の両手を素早く掴んだ。
正は驚いて小鳥遊を見つめ返す。手を振り解こうとしても力強い手がそれを許さない。
「えいか。おまんは男やき。女ぁ守れよ」
「小鳥遊さん……。子供にこんな酷な事を説明せんでください」
「何を言うちょる。子供だからこそじゃ。大事な話だ。えいな、ようく聞け」
小鳥遊の圧に負けたのか。それとも、この深刻さに改めて動揺したのか、正の目には涙が溜まっている。
「此処に悪い奴が来る。わしが止めちゃるけんど、おまさんはここで母(かか)たちを守れ。えいか母と婆が逃げぬよう二人の手を強く握って、声を出さぬよう見張れ。でなければ終いよ」
正は頷いた。ポロリと両の目から涙が溢れる。
「おまさんらも声は出すな。その声を頼りにアレは来る。相手は、自分にとって都合が悪くてもそれを都合良く歪める。嫌だと断ってもそれは遠慮しているからに違いないと解釈する。答えるな。動くな」
「小鳥遊さんは、どうするんですか?」
「どうなるかは知らん。切るか死ぬかよ」
小鳥遊はそう言って、持ってきた番傘を強く握り、そして少しだけその柄を引いた。銀色に鈍く輝くソレがしまわれている。
「刀か」
祖父が言うのを小鳥遊は頷いた。
「わしの家は代々こういった事を生業にしちょる。怖くて怖くてわしは逃げ出したけんど、こうも縁が出来たなら仕方ないきのう」
そうして、小鳥遊は立ち上がった。
「玄関に背を向けろ。わしがおまさんらの前に立ち「えいぞ」と言うまで、けっして話すな。泣いても良いが、鼻さえ啜るな」
一家は、頷いた。
6
逢魔時。
「ただいま、戻りましたよ」
不意に声がした。
玄関に人影が突然映る。
「ただいまァ」
その人影は、女のように思える。
「お土産を持って来たよ。両手が塞がってねえ。開けてぇ」
小鳥遊はそろそろと居間から出て玄関前に向かった。
震える手に力を込め、番傘の――刀の柄を握る。
「ただいまァ」
影は小鳥遊の存在に気が付いたのかさらに声を大きくした。
「家を間違えちょる」
一度、深呼吸をしてから小鳥遊は言った。
腹から声を出しているつもりだが、声が震えているかは分からない。
「そんな事ありませんよ」
「いや、違う。間違えちょる。去(い)ね」
「そんな事ありませんよ」
「おまんは、誰じゃ」
「まささんの妻ですよ」
「おまんは誰じゃ。名乗れ」
「まささんの妻です」
「まささんとは、誰じゃ」
「まささんは、まささんです」
「名前を言えと言っちょる」
「まささぁああん! わたしですよ!」
痺れを切らしたのか、突然バンバンと戸が叩かれる。
悲痛な、けれど吠えるような声は静まり返った家中に響き渡る。
「まささんなんて者、此処にゃおらん」
小鳥遊の言葉を否定するかのように、戸が強く叩かれる。
人の手の影が、何度も、何度も戸にぶつかる。
「どういた? 名を言えんかよ」
戸を叩く手は、次第に歪み形を変える。それは強い力ゆえか、はたまた手の形をした何かが元々柔らかいもので出来ているかは分からない。
五本の指がひしゃげボロリと落ち、手のひらはいつの間にか拳の影に形を変える。
ゴンゴン、とぶつかるのは、手ではなく頭に変わった。
声は開けて開けてとばかり言い続け、小鳥遊の質問には答えない。
「おまさん、夫の名も言えぬかよ」
声は叫ぶ。
「迎えにきたんですよ」
「……切られたくなければ去ぬれよ」
「時間がないのよお。迎えに、ね。迎えにあがりましたよ」
あれほど注意したのに居間の奧から啜り泣きが聞こえた。すると、小鳥遊が触れてもいないのにかちりと鍵が開いた。
「も一度言う、去(い)ね。逝くべき場所に逝け」
小鳥遊は抜刀の体制に切り替える。指先がすっかり冷たくなっている。
ガタガタと音を立てて戸が、ゆっくりと開く。
「迎えにあがりましたよ」
そして――……。
7
一家の前に小鳥遊は足を進めた。一家はみな顔を伏せ、己の手で口を押さえ泣いている。
「えいぞ。終わった」
そう言うと、わっとみなが泣き出した。
「小鳥遊さん」
そう言った夫は、小鳥遊の姿を見てギョッとした。
小鳥遊の顔は涙と鼻水でグチャグチャになっている。彼の顔を見て小鳥遊は気が付いたのだろう、慌てて着物の袖で乱暴にそれらを乱暴に拭う。
「人を斬ったんですか?」
「違うと言えば違う。そうと言えばそうだ」
小鳥遊がそう言った瞬間、彼の膝が笑いそしてドカリと彼は座った。そして、彼は絞り出すかのような声で「怖かった」と呻いた。
「それで……。どうなったんですか」
「まだ終わっとらん」
小鳥遊はそう言って、咳払いをした。
「明日の朝、塩を持ってきてわしと出掛けとおせ。みなじゃ。三十分もかからんき、すぐに終わる。そうすればこの件は全部しまいにゃ」
それを拒む者は、いない。
一家は涙と鼻水でグシャグシャにした小鳥遊に、そうとう同情したのだろう。家族は「泊まっていけ」と言い、彼に夕飯だけではなく、風呂と布団をも提供した。
皆が怖い思いをし、同じ部屋で寝る事を誰もが拒否せず同意した。
「小鳥遊さんは、坊さんなの?」
夕飯を食べ終わった正は、和傘の調整をしている小鳥遊を見に訪ねた。
あれほど怖い顔をしていた小鳥遊が子供のようにボロボロと泣いていたことにショックだったのと同時に親近感が湧いたのだろう。いつの間にか、正は彼に心を許している。
小鳥遊は一度、番傘から目を離し、キョトンとした顔で正を見た。
「いんや、わしは違う。わしゃ、書生よ」
「このことも書くの?」
「どうじゃろうな。書きたいと言えば、書きたいが……」
そう言って、小鳥遊は身を震わせた。
「怖くてかなわん」
「勝てたのに?」
「あんなぁ」
小鳥遊は呆れるような笑うような声で言う。
「怖いから勝つしかなかった。負けたら死んじょった。わしだけじゃない、おまさんらも。だから、怖くても勝つしかない」
「僕も戦えば、良かった?」
「いんや、無理に喧嘩をしかけたらいかん。いらん怪我して母を泣かせちゃいけんがよ。そういう時はな。慣れてる奴に頼むのが、一番えい」
「小鳥遊さんみたいな?」
「勘弁しとおせ」
小鳥遊が困り果てた顔で笑ったので、正も釣られて笑った。
「さ。寝るとえいよ。今日はみなで寝るち言う話じゃった。なんも怖がらんでえい」
「怖い夢を見たらどうしよう」
「ほいたら……。ハサミはあるか?」
子供は頷いて立ち上がったが、すぐに小鳥遊を見た。怖いから部屋までついてくれとせがむ目に彼は負け、ゆっくりと起き上がった。
「ハサミでどうするの?」
「コレはなぁ、縁を切ってくれるがよ。大事にされた分だけ悪い縁を切ってくれる。だからな、「悪い夢を見させんで下さい」ち、思いながら頭の側に置くとえい」
「ハサミが?」
「そう。ハサミがよ。ほいでも悪い夢を見るならそのハサミは大事に使われんで鈍ってるかもしれんき、大事に使ってやればえいにゃ」
正は半信半疑で己が持ってきたハサミを見ている。そうして、小鳥遊を見て頷いた。
「でも、寝るまで居てね」
「ほにほに」
「小鳥遊さんは、明日帰るの?」
「わしにも家があるがよ。……明日で全部解決するき、なぁんも心配はいらん」
「明日から一人で寝なくちゃダメかな」
「おまさんは母たちと一緒に寝てもかまわん。それは恥じゃない。母たちも、おまさんを独りで寝かせると気が気で寝れん」
「僕が子供だから?」
「そう。連れて行くには丁度良い大きさよ」
小鳥遊はあからさまに意地悪そうな顔をして笑った。その悪ふざけが理解出来たのか、正は引きつった笑いを浮かべる。
8
次の日、早々に小鳥遊と一家は外に出た。
小鳥遊は誰とも口を利かず、まっすぐ前を見迷いもなく歩いて行く。その先に人だかりがあった。
「見てもえいが、心にくるぞ。気を強く持てる者だけ見ろ。ないなら見るな。拝んでもえいが、同情は絶対にするなよ」
小鳥遊にそう言われて、女二人は顔を背けた。
「何があった」
「土左衛門ですってよ」
「この前の大雨で流れたらしい」
「可哀相に綺麗な女だ」
その言葉に、一家は震え上がった。
そこに転がる女は、両手で一枚のハンケチを強く握っていた。
不思議なことに、そのハンケチは濡れてこそいたが、誰かによって絞られた形跡があった
サポート有難うございます。紙媒体やグッズ作成に使用したいと思います。
