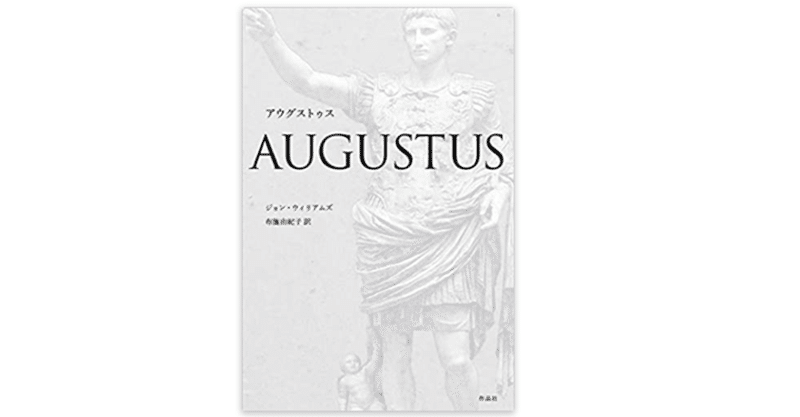
『アウグストゥス AUGUSTUS』 ジョン ウィリアムズ (著) 歴史にもローマにも特に興味がない人も、ぜひ。一人の人間の人生を、まるごと小説に描きこむ、『ストーナー』の作者の、もうひとつの傑作でした。
『アウグストゥス』 2020/9/2
John Edward Williams (原著), ジョン ウィリアムズ (著), 布施 由紀子 (翻訳)
読書人生師匠の師匠、しむちょんが、読後、
「もぉ〜〜〜ほんとに、私なんかが感想言ったらもったいない。黙ります。」と書いた本です。
いや、本当に、そういう本でした。
なんだけれど、感想文を書くことを、唯一、余生のやるべきこととしている私としては、書かないわけにもいかないなあ。そうじゃないと、ほんとうに何にもしない人になるから。
この作者、ジョン・ウィリアムズさんには、『ストーナー』という名作があり、出版当時はほとんど売れなかったのが、何十年かしてから大ヒット、ということで話題になって、そちらは読んだことがあったんですね。
『ストーナー』は、無名の大学教授の、静かな人生を描いた、地味なんだけれど(地味だったから発表当時は売れなかったのだけれど)、素晴らしい小説で(だから何十年もしてから売れた)。
そういういきさつを知っていたので、なんとなく、この作家は『ストーナー』一作しかない人なのかと、なんとなく、思い込んでいたのでした。が、なんと、この『アウグゥストゥス』で、ちゃんと、全米図書賞も取っていたのでした。でも、この小説も、地味、ということで、通には激賞されたのだけれど、あんまり売れなかったらしい。
片方は無名の大学教授、片方はローマ皇帝なのだけれど、どちらも、1人の、静かな,内省的な男の人の、人生のまるごとを、静かな静かな筆致で描くという小説なのですね。まるごとということは、当然、老年、最後のときの心境・境地というものも、描くわけです。そこのところが、本当に素晴らしい小説なのですよ。
ところが、筆者が、『ストーナー』を書き終わったのが、41歳のとき、『アウグストウス』は、43歳で書き始め、50歳で出版している。老いが近づく予感はあれ、まだ、若い。壮年期。この、壮年期なのに、人生まるごとを、老境まで含めて描くことについて、技術的な難易度もなのだけれど、その動機についても、興味がある。その点での達成度が、著しく高い。
どうも、「老境小説と筆者の年齢」問題と言うのは、私にとっては強いこだわりと関心なのだ、というのは、イシグロカズオ論を書いても、いとうせいこうのディストピア小説を論じても、どうしても、そのことが気になるなあ。人は、死ぬときに人生をどう思い返すかを想像して、先取りするために、小説を書くのかなあ。
若い時の仕事への情熱も、恋愛や結婚生活についても、その年齢のときのリアルタイムの描写と、すべてが過去のこととして改めて老境から回顧されるときの視点とが、複雑に、多面的に照らし出されるという、そういう特徴を、この作家は持っている。その点が、無名の人物を描いても、歴史上の偉人を描いても、同じように、本当に見事に描き出されるのですね。
この小説、三章からなっていて、第二章は、アウグゥストゥスの娘、ユリアを中心に、皇帝になった後の時代を描いていくのですが、女性を主人公としても、その人物造形、心理描写、もう、本当に素晴らしい。
この小説、全部が、非常に多くの登場人物の間の書簡か、回想録、その断章の積み重ねで構成されています。ものすごくたくさんの人が出てくるのですが、一人一人の個性だけでなく、人生の軌跡が、読み終わると、鮮やかに印象に残る。多くの家族や友や政敵や、そういう人たちの人生の中に置くことで、主人公、アウグゥストゥスという、理解しにくい(例えば、カエサルと較べると、地味だったり冷淡だったりという印象がある)人物について、複雑かつ魅力的なその人格、内面が伝わってくるわけです。
ものすごくお薦め。大傑作でした。下に、第三章、老境のアウグゥストゥスの手記、手紙から引用します。といっても、ジョン・ウィリアムズさんの、完全な創作です。もちろん。サスペンスでもないから、ネタバレとか気にせず、引用しちゃいます。といっても、これだけ読んでも、今は何も感じないかもしれない。小説を読み進んで、ここに到達したときの、沁みるように、「わかる」感、ぜひとも。味わっていただきたい。
ヒルティアに会って以来、愛には、官能の歓びに惑わされる他者との結合より強くて寿命の長い愛、相手の謎に思いをめぐらし、ほんとうの自分に出会う精神的な愛より、さらに強くて永続的な愛があると思うようになりました。愛した女は年をとるか、男を超えて成長していきます。肉体は衰える。友人たちは死んでいく。子供たちは、赤ん坊のころに親が見ていた可能性を満たし、そして裏切ります。親愛なるニコラウスよ、きみがほんとうの自分を見いだせたのも、あの詩人たちが最も幸福でいられたのも、そのような愛があったからでしょう。それは、古典学者が原典にいだく愛であり、哲学者が概念にいだく愛であり、詩人が言葉にいだく愛です。そう考えれば、北方のトミスで流刑生活を送っているオイディウスも、ひとりではありません。遠いダマスクスで、本を友に余生を過ごすと決めたきみも、ひとりではないのです。このような純粋な愛は、命あるものを必要としません。それが最も崇高な愛の形であることは誰もが認めています。なぜなら、それは限りなく絶対不変に近いものへの愛だからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
