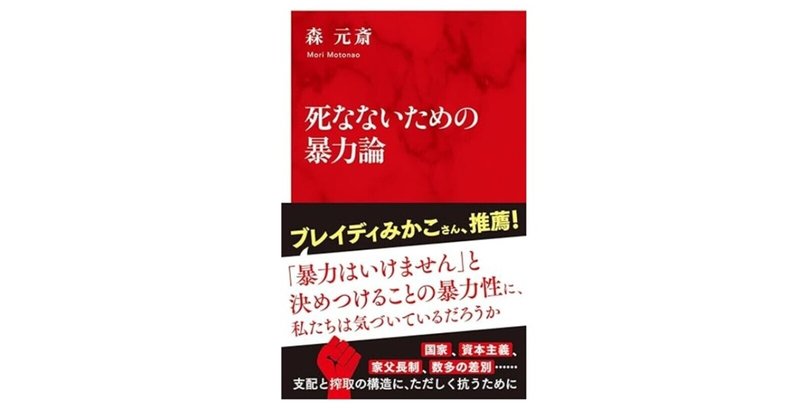
『死なないための暴力論 』森 元斎 (著) アナキストにしてデヴィッド・グレーバー大好きな著者による「アナキズムと暴力」論でした。グレーバー著作背後に常に感じられるアナキズムをどう考えるか、その補助線を頭の中に引くのに役に立ちました、僕にとっては
『死なないための暴力論 』(インターナショナル新書) 2024/2/7
森 元斎 (著)
Amazon内容紹介
ブレイディみかこさん、推薦!!
「『暴力はいけません』と決めつけることの暴力性に、私たちは気づいているだろうか」
「暴力反対」とはよく聞くけれど、じつは世の中は暴力にあふれている。
国は警察という暴力装置を持っており、問答無用で私たちから徴税する(そして増税する)。資本主義は、私たちを搾取し、格差を生み出す。家父長制は男性優位・女性劣位のシステムをつくりあげる。一方で、こうした暴力に対抗して、民主化や差別の撤廃などを成し遂げてきたのも、また暴力である。世の中にあふれる暴力には、否定すべきものと、肯定せざるをえないものがあるのだ。
思考停止の「暴力反対」から抜け出し、世界の思想・運動から倫理的な力のあり方を学ぶ。
ここから僕の感想。
ちょっと関係ない話からスタート。映画「スターウォーズ」の世界ではジェダイの騎士たちが使う力は「フォース」っていうじゃん。あれ、暴力「バイオレンス」とは違って、正義の力だっていうことなんだと、映画製作者は主張したいんだなと理解していたのだな、僕。 ジェダイは銀河共和国の平和維持者で、その力はフォース何だと。「フォース」は暴力じゃあないと。そういえば米国空軍とか「エアフォース」とか言うしなとか。
でもですね、この本ではまず、国家や権力が使う暴力、権力のピラミッドの上位者が下位者に振るう暴力と、それに抵抗するために下位者が使う暴力を区別するわけだな。そこまでは良い。
そういうことを考えた哲学者ジュルジュ・ソレルさんという人がいて、暴力の哲学といえばまずこの人なんだそうだ。で、ソレルさんもね、本書から引用しますね。
〈まず、ソレルは暴力を二つに区分している。「フォルス(force)」と「ヴィオランス(violence)」である。〉
おお、きたきた、やっぱりスターウォーズ通りじゃん、と思ったらばさ。続けて引用。
〈フォルスは「強制的物理力」であり、国家や資本が、戦争や公害や逮捕や抑留、拘禁などの仕方で身体に物理的に強制力を働かせることで行使していくものである。一方のヴィオランスは「人間の生を高揚させる激烈な力」と述べている。ベルクソンという哲学者が述べていた「生の飛躍(elan vital)にヒントを得た概念で、人間と社会を創造的に切り拓いていく能力であり、職人や芸術家の美的な生産活動に顕著だと語っている。ソレルはプロレタリアート(労働者階級によるゼネラル・ストライキを、フォルスを押し戻すためのヴィオランスの好例としている。〉
あれれれれ。フォースが権力が行使するものでバイオレンスは抵抗や創造の原動力、いいものだって言っているな。
ついでベンヤミンの神話的暴力はフォースの方で、神的暴力はバイオレンスの方で、とか、いろいろあるのだが、とにかく、権力関係の上下において、上の者が下に働くフォルスに対して、それに対する抵抗としてのバイオレンスを肯定する、という立場でこの本は書かれているのだな。
やっぱし「スターウォーズ」は米帝・資本主義肯定イデオロギーだからフォース=正義っていうことなのかな。ちょっと混乱して、今までの思い込みが逆転して面白かったという話でした。
さて、本書の本題の方にだんだん入っていく。
最近の日本では、とにかくガンジー的非暴力抵抗が正しくて、上からの非対称で圧倒的な暴力に対しても、抵抗は非暴力でないといかん、それのみが正しいというような言説が世の中を支配しているが、「いやあ、歴史的にも、抵抗運動はたいてい暴力なくしては成功しておらんぞ。インドの独立も非暴力のガンジーだけでなく、武装闘争を繰り広げていたチャンドラ・ボースら多くの活動全体で成し遂げられたし、南アのネルソンマンデラも、非暴力は戦術的に選択しただけで、闘争全体の中では暴力的手段も戦術的に選んだし、キング牧師の非暴力とともにマルコムXの戦いがあったのであるというようなことが縷々語られていくのであるな、この本。
そして、次第に明らかになるのが、この人、アナキストなのだな。なので、僕同様、デヴィッド・グレーバーが大好きなのである。いろいろたくさん引用されている。
ただし僕の「デヴィッド・グレーバーのアナキズムは暴力の否定(フォルスの否定)である」という理解なのだな。僕がデヴィッド・グレーバーの『アナーキスト人類学のための断章 』について書いた感想noteから引用するね。
〈著者は、政府こそ、暴力装置である。とまず置く。マックス・ウェーバーの言うような意味で。とすると、政府を持とうという志向は、すなわち、(今、もし反体制であったとしても)、暴力により他者を支配しようという志向だということ。左翼や社会主義や共産主義も、権力奪取に成功し国家となった瞬間に暴力装置として、たいていは国民を弾圧し、反対派を粛清する暴力性をあらわにする。いや、反体制闘争のさなかでも、内部にも外部にも暴力的闘争を持ち込む。著者は、そうした「異なる考え方の人間を暴力によってコントロールしよう」という志向自体を否定する。つまり「アーキズム、政府の否定、国家の否定」とは、暴力で他者をコントロールしようということ自体の否定なのだ。それを「アナーキズム」と呼んでいるのだ。いや、それ以上のことを言っている。自分と違う考え方の相手に対し、自分の考え方に屈服させて、考えを改めさせようということ自体を否定する。平和的な合意形成のしかたをもとにした社会を志向するのが「アナーキスト」だと、筆者は言う。〉
これに対して、こっちの本の著者、森氏は、「アナキズムには、やっぱり暴力は必要だぜ」的な立場である。
〈さて、本書が書かれるに至ったきっかけを、いくつか述べておこう。一つは、日本におけるアナキズムの流行に対する一種の危機感だ。アナキズムには本来さまざまなレイヤーがあるのにもかかわらず、「ゆるふわアナキズム」みたいなものが日本で流行っており、「これこそがアナキズムなんだよね」という風潮が広がっている。〉
なんというか、権力に抵抗したり、アナキズムを志向する人が、日本では同時に「抵抗は非暴力でなければならない」に毒され過ぎていて、力を失っているのではないか、筆者の言葉を引用すれは「体制に何も圧を与えることができていないのではないか」というのが森氏の基本的意見なのだな。上からの暴力『フォルス」に対抗するには、下からの、対抗的な戦い方が必要で、それは非暴力じゃなくて「反暴力」だというのね。反暴力の戦術的手段として暴力、バイオレンスはありだ、そういう立場なのだな。
第三章「自律・抵抗する、下からの反暴力」
という章では、三つの具体的事例が扱われていて、それぞれ興味深い。
一つ目が、イギリスにおける女性参政権獲得の「サフラジェット」運動。これ、なんとなくは知っていたけれど、中心人物だったエメリン・バンクハーストと、第一次大戦中にそこから袂を分かつ次女、シルビア・バンクハーストの運動のあり方を対比させることで、反体制運動自体がミニ国家化(内部が権力構造化)してしまった母親の組織WSPUに対し、内部が権力構造化しないような運動と組織のあり方でシルビアは運動を展開していった。それを「反体制」ではなく「反操行」と言うんだそうだが、著者の「反体制運動や組織自体を否定するアナキズムへの志向」というのを理解する上で、分かりやすかった。アナキズムというのは反体制運動自体が権力構造化することも避けようとする運動のあり方だ、と言うことなのだな。
二つ目がメキシコのサバティスタ民族解放軍についてで、これは詳しく知らなかったのだが、この本を読んでも、経緯と戦い方と複雑さにびっくりで、一筋縄では理解できないなあ、というのが正直なところ。スポークスマン、マルコス副司令官の、「われわれは無茶苦茶だよ」というのは、ほんとそうだよな。これはね、でも面白いから、読んでみる価値はあるぞ。
三つ目がクルド人の「ロジャヴァ革命」について。グレーバーもこの革命をフィールドワークしていたということで、興味深い。クルド人については、ここのところ埼玉県でのいろいろが話題になっているが、どういう政治的状況から難民となっているかを知る、という意味でも、クルド人、ロジャヴァ革命側内部からみるとどういう状況、事情なのかというのを知るには、読むことに価値はあると思うのだよな。
サバティスタについてもクルドのロジャヴァ革命についても、著者・森氏の立場が「上からの暴力に抵抗するための暴力=反暴力に賛成」かつ「国や政府になろうというのではなく、国や政府になろうとしないアナキズム的運動に賛成」というふたつの立場意見から、極めて肯定的に語られている。そういう立場からの記述だということは理解しながら、どう読むかは自分なりに理解・解釈するのが必要、そういう類の本ではあるのだよな。(鵜呑みにしない、違う立場からの情報も知る、その上で考える必要。)
最終、第四章「暴力の手前にあるもの」
ここでも、グレーバーやドゥルーズ・ガタリらの思想と、具体的な社会的事象を行ったり来たりしながら、国家や資本主義のヒエラルキーの上位者がふるう暴力に対抗するための、必要な暴力というのはあるのだという主張を繰り返している。
そう、グレーバーファンである僕にとっては、グレーバーの著作、『ブルシット・ジョブ』でも、遺作の『万物の黎明』でも、最後にアナキズム的な解決とか理想に向けた何かが常に語られていて、それはどういうことなのかな,という問いが最後に残る、そういう本だったのだが。それを考えるガイド本としては「アナキズムと暴力」という補助線を引くために、なかなか有効な本でありました。
あと、日本における反体制のみなさんが、あまりに何か考えるまでもない前提のように「非暴力」が正しい、という立場なのが「体制に何も圧を与えられない」原因なのでは、という森氏の基本的指摘は、これはリベラルの方たち、左翼の方たち、一度、ちゃんと考える必要があると思うのだよな。
例えば、フランスの農民の、高速道路封鎖ストライキ、みたいなことっていうのが、日本では絶対起きないじゃん。それでいいのかしら、というのは、ほんとに思うのである。そういう意味で、きっとリベラル、左翼系のみなさん、気に入らないと思うけれど、賛成はしないだろうと思うけれど、それでも読んでみてほしいなあ、そう思ったのでありました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
