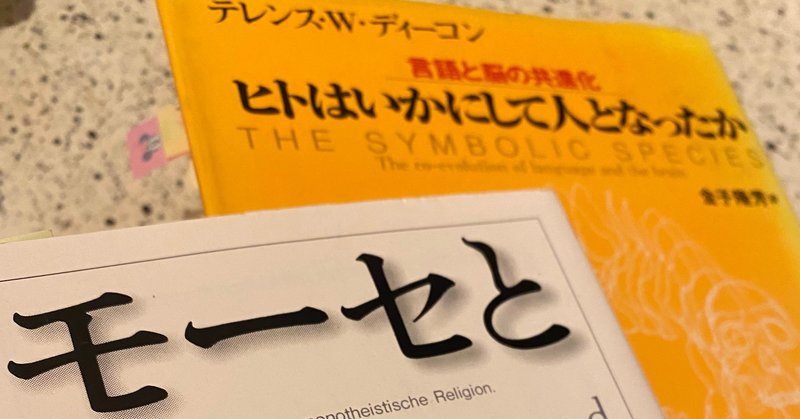
言語思想の極致は感染であり憑依であり
所用でテレンス・ディーコンの『ヒトはいかにして人となったか』を再読していると、おやっ!と思う一節に目が留まる。
「ある意味で言語をヒトの脳を宿主として寄生し繁殖する別の生命形態と考えるのも有益である」(テレンス・ディーコン『ヒトはいかにして人となったか』p.120)
言語が、ヒトの脳に寄生する別の生命である、という記述。
これは単なる「たとえ話」「言葉の綾」を超えたもっともらしさ、事実らしさを生じる記述である。
「言語をウイルスと考えるのはそんなに突飛なことではない。言語は生命のないアーチファクトであり、音のパターンであり、粘土や紙の上の文字であるが、ヒトの脳の活動に入り込む、脳はそのパーツを複製し、システムに集成し、受け渡していく」
そしてこれ「言語をウイルスと考える」である。
ウイルスだなんて、不穏当なことをいうものだ、詩的言語の美を忘れたのか。と言いたくなりそうなところであるが、考えてみれば言語は、ヒトを平然と死に追いやることもある。
言葉には確かに危険なところがある。
だからこそ、私たちはだましだまし言語と共生していけるように、細心の注意を払ってそれをなだめすかしては、悪を善に転じ、善がまた悪でもあることを暴いては、またそれを善へと転じるという両義性の曲芸を演じ続けないといけないのだ。詩の言葉はおそらくそういうところで生きている。
善は悪であり悪ではなく、悪は善であり善ではない。
そういう両義的な「宙ぶらりん」を許すことで、人間は言語という寄生生命を「解毒」してきたフシがある。
じっさい言語を、動物の叫び声のような、現実の何かとの一対一の関係に固まった一義的な信号のレベル一辺倒に留めたままにしていると、圧倒的な善を称する声が、悪と称されるものを死へと追い立てる。
もちろん、ここでいう善は悪ではないという限りで善であるだけで「善とはなにか」という答えを予め持っているものではない。要するに言葉が善だと言い切ってしまえば、それが善なのである。というレベルの善。悪もまた同じである。
言語がウイルスだとすると、言語ウイルスは悪であり、人間は善なる受難者なのだろうか?
この答えは否である。
言語と脳(ヒト)をそれぞれ別々にどこかで完成済のものと考えて、その事後的な関係を、これまたどこかで完成済の善と悪の対立関係に重ね合わせては、なにか「意味がある」かのように感じてしまうことは、たしかにできる。
しかしこれも言語ウイルスが人間の脳に残したひとつの、あくまでもひとつの、複数の可能性のなかのひとつの、インパクトである。
逆もまた真なり、と言う事で、ヒトは言語ウイルスを駆除することなく、それがコピーし続け、増殖させ続ける「意味」というものを、人体生存の糧にできるようになる。一つの意味が増殖し続けるところに、反対の意味をぶつけることで、いうなれば「対消滅」を引き起こす。
そうして誰も見たことも聞いたこともないインドラの網のようなものを、記号の関係だけで壮麗に築き上げ、揺らし、その音を奏でさせ、夜の闇に星の輝を見出したり、夜明けを思ったりすることができるようになるわけである。
ヒトと言語の共進化。言語がヒトでありヒトでなく、ヒトが言語であり言語でないという「ねじれ」の運動を考える。このように考えるということじたいが、言語ウイルスとヒトが束の間の共生体をなしている証拠である。
この共生体は、もちろんヒトの死をもって終わってしまうのであるが、しかし生前の共生体が撒き散らした言語ウイルスの複製たちは、また別のヒトの個体に「伝染」し、そこを宿主として、新しい声と文字を生み続けるのである。
束の間、言語ウイルスの乗り物になった、された、「この私」は、幸福なのだろうか、それとも不幸なのだろうか。
などと問うてしまう、問えてしまう言葉が脳裏に浮かぶこと自体、そう、他ならぬ「それ」が生きているが故なのである。
問いはすでに答えであって、答えはいつまでも問いなのである。
ちなみに、言語をウイルスに例えられるのはどうしても我慢ならないという方には、言語を死者である祖先に憑依されることと捉えるフロイト(『モーセと一神教』を一読することをおすすめしたい。
といっても、オバケとウイルス、好きな方を選べというのも酷ではある。
しかし、オバケは少なくともウイルスではない。
そしてこの「ではない」が、意味するということの全てなのである。
参考文献
こちらがテレンス・ディーコン
こちらがフロイトの『モーセと一神教』
関連note
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
