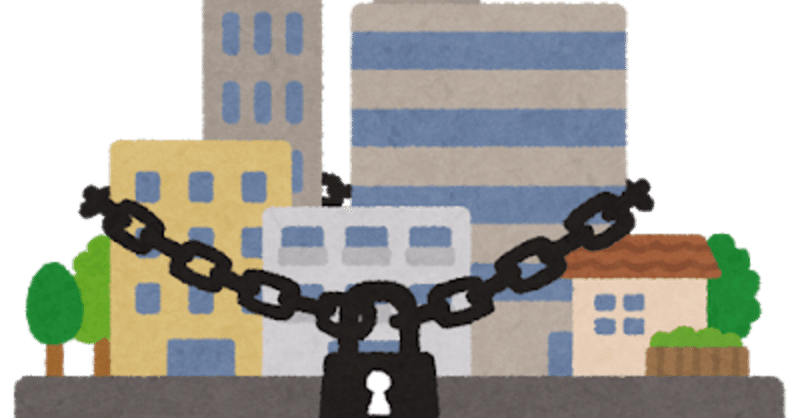
『新型コロナからの気づき―社会と自分の関わりを中心に (3)民主主義は崩壊するのか?(柳澤協二氏)』
[画像]ロックダウンのイラスト。中国が武漢で実践し、小池百合子東京都知事の発言から日本でも話題となったが、第一波の日本では中国のような強制的な措置は取られなかった。
【道しるべより特別寄稿のご紹介】
第2回で、コロナ禍での自己実現のあり方を考察した『新型コロナからの気づき』。
https://note.com/guidepost_ge/n/na5ddfd8cbe31
第3回では、新型コロナウィルスをめぐる体制の異なる国家を考察し、いわば社会・国家の自己実現のあり方に迫っていきます。各国が未知の感染症と向き合う今、民主主義国家が発揮しうる強みを考え直します。
民主主義は崩壊するのか?
コロナという目に見えない、得体のしれない脅威にさらされるなかで、人々は政府の対応の甘さを批判しました。一方、中国は、有無を言わさぬ都市封鎖で、感染の波を乗り越えたように見えます。そこで、民主主義は危機対応において独裁制にかなわないのではないか、という疑問が生まれています。
しかし、人々が実際に感じてきたのは、自粛に伴う不自由さであり、生活の危機です。中国のように、政府が社会を管理してほしいとは、だれも思っていない。
憲法第13条で「個人の幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り国政における最大限の配慮」が求められています。コロナとの関連で言えば、感染拡大を防ぐための自粛要請は、公共の福祉からの要請であり、医療体制を整えて行動の自由を回復することが国の責務だということです。個人の立場で言えば、人にうつさない努力をしながら、人とのつながりのなかで自己実現していくことであって、それを政府が過剰に妨害してはいけないということだと思います。
そうはいっても、状況によっては、今回のコロナに限らず、ロック・ダウンが必要な場合もあると思います。それは、医療体制の崩壊を防ぎ、救えるはずの命を失わないようにするためであって、それに備えた体制を準備してこなかった行政の責任が自覚されなければならないと思います。
福島の原発事故で、住民が強制的に排除される"逆ロック・ダウン"の措置がとられましたが、その一義的な責任は、科学的に想定される地震・津波に備えてこなかった国と東電にある。それと同じ理屈で、コロナも"想定外"ではなかったはずです。

[画像]福島第一原子力発電所、水素爆発後の4号機建屋。初動対応、当初の想定、事故後の危機管理など、日本社会に多くの課題を投げかけた。
(出典:東京電力ホールディングス)
そこを抜きにして、政府に絶対的な権能を与えることが問題なのだと思います。政府が、科学的根拠に基づいて、国民の同意を得たうえで強制する。そこに、中国のような独裁制との違いがあります。国民が納得して強制を受け入れることができれば、そして、国民の側も自覚的な制約のなかで自分を見失わなければいいのだと思います。そう考えれば、民主主義も、まだまだ捨てたものではない。

[写真]かつて日本初代首相・伊藤博文が帝国憲法起草にあたっての研究に訪れたオーストリア・ウィーンにそびえたつ国会議事堂(スタッフ撮影)。1883年に完成した議事堂は、自由と法治に基づく民主主義が誕生した古代ギリシャにモチーフをとっている。民主主義が発達した欧州は今ポピュリズムの台頭により混迷を深めているが、オーストリアが史上初の緑の党との連立政権を樹立するなど、各国が霧の中で最適解を模索している。(2016.01.09 道しるべスタッフ撮影)
危機における民主主義のカギは、国民の同意と自覚です。それで危機を乗り越えれば、独裁制よりもはるかに優れた制度であると胸を張ることができると思います。
執筆者ご紹介
柳澤協二(やなぎさわ・きょうじ)
東京大学法学部卒。防衛庁(当時)に入庁し、運用局長、防衛研究所所長などを経て、2004年から09年まで内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)。現在、国際地政学研究所理事長。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
