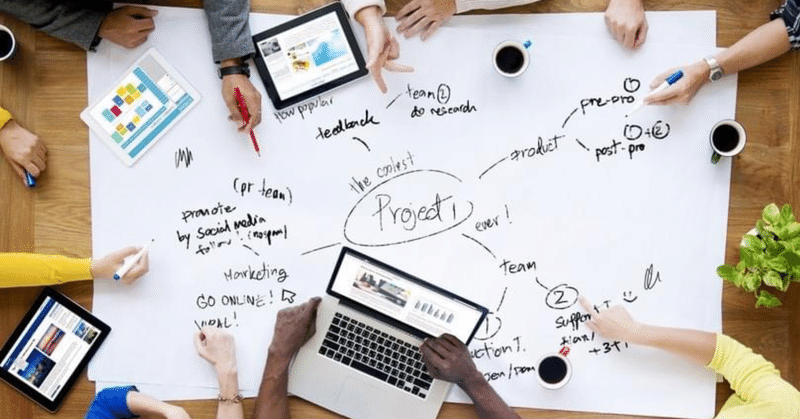
オンラインコミュニティmarginって、どんなコミュニティ?
時々、僕が運営しているオンラインコミュニティの過去記事をnoteにコピペしてアップしています。
普段はメルマガみたいなものなので、割と経営論や支援論などについて僕なりの視点で捉えているものについて書かせてもらっています。
1年くらい前に書いたものをnoteにアップしているわけです。
なんとなくそれをお読みいただければ普段どんな記事が投稿されているのか、ということはイメージしてもらえるのかな、と思っているんですが、じゃあそれだけのコミュニティなのか、というとそういうわけじゃありません。ちょこまかと活動はしています。
ありがたいことに、岡山の片田舎が主な活動の舞台なのにも関わらず、興味を持ってくださって参加してくださる方もちょっとずつ増えてきていて、思いの外いろんな方が見てくれているんだなぁ、ということを実感していますが、それ故過去記事のコピペだけでコミュニティのことを紹介した気になっているのはちょっと雑だな、とも感じています。
なので、立ち上げる際の理念、みたいなものはWEBサイトにも書かせてもらっているんですが、もう少しだけオンラインコミュニティ「ふくし会社margin」というものについてご紹介も兼ねて書かせてもらおうかな、と思います。
興味があればお読み下さい。
僕は支援の仕事、というか福祉という分野には課題もたくさん感じてますが、基本的には可能性や伸びシロしか感じていないんですが、何というかずっと纏わりつくような違和感というか閉塞感みたいなものも感じてたんです。
福祉制度にはたくさんのスキマがあって、でもそこを埋める事には誰も手をかけない。
多くの福祉経営のテンプレートは、いかに効率よく制度報酬を得てやりくりするか、というゲームの中で競ってる。
少なくとも地域の福祉の目指す大筋の目標はそんなに違わないはずなのに、それぞれの事業体は自分達のイデオロギーで支援を行なっていてあまり交わらない。
離退職が多く、業界に人材が残らない。あまり生き生きした顔で支援をしてる人がいない。
支援者さんの顔が見えない。(1人1人とお話しするとすごく個性的で面白い人はいるのに、それが打ち出されも活かされもしてない感じ)
そんな感覚がずっと僕の中のモヤモヤとしてありました。
そんな時、たまたまご近所で子ども食堂をされている団体さんがいて、関わらせてもらう機会がありました。
同じ福祉でも守備範囲が違うはずのその場所に、縁あって就労移行の利用者さんを連れて参加させてもらうようになったんです。
何度か通う中で見えるようになった景色は、子どもも大人もご年配の方も、健常者も障害者も、なんなら支援者とか参加者とかも全く関係なく、みんなで飯を作り、手伝ったり手伝われたりしながら声を掛け合って一緒に活動を作っている景色でした。
その時になんかめちゃくちゃ感動したと同時に、フッと僕の中で目標が定まったんです。
「まち(コミュニティ)をつくる」という。
ありきたりかも知れませんが笑。
これがきっかけです。
じゃあ僕のまちづくりの夢を叶えるためにオンラインコミュニティを作ったのか、というと、それも多少はあるんですが、ちょっと違います。
僕個人の下心としては、まちをつくろうとしても、僕はそんな影響力も認知度も持ち合わせていなくて、当然僕が所属している法人にもまちをつくるなんて体力はありません。
もし本気でやろうと思ったら、僕自身がもっといろんな人に知られないといけないし、まちをつくるなんて発想を応援してもらえるようにならないといけません。
そのために僕自身が活動を生み出さないといけない、という部分については、オンラインコミュニティを作る動機になっています。
ただ、僕個人の目標を叶えるためだけに人を巻き込む活動をする、という建て付けは僕の中ではフェアじゃありません。
その時にずっと僕が感じていた「福祉という分野に感じていた違和感や閉塞感」のことを思い出しました。
多分どちらにしても僕の目標を叶えるために進んでいくにしても、この違和感や閉塞感をクリアしていかないといけないことは間違いなくて、そしてそれが他の福祉に携わっている人達にとっても同じであれば、僕が始めようとする活動にも少しは価値があるんじゃないか、と。
事業所の看板や所属に捉われずに、あくまで1人の「福祉人」として参加する事ができて、できれば個々の思いで集ったり参加したり、もちろん参加しなかったりできるちょっと「ゆるめ」の集まり。
普段の仕事や所属先ではなかなか提案できないような発想やアイデアを出すことや、叶えるためのアクションを起こせる場所。
支援しなきゃいけない事が分かっているのに、「制度にないから」「採算が合わないから」「会社のルールがあるから」みたいな制約で諦める、なんてことをしなくていいような福祉を生み出すこと。
既存の福祉のあり方や経営の考え方に思考停止して倣うんじゃなく、いろんな視点やアプローチにチャレンジすることができること。
そんな事をやっていくために立ち上げたコミュニティです。
ひとことで言うと「福祉をもっと面白くしたい福祉人が集う場所」と言ったところでしょうか。
開設して1年が経ちますが、最近はコミュニティ発信の活動として障害者の婚活支援を始めたり、障害者の性について地域での取り組みを生み出そうとしてみたりしています。
それ以外にも、制度や既存の枠組みの中で疑問を感じたり、窮屈さを感じているものをどうにか解放できないか、と仲間とあれやこれやと議論をしながら実験を繰り返しています。
今の福祉の制度や仕組みの中では埋めきれていない余白を埋め、未来の福祉の可能性の余白を作りたい、という想いを込めて「margin(余白)」という名前にしました。
名前に負けないコミュニティになれるよう、これからもちょくちょくいろんな活動を放り込んでいきたいと思っていますので、もし興味があれば覗いてみて下さい。
▼marginの理念はこちら
▼marginに興味がある方はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
