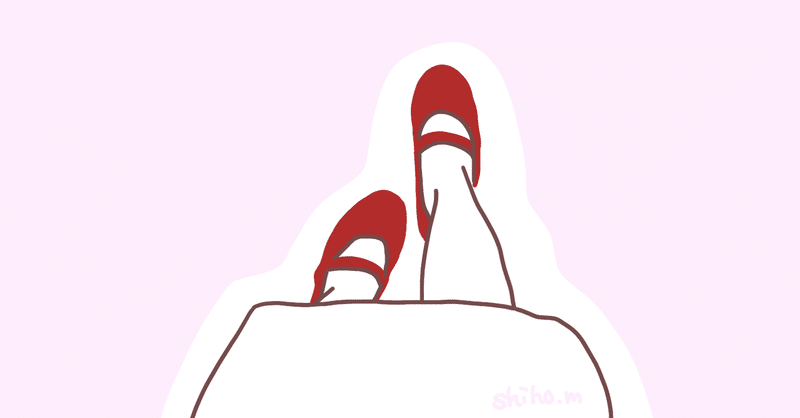
学歴と仕事の関係5
前回までのお話
慶應生だけど就活ナメてたせいでめっちゃ苦労した私、社員食堂等の運営会社に内定をいただく。飲食業未経験だったので、大学4年生の後半はレストランでアルバイト。晴れて2014年4月に入社するが、待っていたのは怒涛の現場でのOJT。自分で選んだ道なのに、「慶應卒なのに飲食業」というところにコンプレックスを感じながら働き、数々の失敗を重ねる。10月からの本配属は希望通り、本社の管理部門になった。
やっと本題
前回までは私の就活からOJTまでの話しかしていなかった。やっと本題である。タイトルにある通り、学歴と仕事の関係。ここからは私の考察になる。あくまで私の経験に基づいたものになるので、考えに偏りがあるのは許してほしい。前の4つの記事を読んで、「この人大変だったんだなぁ」と思ってくれた人もいるだろう。問題はそこだ。
そもそも、なぜ私はあんなに大変な思いをしなくてはいけなかったのか?
大学卒業したらどうなるんだろう
大学生の頃、私は卒業した後のイメージはほとんど持っていなかった。高校生の頃までは漠然と小説家になりたいと思っていた。中学・高校と文芸部に所属し、短い小説を年に4本ほど書いていたのだ。コンテストで賞をいただいたこともある。中学生の書き始めの頃は下手くそで、合評会で先輩方に厳しいことを言われたこともあったが、経験を積むうちに少しずつ上手くなり、自分でも面白いと思うものを書けるようになっていった。大学入学後も同じようなことをするつもりで文芸サークルに入部したが、中高の文芸部とは全く雰囲気が違って面食らった。詳しい話はまた別の機会に譲るが、とにかく私は、小説が書けなくなった。書きたいものがなくなった。そんなわけで、私の小説家になりたいという夢は遥か彼方遠くに行ってしまった。
大学院進学も一瞬考えたが、そこまで極めたい学問があったわけではない。となると、消去法的に就職することになる。「家事手伝い」をさせてもらえるほど私の家は裕福ではない。
当時持っていた就職後のセルフイメージは、キレイなオフィスでカツカツヒールを鳴らしながら闊歩してカタカナ語を駆使している、という典型的な「バリキャリ」だった。まさかキャベツを持って厨房をウロウロすることになるとは思わなかった。
こんな私を愚かだと笑う人もいるだろう。しかし、「私もそうだった!」と共感してくれる方も多いのではないだろうか。
私は、「学校」と「仕事」が分断されていることが問題なのではないかと考えている。
理系分野や専門職になるための勉強をしていた方にとっては、勉強したことが仕事に直結するのでこの感覚はないかもしれない。しかし文系学部出身の人間は、勉強したこととは全く関係のない領域に放り込まれるケースはよくある。例えば私は大学では教育心理学のゼミで統計を使用した研究をしていたが、会社では仕訳を切ったり、助成金の申請をしたり、Excelでマクロを作ったりといった、全く関係ない業務を行なっている。(これらは本配属で本社勤務になった後の話だ)
誤解のないように書いておくが、学生時代にやったことが全く役に立っていないということではない。仮説を立てて検証していくプロセスの組み方や、一つ一つの事象に向き合って問題を解決していく姿勢などは学生時代に培って、今に生きていると思う。
ただ、今の業務はよく言えば巡り合わせ、悪く言えば会社の指先一つで決まったことで、私の意思はあまり反映されていない。いや、というより意思表示できるほど私に知識や意欲がなかった。本配属面談の時だって、希望として伝えたのは、「本社の〇〇部に行って、縁の下の力持ちとして働く皆さんの支えになりたい」みたいなことだ。
最近は「配属ガチャ」というという言葉があるらしいが、自分の仕事内容をガチャに決めてもらっていいのだろうか。学生時代から将来働くことを意識して生きてきたら、その後の人生は違ったものになるのでなないだろうか?
私が言いたいことは、学生時代からキャリア教育を!とか、学生時代にアルバイトを経験しておくべき!とかではない。この問題の根はもっと深く、暗いと思う。
あとちょっと続く!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
