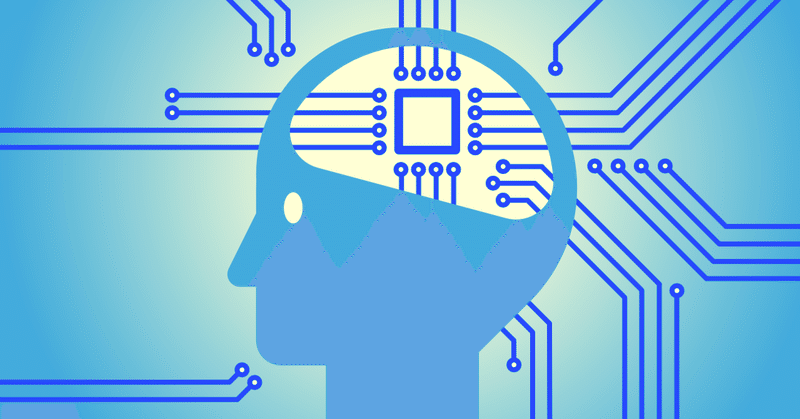
知能の捉え方②
知能の捉え方①では、「知能を1つの指標のみで測定する」流派について紹介した。
「知能を1つの指標のみで測定する」のは、測定対象の指標をIQでおくとすると、数値で算出できるため有用だ。一方で、言語適知能、論理・数学的知能といった項目のみでは、人間の能力の全てを評価することができないと考える者も登場した。
本noteでは、このように考える者たちを「知能を複数に分けて捉える」流派として、代表的な認知心理学者であるハワード・ガードナーの理論について言及したい。
ハワード・ガードナー
ガードナーは、アメリカの認知心理学者であり、ハーバード大学教育大学院の教授である。
彼は、1983年にMI(Multiple Intelligences)理論を提唱した。それまでは、ビネーらによって広まった知能の定義を元にした「言語、論理・数学的な知能」を高めるための教育カリキュラムが実践されていた。しかし、このカリキュラムの場合は、そのような言語・論理・数学的知能が豊富でない子供の可能性を制限してしまっているとガードナーは感じた。そのため、「知能は単一ではなく、複数ある」と定義することで、学習の可能性を広げようと試みた。その過程でMI理論が構築された。
MI理論で、ガードナーは知能を「問題を解決したり価値あるものを創造したりするための能力」と再定義*した上で、より広義な8種類の知能に精緻化した。
*「MI理論に基づく授業開発の試み」(2021)中村、今井、酒向著,p.248より
8種類の知能について説明する。
①言語的知能
概要
話をする、文字を書くなどの能力
発達させると、言葉を使って人を説得できるようになる
鍛える方法
文章を読む
文章を書く
考えたことを話す
②論理・数学的知能
概要
論理的なパターンや関係性、抽象的な概念を理解するなどの能力
発達させると、抽象的な概念を用いながら、何かを論証することができる
鍛える方法
計算をする
質問をする
物事のパターンや関係を探る
明確な目的のもとで何かを検証する
③空間的知能
概要
空間のものを的確に認識するなどの能力
発達させると、色・線・距離などの要素を複合的に組み合わせて認識できる
鍛える方法
何かを組み立てる
図や絵を書く
絵や映画を見る
何か3Dのものを設計する
④音楽的知能
概要
メロディーやリズム、音の高低・速さを認識するなどの能力
発達すると、演奏したり、リズムを作り出したり、音程を聞き分けたりすることができる
鍛える方法
音楽を聴く
歌を歌う
楽器を演奏する
手でビートを刻む
⑤身体運動的知能
概要
自分が思っていることを体を使いながら表現するなどの能力
発達すると、手先を器用に使ったり、体を使って取り組んだりすることができる
鍛える方法
色々なものに触れる
ボディランゲージ・ジェスチャーを使う
動き回る
⑥対人的知能
概要
相手の気持ちを判断して察する能力
発達すると、相手の表情・声をもとに相手の気持ちを判断して、それに対応した反応をすることができる
鍛える方法
色々な人と話す
友達を作る
⑦内省的知能
概要
自分の長所や短所などを把握し、それに応じた行動をするなどの能力
発達すると、自分自身についてよく理解し、自分の考えを尊重しながら、行動基盤を形成できるようになる
鍛える方法
自分の長所や短所を振り返って自己分析をする
性格の類型について学ぶ
⑧博物的知能
概要
身の回りの事象について違いを見つけるなどの能力
発達すると、一度見つけた分類軸を捨てて、違った視点から分類できるようになる
鍛える方法
身の回りの事象に触れる
複数の事象についてどのようにすれば違いを見つけられるかを考える
※ガードナーは、のちに霊的知能や実存的知能などさらに複数の知能が存在すると言っているので、網羅性は担保されていない。ここでは、知能として特筆して重視すべきものが8個あるという見方をしたい。
上記8つの知能において、主にIQに関係するところは言語的知能と論理・数学的知能の2種類のみである。
MI理論は、全ての人は、ある知能に恵まれていなくても、他の複数の知能の組み合わせによって、それぞれの適所で活躍できるという意味で、また、自分が長けた知能の組み合わせを近いすることで、自分に合った職業や趣味を見つけることができるという意味で、教育界に大いに貢献した。
ちなみに、ハーバード大学教育学大学院では、「プロジェクト スペクトラム」と称して、ガードナーのMI理論を踏まえた教育カリキュラムの開発が行われている。
参照
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/6/61578/20210325142017401772/cted_011_247_261.pdf
https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/affiliate/misawa/download/MISAWA_study1.pdf
http://www1.iwate-ed.jp/tantou/tokusi/jissenhen/jissen_07.pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
