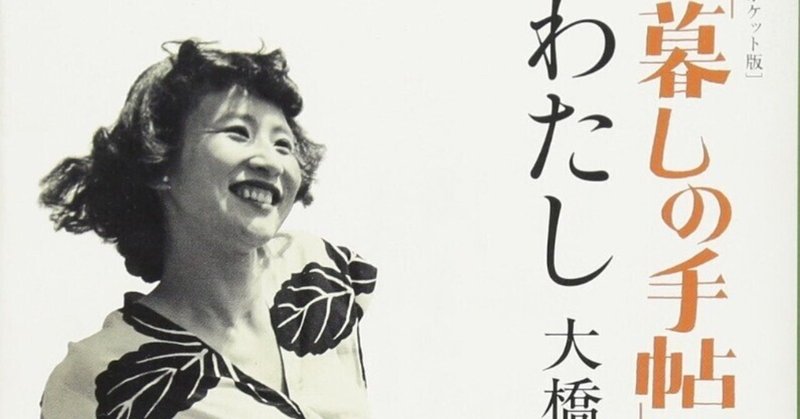
大橋鎭子『「暮しの手帖」とわたし』に読む雑誌創刊の志
大橋鎭子『「暮しの手帖」とわたし』(暮らしの手帖社)↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4766002008/
NHK連続ドラマ小説「とと姉ちゃん」にも描かれた、大橋鎭子『「暮らしの手帖」とわたし』を読了。戦後日本を駆け抜けてきた女性の一代記。幼くして父を亡くしたことから、10歳にして一家の大黒柱としての自覚に目覚める。先ずは銀行勤めから、大学で学ぶ直し、新聞社勤務を経て、雑誌を創刊。ここで名編集者・花森安治との出会いによって、名雑誌「暮らしの手帖」が生まれた。闇市が跋扈する時代に、お洒落な生活スタイルを追求した雑誌は世間から大歓迎された。しかし柳の下に泥鰌は何匹もいる世の中。あっという間に窮地に追いやられた「暮らしの手帖」だが、社長である大橋鎭子は資金繰りに奮闘。この時に旧同僚だった3人が退職金を返上して銀行に融資を認めさせたシーンには落涙。事業って最後は人次第。結果的に「暮らしの手帖」は、社会に変革をもたらせるほどの、押しに押されぬ雑誌に育った。この他にも読んで涙するシーン、好奇心での突貫小僧ぶりに大笑いする場面などが満載。そして何より世話好きは、奇人変人の部類に入るくらいのお節介焼き。そんな彼女の人格は、日本のみならずアメリカでも愛された。雑誌創刊に限らず、仕事には、人生には何が大事かを教えられる一冊。『「とと姉ちゃん」観ておけばよかった』と、今になって後悔している。
実はこの本を読んだきっかけは、今の職場の社長が読んでいたから。読んでいた動機が「新たに引き受けた雑誌を、どうやって盛り立ててゆくかのヒントを探していた」とのこと。それを聞いて『そこまで考えてくれているんだ』と、いたく感激。だったら自分も読まないわけにはいかない。この方に引き受けて頂いて、本当に良かったと実感。編集長も幸せ者である。自分は取次出身であるが、出版業界の大半の人は書籍に従事していて、雑誌の仕事をしている人はごく僅か。それは単品注文単位に動く書籍と違って、大量生産・大量流通を前提とした雑誌は極度に合理化されている結果として雑誌畑の人は数少ない。昨今の雑誌という媒体は、ネットやスマホに押されて急激に凋落しつつある。ハッキリ言って、中小書店は雑誌で食ってきた。書店の減少を嘆く声はあっても、雑誌の振興策を声高に語る人は少ない。取次の仕入窓口に行っても「好調な雑誌は今はない」、業界のご意見番に尋ねても「特に(振興策は)ない」とのおぼつかない答え。今、雑誌における有効な販促策を、出版社や書店のこれはと思う方々にヒアリングして回っている。取材した方々からは、実地に学んだ有効な成功例やアイデアが聞ける。決して打開策が何もないわけではない。そんな中で『「暮しの手帖」とわたし』を読んだことは、故大橋鎭子社長に叱咤激励されたようで、ますます大きな勇気を得た気分になった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
