
『踊れないガール』を文学フリマ東京で発売します(A-31)
2023年11月11日(土)「文学フリマ東京37」にて新刊『踊れないガール』を発売します。1000円です。
私は踊れない。踊れないから沖縄に居場所がないんだ――踊ってばかりの場所、沖縄で踊れないことを自覚する少女の哀しみと成長を描く表題作「踊れないガール」。料理が下手な祖母、自宅警備員の祖父、ニセモノのお金を作る工場で働く元神童の伯父、退職後にヤギを飼う父、頼んでいないのに金魚の作り方を教えてくる老人、泡盛を飲み泥酔するおじさん。沖縄を舞台に様々な人との交流を回想するエッセイ集。

装画は直江あき
A-31 (第一展示場)にブースを出しています。

私が今まで書いた沖縄にまつわるエッセイをまとめています。目次はこんな感じです。

また幻の期間『ぽてと元年』も買えます。
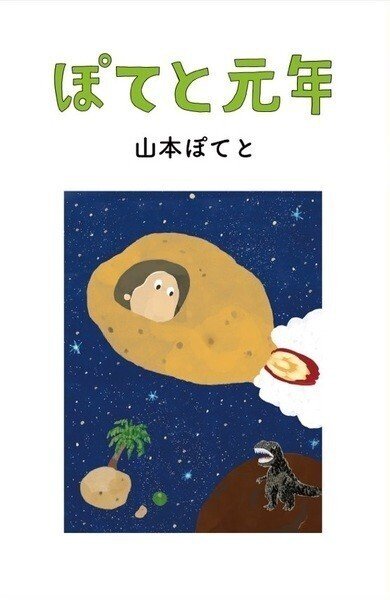
当日は、TBSラジオ「文化系トークラジオLife」番外編Podcast『働き者ラジオ』のしおりも配布予定です。
しおりだけでもぜひ貰いに来てください。
~以下試し読み~
「踊れないガール」
自分でいうのもなんだけど、私は勉強もスポーツもできるピカピカの優等生で通っていて、友人たちともなかなか楽しくやっていて、親や親戚、ご近所との関係も良好だった。でも、故郷の沖縄は居心地が悪い。
「沖縄に帰ってこないの?」
とみんなが聞く。
「仕事がないからね」
と私は答える。 「お母さんもお父さんも寂しいはずよ」 「だからねぇ」と私は私が思う苦い顔をする。ゴーヤー三個分。
どうして沖縄に居場所がないように感じてしまうんだろう。ゴーヤーだって東京のスーパーで見つけたら買うくらい大好きなのに。大人になってしばらくして気がついた。私は踊れない。踊れないから沖縄に居場所がないんだ。
私は踊りが苦手だ。自覚したのは、幼いころだった。幼稚園の運動会で踊ったダンスを見て母は「なんかね、面白いね。ふふふ」と言った。私は子どもらしいかわいらしさについて言っているのだと受け止めたが、だんだんと自分の踊りが下手であることに気がついた。
沖縄では踊る機会がたくさんある。運動会や学芸会だけではない。地域のお祭りもあれば、結婚式もある。それだけではない。あらゆる会が頻繁に催され、会は「かぎやで風」という踊りがなければ始まらず、「カチャーシー」という踊りがなければ終われない。
特にこのカチャーシーがくせもので、フリースタイルダンスなのだ。肩より上に手を上げ、手首をグニャグニャと動かす以外、踊りの形は決まっていない。それゆえに技量の差が露骨にでてしまう。しかも自由参加だ。かといって、本当に自由参加なわけではない。そして沖縄の人たちの踊りを見る目は肥えている。誰が上手くて誰が下手くそなのか、一目で分かってしまう。
例えば結婚式。会の最後にカチャーシーがはじまると、目立ちたがり屋のおじさんが先陣を切り、指笛を鳴らしながら舞台を駆け回り盛り上げる。新郎新婦は笑いながら手首をぐにゃぐにゃする。次におばぁやおじいがゆっくり舞台にあがり、熟練の手首ぐにゃぐにゃを披露する。親戚のおばちゃんなんかが「あい、○○のおばぁは踊りじょうず」と言う。おばぁの踊りは、肩より上に手を上げることすらしない。胸の前で少しぐにゃぐにゃと手を動かすだけで、それは踊りになる。今度は小さい子どもが手をぐにゃぐにゃするとそのかわいらしさに会場が沸く。
そうして、老若男女が少しずつ舞台にあがっていく。曲が終わるまで手首をぐにゃぐにゃし続ける。苦手でも輪の中に入って踊る、それがお祝いの気持ちなのだ。私はだいたい人の後ろに隠れながら、輪の中に入ったふりをして、手首をぐにゃぐにゃする。でも私は一六五センチと沖縄女性の中では長身で、なかなか隠れることができない。腕はどんどん下がり、顔はひきつってくる。下手くそだと思われているんだろうなと考える。背中のあたりがもぞもぞする。曲が終わると、拍手に包まれる。空気が昂揚している。みんな笑顔で席につく。私は背中をできるだけ小さく小さく丸めながら、人の流れに沿って歩く。
そのまま歩いて東京に出てきた。
だからと言って、東京にいても居心地がいいわけじゃない。踊れない事実は、いつも私について回ってきた。もう踊らなくてもいいのに、いつだって居心地が悪い。踊れない私は、ダサい。踊れない私は、人の輪に入れない。だって、世界のリズムに乗れないんだから。でも都会では、踊れなくてもみんなが見逃してくれる気がして、少し安心できる。
踊りが苦手な沖縄の人間がいるならば、サンバの踊れないブラジル人もいる。道行く人から「ばきゅん」と鉄砲で撃たれて、「う、やられた」と言えない大阪人も、ウォッカを飲めないロシア人もいる。モテないイタリア人だっているはずだ。私はときどき彼ら、彼女らのことを想像してみる。世界の端で、背中を小さく小さく丸めながら生きているのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
