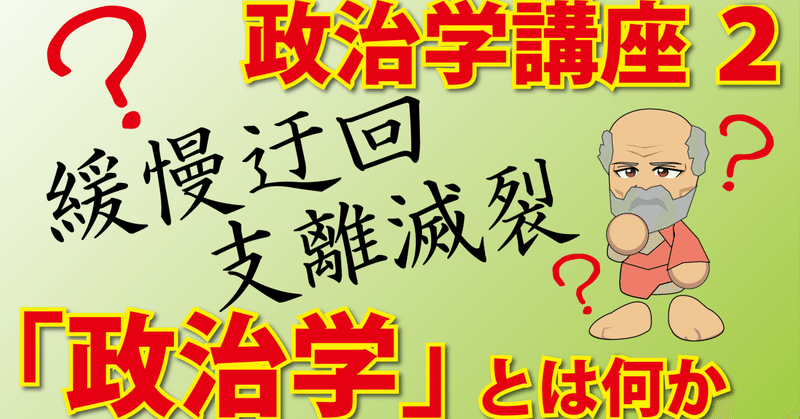
【政治学講座2】政治学とは【体系的知識】
政治学講座(たぶん全十回くらい)
参考文献 中村菊男 著,政治学 改訂第3版,2010
〇Attention〇
最終的に大学の教養科目で習うのと同等の教養が身に付く予定。
最新の研究を反映していない、内容が古い可能性がある。
極力中立を目指すが政治を扱う以上、偏りは避けがたいので注意。
内容を鵜呑みにせず自分でも調べて使える知識にしよう。
第二回 政治学とは
↓動画(簡略)版↓
政治学は国家と称する無形観念の性質および作用を考定する一種の形而上学にして、その範囲最も広漠なるものなり。
故に、学海広しといえども、その進歩の緩慢迂回なる此の学の右に出るもの有らず。学派多しと言えどもその支離滅裂する、またこの学の如きものあらざるなり
(カール・ラートゲン,『政治学』,1893)
はじめに
この講座は「政治学講座」と銘打っている通り、【政治学】について学ぶ講座である。
実はこの【政治学】という言葉、完全に対応する学問が欧米には無い。
日本語の【政治学】が示す学問領域は欧米の「political science(政治科学),politics」よりも扱う範囲が広く、具体的には、本来「政治哲学(応用哲学)」や「政治史(史学)」で扱われるべき領域をも含んでいる。
(ちなみにドイツでは「Staatswissenschaft:政治経済意味で国家学と訳す)」という)
日本の政治学から政治史と政治哲学部分を省いたものを政治過程論というが、欧米でこれに対応する「political process theory,Political opportunity」は政治社会学の影響を受けた社会運動論を指すという。
これは日本が西洋から近代的な政治を学ぶ時、前提となる西洋の歴史や考え方そのものがほとんど知られていなかった事に由来しており、「当時の日本人が近代政治を理解するのに必要なもの全部入り」として学ばれた【政治学】が今日でも引き継がれているのである。

今回の内容はそんな【政治学】の日本独自な部分が多い回になっている。
つまり、政治の歴史とその研究方法である。
「政治」研究の歴史
政治学は第一回で解説した「政治」という現象を研究対象とする学問であるが、前回述べた通り、人間と政治は切り離せないものであり、それに対する学究もまた歴史上、かなり古くからおこなわれて来た。
それは諸子百家や古代ギリシャの時代にさかのぼり、諸子百家の内六家(陰陽家・儒家・墨家・法家・名家・道家)は、いずれも大なり小なり政治的な主張を内包し、また、記録が少ないため詳しくは分からないが、ソクラテス以前の哲学者、ソフィストと呼ばれた人々の中にすらも国家や政治について考えた人々がいた。
中でもプラトンの『国家(Πολιτεία:ポリティア)』やアリストテレスの『政治学(Τα Πολιτικά:タ・ポリティカ)』などは現代まで知られた名著であり、現代英語の「政治」の語源もギリシャ語の都市国家(πόλις:ポリス)に由来している。
プラトンは「哲人王」で有名だが代案として「夜の会議」も提案しており、どちらにせよ統治者は国制・法律の目的である徳・善を追求・護持していける者でなければならないとした。
アリストテレスは前回でも見たように人間は社会的な生き物であると述べたが、その社会は人々の善悪の共有から生まれるとしている。そして、そこで行われる政治は『人間というものの善』こそを究極目的としなくてはならないとした。
さて、古代ギリシャの哲学者が政治問題を考える時、彼らはその解決を倫理に求める点で一致しており、彼らが個人の良い生き方とは何かを考える「倫理」とそれを実現する社会を作る「政治」が一体不可分であると考えられていた事が分かる。
前回、古く政治が祭祀と結びついた「まつりごと」であったと述べたが、古代中華王朝や日本の天皇が祭祀を主宰し儒家が聖人君子による徳治を主張するのと同じく、古代ギリシャにおいてもそれぞれに徳を司る神々に対する宗教的倫理および慣習や思惟からもたらされる倫理的正しさと政治は強く結びついていた。
このように古代ギリシャにおける政治の主題は倫理であったが、古代ローマ・中世ではそれがキリスト教の影響を受けて発展した一方、新たな政治の主題として法律が現れる。
特に東ローマのユスティニアヌス帝は、後に再編され『ローマ法大全(Corpus Iuris Civilis)』と呼ばれる法典を編纂させたが、これは現代まで続く大陸法の基礎となったとされる大偉業である。
契約など民法中心に発展したローマ法に対し、フランク王国で発展した刑法を中心としたサリカ法は中世以降、欧州の相続に大きな影響を与えた事で有名である。
さらに時代が進みルネサンス以降になると、今度はそれまでの宗教的倫理偏重から脱却し、実証主義的な立場から政治が論じられるようになる。
例えば、フィレンツェの外交官ニッコロ・マキャヴェッリはその著書『君主論(Il Principe:イル・プリンチペ)』で徹底的なリアリズムに基づいた権力の獲得と維持について述べ、彼の手段を選ばない政治的態度は「マキャベリズム」と呼ばれている。
マキャベリズムは悪逆非道のようにも言われるが、これを述べた本人の意図は当時の「分裂し貧弱なイタリアを救う事」にあり、そのためには当時統治者がすべきこととされていた伝統的な美徳の養成などにかまけるのでは無く、君主が強力な権力を確立し、非道ともいえる実利の追求を行うべきとしたのであった。
さらに近代にはいると、みんな大好き「社会契約説」が様々な人物によって提唱されるようになる。
とくにトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』やジョン・ロックの『統治二論』、ジャン・ジャック・ルソーの『人間不平等起源論』と『社会契約論』が著名であるが、これらは社会が構成される以前の【自然状態】を仮定し、これを考察する事によって国家は統治者と被統治者間の契約によって形成するに至ったとするものである。
これらは自然状態の解釈や国家を形成する動機に差異があるが、アメリカ独立(とくにロック)やフランス革命(特にルソー)に影響を与えた。
第一回の講義で政府の存在意義は国家の秩序と平和を維持し国民の幸福を向上する的な事を述べたが、これの元ネタが社会契約説で、社会契約でされた契約とは「国民が好き勝手に暴れる権利などを取り上げ、代わりに政府が国民に秩序と幸福を与える契約」である。
社会契約が革命や独立の理論的後ろ盾になったのは、王政が社会契約に反したので古い社会契約を打ち切り、自分達で新しい社会契約を結びなおすという理屈である。
彼らは王政との社会契約を破棄し、新たに共和制政府との社会契約を結ぶことにしたのである。
またこれら三者のうち、二者が革命や独立、共和制革命に影響したのに対し、ホッブズのみ異質で絶対王政の王権を擁護する内容になっている。
同時期、後世、保守主義の父と呼ばれたエドマンド・バークは『フランス革命の省察』でこれを批判し、とんでもない暴政が起きると予見した事が知られているが、実は社会契約説を否定しているのではなく「本源的契約」に基づく容易に切ったり結んだりできない独自の社会契約説を唱えてルソーのそれを批判していた事はあまり知られていない。
エドマンド・バークはこれに反対して社会契約は簡単に切ったり結びなおしたり出来ないと主張し
ちなみにバークはフランス革命は批判したがアメリカ独立は擁護している。
この違いはバークが主張した本源的契約が守られているか否かにある。
少し時期が前後する(ルソーの前)が、モンテスキューの『法の精神』で示された「三権分立」はアメリカ合衆国憲法に採用されて以降、各国の憲法に採用され、今の日本国憲法でも採用されている。台湾など国によっては五権だったりする。
このように、近代以降に登場した考え方の多くは現代でも直接的に大小の影響力を与えている。
なかでも「最大多数の最大幸福」で有名なベンサムの【功利主義】やジョン・スチュアート・ミルの『自由論』や『代議制統治論』、ハーバード・スペンサーの『人間対国家』などは現代でも重要な政治思想である【自由主義】に大きな影響を与えた。
自由主義については、また後の回で詳しくやる。
以上は皆、英国の人物であるが、ドイツのフィヒテは『ドイツ国民に告ぐ』や『愛国主義とその反対』などで自文化中心主義と世界市民主義を両立する独自の国家学を説き、ヘーゲルの『法の哲学』や歴史哲学講義はプロイセンの国威発揚に役立っただけでなく、これらの著作や講義から抽出された進歩史観や弁証法はマルクスとエンゲルスに微妙に誤って受け継がれ、後世のロシア革命や共産主義運動に多大な影響を残している。
例えば、マルクス等は資本主義の破綻と共産主義社会到来を『予言してしまっている』が、本来、ヘーゲル弁証法では予測は出来ても予言はできない。
例えば、「テーゼ:ポールペン、アンチテーゼ:宇宙でボールペン使えない」に対するジンテーゼは「アメリカは宇宙で使えるボールペンを開発した。一方、ソ連は鉛筆を使った」という風になる。
このようにジンテーゼは常に複数存在する可能性があり、未来に対する言及ではそれがどのような形で現れるか確定は不可能である。
事実として資本主義は福祉政策によって修正されながら今でも続いている。
社会主義運動はマルクス以前にも存在したが、終末論的なマルクスの「資本主義の破滅と共産主義による救済の予言」は、その後100年以上にわたり多くの人々を駆り立てた。
特に、エンゲルスは認めた非暴力手段による共産革命を否定する「マルクス=レーニン主義」がスターリンによって確立された後は、狂信による手段の正当化によって世界中で様々な悲劇が生じる事となった。
一方、20世紀前半には社会学者として知られるマックス・ウェーバーが『職業としての政治』をはじめ多くの政治に関する言説を行い、前回述べた政府以外の多様な政治的営みについても多くを論じている。
そして、20世紀後半に発表されたジョン・ロールズの『正義論』は今日でも欧米政治の主要な理論的裏付けとして強い影響力を持っている。
これは、それまで主な政治哲学的規範とされて来た功利主義に代わるものとして主張されたもので、「あらゆる善は各人で指標が異なるため一概に評価計算できない→よって功利主義は不適当→あらゆる善に対して中立的である=正義」という理屈で、政治規範として「公正としての正義」を採用するものである。
これは本来は福祉社会を擁護し正当化するものであり、当時現れたアメリカの新保守主義に対抗するためのより公平な規範を打ち立てる意図があった。
(アメリカの新保守主義は宗教右派を含む「伝統主義」と「経済右派」と「自由至上主義」が反共産主義で結びついて出来たやつで、妊娠中絶、国民国民皆保険や高収入への高い課税に反対する感じの奴である)
しかし、実際には、むしろ、ロバート・ノージックの『アナーキー・国家・ユートピア』で主張された最小国家主義等と共にアメリカの新保守主義的な政策を正当化するのに利用されてしまった。
『正義論』
近現代では特に重要なので少し解説する。
ロールズは人間の価値観がそれぞれ異なるために功利主義的に物事の価値を一律に比較・計算する事は出来ないと考え、それに代わる規範として「公正としての正義」を掲げた。
彼の主張する「正義の原理」は心身財産行為等の基本的な自由が担保され、誰もが参加できる開かれた社会制度を前提とした上で、社会的・経済的不平等が容認されるのはその不平等が地位や職務に付帯するもので最も不遇な社会構成員の利益になる場合に限られるというもの。
具体的に言うと「最も不遇な人の便益になる不平等のみが許容される」。これを「格差原理」という
例えば医師免許持ってる人しか医業が出来ない(職務に付帯し不遇な人を含む皆の利益になる)とか課税の累進性を高めて低所得者の税負担を減らし消費税のような逆進性のある税はやめろ(経済的地位に付帯し不遇な人の利益)的なやつである。
これは本来、格差を是正し福祉国家を擁護する考えであるが、歴史的にはむしろ最下層以外への福祉削減・停止を正当化して中流層の零落を促進し、トリクルダウン(富裕層に富が集めれば貧困層に恩恵を与えるという誤りが確定した説)のような格差拡大政策を擁護する側に利用されてしまった。
独裁超キライなルソーの思想がフランス革命で独裁に利用されたのと同じ流れである。
一方、これに対抗する共同体主義には、チャールズ・テイラーやマイケル・サンデルがおり、主な著作には『自由主義と正義の限界』などがある。
共同体主義は行き過ぎた個人主義に対する反動ともいえるものであり、ロールズのみならず近代の自由主義的な立場ではまず個人という存在があって次にその集団たる共同体があるという前提で議論がされてきた。
しかし、前回述べたように人間は生まれた時から社会に属し、社会によって育てられる以上、共同体が持つ文化や歴史、そこからもたらされる価値観から完全に独立した個人というものは存在しえない。
共同体主義はリベラリズムが人間存在に対する共同体の重要性を軽視している事を指摘しロールズの政治哲学的規範性を否定してしまったが、リベラル・コミュニタリアン論争で知られる彼らの争いは本来共に公平な福祉社会を擁護するリベラル勢力内の論争であるといえる。
一方、アメリカから共同体主義を導入したドイツでは移民等異文化の共同体と相対化された結果、元々あった伝統的な共同体において共有されるべき価値基準が共有されず、むしろ共同体が破壊され分断されるという評価もある。
以上、古代から近現代まで政治にまつわる主要な著書や主張を紹介してみた。
こう見ると政治家や外交官のような実務家だけでなく、哲学者や経済学者、社会学者など色々な背景を持つ人々が政治について考えてきたこと、そして、地域や時代によって政治にとって重要とされていた事が違うことがわかる。
今回の頭で紹介した文は日本で最初に出版された政治学の本に書かれていたものであるが、意訳すれば『政治学は進歩が遅い上、みんなバラバラのこと言ってる点においては他に並ぶものが無い』である。
おなじ「政治」であっても、時代や地域により制度もそれを用いる人の考え方や生活様式も全然違ってくるため、研究者たちの論説に統一性が無くなってしまうのも必然であり、その複雑怪奇さは人間存在に深く結びつきながら人間だけにおさまらない政治学の特色と言える。
政治学と関わりのある学問
これから政治学の研究方法について述べていくが、先に政治学を研究する上で関わりの深い学問を紹介する。
政治学が扱う対象は広範であり、これを正しく考察するには様々な分野から研究成果を援用する事が肝要なのである。
具体的には社会を構成する「人」、社会が存在する「空間」、社会が経てきた「時間」の三つ。
これらを専門に研究する他の学問を学べば、政治についてより深く考え学ぶ事が出来る。
政治について考えるには、まず、それを運用する人間を知る必要がある。
社会に生きる中で人間がどのような反応をするかを知るには心理学・社会心理学、脳科学等の学問の知見が必要となる。
次に必要なのは、国家共同体と土地との関連性を知る事である。
前回「空間的制約」と述べたように、海があれば海運や漁業が盛んになり、それに適した社会組織や文化が生じるというように、社会共同体はそれが存在する場所の自然環境の影響を受けており、これについて知るには地理学の知識が役立つ。
「空間的制約」の話に続くのは「時間的制約」、つまり歴史あるいは考古学である。
今は過去の積み重ねの末に存在するのであり、今を知るにも時間的に繋がった過去からの経緯を知る事は重要である。
また、古くから政治学は歴史と深いつながりがあり、歴史は政治学の研究素材となる各時代・各地域の国家の形成から衰退、政治勢力の興亡といった数々の政治的事象を提供してくれる。
なお歴史でカバーできるのは文字資料が存在する範囲に限られるため、政治の起源、有史以前の原始的な社会組織や人間の原初状態を考えるには人類学・民族学の研究を踏まえる必要がある。
次に、政治学と結びつきが深い学問として経済学がある。
狂騒の20年代とそれに続く大恐慌時代を見ても分かるように、経済は国家や国民の生活、政治に大きな影響を与える。
もともと経済学は古代から政治学の一部とされており、19世紀に経済学として独立するまでも政治経済学(political economy)と呼ばれていた。
ちなみに経済の語源となった経世済民も元は経済に限らず政治一般を対象とした話であった。
この他、世論調査などの量的観測やデータの分析には統計学が必須である。
政治学の研究方法
政治学は自然科学と違い、実験して確かめるというのが難しい。
最近は実験政治学というのもあるが、世上で行われる政治現象においては一度起こった現象を同じ条件で反復する事は基本的に不可能である。
例えば、ある国である政策が導入されたとして、別の国で同じ政策を導入する場合でも、元の国と別の国とではそれを構成する国民やその文化や生活様式などが異なってくるため、全く同じ前提を用意する事ができない。
もし同じ国で二度同じ政策をやるにしても、その国には前回の経験が残っているため、前回と全く同じ結果になるかは未知数である。
仮に今、再びナチスに権力を掌握させようとしても、それを防ごうという働きが起こって上手くはいかないであろう。
それからナチは社会主義者を攻撃した。自分の不安はやや増大した。けれども自分は依然として社会主義者ではなかつた。そこでやはり何もしなかつた。
それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、というふうに次々と攻撃の手が加わり、そのたびに自分の不安は増したが、なおも何事も行わなかつた。
さてそれからナチは教会を攻撃した。そうして自分はまさに教会の人間であつた。そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであつた。
閑話休題
そんな政治学の研究手法としては、まず「比較政治学」がある。
これは各国の政治形態、統治制度・政治行動・紛争・経済発展等の原因や結果を比較検討する方法で、現在でもポピュラーな手法である。
比較する事で、それぞれの特質や共通点を洗い出し、異なる政治制度になぜ類似点や相違点があるのか、またそれらの制度間に発展の変化がどのようにして生じたのかを明らかにしようとするものである。
次に社会学・社会心理学の見地から心理の働きや社会との関連から政治現象を見ようとする「社会学的・心理学的アプローチ」。似たものに政治心理学(社会心理学)と社会政治学(社会学)がある。
そして、古典的な「演繹的アプローチ」。
これは政治とはかくあるべきという政治原理を想定し、それに基づいて理論を展開するやり方である。
政治学研究の困難性
既に述べたように、政治学の研究は他の学問に比べて遅く、政治に関する学問は古代ギリシャからかれこれ三千年近く存在するにもかかわらず完全な体系化が未だにできていない。
この原因には次のような政治学特有の困難が挙げられる。
1.政治学が研究対象とする政治そのものが非合理的であるため、これを合理的に説明する事が難しい。
人間は非合理な行動をとる生き物であり、割とよく社会運営にまで非合理を持ち込む。雀を減らして害虫の天国を作ったり、鉄製品を溶かして屑鉄を作ったりもする。
2.政治についての資料が少ない。
最近は選挙前などに政治意識や政策に対するアンケート調査がされたりしているが、過去の政治的事象がどのような議論の経緯・政治意識で起きた物かは限られた史料から推測するしかない。
歴代中華王朝の史書などは次の王朝(滅ぼした側)が編纂するのが通例で修正や誇張が当然に入っているし、その当時の国民が政治現象に対して何を思ってたかはそもそも記録が残ってる方が珍しい(この点、日本は庶民や文化人の日記資料が多い)。
3.研究者が党派感情や権力者へのおもねりから偏向する恐れがある。
政治に関わる事で政治現象についての経験的知識を得られる一方、党派性にとらわれて正確に政治現象を把握できなくなったり、権力者や党に忖度した発表をしてしまう場合もある。事実かどうかは置くとしてカール・シュミットはそのように見られた人物である。
4.個人の先入観や偏見により客観性を失う。
政治学のような社会科学は民族的偏見や個人的な好き嫌いが入る余地が大きい上に実験で確かめられる自然科学と違って是正する手段に乏しい。
本人が自覚していない場合も多いので、非常にやっかいな問題である。
社会学者の話になるが、”夫婦同姓は江戸時代の風潮を引き継いだのではなく軍国主義と家父長制の押し付け”という主張を通すために氏姓が持つ戸籍と名乗りという二つの側面の内、都合の良い方を使い分ける(近世には同氏の名乗りがあり中世には戸籍が無いが、夫婦別姓は戸籍上の問題なので日本はずっと夫婦別姓と結論)というのがある。
5.時間的空間的制約によっても偏見や党派性を帯びる。
例として、モンテスキューが黒人を滅茶苦茶差別していたのはよく知られているが、これは本人の資質に完全に帰されるものではなく、当時の常識、世界状況や白人と有色人種の地位などといった偏見を生じ肯定する環境の影響を差し引く必要がある。
6.用語が統一されておらず多義的で曖昧である。
今回のはじめに【政治学】が指す学問が欧米と完全一致しない事を述べたが、国家・民族・自由・民主主義などの言葉も論者によっていろいろな意味、文脈で用いられる事がある。
例えば、次回「国家」についての講義でやる内容だが、国という言葉を政府の意味で使う人が多い一方、国には国家、つまり、政府と国民と領土と主権等すべてを指す用法もある。
昔、「保育園落ちた日本死ね」的な言葉が流行したが、この日本を国家の意味でとらえた場合、これは自分や子供、それ以外の全ての日本国民に対しても死ねと言っていることになる。
結論
政治学は研究するのが難しい学問であり、様々な学問の知識が必要な上、忖度や偏見による偏向に陥りがちのため、未だに完全に体系化されておらず、昔から、色んな論者が色んなことを言っている。
こう見ると政治学って、あんまり大したことないような気もするが、刻一刻と変化している今日の社会情勢と人間存在に対し、政治を研究し理解しようとする試みは、変化を理解し対応する手段を考え、また望ましい変化を考えるにあたり必要なものといえる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
