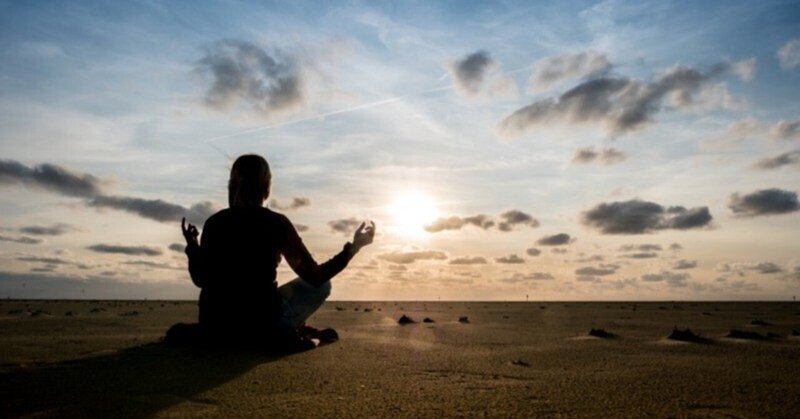
読書履歴#10_日常の気付きを研ぎ澄ませる
読書期間 2022年3月16日~3月19日
はじめに
近所の本屋をぶらぶらしているときに見つけた本です。
ピタゴラスイッチ、解きたくなる数学など超有名な佐藤雅彦さん(表現研究者)の単行本です。
佐藤さんの本はいつも気づきが多くて、読んでいて楽しいのですが、今回は佐藤雅彦さんの思考の秘密を探ってみたいと思います。
日常に潜む「不可解」に焦点を当てた27編の内容です。
まとめるというか、いつも様に私の備忘メモ(兼、内容のブックマーク)です。
佐藤さん独自の表現での楽しみ方があるので、面白そうと思った方は是非手に取ってみてください。
文字数:約6,000
参考図書
①たくらみの共有
・ふと目にNHKの大河ドラマを「なぜ観たのか?」の疑問からスタートし、ドラマ放送界の”企み”に注目
・企みが一体感を生むという気づきから著書の中学生当時の父兄参観の記憶をたどる(担任の先生の挙手の工夫)
・情報化社会でSNSの台頭などは「個の偏重」を引き起こすと説き、みんなで何かを成し遂げる大切が減っていると考察している
②敵か味方か
・とあるシンポジウムで「かつての教え子」と対面した話と「電車でたまたま見かけた男性」の話から、印象の残り方に注目
・二人の過去の記憶を探ると良い印象だったか否か(味方かどうか)の違い
・人間には野性的に判断する機能がまだ備わっている
③おまわりさん10人に聞きました
・道端で道を尋ねる女性とおまわりさんのやり取りについて、筆者が印象に残った地図の収納場所について注目
・他の10名のおまわりさんにも調査をしてみて、それぞれ地図の収納に工夫があることが分かる
・暮らしの多様性を埋める工夫こそが人間的で暮らしをより良いものにする
④~と、オルゴールは思い込み
・オルゴールの蓋の開け閉め=On/Offと、幼少期に蓋の代わりに指でレバーを押し、オルゴールをOffさせていた記憶に注目
・指でレバーで押す=蓋が閉められたとオルゴールに思い込ませると言い換えている
・人間も同じく思い込みにより、内部状態は切り替わり認知に影響をしていると自身の仮眠の経験を基に考察している
★⑤物語を発現する力
・表現研究者という立場上、「物語性」から逃げることはできず、「物語」とは我々にとってどういう意味があるのか?という疑問からスタート
・何気ない大小の三角形が二つ並んだ絵を1枚見てもよく分からないが、それが何枚かに連なり動きがつくと物語を創造する
・このことから「物語を生み出す能力」=目の前に現れた一見不可解な出来事群に対して、納得できる筋道を与える生きていくための力と考察
・この考察と自らの餃子屋の30年の出来事を照らし合わせて検証し、断片の持つ不可解さは物語が開始し、満足感さえ生まれていると気付く
→「物語の創造能力は、断片的な情報群を一件落着させ、禍根を残さず新しい未知に向かうことを可能にしている」と定義
⑥中田のスルーパスと芦雪
・中田英寿が行った、自分は何も触らずにパスを届けるスルーパスと長沢芦雪の「白象黒牛図屏風」からクラっと来た感覚について注目
・中田のスルーパスはパスではあるが、何も触っていないという点ではパスの定義に当てはまらない、芦雪の屏風もほぼ白紙の1枚が含まれておりそれ1枚では意味を失う点に共通点がある
・新しい物事を覚えるのは、その枠組みや繋がり方を増やしていることと同じと説き、人はその枠組みを固定化したり、繋がり方をパターン化しがち
・スポーツや芸術は枠組みの固定化や繋がりのパターン化を壊し、新しいそれらを見せてくれる
⑦もう一人の佐藤雅彦
・同姓同名のトラックドライバーが近くにおり、そのトラックに「私、佐藤雅彦は安全運転を守ります」とプレートを貼り付けていた
・同姓同名はたくさんいるが、このプレートの文言と自分の名前が填り、印象に残っていた
・近くの歯医者にもその同姓同名の人が通っていることが分かり、思いを馳せる話
⑧想像料理法
・韓国への海外出張の帰りに空港で買った冷麺を食す時の話
・その冷麺には、作り方がハングル文字でしか記載されておらず、数字と絵だけで想像でレシピを作り食した
・韓国からの留学生に訳してもらったが大筋あっていたが、疑心暗鬼で食す冷麺も悪くなかったと考察(結果冷麵ではなかった)
※これだけ読むと意味不明ですが、本書はよりユーモラスに記載している(あくまで自分の備忘メモ)
➈広辞苑第三版 2157頁
・20年振りに広辞苑の2157頁(へそくりのページ)に挟んであった、1万円札を見つけ、過去の自分が未来へのいたずらを仕掛けたことを思い出す
・そこからProjectという言葉を連想し、Pro(前に)+ject(投げかける)が語源であることから、未来に投げかけるという意味合いで使っている
・この真意はProject=「将来にその価値が発現されることを強く意識した活動」と定義し、自分たちの目線が目先のことだけに向けられ、スポーツでいうルックアップができていない状態になるのを防ぐ目的
・さらにそこから未来へのいたずらを企画し、未来を創る話をしている
⑩この深さの付き合い
・長年使っていた愛用の万年筆を落としてしまい、修理したが前の書き心地に戻らなかった経験に注目
・ここから二つの気づきを得ている
1、人は目の解像度よりも、触覚の解像度の方が遥かに高い
2、ものや人との付き合い方に深さがあること
・人間には外側と内側に殻を持ち、内側まで来るかどうかは深さで決まると説いている
⑪もう一つの世界
・エレベーター待ちで、エレベーター内部の監視カメラ画像を見ることができるシーンでの一幕
・何気なく眺めていると、そのカメラに自分が映って驚いたが、これは単にエレベーターが待っていた階に降りてきただけだった(カメラはエレベーター入口が映る配置)
・この経験がパラレルリアリティの定義に合っており、まだパラレルリアリティが存在するか、この先存在するかも分からないが、その時の気持ちは用意されていると考えている
⑫ハプニング大歓迎
・とある講演で、準備を入念にしていたがハプニングで進められなくなってしまったことからスタート
・このハプニングに際し、筆者は二つの事を考えた
1、入念に準備した内容に頼るのではなく、いまここで話したい事を話そうと思った
2、ゴルゴ13(⁉︎)の話。ある回でゴルゴ13の行動を全て解析した教授と対峙する場面で、ゴルゴ13はなんでも屋に「自分を攻撃しろ」と依頼した。
これで自分にも予期できない状況に身を置く事で、教授の動きを止めて勝つ話
・ここから、企画について言及。企画は重要だが、準備されたものには限界があり、ある枠の中の考え方
・ハプニングは枠から解放されるチャンスでもあると説く
⑬ものは勝手に無くならない
・図書館で借りた数学の歴史本を気付けば二冊借りていた経験から、ものは勝手に無くならないと気づいた話
・さらにそこから、生後8ヶ月で人間に身につく「物の永続性」について言及
・これを体現するために本書では3つのシーンの絵を紹介し、描かれたネズミの動きを考える人間のクセについて説明
※物語を発現する力とも少し似ている
⑭はじめての彫刻
・とある企画で藝大美術館を巡っているときに、40年前の記憶がよぎった話
・同級生と近所の砂浜に出かけた時に出会った女性の裸像の彫刻
・芸術を志したわけではないが、表現研究者となった今、彫刻の記憶に思いを馳せる話
※本書ではもっと淡くロマンチックな表現がされています。
★⑮見えない紐
・筆者がよく用いる作法(プロトコル)についての話
・ここで言う作法とは、例えば絵本の場合、従来は物語があり、それを軸に読み進める作法
・一方で「ウォーリーをさがせ」では、大勢の人々に紛れるウォーリーを探すという作法
・表現研究者とはいわば、「作法」の研究と開拓をしていること
・作法を「話すため、見るため、読むために前提となるきまりや約束事(=プロトコル)」と再定義すると分かりやすい
・良いプロトコルとは電話の「もしもし」のように無意識の存在にならないといけない
・作法は単に頭ごなしの約束事だけでなく、人間の習性にある程度沿ったものでなければならない(文の並びを実例にしている)
・当然のようになってしまっている作法も再度捉え直すと、体験できなかった新しい表象が潜んでいることもある
⑯ふるいの実験
・暮らしの手帖で紹介された実験
条件1:対象者は40歳以上
条件2:眼鏡またはコンタクト
条件3:女性
条件4:ご主人が銀行関連の人
条件5:一男一女の人
条件6:入院して手術したことのある人
条件7:海外渡航歴なしかつ介護を家族で行っている人
条件8:犬とインコを飼っている人
・この条件を全てクリアする人はいましたか?
⑰言語のはじまり
・フランスのアヌシーという町の国際アニメーションフェスティバルでの一幕
・ある夜にフェスティバルにインスパイアされて良いアイデアを思いついたが、よりによってメモするためのペンがなく苦悶しながら、眠ってしまう
・翌朝目覚めて、ホテルにある備品が意味深に並べられており昨夜のアイデアを思い出すことができた
・ことばとは『象徴機能を持った単語をある順序で組み合わせることによって、世の中の森羅万象との対応をつけるシステム』という、岡ノ谷一夫氏の定義を思い出した話
⑱無意識の引き算
・近所の有名な豆大福屋でお釣りをもらう時に生じた疑問に注目
・私たちは普段の生活で無意識に楽々やっている事はたくさんあるが、計算となると話は別になる
・キース・デブリン氏はいくつかの引き算をやったとき、人の頭は引き算モードになると紹介
・人間にとって扱いやすいのは、数値で行う情報処理ではなく、形で行う情報処理であると考察している
⑲小さな海
・東京藝術大学の横浜にある校舎までの通学路で見つけた小さな潮溜まりを見た時の話
・そこにいる小魚と筆者が育った伊豆半島の駿河湾で遊んだ頃の記憶を重ねるお洒落な話
⑳意味の切り替えスイッチ
・沼津市の千本松原を年始に音楽を聴きながら散歩している時の一幕
・軽快に歩いていたが、暗くなり風も強くなってきた時にミュージックプレイヤーのバッテリーが切れてしまった
・この時、ヘッドホンが音楽を聴くものから耳を寒さから守るものに変わった
・我々は日々多くのことを感じ取っているが、意識して分かっていることはその一部だと考察
※ある日の散歩の話を風情たっぷりに文字で描写した美しい話
★㉑船酔いしない方法
・ある英会話本にあった「ものが二重に見えるんです(I'm seeing double)」と言うワードを見つけたときの話
・使う機会の全くなかったそのワードに、ある映画で出会う
・『暮らしの手帖』は読者の暮らしに役立つ工夫や知識を披露しようと思ったが「汎用性」がなく断念していた(まさにI'm seeing double)が、そんな考え方自体が面白いと編集担当者に励まされた
・ここで著者の船酔いしない方法として、胃が地球に対して上下しなければ良いという気づきの話
・デザインとは「より良く生きるための方法」でアートは「なぜ生きるのか」と考えている
・船酔いしない方法も日常のデザイン
㉒シラク・ド・ウチョテです
・暮らしの手帖の精、シラク・ド・ウチョテの話
・シラク・ド・ウチョテが本の精として読者に自分の説明やお願いごとをする、少し不思議な気持ちになりながらほっこりする話
㉓耳は口ほどにものを言い
・筆者の亡き父が大きな耳を持っていたことから始める話
・一般的に耳は口や目と比べてその人らしさを表すのに決定的と思われていない
・指紋は個人を特定するために使われることが一般的だが、近年耳紋も個人特定として使われている
・介護が必要な母の眠る顔を見て、父の面影から耳に注目した拡がりのある話
㉔板付きですか?
・とある撮影で被写体のモデルから「板付きですか?」と言う質問から始まる話
・板付きは専門用語で、カメラが回り始める時に既に役者がその画角に入っていること
・被写体のバレリーナが発する「板付き」とはまさに舞台という板に付いている役者を意味しており、言葉の意味の合致具合に注目する
㉕一敗は三人になりました
・2010年の大相撲の九州場所で豊ノ島、把瑠都、魁皇、白鵬の4力士の接戦の中で発生したニュースの見出しに注目
・4力士が一敗で拮抗するなか、「一敗は三人になりました」=誰か一人負けたを意味する見出し
・一見分かりにくいが情報に富んでいる
・人とのコミュニケーションにおいて伝える内容は分かりやすい方が良いかというと、必ずしもそうでない時もある
※ここまで読んで、少し気付きを広げる力が付いたのか、大相撲の『大』がなぜついているのかをついつい調べてしまいました
㉖「差」という情報
・ある寒い朝に温めておいたシャツに腕を通した時に感じた感覚に注目
・温度の差が濡れてもいないシャツに湿りを感じさせる情報となっていた
・人は動くもの認識したり、音を感じたりする時に無意識にさまざまな「差」をとり続けている
・ポール・オースターが選んだ「ファミリークリスマス」は、貧しい家族がクリスマスプレゼントを買えない中で、末っ子が失くしても困らないものをコツコツ隠し、それらプレゼントとして家族に渡す話から、プレゼントは新しいものが増える「差」だけでなく、失くしたものが出てくる「差」もあると考察
㉗その時
・2011年3月11日の地震の避難所で妊娠中のスタッフを気遣い、地震、津波、境内、騒乱、人々の助け合いから、筆者のとある記憶と結びつける話
・1854年にロシアから日本に来たプチャーチン提督が津波の被害に遭い、戸田村の人々に助けてもらう話
・100年という時を経て残ったものは災害の爪跡でなく、プチャーチン提督一行のために村の人々が行った助け合いから育まれた造船技術
・2011年にお腹の中にいる子供はこの震災を知らないで産まれるが、悲惨な事実だけでなく、それを乗り越えた先にある具体的な希望に巡り合う事を願う筆者の想い
<所感>
冒頭で説明したようにこの27編は
日常に潜む「不可解」に焦点を当てた内容
です。
私はこの本を読みながらエッセンスだけ抽出しているので、これだけ読むと意味不明な話が並んでいると思います。
でもそれがこの本の面白さだと思いました。
一見、なんでもない日常の出来事から、思いもよらない話との共通点を見つける佐藤雅彦さんはさすが!と思いました。
しかも文章が面白い!
私自身がこの本から得た、最大の気付きは
違和感を大事にし、その違和感が何かを探求することで新しい発見がある
ということでした。
この本から感じる感想は人それぞれと思いますが、必ず何か『気付き』を得ることができると思います。
※★がついたセクションは、特にまた読み返したいと思った印です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
