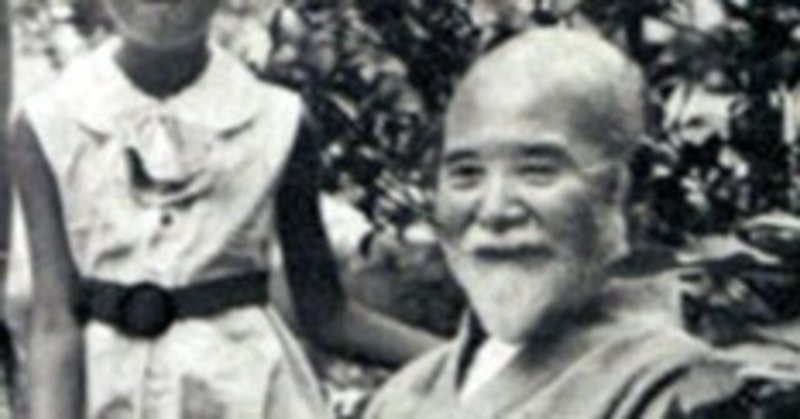
読書履歴#9_大正時代の経済混迷を救った男~髙橋是清~
読書期間 2022年3月14日~3月16日
はじめに
「本読んではnoteにまとめる」ということもだいぶ習慣化できてきています。
小説は読まないのですが、ビジネス書以外にも歴史の本などもかなり好きです。
noteを始める前に読んだたくさんの本もいつかまとめていきたい!と思いつつ、ついつい新しい本が増えている今日この頃です。
今回は歴史の中でも偉人伝に近い形で「高橋是清」に焦点を当ててみました。
高橋是清に焦点を当てたのは、だいぶ前に読んだ以下の本の影響です。
この本もめちゃくちゃ面白いので早くnoteにまとめたいと思っています。
高橋是清に焦点を当てるきっかけになった本
これまでこうした本をnoteにまとめたことがないですし、本で読んで楽しむものだと思うので、
自分の頭のブックマークを作成する
ということを目的に、「人物像」「略歴」「功績」「気づき」という視点でまとめてみることにしました。
参考図書
文字数:約2,700
■人物
・ビジネスの見聞を広める努力を怠らない
・人の頼みごとはことわれない
・物欲が薄い
・一貫していかなることにも、それを本位とし、自分に重きを置かない
・困難な状況に直面する方が、課題解決に向けて努力するタイプ
■略歴
1854年 江戸の芝中門前町(現町名:港区芝大門)で生まれる
1860年 桜田門外ノ変
1867年 是清 サンフランシスコ到着
1868年 明治元年に帰国
1869年 大学南校(現在の東京大学、法・理・文学部の源流)の教官となる
1870年 放蕩生活(自ら志願して無職)
1872年 開成学校(元の大学南校)に入学
1876年 東京英語学校の教官となる、同年妻(西郷柳)を持つ
1877年 西南戦争、コレラ蔓延
1885年 専売特許所長
1887年 優秀な青年(串田、吉田の2名)を連れて、渡米
1887年 高橋是清は米国で特許の研究、その後イギリス、フランス、ドイツに渡り、各国の特許事情について学ぶ
1890年 前田正名からの要望でペルーに渡る(是清、36歳)
1893年 日本銀行入行(下関)
1894年 日清戦争
1900年 日銀副総裁就任
1904年 日露戦争、外債確保のため米、英へ
1905年 9月、日露戦争終戦
1920年 東京株式市場が暴落
1923年 関東大震災
1931年 満州事変
1933年 帝人事件
1934年 6度目の大蔵大臣就任(79歳)
1936年 二・二六事件で暗殺(享年81歳)
■功績
・モーレー博士との生活で知的財産の重要性に気づき、国内で認知されていないときからその重要性を説き、特許庁創設まで成し遂げた
・日露戦争勃発直前から外貨整理を実施し、戦争に必要となり得る外貨を把握していた
・日露戦争で必要な戦費を外債で賄うため世界を行脚し、日露戦争の戦利に裏から貢献した
・東株式市場暴落、関東大震災と激動する中で政府による企業支援を実施
■気づき
・渡米中に奴隷になったという話は有名だが、その背景には当時の日本人が明らかに米国人から見下されていた、という時代背景もあることが分かった。
また、(違法な)契約書が起点になっていることからも、米国には契約文化が根付いていたことも分かった
・帰国後、放蕩生活に陥り大学の教員職も(自ら)失い、無職になってもすぐに重要な職にありつけていることから、当時の日本はいわゆる「できる人」がまだ限られていた、ということが分かる
・渡米中の苦労話が逸話として多いが、帰国してからの数年の職の失い方の方がすごい。この当時はこんなものなのだろうか。
・生活が落ち着いた(1880年頃の共立学校経営など)と思うと、投機にチャレンジして失敗したりと、なかなかのヤンチャぶり
ただ失敗から興味を持ち成功の秘訣を探ることに注力することがすごい
・特許庁新設の際(1888年)に、大きな建物を20年後に増築すると宣言している
「むしろ増築しなければ日本発明界の進捗はおぼつかない」と発言しており、経済発展の礎が知的財産にあることを予期していた
・ペルーの鉱山事業失敗は高橋是清以外の外乱による影響が大きかった。
にもかかわらず、日本国内からの批判をただ受け続けた点に男気を感じる
・日銀に入行する前のステップとして勤めた、日銀新築工事を請け負う建築会社で、在庫管理や支払い条件の見直しなどビジネスセンスが高い
また当時大倉組を仲介して、賃上げや工期遅れが発生した点を直営にし、インセンティブ設計まで実施している
・1895年の日清戦争終了後に、横浜正金銀行(現・神奈川県立歴史博物館)に異動。そこでも外国為替のやり取りなど改革を起している。課題を見つけてそれをクリアする案を見つけるスピードと実行力がある
・正金銀行では系統・派閥があり業務を進めるための規定が限られた人しか見ることができなかった。そこに違和感を持った高橋是清が、規定を見直し完全なものに仕上げて、誰でも閲覧できるようにした
→当時からある、目に見えない謎の組織ルールにも果敢に立ち向かい全体最適を常に意識できる人
・バブル崩壊と大正末期から昭和初期の経済の不況シナリオはよく似ている
・大正9年(1920)以降に、政府が繰り返し行った企業の救済措置が企業の破綻を繰り延べし、当面繕う形になり、結果として財政膨張を続けたことは、2013年以降に日銀が行なっていることと似ている
・蓄財の目的を「精神を磨き一身の品性を高め、ひいては国民全体の品性を高め、さらに子孫の品性を高めるにある」と説いた
・1936年の大蔵大臣当時、勢いを増す軍に対して死を覚悟して公然と批判する勇士は、悪いものは悪いと言える、日本人特有の空気というものを超えたあるべき姿
<所感>
一人の偉人にスポットを当てた良書でした。
いまの時代に最も必要とされるイノベーターの生涯を知るにはとても良い偉人だと思いました。
日露戦争の詳細は、「坂の上の雲(司馬遼太郎)」を以前読んでいたので、色々な場面がリンクし、高橋是清の行脚の話に臨場感を感じました。
変わることを嫌い、上のいう事を正しく聞くことが最も美徳だった時代において、課題を課題と認識し、しかるべく対策も添えた提案力は見習うべきだと思いました。
その他気づきでも印象的な部分をたくさん挙げていますが、特に
正金銀行では系統・派閥があり
業務を進めるための規定が限られた人しか見ることができなかった。
そこに違和感を持った高橋是清が、規定を見直し完全なものに仕上げて、
誰でも閲覧できるようにした
これは今の時代の大企業も参考にすべきだな、と深く印象に残りました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
