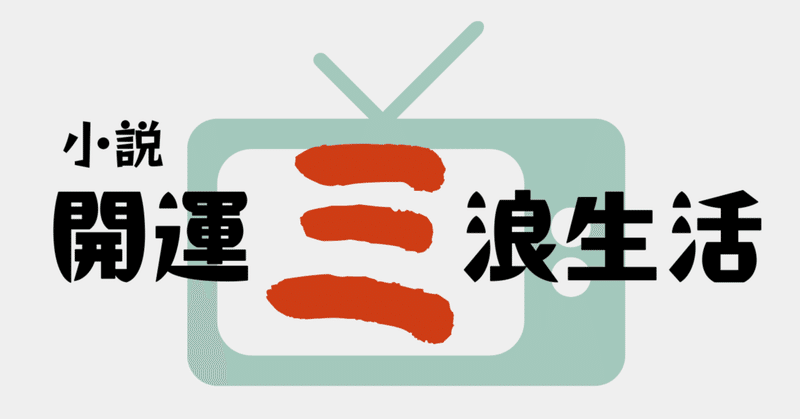
小説 開運三浪生活 18/88「理数科ブランド」
勉強では三年になってもなんとか学年上位をキープしていた文生だったが、学年が上がるにつれ試験の点数は少しずつ下がっていった。世間から「あいつ落ちぶれたな」と言われない順位ならよしとした。なかでも理科はいつもいまひとつで、学年十位以内に入るのがやっとという時もあった。それでも合計点で帳尻を合わせ、悪くても三位にはとどまることができた。授業中の集中力と一年の頃の貯金とプライドで、なんとか持ちこたえている感じだった。
文生はいわゆる進学校への進学を志望していた。隣のS市には進学校が二つしかなく、いずれも公立で、片方が男子校のH高で、もう片方が女子校だった。文生にとって選択肢は一つしかなかった。H高は普通科八クラスと理数科一クラスから構成されており、理数科は地区最難関と言われた。要するに特進コースである。
極端な話、高校を出てどこの大学に進むかよりも、H高の理数科に入れるかどうかのほうが世間の関心事だった。一種のブランドである。普段は話題に挙がらない目立たない家庭から合格者が出ると「あそこの親、息子が理数科なのにちっとも威張ったりしねえ。えらいんだぁ」と大げさにほめそやし、村の有力者の息子が受験に失敗しようものなら「何百万もかけて家庭教師つけたり塾行かせたりしたのに、それでも理数科行けなかった。その程度の頭だったんだ」と、事の真偽も確かめずにこきおろした。
そんな会話が隣近所で交わされているのを、文生は小学生の頃から何度も耳にしていた。おっきくなったら俺も理数科に入んだろうな――とおぼろげながら思い描いていた文生少年は、もし受からなかったら大変なことになる、と戦慄した。中学に上がると、母親が近所の人たちから「フミオちゃん、理数科行くんだっぱい」と言われる機会が増えた。文生だけでなく母親も、世間からの注目にプレッシャーを感じるようになっていた。
文生の中学からの理数科への進学者は、だいたい一名かゼロだった。中学の教師陣にとっても、男子生徒の中でその年一番の秀才を送り込む先が理数科であり、一年の頃から学年上位の常連だった文生はその筆頭候補と目されていた。その期待は当の本人も感じてはいたものの、三年の二学期が始まり冬になっても、受験勉強にはまったく身が入らなかったのである。「まあどうにかなっぺ」と高をくくりながらも、努力しないことへの焦りが文生を包んでいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
