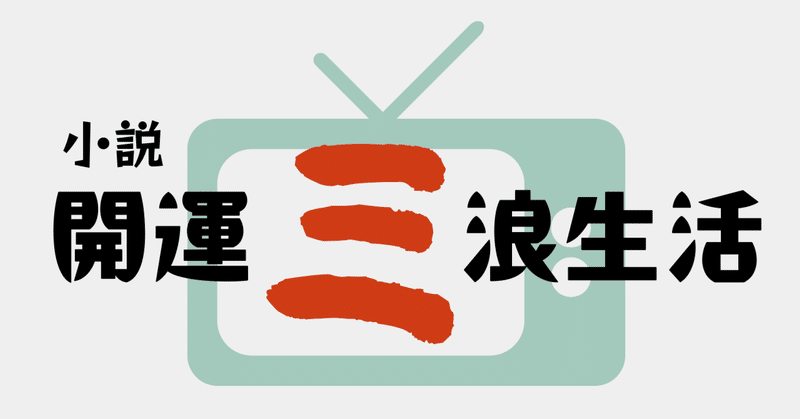
小説 開運三浪生活 25/88「遥かなり、大学スポーツ」
夏休みが明けると文化祭の準備が始まった。文生が通うH高は三年に一度しか文化祭が行われない。どういう経緯でそうなのったか、市内にある三つの高校での持ち回り開催となっていた。文生のクラスはお化け屋敷をやった。三年生は高校生活最後の大イベントということで連日おおはしゃぎし、共学一期生である一年生は女子がいることで華やいでいた。間に挟まれた文生たちの学年はやや盛り上がりに欠けていたが、それでもクラス内は活気づき、文生も楽しみながら準備に参加していた。
お化け屋敷に使う大道具は、クラス担任のデスクがある化学準備室を使わせてもらった。ある日、DIYの一仕事を終えた文生はクラスメイトの野田と化学準備室のソファでだべっていた。書棚を何気なく眺めていた文生の目に、一冊の漫画本が留まった。背表紙には柔道着姿の細目の青年が描かれている。漫画を読む習慣がなかった文生だったが、思わず手に取った。
「柔道なんて、興味あったっけか?」
野田が怪訝な顔を向けた。
「最近、ちょっと、ね」
生返事で文生はページをめくった。
「へえ、フミオ、帯ギュなんて読むのか」
あとからやってきた木戸の一言に、文生は顔をあげた。
「俺らが中三ぐらいまでだっけ? 連載してたの」
なんだ、もうとっくに完結してんのか。文生はちょっと残念がった。出会うのが少し遅かった。
それは『帯をギュッとね!』という漫画の第三巻だった。その後も化学準備室に行くたびに文生はつまみ読みし、文化祭が終わると満を持して古本屋へと向かった。いきなり全巻セットを買って帰ると「漫画を読むなんて不真面目の極み」と信じる母親にバレるおそれがあるため、五冊単位で小刻みに買い足しては一気に読み終え、最終的に全三十巻を読破した。実質、文生が初めて出会った漫画だった。『北の海』よりも詳細に柔道そのものが描かれ、現代の高校生男女の躍動する姿が文生の心を躍らせた。
――今から柔道、始めてみっか?
立て続けに柔道作品に出会ったことで、この単純な男は熱くなった。情報通の野田によると、校内には一応柔道部は存在していたが、よほど人気がないのかそれとも共学化の影響か、部員は二年生の男子一人だけとのことだった。
――そこに俺が入って二人になれば、ある意味救世主じゃねえか。
――来年もし新入生が何人か入れば、団体戦にだって出れる。
――高二で柔道始めた男がインターハイを目指す。熱いじゃねえか。
妄想が止まらない文生だったが、時すでに高二の十月である。ただでさえ幼少の頃から運動音痴で鳴らしてきた自分が半年そこらで使い物になるほど、さすがに柔道は甘くないはずだ――さすがにそのくらいの察しはついた。ならばと、この諦めの悪い男は代替案を自らに提示した。
――そうだ、俺には卓球があるじゃねぇか。
文生が卓球をしていたのは中学三年の七月までだった。団体戦で軍市大会、県南大会と勝ち進み、目標としていた県大会では予選リーグであっさり敗退した。部活引退から受験勉強への切り替えが、文生はなかなかできなかった。中学生活にぽっかりと穴が開いてしまったような感覚だった。
文生はまだ卓球に未練があった。物心ついた頃から運動音痴と馬鹿にされ続けてきた彼にとって、卓球は初めて自信を持ってプレーできたスポーツだった。フォアサイドに浮いたチャンスボールに飛びつきスマッシュを決めた時の快感は、試験で百点を取った時の嬉しさよりも確かな感触で、刹那的で、それだけに中毒性があった。
――俺でも、こんな動きができる!
真夏の自由な日々を持て余すと、文生の足は自然に中学の卓球場へと向かった。今度はOBという気楽な身分だった。後輩も顧問も歓迎してくれたので、居心地は悪くなかった。高校一年の頃にも数回、中学の部活に顔を出すほどだった。
ただ、部活は中学だけと決めていた。理数科に入る以上、勉学最優先にならざるをえない。部活などやっている場合ではない、という感覚だった(実際のところ、クラスの半数近くが普通に部活と勉強を両立させていたのだが)。
あわよくば宅浪を経て、それなりに卓球が強い大学へ進む。そして学科は理系。文生の進学プランが決まった。この野望は、野田にも木戸にも話さなかった。きっと二人ともかなり微妙な反応を見せるだろうし、木戸に至っては「じゃあ、高校でも卓球続けりゃよかったのに……」と冷静でつまらないコメントをしてくるに違いなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
