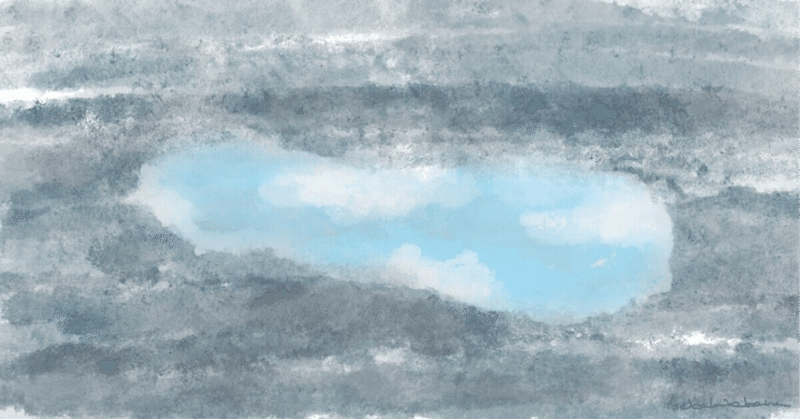
水たまり
まず光があり、次に雷の音が響き、そして、我々の住むこの山間の町は、重苦しい雨雲に覆われ、しつこいほどの雨が、降り続けている。強い雨というわけではないが、ずっと止まないので、降雨量は膨大なものになっている。この町の何処かに貯めこまれた水は、我々の全て流してしまうほどの力だろう。私は、最近再就職した工場の近くで、実家に残っている姉と会った。一帯は、鉄条網に囲まれた空き地と、いくつかの工場しか見えない。排水溝が、ごぼごぼと不吉に聴こえる音を立てている。その隣には、池と見まごう程の水たまりがあった。雨水が泥を溶かし、濁り水となり、なみなみと満たされる。底はおろか、数センチ先も見えない。ひょっとすると、堀のように、百メートルは深さのある溝かもしれない。人と天が地に作り出したその深淵の度合いは、いくら目を凝らしたところで、判別は不可能であった。誰が何の目的で掘ったのかまるで分からない。これは私が子供の頃から、大地に穿たれていた。
「雨が、凄いねえ」
いまさら、興奮した様子で姉は呟き、空を見まわした。
私はその赤いレインコートの毒々しい色と、もう会わなくなって二年も経っているのに、まったく減退する気配のない突飛なセンスに気を取られ、内容は聞き洩らしてしまった。
「何だって?」
「雨の話よ」
私も空を見渡した。全て、灰色だった。
「もう百日間続けて、雨だそうだね」
私は呟いてみた。そうだった。それがどれほど異常な事なのか、姉も私も、この町の住人も、理解出来ていないようだ。工場の灰色の建物の向こうには、ひときわ広い空き地があり、雨に打たれ続けるショベルカーがあり、その向こうには森がある。空き地には、私の目の前にある水たまりほどではないが、大きな水たまりがいくつか出来ている。ショベルカーが掘り出したものだ。数十メートルの深さがあるものもあり、落ちたらきっと死ぬだろう。その水たまり一つ一つが、重苦しい岩の塊のような雨雲を映し出しているだろう。姉が少し表情をこわばらせ、少し脇に寄るように言った。山のように土を満載にしたダンプカーが、私たちの横を通り過ぎた。
私は少し前まで都会にいて、快適なオフィスでデスクワークをしていたのだが、気付いたら、また故郷にいた。どうやら、私の人生に何かが起こっている事は分かっているのだが、私にはどうしようもない事だった。それが、私の人生だった。故郷に戻るなら、実家に住むか、と姉は言ってくれたが、私は断った。私は小さなアパートを借りた。そして、いま目の前にある工場に明日から勤め始めるのだ。姉は、私の勤務先を見ておきたいと言った。
「つまらないところだろ?」
工場の周囲を歩きながら、私は呟いた。何処までも続く気が滅入るような風景。雨によって湧き上がる陰気な土の匂い。唯一、生命力を持っていると感じられるのは、姉のレインコートの赤だけだった。
「ま、とにかく、頑張って」
ありがたい言葉だった。だが、言葉は、どうしても私の心の奥にまで響いてこなかった。あらゆるものと、交感を拒否している何かが、私の心臓付近にあるようだ。それは私の意思で生み出したものではない。
「心の病で退職?」
澤田の口角が上がるのが分かった。
荒れくれ者が多そうな職場だったので、初日から絡まれる事は覚悟の上だった。彼の態度は、心に関する病は、軟弱でオツムだけが発達した奴がかかる病気だと、言わんばかりだ。私は卑屈にならなかったし、憂鬱な表情を浮かべなかった。精一杯低姿勢で、雨雲の上にある、太陽のような笑顔を浮かべた。澤田は私の意外な行動に気圧され、それを補うかのように、私への親密な情を溢れさせた。周囲の男たちにもそれが伝わったようで、態度を決めかねていた彼らからも、友好的な感情、空気が伝わってきた。
「ま、頑張りな」
上手く取り入ったと思った。誰とでも仲良くする必要はない。一番の権力者と仲良くなれば良いのだ。
「しっかし、異常な天気だな」
梅雨でも何でもないのに、三か月も雨という事の重大さが、この男にもわかっていないようだ。だが、私はそんな事は指摘しない。それより、仕事を覚える方が先だ。ここの仕事内容というものは、いまいち、私にもわかっていない。私の勤務地は工場ではなく、そのとなりにある広い敷地だ。ただひたすら、土を掘り、それをダンプカーに乗せるのだ。その土に価値があるのかどうかもわからない。
「プリンどうですか?」
私は差し入れを渡した。土で汚れた男たちがプリンを食べる光景は見ものであった。
「で、仕事だが、ひたすら、穴掘ってもらう」
「ここに何か埋まってるんですか?」
「知らん。何もしらん。ただの土」
私はそれ以上は何も聞かなかった。守秘義務という奴で、一切仕事の目的は教えてくれなかった。
「ショベルカーを使うんですね」
私は窓から見えるショベルカーを指さした。ショベルカーはその鋼鉄の関節をぎこちなく動かし、黒い油を全身に巡らせ、何の目的に使うのかわからない穴を掘り続けている。あれを私が動かすのか、とぼんやり考えた。免許はいらないと言われた。それが正しい事なのか分からないが、とにかく運転を教えると言われたので、心配はしていなかった。
「誰でもできる」
澤田は笑顔で言った。
「初日からはキツイだろうから、一週間は手作業だな。その間、運転を見ておいてくれ」
石などをシャベルで取り除く作業があり、それは手作業だという。
「上から土をかけられんようにな!」
澤田は、ぞっとする事を言って、そして、私が怯える様を見て満足そうにうなずいた。私はそれから、ひたすらスコップで穴を掘った。穴を掘ると、次の日には雨水が溜まっている。それをポンプで吸い出し、続きを掘る。何日も何日も繰り返した。筋肉は使うが、脳は使わなかった。心は癒えもしなかったが、悪化もしなかった。筋肉と連動して、心臓は活性化したようだ。血の巡りが良くなり、心はある種の勢いをつけたのか、私自身に語り掛けてきた。自分が、本当にやりたい事はなんだ? やりたかった事はなんだ? 勉強、仕事、快適な暮らし。人々を便利にする技術。ロケットを使って火星への移住。私のやりたい事は火星に行けば見つかるのか? 火星か、と私は思った。今の私は火星の労働者みたいなものだ。それから、私は私の心に呟いた。自分が本当にやりたかった事とは、この穴を掘るぐらいなのかもしれない。私は私の心にそう言うと、私の心は沈黙した。
仕事を続けていると、私の周囲がにわかにざわつき始めた。
穴から這い出て、顔を上げると、遠くに赤い点があり、それがちらちらと瞬いている。みんなは、同じ作業をしすぎて、幻覚でも見たのかと思っているようだが、それは違う。幻覚でも奇跡でもない。あれは、赤いレインコートを着た少し変わった私の身内なのだと、私にはすぐに理解できた。
「誰だ、あれは」
事務所から出てきた澤田が、呆れ顔で赤い点を眺めている。そして、仕事の手を止めている作業員に、仕事に戻れと注意した。姉は私しか目に入っていないのか、私に向けて頻繁に何かをアピールしている。澤田も察したようで、私の傍に来て、何者だ、と言った。
「姉です」
と私はうつむきながら言った。
彼女の後方の小さな山が、雨に打たれて崩れようとしている。山のあちこちから、どばどばと濁った水流が流れている。
「あんなところ、危ないぞ。しかも妊婦さんがなあ」
妊婦と聞いて、私は驚いた。そんなはずはなかった。
「妊婦ですか?」
「みてみろよ」
目を凝らしてみると、確かに腹部が大きく膨らんでいる。これははたして、現実なのかと私は思った。昨日会った時には、普通の腹であったが、たった一日で生命が宿るものだろうか。いずれにせよ、あんなところに居させるわけにはいかない。
「雨で流されるぞ」
澤田は私の肩に手を置いた。
「事務所に入ってもらえ」
澤田はため息を吐き、私に青い傘を渡す。
私は姉のところに向かった。雨が強く、澤田からもらった細い傘は折れそうになった。私は姉のところまで行き、手招きする。姉の後ろでは水流がとめどなく流れ出している。
「実家からね、あんたの家に行く途中でね、寄ったのよ」
姉が言った。
「そこ危ないからさ、事務所に来てよ」
私がそう頼むと、姉は事務所を見て、顔をしかめる。
「めんどくさい」
「崩れるんだよ」
私と姉の足元は、今にも崩れそだった。互いの傘はすでに少し曲がっている。
「それより、その腹は……」
「タイムカプセルだよ」
「タイムカプセル?」
姉はレインコートを開けると、腹から銀色の近未来的な球を取り出した。その時、私の脳裏に様々な思い出が蘇った。蘇るべきではない思い出も全て蘇った。それは私の全てを吹き飛ばすような、圧倒的な感覚で、現実には雨も水たまりも存在しなくて、私という存在は、過去の記憶だけで出来ているのではないかと思えるほどのものだった。感覚の中で、私は現在の自分を探し続けた。そもそも、私など、存在しないのではないかと思えた。全ては作用と反作用から出来ている。私という球がはじき出され、あとは壁に跳ね返り、また跳ね返り、それを繰り返していただけではないか。
「実家から出てきてね。あんたもう仕事終わりでしょ?」
「中身は見たのか?」
「いいえ」
姉の口角が上がるのを、私は見逃さなかった。姉の心が隠された真実を喋りたがっているように見えた。
「見たんだろ?」
「なんで?」
姉は食い下がる。認める気はないようだ。
「こらこら、喧嘩はやめい」
二人で問答しているのを見かねて、澤田もやってきた。
「早く事務所に来いよ」
「すいませんでした」
私が謝ると、姉も一緒に頭を下げた。
事務所に向かう途中、誰も口を利かなった。
事務所に入ると、澤田は大きく息を吐いた。
「で、なんなんだ?」
「実家に埋まっていたタイムカプセルが、出てきたというんです」
「タイムカプセル?」
姉が机の上に置いた銀色の球状の容器を見て、澤田は首をかしげる。
「ピンボールの玉みたいだなあ」
確かに、巨大なピンボールの玉のようではある。私は急に自分が小さくなった気がした。私だけではない、ここにいるみんなが玩具みたいに小さくなった気がした。
「子供の時の思い出を、入れておくんですよ」
「そんなの、何が楽しいんだ?」
そう言われると、返す言葉もない。このタイムカプセルというものは、何も私が考えたものではない。私も特に面白いとは思えない。時間がこの小さなカプセルの中にだけ留まっている。
「で、何を言い争っていたんだ?」
「姉が、私より先に、中身を見たのではないかと」
「それがどうした? 別にかまわないじゃないか?」
確かに、問題はない。姉が先に開けて、先に中身を見てはいけない。そういう約束をしたわけでもない。ただ、姉が過去を変えるかもしれないと思ったのだ。過去は私の頭の中で変容している。このタイムカプセルは過去を証明してくれる手段の一つだ。もし、姉が中身を開けて、子供の頃、私が姉へ酷い事を言ったので謝罪した、という記録を入れたとしたら、私は姉に謝罪した事になってしまうのだ。私が覚えていても、覚えていなくても関係が無い。
「で、何を入れたんだ?」
「それが、覚えてなくて」
過去の事など、私は思い出したくもなかった。しかし今、強制的に思い出されてしまった。今は死んでしまった父に事ある毎に殴られていた。今それを思い出し心を痛めるという事は、私にとっては実体のない幽霊に殴られているような気分であった。当時は、確かタイムカプセルが流行っていたのだろう。私この銀の器に、何かを詰めたところまで覚えているのだが、何を詰めたのかはさっぱり忘れてしまった。だから、姉に開けられては困るのだ。私の人生は私のものにしたかった。だが、それは幻想にすぎない。私は全てを正確に記憶しているわけではない。私自身が私の人生を歪め、他人も私の人生を歪めている。私の意思など、何処に存在しているというのか。
「なんで今さら出てきたのかなあ」
「そりゃ、雨に決まってるでしょ。雨で土が流れてね」
「結局、開けたくないのか?」
澤田が首を傾げる。
「姉が中身を変えていなければ」
「だから、そんな事してないって」
それを証明する手立ては何もない。水掛け論になってしまう。
「どうしようもないなあ」
澤田が深いため息をついて、銀の器を撫でる。
「また、埋めるしかないだろうなあ」
澤田が言うと、私と姉は顔を見合わせた。
我々は、私が掘った深い穴の前に立っていた。雨が降り注いでいるので、巨大な水たまりとなっていた。水の表面には茶色く染まった雨雲が見えた。
「いいんですか?」
私は胸にタイムカプセルを抱いていた。姉は無実を言い張ったが、私には確信があった。姉の表情に浮かんだいくつもの特徴を私は見逃さなかった。何度も見た嘘の兆候だった。姉も年をとった。その癖は過去の名残かもしれない。それでも姉が嘘をついている確率は五分五分といったところだろう。
「どうせ埋めるんだ」
澤田が言った。掘ったり、埋めたり、本当に何の仕事なのかさっぱりわからない。この業務に関しては守秘義務がある。いくら考えたところ、答えなど出るわけがない。姉が私の過去を書き換えようとした件と同様に、いくら考えても、分かるものではない。私は銀の球を水たまりの中に投げた。水しぶきが上がり、濁った水たまりの底に沈んでいった。
「あんた、逃げたね」
姉は腕を組みながら言った。過去から逃げたと言いたのだろうか。私は何も言い返さなかった。
「今日はもう仕事終わりだ。姉ちゃんと帰りな」
我々は澤田たちに見送られながら、家路についた。
姉と家に帰るなんて何年振りだろうか。
「まあ、仕方ないか」
姉が言った。雨が止む気配はないが、もしかしたら明日止むのかもしれないと、ほんの少しだけ信じられる瞬間があった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
