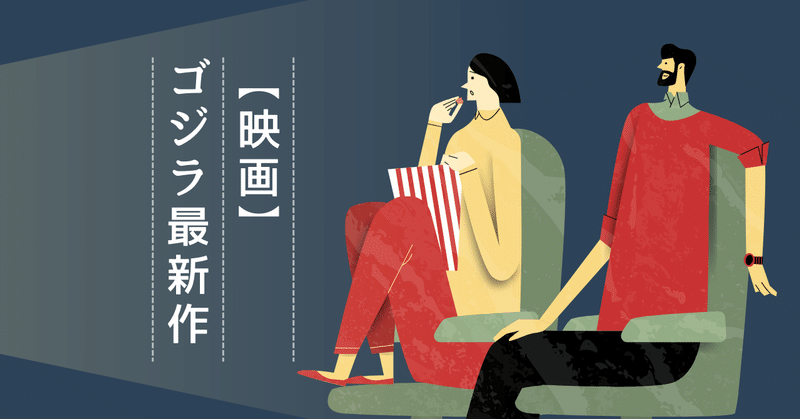
【ネタバレあり】ゴジラ-1.0の概要と感想
ゴジラ-1.0を見ました。せっかくなので感想と概要を書きます。
舞台は第二次世界大戦、終戦前後
ゴジラ-1.0の舞台は、1945年。
第二次世界大戦終戦の直前から話が始まります。
神木隆之介演じる主人公「敷島」は特攻隊として戦場に出たものの、死ぬことに怖気付き、飛行機の故障と嘘をついて島の整備基地に不時着をします。
特攻隊とは:
特別攻撃隊の略。航空機や潜水艇に乗り、搭乗員もろとも敵艦に体当りする攻撃部隊。太平洋戦争末期、日本軍によって「生きて帰らない」ことを前提に編成されたこの部隊は、攻撃を受けた連合軍に恐怖を与え、特に航空特攻は「KAMIKAZE(カミカゼ)」として今でも世界で語り継がれている。
飛行機の検査をした整備隊の橘隊長(役:青木崇高)は、飛行機に故障がないことを敷島に伝えます。敷島の反応で戦争から逃げたことに気づいた橘は、敷島に同情の言葉を投げかけます。するとその晩、島をゴジラが襲います。
このとき出てきたゴジラは、3階立ての一軒家程度。過去のゴジラと比べたらだいぶサイズ感が小さめですが、結構な迫力でした。
敷島と整備隊は一目散に木陰に隠れ、橘隊長は敷島に「飛行機に備え付けられているミサイルで、ゴジラを迎撃してほしい」と伝えます。飛行機の操縦方法を知っているのは、この島では敷島だけだからです。
橘隊長に急かされるようにして、木陰から飛び出す敷島。なんとか飛行機に乗り込んでミサイルの標準をゴジラに合わせますが、直前でまた怖気付いてしまい、その間に橘以外の整備隊は全滅してしまいます。
この話の見どころは、戦争とゴジラ、恐怖心から二度逃げた敷島が、再度訪れる命の危機で橘と再会するところです。腰抜け感がある最初の敷島が、のちのち伏線として回収されます。
ゴジラの危機から逃れ、両親のもとに帰った敷島でしたが、そこはもう戦火のあと。焼け野原になった街の中、隣人の太田さん(役:安藤サクラ)から、両親はすでに亡くなったことを伝えられます。
そんな敷島のもとに、突然子どもを抱えて転がり込んできた大石典子(役:浜辺美波)。見ず知らずの来訪に最初は追い出そうとする敷島も、身寄りのない子どもと女性を無慈悲に追い出すこともできず、渋々住み着くことを了承します。
ゴジラ、二度目の襲来
2年ほど時が経ったころ、銀座にゴジラが襲来。その大きさは、ビルから頭が出るくらいのサイズに成長していました。このゴジラは、多くの人が慣れ親しんだゴジラの姿形をしていました。
また、そこでゴジラが暴れたことによる爆風に巻き込まれた典子と敷島。間一髪で敷島をビル陰に突き飛ばした典子は、自分だけ犠牲になり、敷島は一命を取り留めます。
日本軍は必死に応戦するも、大型ゴジラの前に為す術なし。また、第二次世界大戦後の緊張感の中で他国は戦闘機等を送ることができないと、ゴジラの戦闘に手助けをしてくれないという回答。結局、自分たちでこの問題を解決しなければならず、民間による「ゴジラ迎撃部隊」が組織されます。
そこで敷島が一役買ったのが、罠の張ったポイントに航空機でゴジラを誘導する役。戦争により操縦士がいない中、逃げて生き残った敷島に大役が回ってきます。
橘隊長との再会
航空機は殆どが戦争で使われていたものの、たまたま都合よく残っていた1台の航空機があり、それを使うことに。ただ、使われていない航空機はこのままでは動かず、整備士によるメンテナンスが必要。そこで、敷島は橘隊長に頼むことを思い付きます。
敷島の来訪に最初は憤慨し、暴力をふるっていた橘隊長も、敷島による「俺たちの戦争はまだ終わっていない」という一言、また、「ゴジラは体内が弱く、自分が航空機で突っ込めば差し違えることができるかもしれない」という敷島の覚悟を見て、航空機の整備を了承します。
ゴジラ、最後の再来
ゴジラが再来し、予定通り航空機で飛び立つ準備をする敷島。そこで、橘隊長から操縦機の使い方をレクチャーしてもらい、ゴジラのもとに向かいます。
ゴジラのもとにたどり着いた敷島は操縦技術を駆使し、罠の張ったポイントにゴジラを誘導。民間部隊によるゴジラ抹殺計画が実行されます。
ゴジラに大ダメージを与えた民間部隊でしたが、凡その想定通り、それでもゴジラはまだ生きており、大きな口を開けて民間部隊に光線を吐こうとします。その口に、敷島が航空機ごと突っ込んでいきます。
自らの命を投げ出して突撃したとみられた敷島でしたが、直前で緊急脱出をしており、ゴジラを撃退して命も助かる、という形で物語が終わりました。
見どころ
結構な部分を省きましたが、物語の大方の流れはこの通りです。私が感じた今回のゴジラの見どころは、以下の3点でした。
ゴジラの迫力
第二次世界大戦の日本における世界観
物語のテーマ設定
まず、ゴジラが迫力満点でした。とくに、日本のSF映画はハリウッドと比べて陳腐になる、というイメージがある人もいるかもしれませんが、全然そんなことありませんでした。ゴジラは迫力があり、隣の人はところどころ「ビクッ」ってなってました。
また、「第二次世界大戦終戦の前後」という時代を舞台にしたことも、色々と考えさせられる部分があって良かったと思いました。
まず、当時の「特攻隊」は死ぬことが名誉とされており、命の価値観が現代とは大きく違っていたと思います。「命」という壮大なテーマで価値観の違いを表すにあたり、この時代をもってきたことは受け入れやすかったように思います。
ゴジラが襲撃してきた際、他国が大きな援助をしてくれなかったことも、「自分たちの身は自分たちで守らねば」という価値観が盛り込まれていたように思いました。こういう物語では「いざとなったらアメリカが助けてくれる」というのは裏切られるように描かれることが多いようにも思えます。
そして、敷島が最後ゴジラに向かっていった場面では典子はすでに死んでいると思われていた(実際は病院で生きてました)ため、もし敷島が死ぬと子どもだけが取り残されてしまうという状況でした。
敷島は父親同然のように子どもと接していたため、「自分が死んだら子どもが一人になる」という生きる目的があったというのも、最後に死を選ばなかった理由として描かれています。
また、橘隊長が敷島に操縦機のレクチャーをする回想シーンでは、緊急脱出装置についても説明をしていて、「死ぬな」という橘隊長からのフレーズが印象的でした。後悔に苛まれていた敷島が、生きることを許されたメッセージのようにも感じる場面です。
全体を通してメッセージもわかりやすく、かつ考えさせられる部分もあり誰でも楽しめる映画かと思いました。
大きなスクリーンで見ると迫力が2倍だと思うので、ぜひ皆さんも映画館に足を運んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
