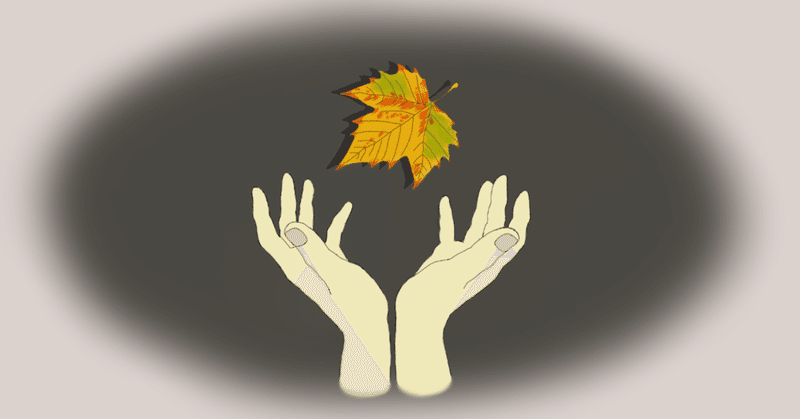
リルケの詩「秋」―木の葉が落ちる
リルケの「秋」を訳してみた。
リルケの詩は難解で、ほとんど理解できるものがない。「秋」はわかりやすい詩の一つだ。
リルケのドイツ原詩
Herbst
Rainer Maria Rilke
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
ヨジロー訳
秋
ライナー・マリーア・リルケ
木の葉が落ちる 落ちる 遠くからのように
天上のはるかな庭が 枯れていくかのように
落ちる 否定する身ぶりで
そして夜には 重い地球が落ちる
すべての星々を離れて 孤独の中へ
私たちみんなが落ちる この手が落ちる
ほかの人を見ても みんな同じだ
でもこの落下を 限りなくやさしく
その両手に 受けとめてくれる存在がいる
語句の説明
木の葉、天、庭――原詩では複数形。いくつもある天のそれぞれの庭が枯れていくというのが原詩のイメージ。
否定する身ぶりで――葉がひらひらと散るさまを表現している。枯葉は落ちていくことに抵抗している。
夜――原詩では複数形。
ほかの人を見ても――「ほかの人々を見るがいい」が直訳。
みんな同じだ――「それ(=落下)はみんなの中にある」が直訳。
存在――原詩のドイツ語は"Einer"。不定代名詞"einer"(ある人、一人、誰か一人)を大文字にして使っている。「特定のある一人」の意。"einer"は英語の"one"に当たる。英語で"One"と大文字にすると、「神、絶対的存在、究極の存在」という意味にもなるが、ドイツ語の"Einer"には特にそういう意味はない。それでもリルケはあえて大文字にすることで、「究極の一者」という意味で使っていると思われる。
解釈
▲第1連
秋、詩人は公園を散歩している。木の葉が落ちてくる。詩人はそれが遠くから落ちてくるように感じる。詩人は、天上の園から落ちてくる枯葉だと空想する。
ゆらゆらと落ちる枯葉は、落ちることを拒んでいるかのようだ。なぜなら、それは死への落下だからだ。
▲第2連
詩人の想像力は一気に大気圏を突き抜ける。宇宙空間での地球の落下が語られる。「重い地球が落ちる」という大胆な表現で、読者は突然大きな不安に襲われる。自分の足もとが崩れ、ひたすら暗闇や奈落の底に落ちていくのを感じる。
▲第3連
宇宙から、再び「私たち」に戻ってくる。しかし、暗闇の中で地球が孤独へと落下しつつあるというイメージからはもはや逃れられない。「孤独」への落下は誰も逃れることのできないものであることが確認される。
▲第4連
しかし、最後の連で、「究極の一者=神」による救いが語られる。すべての存在の「落下」を受けとめてくれる者がいることが力強く、確信をもって宣言される。
有神論的実存主義者
サルトルは『実存主義とは何か』において、実存主義を、有神論的実存主義と無神論的実存主義の2種類に分けた。
一般には、キェルケゴール、ヤスパースが前者に、ニーチェ、ハイデッガー、サルトルが後者に属するとされている。
「秋」の詩を詠むと、リルケもまた有神論的実存主義者の一人に加えてもいいように思う。
天上の世界が「枯れ」始めている。キリスト教的神への信仰が揺らいでいるのだ。それが第1連。第2連は、神の支えを失った世界を描く。それは虚無に向かって果てしなく落下し続けるだけの世界、キェルケゴールによって「死に至る病」と呼ばれる「絶望」の世界だ。だが第3連で、やはり私たちを支えてくれる神はいるとリルケは断言する。生は絶望ではない。救済は必ずあるのだと。
「孤独」の中で人は神を再発見するのだ。
この詩を書いた頃のリルケ
「秋」は1902年出版の『形象詩集』に収められている。リルケがこの詩を書いたのは、同年9月11日、パリでのことだ。
前年の4月、リルケは彫刻家のクララ・ヴェストホフと結婚し、12月には娘も生まれていた。しかし、結婚生活は1年数ヶ月で終わることになった。娘は妻の実家に預けられた。
1912年8月末、リルケは依頼されていたロダン論を書くために、単身パリに赴く。9月1日にはロダンと会っている。「秋」はそれからわずか10日後に書かれた。
リルケはパリに来る前、北ドイツの静かな芸術家村ヴォルプスヴェーデの近くに住んでいた。それがいきなり大都市パリのただ中で暮らすことになった。そこで感じた強い不安と痛切な孤独がこの詩の背景になっているだろう。
おわりに
"Einer"は、諸家の訳を見ると、「一人」「ただひとり」「一人のひと」「或るひとりの者」と訳されている。ただ、「神」が想定されているので、「人」や「者」という語は使いにくい。
最初は「誰か」と訳していたが、それでは急に身近になってしまう。恋人、家族、友人などを思い浮かべる。それで「存在」にした。これなら神らしい?
ただ、僕自身は無神論的実存主義者なので、この詩の第4連には抵抗感がある。まあ、無理に神に結びつけず、漠然と「自分を支えてくれる存在」くらいに理解しておくことにしよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
