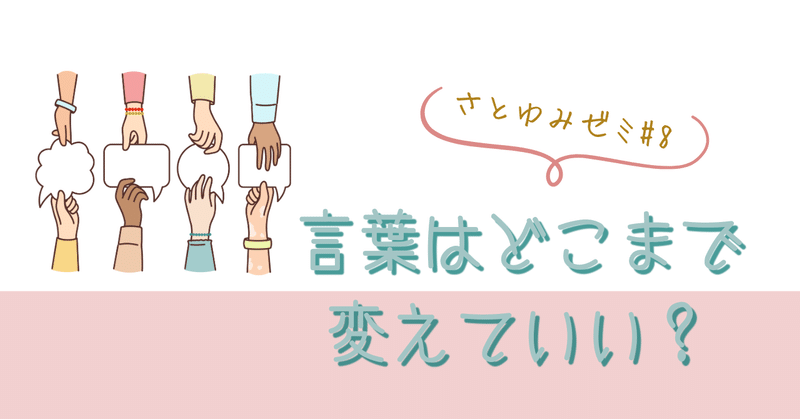
さとゆみゼミ#8|人の言葉はどこまで変えていいか問題
ゼミの最初に、4〜5人のグループでディスカッションをする。取り組んでいる課題について、お互いに悩みや考えをシェアする時間だ。
今回は、インタビュー原稿について話した。記事の素材は、さとゆみさんが医療コラムリストのライターさんに取材したときのもの。
人の言葉を変えることを怖がらないで
多くのメンバーが「言葉をどこまで変えていいのか」悩んでいた。さとゆみさんは、次のように教えてくれた。
たとえば、友だちから聞いた話を、家族に伝えるとする。その時に、テープ起こしをそのまま聞かせるわけじゃないよね?
「今○○ちゃんは、△△という会社で働いていて、そこに嫌な上司がいるらしくてさ。その人に〜」のように、相手の予備知識を踏まえて、一番わかりやすい言葉で伝えるでしょう。
その場にいなかった人にもわかるように、おしゃべりする。それを書き言葉に整える。
そう考えると、9割くらいはテープ起こしのままにならないそうだ。
1時間で話したことを、数分で読める文章にする。その編集作業を、怖がらず面倒くさがらずやるのがライターなのだ、と教えていただいた。
「そんなこと言っていない」といわれる理由
取材相手の言葉を意訳して、「そんなこと言っていない」と嫌な思いをさせたらどうしよう。
さとゆみさんは、次のように教えてくださった。
話した言葉を、一言一句覚えている人はほとんどいません。
なぜ「そんなこと言っていない」となるのかというと、意訳の方法が真意と外れているからです。逆に、実際の言葉でなくても、真意と合っていれば「そうそう。そういうことが言いたかったんだ」と喜んでもらえる。
その人が「真に言いたいこと」を伝えるという視点が大切だと分かった。
「真意を掴む」。言うは易く行うは難し。
真意を掴むために、質問を重ね、よく観察する。決めつけたり思い込んだりしないように、常に頭を柔らかく。と自分に言い聞かせる。
課題について|読者メリットはどこへ?
提出した課題「佐藤明美編集長の講義レポート」の講評が返ってきた。
撃沈だ。
修正どうのこうのではなく、根本から間違っている。ゼロから書き直そう。
【やらかしたこと】
・お前、誰やねん状態のまま、感想を語り続ける
・佐藤明美さんの言葉より、感想のほうが分量多い
・読者にとって役に立つ内容を盛り込めていない
レポートの掲載を想定している媒体は「さとゆみライティングゼミ」。受講を悩んでいる人の背中を押すことをゴールとした。
すっぽり抜け落ちていたのは、「読者メリット」。この記事を読んで、「明日からやってみよう」と思えるメリットはある?とさとゆみさん。
わかりやすい例で、教えていただいた。
「アイラインをキレイに引きましょう」といわれても、どうやればいいかわからない。
「黒目の上の部分は、アイラインを太く引きましょう」といわれても、理由がわからないからやる気にならない。
「黒目の上の部分は、アイラインを太く引きましょう。なぜなら黒目の縦幅が広くなって、黒目が大きく見えるからです。」と言われて初めて、やってみよう、となる。
私の書いた記事は、最初の一段階で止まっていた。
いよいよ、ゼミも佳境に入ってきた。収穫は「真意を伝える」「読者メリット」。この2つが押さえられているか、常に考えたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
