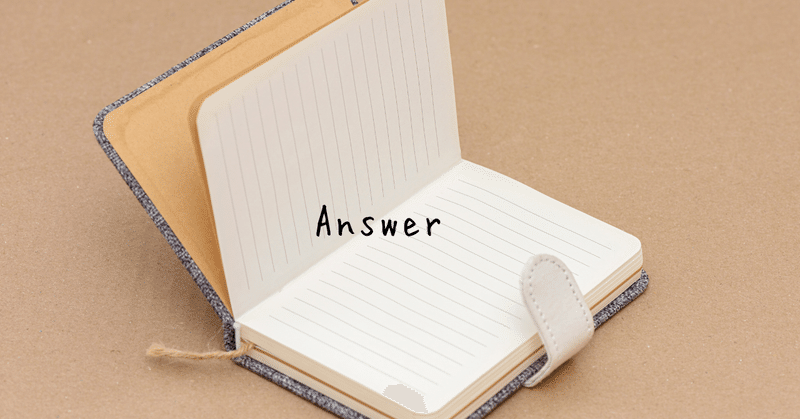
Answer 「p1」
「p0」(前話)
2016年9月末日
夜更け過ぎに目が覚めた。
はるかの1DKの部屋は、リビングとベッドルームの間に引き戸がある。その引き戸が開いていて、リビングのテーブルのほうが、青白い光で満たされているのが見えた。
明日朝早いんだけどな、と思いながら、ぼんやりそちらに顔を向ける。タクミが真剣にタブレットに向かい、手を動かしていた。
漫画を描いているらしい。無性に腹立たしくなった。
生理前で眠くて眠くて、それなのに明日朝も早いから、とにかく洗濯物だけ畳んでおいて、とタクミに言ってベッドに入った。タクミの向こう側にあるソファには、洗濯物が山になったままだ。
ああほんと、嫌になる。明日は研修が入っていて1時間早く会社についていなければならないのに、どうしてくれるんだろう。
タクミが頑張っているのは知っている。でも少しはこっちのことも考えて欲しい、と、はるかはスマホを引き寄せた。
深夜1時。微妙な時間。
結局、トイレに行くふりで起きていき、電気をつけた。
タクミが顔を上げた。
「あ、悪い。起こした?」
ん、ドア開いてたから、と少し不機嫌な声を出すと、タクミは言った。
「ごめんごめん。一回ベッドに入ったんだけど、急に思いついたことがあってさ、書いとかないと忘れちゃうから」
ふうん、と言って、はるかはとりあえずトイレに行った。トイレから出ても、タクミは一心不乱に何か描いている。
「ねえ。洗濯もの。畳んどいて、って言ったよね」
言わないつもりだったのに、つい、言っていた。
「うん。わかってるわかってる」
タクミは絶対わかっていない返事をした。
目も覚めてしまって、仕方がないので、はるかはソファの洗濯物を畳んだ。自分の下着類以外は、Tシャツとか靴下とか、ほとんどタクミの洗濯物だ。ため込んでいたのを洗濯機に突っ込んだようだ。
「ねえ。もう寝なよ。明日でいいでしょ。私も明日早いんだ」
「うん。わかってるわかってる」
苛々はため息になって出て行った。
タクミとは、一緒に暮らしているわけではない。付き合い始めて間もない頃から、帰りたくないといっては、ひとり暮らしのはるかの部屋に何日か泊るようになった。彼は実家暮らしだったし、そんなもんかなと思った。同棲、というほどはっきりしたものではないし、何日か泊ると、戻っていく。頻度は気まぐれで、1ヵ月いたこともあるし、2週間来なかったこともある。
タクミは最近、会社を辞めたいと言うようになった。漫画に集中したいのだという。ブラックなんだ、働かせすぎだと文句ばかりいうけれど、会社勤めをしながらだって、漫画は描けるはずだ。自分を追い込むんだ、なんて言っているが、会社を辞めたらはるかの家に入り浸りそうな気がして仕方がない。
深夜に喧嘩しても仕方がない。それで損をするのは、はるかだ。
ソファの傍に置いてあるチェストの上に、買ったばかりの手帳があるのが目に入った。帰宅してから慌ただしかったので、今年の手帳と一緒に置きっぱなしになっていたようだ。
そう言えば、ゆっくり見ていなかった、と手に取る。9月発売の「ほぼ日手帳2017」。やっと買えた。手帳としては高額だが、これは、はるかの「やる気」に繋がっている大事なアイテムだ。スケジュール以外にも、愚痴、日記、本を読んでいて気にいった一文——それらを書き込むことで、自分を奮い立たせる。気軽には買えない金額も、それだけ、仕事を頑張ってきたんだ、と思うと高くない。手帳の仕様やカバーが毎年変わるので、文具オタクとしてはついつい、毎年違うカバーが欲しくなる。その年にしかない、というレア感もいい。
今回も、刺繍柄のカバーがあった。刺繍ものは手仕事が多いので普通のカバーよりさらに高いのだが、手芸が好きなはるかには、それも大きなポイントだ。「東欧の針仕事」とどちらにしようか悩んで「ウクライナの花」にした。
コレクターの心を鷲掴みにするカバーだけではなく、この手帳の何が好きと言って、インクがにじまないというトモエリバーの方眼の紙質が好きだ。1日1ページと、書くスペースが大きいのもいい。ぱらぱらめくる。新しい手帳を手に入れたとたん、急に今使っている手帳が古く感じる。月間スケジュールは12月からついているが、とても待ちきれない。新しい手帳に早くなにか書き込みたくなる。
そんな気持ちを抑えて、重ねて置いてあった今の手帳をめくった。2016年のカバーは「こぎん刺し」の「漆黒」というデザインだ。とても気に入っているのだが、1年も使っていると麻の薄いベージュの部分が薄汚れてしまった。でもそれも、頑張った証だと思えば誇らしく愛しい。
2016年は、タクミの記録で溢れている。でも最近は、空白のページが目立ってきていた。新鮮さが薄れてきたのもあるけれど、タクミが会社を辞めたいというようになってから、なんとなくもやもやして、そのもやもやをトモエリバーの方眼に吐き出すのが嫌で、何も書かない日が増えていた。
そう言えば、ハロウィンのホテルを予約しなければ。危うく忘れそうになっていた。会社の福利厚生でテーマパークのチケットが貰えたので、タクミには内緒で、オフィシャルホテルを予約しようと思っていた。半同棲のような暮らしは、日々心からときめきを奪っていく。生活のリズムの違いとか、生返事とか、洗濯物とか。——ここは少しイベントでテコ入れを図ろうと思っていた。
ちらりと、まだ熱心にPCに向かっている彼の横顔を見つめたが、彼は集中していてまったくこちらを見なかった。
横顔と声は、斎藤工なんだよね。名前もタクミだし。
心の中で、はあ、とため息をつく。わかってる。自分が面食いだってことくらい。
ネットでチェックしたら、ハロウィンの限定キャンペーンの部屋の予約は1ヵ月前からになっていた。もう、明日には予約しなきゃいけないんだった、と焦って手帳のページを開く。
テコ入れのため「ハロウィン予約」を力の入ったハートマークで囲んでいた。
が、そこに、どういうわけか書き込みがしてある。
なんだこれ。覚えがない。
——予約不要
ゾクッとした。自分が書くわけがない、と思ったが、自分の字みたいに見える。タクミが書いたのだろうか。誰かが見て、いたずらしたのだとしたらたちが悪い。公共の場所に置き忘れたり、会社の机に置きっぱなしにしたことがあっただろうか、と思い出そうとしたが、そんなことはしたことがない。
やだ。なんか、キモい。
そう思って、はるかはそばに置いてあったペンで、その「予約不要」を二重線で消した。
「ねえ。タクミ。手帳見た?」
顔を上げて彼の横顔に話しかけると、集中していたタクミは「え?何?」と答えてしばらくしてから時間差で振り向いた。
「手帳。ここに置いてあったやつ。中、見た?」
「知らないよ。そこにあったのなんて知らなかった」
そんなこと、と言うようにそっけなく言うと、彼はまた、PCに向かった。
「うそ。見たでしょ。それでなんか書き込ん――」
書き込んだんじゃないの、という言葉が出なかった。
はるかは息をのんだ。
二重線で消した「予約不要」の、ハートマークの隣に、字が出現しているのだ。たった今、誰かが書いている、というように、文字はさらさらと、紙の上に流れていく。
「うそ……」
思わずつぶやいた。
「何?俺ほんと、全然見てないって」
PCから目を離さずに、タクミは言った。
「え、でも、―—でもこれ」
「なんなんだよ」
少し苛立たし気に、タクミが振り向いたが、その時にはすでに10月1日のページには誰かが書いた文字が確固たる勢いで存在していた。
ハロウィンは行かない方がいいからね
「で?なんて?」
タクミの言葉に、ううん、なんでもない、と思わず言ってしまった。
まさか、目の前で紙に字が現れたのだ、などとはとても言えない。
はるかは、思わずぱたん、と手帳を閉じた。
疲れている。夢なんだ。だってこんなこと、あるわけない。明日朝起きたら、消えてるはず――
怖いもの見たさで、もう一度、10月1日のページを開く。
やはり、その字はそこにあった。くっきりと。
気持ち悪い、と思いながらも、はるかはその事実すべてを消したくて、その文にも二重線を引いた。濃く、引いた。
寝不足なんだ、きっと。働きすぎなんだ、私。
そう思い、もう、寝よう、と立ち上がる。タクミは文句のひとつも言われるかと一瞬目を上げたようだったが、そんな彼を無視し、はるかは一直線にベッドに向かった。
――続く
次話「p2」
