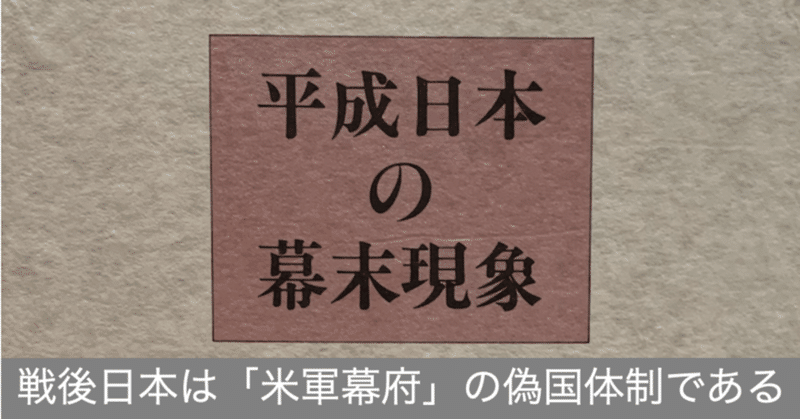
[2] 戦後日本は「米軍幕府」の偽国体制である
戦後という状況
日本の「戦後」という状況を見てみると、中国大陸に関しては内戦に関与したことや、朝鮮半島の植民地化政策に対する非難を、教育界、マスコミが執拗に行い、徹底的に洗脳、自虐意識を植え付けたと言える。
また、孔子の説く政治とは何か、の三原則の「兵」を欠いた状態では、独立国としての体裁は整っておらず、半独立国というべき状態であり、横田幕府による偽国体制と言えるわけである。
日本はサンフランシスコ講和条約をもって、独立したものと錯覚しているが、現実はそんなにあまいものではない。
現在、横田に詰めている駐留米軍司令官は、さしずめ、横田の大番頭にあたり、東京にことがあれば、アメリカにいる「征夷大将軍」の命を受けて出動する。
国家統治の基本機能を説明する時、孔子の教えを待つまでもなく、国家統治の基本機能の一つは治安、即ち国家社会における対外的・国内的安全を確保することであり、その具体的形態は軍事、警察力の保持になり、軍事を横田幕府に依存していることは、国家安全保障とてしては片手落ちとなってしまうわけである。
禁中並びに公家諸法度
現行の日本国憲法のもとでは、第一条が「象徴天皇制」を規定しているが、これは江戸幕府が天皇の政治的機能を定めた「禁中並びに公家諸法度」に対応するものとなる。
武家諸法度
戦争放棄を定める「憲法第九条」に「国権の発動でない」とあえて冠詞をつけた趣旨は、アメリカによる代理戦争にこれを求めたものだと解釈して、また、「交戦権」も日本が持たず、アメリカに授権したと解すると、この条文の本当の意味は「米軍の永久駐留」とも読めるわけである。
また、自衛権という言葉があるが、我が国は自衛権の作用として、米軍に戦争行為と戦争の意思表示などの代行を委任していることになる。こうした関係上、日米間には国際紛争がありえないことと同時に、アメリカに追従せざるを得ない状況にある。
これは、現在のウクライナ情勢における不可解な国際政治上の決断を下さなければならない根拠と推察されるのである。
そして以上が、江戸幕府が国内治安のために軍事力を統制しようとした『武家諸法度』に相当することになる。
特権階級と公地公民
戦後の支配層たるGHQが日本の民主化にあたり、いち早く払拭しておかなければならないと考えたのは、華族・財閥・地主・軍人などの『特権階級』であった。
要するに華族令廃止、農地解放、SCLC証券処理調整協議会による持ち株放出、財産税の実施などの処分により、資産の偏在にメスを入れられ、帝國陸軍海軍は解体された。これは大化の改新の「公地公民」に対応する処分となるわけである。
「政所」自民党
戦後体制の「政所」自民党に対して、著者が、一種のいかがわしさを感じている理由は、自民党が自らの力で政治的覇権を取ったものではなく、アメリカの軍事力により掌握された覇権のうちの、内政部門だけを委託されたに過ぎないからである。
この点で、自ら兵を興そうとした明治維新の志士達とは比べ物にはならないし、毛沢東の如きは「政権は銃口から生まれる」と言ったが、さすがに政治の本質を表す至言であると言える。
しかしながら、戦後の日本国を運営する上での必要性から生まれた政党であることは確かなのだ。
自民党は現実の経済運営に関する責任層を支持者とするものであり、それは大企業の幹部や高級公務員などはもちろん、都市市民としては中小企業や町工場主などである。
しかしなんと言っても最強の支持者は農村部にあり、小規模農家を含む農家票である。
自民党の、米価管理・農村への公共投資・財政補助などの政策的農家保護は、その恒久化を望む農家票を人質にとったものであり、農業そのものを「利権化」して、自民党の支持母体に組み込みこんだのであった。
農民の保守性は日本独自のものではなく、他の国でも往々にして見られる現象である。それは農村部がどの国でも最も伝統的な社会であることが最大の理由であるが、我が国の場合、その農民層が「戦後の或る日突然に」大量に創設された自作農民層であるところが特徴である。
官僚
官僚は比較的日本独自の政治勢力である。そもそも官僚制とは、国家統治構造の一種で、代議制や民主制と対比される言葉である。政治学者の辻清明はこれを「任命職の行政専門官が、選挙とか弾劾といった民主的責任を免除されたまま、政治的支配を行う統治構造である」と定義している。
官僚は、時代の変遷とともに特権的な立場から公僕的扱いを経て、政官癒着の金権的要素をはらんだりもした。戦後、GHQが日本の官僚の有能さを見抜き、また同時に政党政治家の無能さを理解したことで、横田幕府は、政所自民党が、官僚制に頼って内政を運営する構造を是認したのである。
前回の参議院選挙の立候補者を見るまでもなく、ここ数十年の政治家と呼ばれる人間の中に、およそ政治というものを真剣に理解していると思われない者が多く紛れていることは、横田幕府にとっては大変都合の良い事であろう。一方、当のアメリカ本土は、前回の大統領選挙から現在の中間選挙にかけて、明らかな不正選挙工作が行われており、僕に言わせてみれば、民主主義というシステムが既に制度疲労を起こし、崩壊寸前にまできていると思われるわけである。
これに関して、本書が書かれた1989年の時点において著者は、「著者なりの民主主義信奉者であると自負している」と述べている。実際僕も子供の頃はこの民主主義の恩恵に与って成長してきた、という実感はあるわけです。
民主主義は西欧の人文、精神科学が最高点に達したギリシャ時代に先哲が明らかにした政治制度の一種であり、先行するオリエント文化に対立したヘレニズム的な政治センスに根ざす。
さらにこれを後世プロテスタントの社会理念が洗練し、発展させたものである。
したがって合理性に対する志向が強いが、ヘレニズム的理念とプロテスタント的倫理に対応していない国々では、却って民主主義は腐敗しやすいという特徴をもつ。
それは南欧、中南米、フィリピンに例をみるし、中華人民共和国においては民主主義など機能するはずはないことは周知の事実である。
ギリシャの哲学者プラトンは民主主義を「国家が堕落した形態、言い換えれば大衆の消費的欲望が支配する無秩序の政治」と考えていた。
これは、日本を含めた現在の民主主義国家をみれば、まさにその通りと言わざるを得ない卓越した先見の明といえる。
アリストテレスは、プラトンとは反対に中産階級を支持し、多数の支配する政治の価値は哲人政治より高い、としたのは、そのヘレニズム的理想を期待したのでしょうか。その彼にしても「デモクラシー」とは、民主政治の悪い形態を指す場合の用語として用いていた。
この辺りの「衆愚政治」にいたるまでの考察に関しては、また別のテーマを設けて述べて見たいと思う。
人間社会の本質
人間社会の本質だが、およそ人間社会は分業(経済的)で成り立つとともに、集団(社会)を形成している。集団は孤独への恐怖という動物的本能に根ざすものであり、分業は集団を前提として成り立つ、情報交換が生み出す経済システムではないだろうか。
集団は集団の意思に従って動いていくのだが、集団の意思は個々の成員の意思の算術的総和ではなく、集団はそれ自体の固有意思を有す。この固有意思を導出するものは集団内の何者かという問題があり、もちろん全員だ!という見方があるのわけで、この見方を「民主主義」という。しかし現実の社会を見るときに、何事も全員で決定する事態などありえないのは、集団行動の機能が悪くなり外部状況に対応しきれないからである。
そのため、集団の方向を定めるものは集団成員のごく一部となる。これを指導者と言うが、ヤマトではキミ(君)と言っていた。この方向に従って戦略を練り、内部規律を保ち、集団の行動目標を達成しようとするものを幹部といい、ヤマトではトミ(オミ臣)とよんでいた。トミに従って集団の実務を分担するものは人民であり、タミとよばれる。トミがタミを指導する政治制度は「官僚主義」と呼び、実は民主主義といっても社会の実際の運営は官僚主義に依存しているのである。
民主化は精神革命
著者は「戦後の民主化は精神革命」と呼んでおり、戦後我が国は、政治運動に限らず、経済、社会、家族関係、などに対して、残念ながら戦前的なものを覆滅させていってしまった。
それだけにとどまらず、教育、学術、芸術など広く精神活動の面にまで革命は及び、日本人特有の本源的情緒をも、嘲笑、侮蔑し、しかもそれを「進歩性」などと嘯いたのであった。
その流れは今も続き、さらに加速度的に悪くなっている。
日本臣民たる我々の立場が外国人よりも下位に位置づけられ、また、性的マイノリティーの権利の方が強くなり、オリンピックで性別がどちらかわからない選手が出場するという、勝つためには何をやっても良いという風潮を作り出した。
行き過ぎた多様性保護による、意味不明な価値観の押し付けにより伝統的価値観は揺らぎ、また、そのような価値観に基づいた社会活動に沿わなければ仕事にもあり付けないため家庭は崩壊する。
多様性、寛容性なる美辞麗句に身を包み、国家の伝統的価値観を破壊する姑息な国際共産主義者トロツキストの工作に、民主国家は抗えない状態となっているのである。
そのような國體に対する破壊工作に、大学教授や弁護士までもが食い扶持の確保として参戦している状況であり、マスコミが煽るので始末が悪い。
以上のような状況は、日本に限らず、民主主義を標榜している西側諸国全体においても顕著に現れており、そのような国際共産主義的民主主義に対し、正面から「ノー」を突きつけているが、現在のロシアのプーチン大統領なのである。
以上のような現象において、僕が最も憂慮するのは、本国人のマジョリティを貶めるようなことをしたら、本来なんの偏見もない人までをも不快にさせてしまうし、善意あるマイノリティの人たちも含めて、怨恨の的となってしまうことなのである。
本来、人には困っている人や立場が弱い人を助けようという「義侠心」が備わっている。
その「義侠心」こそが「真心」であり、制度で強要するものではない。
故に、義侠心の発動を妨げてしまうことは、少数派側にとっても、決して良い流れとはならないのである。
政教分離
政教分離というものは、実は「神道禁止令」なのです。
どこの国でも民族的宗教をもち、それは国民一般の儀式と習俗に浸透している。
日本の政治家が靖国神社に参拝することを、近隣諸国やキリスト教団体、マスコミが攻撃するのは、このような攻撃がすべて「神道」に向けられていることは注目すべきことである。
これは、神道禁止令が、江戸幕府のキリシタン禁制の裏返しであると考えれば、その実行にキリスト教徒が固執するのにも歴史的背景があると言えるのだろうか。
(経済)
戦後経済の箇所に関しては、著者の最新の見解が「白頭狸」に詳しく書かれており、本書を著した1989年の2年後に起こるバブル崩壊後に大きく日本の経済状況が変わるため、当時の著者の横田幕府への認識とは変わっていると思われるので述べないこととする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
