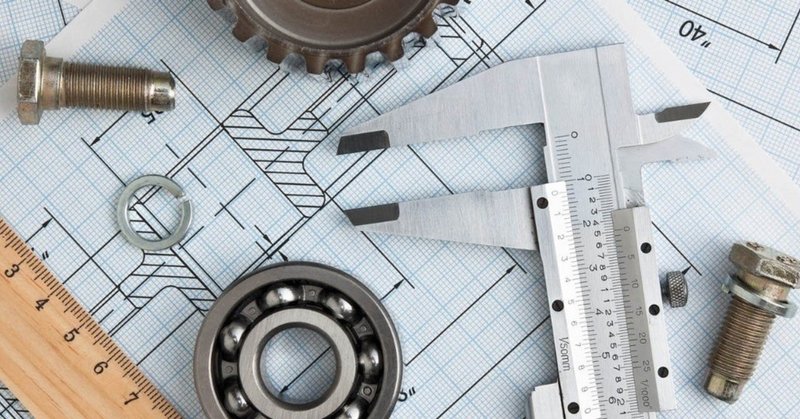
AタイプとBタイプ。あなたはどちらのデザイナー?
少し前に日経の「デザイン経営とはブランド戦略の一つ?」と言う記事が話題になりました。特にデザイナーの方々がこの記事に反応していて「そうじゃない!」と言うリアクションがとても多かったように感じます。
私自身も「そうじゃない」と記事を読んで思ったのですが、同時にデザイナーではない一般の方(もしくはデザイナーの方も)はむしろこちらの記事に書かれているような「製品の色・形をカッコよくする」ことをデザインと思っている方が多いのではと思いました。
なぜこのような認識の違いが生まれているのかが気になったので私なりの考えをまとめて見ようと思います。
Aタイプのデザイン、Bタイプのデザイン
まずデザインには大きく2種類の役割があります。1つ目は「カタチを価値にするデザイン」(Aタイプ)です。具体的には「モノをカッコよく、美しくするデザイン」です。日経の記事ではこちらの考え方を扱い、モノの美しさが重要な差別化要因なので経営においてそこを重要視しなければならないと言う意見です。2つ目は「価値をカタチにするデザイン」(Bタイプ)です。こちらはモノ自体は手段であって、「価値を具現化する(ユーザーがそのモノを買ったり、利用したりする目的をカタチにする)」デザインです。
ここ10年ほどでデザインに求められる比重が急速に「価値をカタチにするデザイン」に変わってきていると感じています。そのターニングポイントになったのは「デザイン思考」と言う考え方が普及してきてからではないかなと思います。デザイン思考はIDEOのデビッド・ケリーが提唱した考え方で、同じくIDEOのティム・ブラウンの本「デザイン思考が世界を変える」が有名です。
それまでは多くの日本のメーカーや制作会社、広告業界には「意匠課」がデザイン部門として置かれていましたが、その名前の表す通り「意匠課」は「カタチを価値にする」役割と考えられていました。実際に辞書を引くと意匠の意味は「「美術・工芸品などで)物品の外観を美しくするため、その形・色・模様・配置などについて、新しい工夫を凝らすこと。その装飾的考案。デザイン。」であり、造形的に美しくすることが目的としてあげられています。同時にこの頃は「デザイン」は意匠の訳語として扱われていました。
一方で前述のデザイン思考に代表される「デザイン」にはこの「意匠」という意味以上の意味が含まれており、「デザインとは課題解決である」とよく言われる定義はこの文脈で使われています。
それまでは「デザイン=意匠=モノの美しさを作ること」だったのが「デザイン=問題解決」に(特にデザイン業界で)比重が移り変わりつつあるのですがそれが世の中にはあまり定着していないのが今回の日経の記事に現れてるのではないかと思います。
Aタイプの例
もう少しイメージしてもらいやすいように具体例を上げようと思います。
こちらは1930年代のアメリカで使用されていた鉛筆削りです。
基本的な構造は現在の鉛筆削りとも差はないので、馴染みのあるものだと思います。
この鉛筆削りをレイモンドローウィという非常に有名なデザイナーが手がけたものがこちらです。
流線型の美しいデザインです。この鉛筆削りには背景があり、当時のアメリカでは車のデザインで「流線型」の形が流行していました。この鉛筆削りはその流行を反映したデザインで、多く売上げた商品になったようです。
もう一つはレモン絞り器です。
こちらも基本的な構造は今売られているレモン絞り器と変わらないので馴染み深いと思いますが、これを同じく有名デザイナーフィリップスタルクが手掛けたものがこちらになります。
こちらは現在も販売されているロングセラーで、おしゃれなお店で飾られているのを見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。
少し極端な例をあげましたが、いずれもその物自体の造形を美しく、カッコよくすることで価値を生む=「カタチを価値にする」デザイン(Aタイプ)の例と言えます。
Bタイプの例
「価値をカタチにする」(Bタイプ)デザインの事例も上げたいと思います。
こちらは病院のMRI検査装置です。この検査装置の開発するGEヘルスケア社の担当者はMRI装置を改善するために小型化、効率化に取り組んでいました。
その中で改善できるポイントを探すために実際にこの装置が使われている現場を見に行ったのですが、そこで見たのは検査を受ける子供がこの装置を怖がり泣き叫んでいる姿でした。この装置はその仰々しさから子供達に威圧感を与えてしまい、結果的に検査装置に入れるために鎮静剤を打たなければならない子供もいたそうです。
そこで担当者は子供にヒアリングを重ねこのようなMRI装置を「デザイン」しました。

子供達はMRIを受けることが目的ではない、「元気になって楽しく遊びたい」ことだと考えた担当者はMRIを冒険の一つのシーンのように演出し、子供達がワクワクしながらこの検査を受けられる空間を作りました。
この担当者がデザインをしたのは「子供が恐怖を感じずに検査を楽しめる」と言う価値であり、それを具現化するためにこの空間をデザインしました。
もう一つの例としてバルミューダのトースターを挙げたいと思います。家電業界のヒットの中でよく取り上げられ、デザイン家電として紹介されることも多い商品です。

もちろん洗練されたカタチの商品ですが、そのカタチは美しくすることが目的になっていません。実際にこのトースターをデザインされた松藤恭平さんのインタビューがこちらに掲載されていますが松藤さんは「おいしそうなものが出てくる形ってどういう形? 」と言うことを意識されてデザインをされたそうです。『パンを焼く機械ではなく、おいしく食べる体験を作るんだ』と言うバルミューダ寺尾社長のディレクションのもとでその体験=価値を実現する「カタチ」としてデザインされた例だと思います。
まとめ:あなたはAタイプ、Bタイプどっち?
このように「カタチを価値にするデザイン」(Aタイプ)と「価値をカタチにするデザイン」(Bタイプ)の2タイプの役割がデザインにはあるのですがそれがあまり意識され図に「デザイン」と言う言葉が使われているのが混乱の原因な気がします。
またデザイナーもこの2タイプのどちらか得意かが別れるような気がしています。私自身は「価値をカタチにするデザイン」が得意なのですが、うっとりするような美しい、カッコ良いデザインをする「カタチを価値にする」のが得意な先輩や後輩のデザイナーを見ると羨ましいなーと思います。
デザイナーの方は普段の仕事で「カタチを価値にする」ことが求められているのか、「価値をカタチ」にすることを求められているのかを意識すると仕事を依頼してくる人とのコミュニケーションがしやすくなり、またデザインの依頼をする人も自分がどちらの役割をデザイナーに期待するかを意識できると自分の期待を実現できるようになっていくのではないでしょうか。その関係が浸透していけば世の中のデザインに対する理解も広まっていく気がします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
