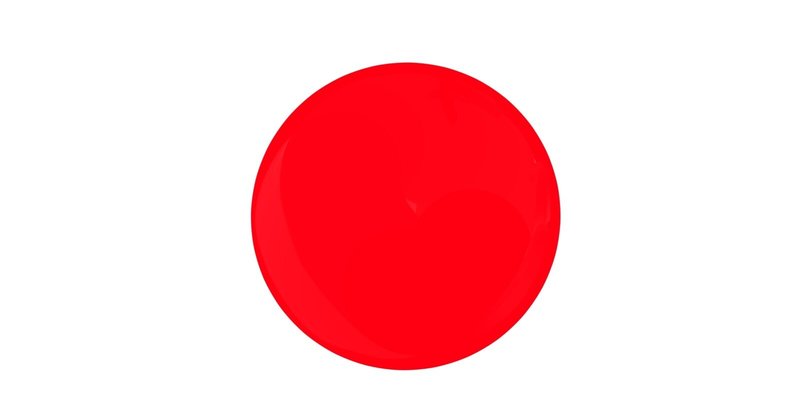
プロイセン王国とドイツ帝国 卵味のピザは如何にして腐ったのか
現代の国学
「やまとこころ」と近代理念の一致について
第一章
人間と宗教と啓蒙の歴史
プロイセン王国とドイツ帝国 卵味のピザは如何にして腐ったのか
EUにおける今日の問題は、ドイツの無計画な難民の受け入れが最たるものの一つだ。難民を功利主義を意識して受け入れることは政治的選択であるが、経済的な用意を怠るならば政治的選択であるとは言えない。
ドイツの無計画な難民受け入れは政治的な感性や経済的な繁栄との並立を目的とした人助けではなく、過去への贖罪と言った道徳観念から起きたものだろう。メルケル首相は現実問題に対して何を成すべきかではなくて、思春期の少女のように自分達が何者であるかについてしか考えていなかった。そして、防衛問題を考慮すれば、トルコのEU入りは重要な問題となるが、世俗派のトルコは白人キリスト教徒ではないが故に、EUに入ることが出来ないようだ。
こうした妄想的な宗教観によるキレイゴトは、現実的には公共の混乱と難民への反感を引き起こし、それによって逆説的に人種差別を誘発させる結果に終わる。ヒステリックなドイツがヴァーチャリズムを好むことは事実であるが、妥協と功利主義を必要とする政治領域ではロマン主義的な幼稚さは良い結果をもたらさない。
残念ながらドイツが行おうとしたことは、世界に対して観念的正当性を顕示するプロパガンダであって、この点においては一九三六年のオリンピックと同様であったと言える。とはいえ、いつの時代でもドイツの行動は問題解決ではなくて自己正当化が目的であるということは、歴史を観察していれば明らかなことだ。
効果的な判断を貫く功利主義ではなくて、権威に殉じる狂信を尊ぶドイツは、戦前戦後でその服従の対象先がナチスからキリスト教に変わっただけでしかない。彼等は自らが権威に許されるかどうかを問題にしていて、自らの所業の結果責任を自らに負うつもりがまるでない。権威に許されることだけを求める奴隷には、自省をすることなど絶対に不可能なのだ。
こうした心性は理想主義というよりも無い物ねだりでしかないが、ドイツが自らの無責任な姿勢に気づいていないというのならば、それは「裸の王様」ならぬ「裸の神官」とでも評するべきだろう。なんであれ、彼等が芸人である「裸の銃を持つ男」でないことは絶対に間違いがない。過ちの因果を理解しえない愚者は、進歩することが出来るわけもなく、永久に同じことを繰り返し続けることになる。つまり、「君臨すれども統治せず」がイギリスで、「謝罪すれども反省せず」がドイツであるということだ。
しかしながら、聡明な読者の中には、ドイツと言えばレアルポリティーク( Realpolitik )という言葉が有名ではないかと憤慨する方も居ることであろう。邦訳すれば「現実政治」と呼ぶべきこの言葉とは、ビスマルクが体現したマキャベリズムとされる。
だが、ビスマルクが宰相を務めたドイツ帝国は、権威に迎合する衆愚の国家であるアメリカ合衆国とは異なって、名は体を現したものではなかった。つまり、「ロマン主義的でもなければ、ヴァーチャリズムでもなく、ましてやドイツ的ではなかった」ということである。
ビスマルク時代のドイツ帝国は、伝統的なドイツ文化を持たない東部の新興国家であるプロイセン王国が政治的中核であった。このプロイセン王国は功利主義を伝統とする軍事国家であり、人間の権利や公共の福祉といった考え方が大切にされ、自由と寛容を国是としていた。プロイセン王国がプロテスタントの移民を多く受け入れたことは事実であるが、この国の本質は近代的啓蒙思想と現実政治であり、宗教的な要素が希薄な国家だったと言える。
プロイセン王国の建国者のフリードリヒ大王が戦上手の芸術家であるとすれば、ビスマルクは殖産興業に長じた政治家であったと言えるだろう。ビスマルクの政治に誤魔化しがなかったわけではないが、それらはプロイセンの民主主義を守ることを目的としていた。
政治家ビスマルクは、その演説の中で「ドイツがプロイセンになるのではなく、むしろプロイセンがドイツにならなければいけない」と述べたことがある。オベンチャラに卓越していたビスマルクの本心はこれとは正反対であったが、この時代にはプロイセンはドイツとは別物であると認識されていたことは事実なのだ。
ビスマルクは大の卵好きであり、朝食に十個以上の卵を使ったオムレツを食べることもあった。現代でも卵を乗せたピザのことをビスマルク風というのは、彼の卵好きに由来している。ドイツというピザの下地の上に、プロイセンという卵が乗ったものがドイツ帝国であるが、このピザは殆ど卵の味しかしないピザであった。現実政治とはプロイセンの滑らかな口当たりであって、硬いだけのドイツ的歯応えではなかったのだ。
ビスマルクが宰相であった時代のプロイセン国王のヴィルヘルム一世は、民主制の導入には急進的というよりも斬新的であって、慎重な保守派ではあったが頑迷な権威主義者ではなかった。政治的バランス感覚を持っていた国王は、おそらく「ドイツ人民が求めた民主制」の裏にあった「ナチズムという民族主義」の萌芽を見抜いていたのだろう。
国王ヴィルヘルム一世は、ドイツ帝国の皇帝号を戴くその前夜に、「ドイツの汚冠よりもプロイセンの王冠の方が遥かに偉大である」と言い放った。その後の歴史を観察する限り、ドイツの民衆はヴィルヘルム一世よりも遥かに権威主義的であったのだから、この予言は完全に的中することになった。
ビスマルクの政治は現実政治であったが、ドイツの民衆はその後の選挙で神官を支配者に選んだ。王様と大臣が神官に煽動された民衆に阿ることなく、政教一致と人種差別を否定して政治を行っていれば、ナチスなど生まれるわけもない。しかしながら、民主制を観念的に信仰するアメリカの価値観ならば、人種差別を認めないことがおかしいという神学理論が跳梁跋扈することは間違いがないし、神官と民衆は狂ったように政教一致の十字軍を求め続ける。
実はアメリカの歴史は、宗教原理主義と奴隷制度の集団なのだから、イラク戦争の後の混沌にISILのような宗教原理主義と奴隷制度が誕生するのは必然の現象でしかなかった。今日のアメリカは日本を人身売買報告書において批判しているが、苦役的な労働制度の正当化はアメリカ史の暗部そのものであったことを見て見ぬ振りをしてはならない。
プロイセン王国においては、宗教や人種を問わず、国家に貢献する人間であるならばプロイセン人であるとされ、「各人には各人のものを」という個人の自由を重んじる理念が重んじられていた。「各人には各人のものを」とは元々はローマ帝国の標語であったが、プロイセン王国の黒鷲勲章にはこの標語がラテン語で記されている。このプロイセン王国の近代国家的な感覚はギリシャ・ローマ的な気風に由来するものなのだ。
プロイセン王国は伝統的に多くの高所得者や技能者の移民を受け入れ、その中にはユダヤ人の移民も存在していたし、トルコ人の移民を受け入れようとしたこともある。プロイセンは宗教に対しては兎に角無頓着であって、民族主義を取らずに有能な人間を抜擢するといった功利主義が存在したのだ。この国は、公共への貢献という国家主義によって国民が統合された国民国家であって、民族主義によって権威の下に均質的同化を行う権威主義社会ではなかったということだろう。
こうした世俗的なプロイセンとは対照的に、古くは聖界諸侯という司祭が政治を行う制度を保持していたのがドイツである。ドイツにおいては為政者が神官に洗脳されるどころか、神官と為政者が兼業であったわけであって、これはヒトラーという宗教家が政治家に選ばれたことの一つの起源だろう。国家主義を否定する彼等は、法治権力ではなく道徳的優位によって政治を行うことしか出来ない。
神聖ローマ帝国は現代のドイツの祖とされるが、この神聖という看板は、キリスト教の政教一致国家であることを示している。ヴォルテールは神聖ローマ帝国を、「神聖でもなく、ローマ的でもなければ、帝国ですらなかった」と評価したが、最初については間違っていたと言えよう。
ドイツ帝国というプロイセン王国とその衛星領域の集合体は、時代が経つにつれてドイツの宗教的な民族主義の影響力が増えることとなった。ドイツ帝国という名前のピザも賞味期限を過ぎて腐敗が始まり、現実政治という卵の味はカビ臭くて苦いだけの政教一致に堕落したわけだ。王室によって担保されていたローマ的な民主主義が、民主制によって徐々に神聖ローマ的な権威主義にすり替わってしまったのだ。
偉大なるプロイセン国王ヴィルヘルム一世が死去してからは、ワーグナーの「神々の黄昏」が現実化することになる。ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世はプロイセン国王の祖父とは対照的に、プロテスタントの信仰に熱心であって、そして国家主義的というよりも民族主義的な性格を持っていた。プロイセン王国は基本的にオーストリアとは同盟を結ばなかったし、ビスマルクの独墺同盟もロシアとの同盟の当て馬でしかなかったが、ドイツ皇帝は民族主義によってオーストリアとの同盟を重視したのだ。
ヴィルヘルム二世は宰相であったビスマルクを更迭して皇帝親政に励み、実体的感性と文化的知性を伴わない攻撃的な外交を繰り返す有り様であった。存外に領土的野心が薄く内政重視であったビスマルクは、植民地獲得競争には熱心でなかったが、誇大妄想的な民衆とヴィルヘルム二世はドイツ帝国の過大な拡大政策を引き起こした。黄禍論という人種差別を喧伝したのもこの時代のドイツであって、これは日露戦争の遠因でもある。
ルネサンス的な国家であったプロイセン王国と民族主義が蔓延したドイツ帝国の関連性をして、ローマ帝国が神聖ローマ帝国に成り下がったと言ってもなんの問題もない。グリム童話の眠り姫は王子様のキスで夢から目が覚めたが、ロマン主義のドイツはプロイセンの啓蒙によって近代に目覚めることがなかったということだろう。実体を拒絶して幻夢に引きこもる心性がドイツロマン主義であるのかも知れないが、ナチズムは実体を破壊する悪夢であった。なんであれ、こうした幻夢や悪夢は、実体的な理念から最も離れたものであることは間違いがない事実である。
帝国が広くなれば、元来の気風を維持することは出来なくなってしまうという歴史の法則がある。プロイセン王国も版図をドイツ圏に拡大した結果として、ドイツロマン主義に逆に侵略されることになった。ローマ帝国も肥大化したことによってローマ的な気風を維持できなくなり、その結果として神聖ローマ帝国が生まれた。国家に必要なものは富国強兵であって、過度の領土の広さはむしろそれを阻害するだけのものに過ぎないのだ。そして言うまでもないことだが、富国強兵の本質とは、軍事権力の強さよりも科学技術の強さに存在している。
大日本帝国もこの例に漏れず、天皇機関説という近代民主主義国家の理論を一度は確立しながらも、アジア大陸への領土の拡張に伴って天皇を儒教的に再定義しただけの天皇主権説に劣化することになった。二次大戦中には、元来の日本らしさというものはまるで消え失せていた。必要なことはアジア大陸に人間主義を広めることであって、決してアジア主義によって日本が儒教化することではないのだ。アジアから儒教が消えることが無い限りは、地域的な平和と友好は絶対に成立し得ることが無い。
天皇機関説とは、国家主権は国に存在し、政治主権は名義上は天皇に存在すれども、その実行は議会が行うという政治学説である。これは、観念的な学説理論ではなくて、明治維新以前からの歴史的な事実であり、「君臣共治」と呼ばれた伝統的な慣習を、ただ理論化し直しただけのものであった。その実において、日本には天皇に政治的実権が存在していた時間など殆どなく、天皇とは国家主権を象徴的に司る儀典的な役割であった。
一方で、天皇主権説は国家主権が天皇に存在するといった中華の天帝史観のコピーであって、これはアジア的な儒教的世界観でしかない。いわゆる戦前的な空気とされるものの正体は天皇主権説であって、それは儒教の権威主義であり、つまりは明治の気風の対極である。時代的限界もあって維新志士の精神が完全に儒教から自由であれたわけではなかったが、彼等は本質的に近代的自由を目指していたことは疑いようがない事実なのだ。
明治時代の日本には、清と協働して近代化を目指す興亜論という理論が存在していた。だが、儒教に毒されていた中華と共闘するならば、天皇機関説を造ることなど不可能であって、残念ながら中世に停滞すること以外はできなかっただろう。
日本の歴史は君主制であっても「まず国ありき」であって、「まず君ありき」の中華とは異なっている。天皇と官軍が立憲君主制の政治を行うのが日本の伝統であって、皇帝と宦官が政教一致の政治を行うのが中華の蛮習である。立憲君主制の日本の官軍は一定には「お国のために」という公共意識は存在していただろうが、専制独裁の儒教の宦官は「お上のために」と私利私欲でしかなかった。
私の記事が面白いと思ったならば、私の食事を豪華にしていただけませんか? 明日からの記事はもっと面白くなります!
