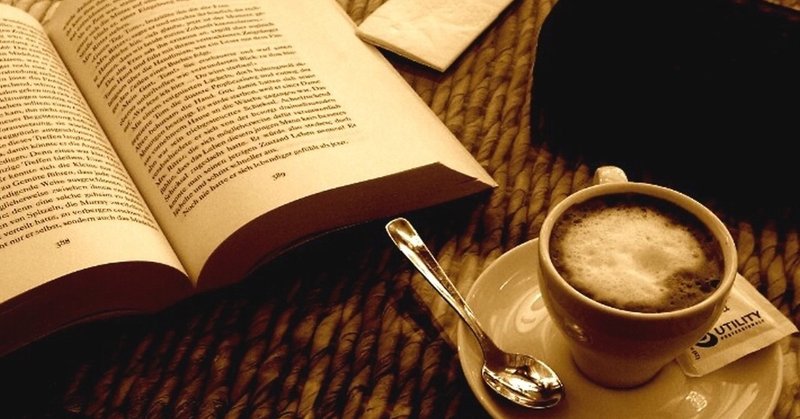
人生で引き寄せるものは、巡り巡って結局リンクする。
最近シェイクスピア物語にはまっている。友人の紹介で出会った前世が見える人に、「あなたは500年頃前に、イギリス王室おかかえのエンターテイナーだった過去生が今に強く影響してるね。シェイクスピアなどの舞台に携わっていたのね。あととにかく旅人ね。魂はふらふらしていたいって。表現者として魂の記憶があるし、今世も自分の感性を表現して生きていくことが軸になるわ。」と言われたことに起因する。ならば、すべての物語を読んでみよう。
もう一つ、イギリス英語の習得のために英語も学び直している。5年間も旅をし続けていることで、英語でのコミュニケーションは問題ない(ちなみにアメリカ英語)。だが数ヶ月前、私の師匠から「3年後、仕事で家族でドバイに引っ越すことになるんだけど、あっちの暮らしが落ち着くまで、通訳兼ベビーシッターで一緒にドバイに来ない?」と。
世界を飛び回って、仕事もできる人間になりたいと思っていたし、ちょうどいいチャンスだ。返事は迷いなしに、イエス。
「世界の中心はイギリスだし、アメリカ英語だと契約書が通らない国も多いから、イギリスのビジネス英語を身に付けておいて欲しい」と言われ、私はその足で近所の図書館に向かい、イギリス英語に関する本をどっさり借りて、その日から勉強を始めている。
同時にこの数ヶ月間は、ツタヤで偶然声をかけられて仲良くなった、アメリカ人夫婦のベビーシッターもしている。もちろん子供と遊ぶ時にはアメリカ英語を使っている。アメリカ人の強烈なテンションと、前つんのめりなスピード感覚や、終わりのない上昇志向は、休まることを知らないが。
これらは一時帰国の間で引き寄せ合ったものだ。ちなみに、私は自他共に認める影響されやすい人間である。それが悪いこととも全く思っていない。人に影響を受けなければ、いったい何に影響を受けて生きていくのだろう?
影響を受けようとしない人には成長もへったくれもないだろう。
小さい頃は親に、大人になっても友人や上司などの他人からの影響に加え、漫画も、スポーツも、ゲームも、美しい街も、孤独な夜を救う音楽も、夢のきっかけだって、すべて人が関わっている。
「人の役に立つこと」「ワクワクすること」を軸に、縁あることを頼りに変化させていく人生は、RPGゲームのようで気に入っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
確かに小さい頃から、ブロードウェイや宝塚の舞台がテレビでやっていれば欠かさず見ていた。あの非現実的な空間で、現実離れした衣装に身を包んだ俳優が演じる世界に、なぜか強烈に惹かれるのだ。
ミュージカル映画は、えーまた見てるの?と周りが呆れるほど、繰り返し見るし、ニューヨークのブロードウェイやパリのオペラには、例え1人だろうが言葉がわからなかろうが、足を運んでいる。
「ホントそうゆうの好きだよね〜」とよく友人や彼氏に言われるが、過去の記憶だと言われれたことで納得がいった。
シェイクスピア物語は、登場人物がほぼ王室関係者であり、身分階級の時代だからであろうか、ゴマをすって王位継承権を得たり、心底慕っているフリをして暗殺したり、はたまた亡霊が復讐を促したりと、すべての物語において、皮肉めいた表現があちこちに見られる。またその言い回しは、イギリス英語と全く同じだ。はっきりものを言わずにスマートにことを成すのが美しい文化なのだろう。
今で例えるなら、人の子に「やかましい」と言う代わりに
「お子さん、ピアノがお上手ね、賑やかでよろしいこと」
「あら、うるさくてどうもすみません。注意しておきますので」
という、京都独特のあの表現だ。
国を代表する小説や物語は、その国の性格を知るのにいい手がかりとなる。物語には亡霊が出てくる話もよくあるが、多くのイギリス人は幽霊を信じているし、実際に幽霊が出る物件は人気の為、価格が下がるどころか上がるのだ。
アメリカに影響を受けている日本において、私たちがよく耳にする英語は、映画やドラマを始め、ぐさっと刺さる程に単刀直入なアメリカ英語だ。
なぜ同じ英語なのに、国によってその性格が違うのだろうと思うが、物語1つ読むだけでも、イギリスと言う国の性格が表れているので納得がいく。アメリカ英語がイギリス英語に比べて、言葉数が少なく単刀直入であるのも、無駄を嫌い、スピード勝負で新しい価値を生み出す競争社会な性格が少なからず関係している。
「おもてなし」や「もったいない」という多言語に訳せない言葉だからこそ、日本独特の文化であるように、文化と言語はリンクする。
同時に、私が縁あって引き寄せているあれやこれやのすべてもそれぞれ絡み合ってリンクしているように思う。人は日々そうやって人生をクリエイトしていくのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
