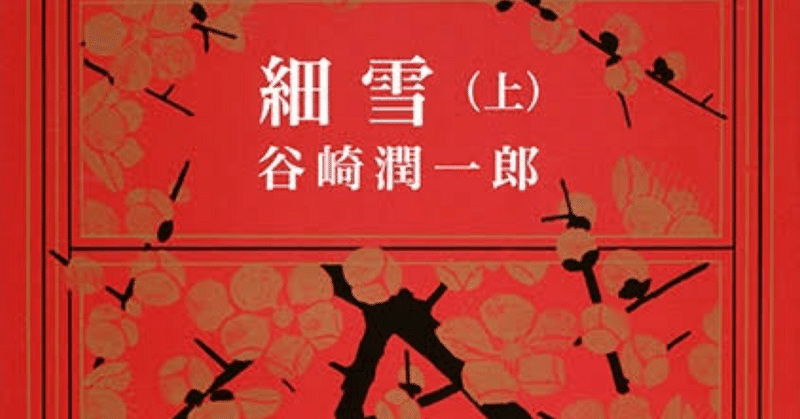
【ゆる批評】細雪2.0(その2 女性の群像悲喜劇)
『細雪』は4人姉妹の物語である。
わたしは、どうもこの「4」という数字が気になる。
モデルとなった谷崎夫人の姉妹が4人であったことに帰結できるが、4人姉妹の物語あるいは4人の女性の物語は、奇遇にも古今東西で複数存在している。
1995年に金井恵美子が、80年代を舞台に4人姉妹を描く『恋愛太平記』を発表。2015年に、三浦しをんが『あの家に暮らす四人の女』、2016年に綿矢りさが『手のひらの京』(これは3人姉妹のお話)を発表する。
「姉妹」に限定せずとも女性4人の群像劇には中国系アメリカ人作家Amy Tanが、中国系アメリカへ移民の4組の母と娘を描いたThe Joy Luck Club (1989) がベストセラーとなった。
映画化もされた。
日本では宮尾登美子が土佐を舞台に元芸妓の4人の娘の生涯を描く『寒椿』(1977)がある。
4に注目するなら、ドラマも映画そうだ。
HBO制作の『セックス・アンド・ザ・シティ』も『ガールズ』も。
韓国映画SUNNY(これは5人か)、漫画原作のNHKドラマ『デイジー・ラック』も4人の女性。
古典に話を戻すと、イギリスでは『高慢と偏見』、アメリカでは『若草物語』が、長らく人々に愛される、4人の女性の物語として残っている。
4人姉妹、あるいは4人の女性の物語が多いのは、なんでなんだろう?
モデルはモデルとしているわけだけれど、ある程度のフィクション性を加えて4人の女性の人生を語ることには、どういった因子があるのだろう。
自分なりに、考察してみた。
女性のアンビバレントさ
女性の群像劇の数々は、女性の生き方とか人生設計のアンビバレントさの表れ、かもしれない。
ヒロインの人生を、書き手がつくることは、たとえフィクションであっても大きな恣意性を孕んでいて、責任が重い。
そのヒロインが1人しかいなければ、その生き方を指示してるような物語空間を創り出すことになってしまう。
結婚して幸せになること、はたまた手に職をつけて経済的に自立して恋愛を恋愛として楽しむこと、有閑夫人になって不倫三昧すること。
別にどうだっていいのだ。フィクションなんだから。
でも、これらのフィクションにおいて女性を取り巻くのは(時代も手伝って。今ならここまで単純な話じゃないわけだけど)小さな物語、自分の半径10メートルくらいで起こる出来事。
悪く言えば閉鎖的。(よく言えば身近な物語。)
「フィクションなんだから、どう描いてもいい」の法則が、このことで少し揺らぐ。
『若草物語』の時代、小説には今よりも(少女たちの希望の光になる、お手本になる、というような)道徳教育機能があった。
「家の中」という私的領域を描いているわけだから、読者の道徳規範や価値観に添わせなければならないだろう。(暗黙の、表現の不自由とでも言うべきなのか。)
だから、当時の道徳観的に『細雪』を妙子だけの話にはできないし、『若草物語』はメグやエイミーだけでなくジョーを据えることで、家庭の外に生きる女性の物語を、少女達に提示したのだろう。
幸も不幸も
女性の群像悲喜劇の中で、特に私のこころに大きく残っているのは、
前でも触れた宮尾登美子著『寒椿』だ。
土佐高知を舞台に、同じ芸者置屋で育った芸妓4人の戦前戦後を通した人生を、置屋の娘悦子がその記憶を掘り起こしていくという小説で、章はこの4人の女性それぞれにスポットライトを当てている。
宮尾登美子って、女性の苦しみを書かせたら右に出る者はいないのではないだろうか、と思うのである。
4人のうちで、最も年上の澄子は、芸妓と娼妓を経て自らの男運の無さに気づくわけであるが、そんな折に出会った銀行の頭取と深い仲になる。
彼の愛人として家までも手に入れ、芸妓として最高の出世をしたと思った挙句、階段から落ちて全身麻痺を負ってしまう。
その後、3人の芸者の話が続くのだが、これがなんとも。
読むに耐えがたいほどつらい。
特に、真ん中2人の話は、貧困、親からの虐待・ネグレクト、朋輩との確執、客商売のつらさ―この時代の女性の辛さを全て集めたんじゃないだろうかというほどつらい。
最後の章の、妙子は「利口で無口だ」と描かれる。
彼女は後に、バーで知った男性と結婚し、社長夫人になる。
この出世を、芸妓時代の朋輩からは僻まれるわけだが、
夫の会社が軌道に乗るまでは、彼女の血反吐を吐くような努力があったことが明かされていく。
ヒロインは1人では足りない
苦しみ、貧困、幸不幸を描こうとするならば、ヒロインは1人では足らない。
結局のところ、『寒椿』は、幸不幸に関わらず全員が過去に(そして現在も)芸妓であったことの業や禍根を背負って生きる運命にあることを考えれば、この中の誰かのみをヒロインにすることは完全に「足りない」のかもしれない。
一方で現代のフィクションも、ヒロインが1人では不十分だろう。『セックス・アンド・ザ・シティ』(現代、といってももう20年以上前になるんだけれど。)仕事ができ、性に放埓なサマンサだけではだめだし、かといって保守的なシャーロットだけでも足りない。これは、傷を描くためではなく、キャリア考察の観点で。
ヒロインが「足りない」ことは、
女性の人生を、得てして影響力のあるフィクションの中で(すら)定義することが、つまり1つに限定してしまうことが、
難しく、危ういからである。
女性は家の中か外か、両方か、を書き手(主体)は常に考えあぐねていることは、現実もフィクションも(リアリズムである限り)、古今東西変わらないのだろうし、だから多様で面白い部分もある。(そんな程度の多様さは多様さじゃない!と言われかねないが。)
多様であり、アンビバレントなのだ。
そして、彼女達が受けてきた傷や抑圧は、1人のヒロインに背負わせられないほど深く、悲惨なものだったことを群像劇は語る。(『寒椿』とAmy TanのThe Joy Luck Clubがそうだと。両方、女性の抑圧が激しい東アジアの物語ですね。)
その点で、「4」は非常に据わりの良い数字なのかもしれない。
1では足りない。
2だと、保守とリベラル(あるいは最高と最低)の両極しかいない。
3でもいいのだが、もう少しスペクトラムに、中間層を厚くしたい。
だから4。(もしかしたら4は、書き手のキャパ最大限なのかもしれない。)
女の子、女の生き方は今も昔もアンビバレントで、選択あるいは個人の努力で幸にも不幸にもなってゆく。それは、旧時代を経て戦争を経て、今再び新自由主義時代の中で増幅されているのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
