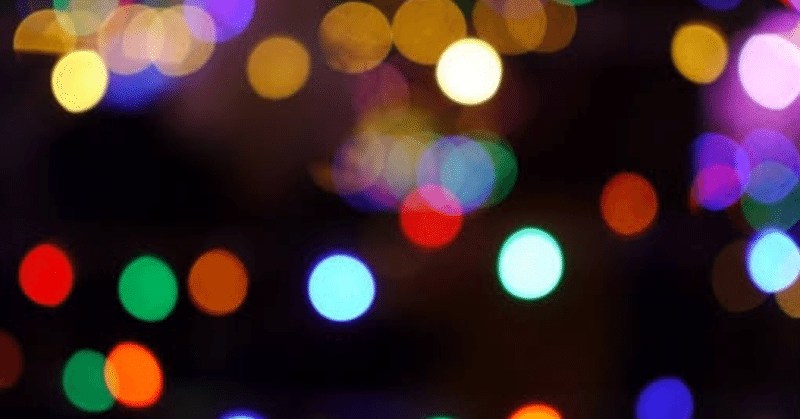
【ゆる批評】エモくてたまらないものたち2019
なんだかいつも、まとまった感想とか小説を書いているのだけど、ここでは徒然なるままに「エモい…」と、感じる本、漫画、音楽について書きたい。
私は、「エモい」という言葉がスキだ。
郷愁、後悔、甘酸っぱさ、懐旧、懐古…さまざまな言葉と意味が、この「エモい」というひとことに集約されてしまう現象には、否定的な声もある。
他にいくらでも言い表しようのある、様々な感情が、ひとこと「エモっ。」と言えば済んでしまうから。
でも、私がこの言葉をいいなぁ、と思うのは、「エモい」という言葉が持つ「共感力、共感のパワー」の可能性に惹かれるからである。きっと、エモい、という言葉を私たちが発するとき、その感情は、対象の中で、もしくは自分の中のみで認知され、完結されるというよりは、見知らぬ人同士が共有する何かしらのムードがあるのだと思う。
「エモ小説」の代名詞のように(これがどこまで人口に膾炙しているかはちょっと不明なんだが)なっている燃え殻さんの、『ボクたちはみんな大人になれなかった』。
嘉島唯さんの、この小説に対する見事なまでに批評は、作品の「エモさ」の正体を「固有名詞」と結びつける。
主人公が、行きずりの若い女性とラブホテルにいる。
そこで、宇多田ヒカルの『Automatic』が流れる。女性が「ねぇ、懐かしくない?」とつぶやく。
この小説には、当時の流行音楽、漫画、アニメの固有名詞がふんだんに登場する。きっと、そういっためまぐるしい「消費文化」が、最も効果的に小説が描く当時の感情を、特に「恋の記憶」を呼び覚ますからだろう。
サブカルに傾倒するカップルたちが、別れた後も、その曲、アニメ、漫画を思い出すことで、当時の記憶が誘発され、脳をかすめる、というプロセスだろう。だからもちろん、読み手側も宇多田ヒカルの『Automatic』と目にすることで、「自分の体験」も引き起こされる。
しかしながら、「エモさ」の共感パワーは、ここにとどまらない。
私は、1996年生まれで『Automatic』はテレビの懐メロ特集で見たことがある程度だった。(音楽に明るくなくて申し訳ないが)
だけど、この小説を読むと、たとえ『Automatic』時代を知らなくても、この曲名があることで情景がはっきりするのだ。「ラブホテル」だけだと、あまりに普遍的でぼんやりとする、頭の中の輪郭が、固有名詞によって具体的なものになる。これが、たとえその時代、空間を知らなくても「エモさ」を発動できる仕組みなのかもしれない。
「あー、あのくらいの時代の曲がなんとなく流れてる感じの、ラブホテル。」と、頭が勝手に演出する。
こういう、「固有名詞によるエモさ」、「具体性への共感」(たとえその時空間を知らなくても起こる)、あるいは共感的な懐古、ががんがんに発動されるものたちを紹介していきたい。
小説
①ダンス・ダンス・ダンス(上・下)/村上春樹
「固有名詞➡エモさ」の源流って、村上春樹なんじゃね?と思う。
もうこれまでたくさんの批評家が指摘しているように、村上春樹は実在の音楽(特にジャズ)、映画、あるいはファミレスなどのチェーン店の名前を小説に多く登場させることで知られている。
(あらすじは、かなり複雑なので敢えて書かないが、)『ダンス・ダンス・ダンス』は春樹の小説の中でも多く、読み手の感情をかきだすような固有名詞が登場する。冒頭。主人公はフリーライターとして仕事をし、以前一度泊まったきりの、札幌にある「いるかホテル」というシュールでキッチュなホテルのことを幾度となく思い出す。非現実的な架空のホテル、と「札幌」という地名の具体性の不調和が面白さでもあるし、主人公の受け身なのにセンチメンタルな動作や心情は、なんだか燃え殻さんの小説にも通じるエモさがあると思う。
②ナイン・ストーリーズ/J. D. サリンジャー
ここへきて、1950年代のアメリカの小説、という固有名詞も共感もへったくれもないようなものを紹介してしまうのだが。これが、エモい。(主観です。すみません。)
『ライ麦畑でつかまえて』の、サリンジャーが書いた短編集。
収録されている「バナナフィッシュにうってつけの日」を勧める。
非常に短い小説で、あらすじは戦争後遺症で精神に異常をきたしたと思われる青年シーモアと新婚の若い妻ミュリエルがハネムーンで、海辺の街のビーチ、ホテルで過ごす物語だが、この夫婦はほとんど会話をしない。
物語はほとんど、涼し気なビーチでシーモアが少女と交わす会話、そして瀟洒なホテルの一室でミュリエルが母親と話す電話で展開される。
恐らくは高級なホテル、灰皿、女性誌のセックスに関する記事を眺めながらマニキュアを塗るミュリエル…エモさには何らかの「安っぽさ」が不可欠なのだろう。やはり、この小説も、ホテルという異空間と生活感溢れるものの共存が読んでいて心地いい。
ここまで書いて気付いたけど、「ホテル」って、エモさのマジックワードなのだろうか。「エモい」という感情に限らないけれど、燃え殻さんの小説も、『ダンス・ダンス・ダンス』(春樹の小説にもホテルは多く登場する)も、「バナナフィッシュにうってつけの日」にも(サリンジャーの名作『ライ麦畑』にも高級ホテルが出てきますね)ホテルが出てくる。
入って、泊まって、出るだけ。何をしてもいい、料金を払えばちょっと散らかしたってかまわない、生活から逃避できる。ホテルはリアル小説の「異空間」ですね。
音楽
①大阪恋物語/やしきたかじん
語りの一人称は女性。
大阪を舞台に「夢を追いかける恋人」を諦め、別れを告げる歌。
金色に染まった街が 哀しいほどきれいやね
二人見降ろす人の河 どこへ流れるんやろ
うまいこと言われへんけど 夢追いかけるあんたを
待てないうちのせいやから 自分のこと責めたらあかんよ
大阪恋物語 安物の恋かしれんけど
うちは死ぬまで忘れんからね 誰よりも素敵な人
ずっとどこで見つめてるから 必ず星を掴んでね
歌詞の関西弁はいかにもやしきたかじん。
でも、エモさの正体はそこだと思う。
関西弁と、タイトルにもずばり入っている「大阪」という地名の具体さ。
わざわざ恋人が「夢を追いかけて東京に行く」というようなことが歌詞に入っていないことから、「大阪で星を掴む」、じゃあ恋人は芸人を目指してたのかな、とか、想像は具体的になる。
この曲のいいところは、歌詞が演歌と同じレベルでセンチメンタルなのに、メロディラインがオシャレなところ。具体的な「大阪」という地名だけなら、上田正樹の「悲しい色やね」でもいいだろう。
でも、「悲しい色やね」はメロディも悲しい。まあ、もちろんそれはそれでいいのだけど、『ダンス・ダンス・ダンス』でも指摘したような「不調和」、悲しい歌詞と失恋ソングにしてはどこかすがすがし過ぎるような組み合わせが面白い。
そしてたぶん、「エモい」という感情は、あまりに重たい懐古的な感情のことは形容できないのだろう。演歌や一般的な歌謡曲が持つような重さのことは指さない。そして、代わりに、この曲の歌詞「安物の恋」にもある、「安さ、キッチュさ」が尊ばれるんだと思う。
②The Way We Were/Barbra Streisand
まあ、エモい歌なんて無数にあるんだけどさ。
失恋ソングの最高傑作なんじゃないかと思うこれは。
同名の映画、The Way We Were(1973)(邦題は『追憶』、まあ当時の洋画の邦題は大概目も当てられないほどセンスがないと今では言われがちだけど、私はこの訳はなかなかいいと思っている。)
ものすごく端的にあらすじを説明すると、大恋愛で結婚したカップルが、お互いの「思想」、「生活」が原因で子供がいながらも破局し、その後一度だけわずかな再会を果たす、というもの。
「嫌いになったわけじゃない」というのが、この映画と歌のポイントだと思う。
Can it be that it was all so simple then
(すべてが、そんな単純なことだった?)
Or has time rewritten every line
(それとも、時が全ての台詞を書きかえでもしたのだろうか)
If we had chance to do it all again
(もしもう一度全てやり直せたら)
Tell me would we, could we
(できるのだろうか、教えてよ)
Memories May be beautiful and yet
(思い出たち。それはまだ、きっと美しくて)
What's too painful to remember We simply choose to forget
(あまりに思い出すのがつらいから、私たちは忘れることを選んだ)
So it's the laughter
(だからもう、笑い話)
この歌は別に、固有名詞が出てくるわけでもないし、エモさにつきものの共感を引き起こす安っぽさもないが、この曲がやはり究極の「追憶、懐古ソング」であることが、なんていうかきゅーん、となってしまう。
思い出すのがつらくて、忘れたって、あ、そんなカッコ悪いことズバリ言っていいんだなみたいな。
そして、この曲もまたメロディと曲調は、かなりさっぱりしている。
さっぱり、というか淡々としているのだ。するすると歌詞が流れていく感じ。重たい恋の記憶を謳うのに、じめじめとしていないところ。これがエモさの側面かもしれない。「エモさ」の本質は、その軽さ、ふわっとした残り香のような一瞬の「懐古」なのかもな、と思う。
漫画
プリンセスメゾン/池辺葵
キーワードは、東京、女性、家、丁寧な暮らし。
東京を舞台に、「持ち家」を買うことを目標に、日々仕事と節約、不動産の内見を頑張る居酒屋勤務の女の子「沼ちゃん」の家との出会いを軸に、様々な「女性ひとり」と家の物語がオムニバス式に交互に語られていく。
周囲が結婚し、家族を持つ。彼女たちはそれを、絶対的な価値にしない。
生きる意味は、仕事でもあるし、趣味でもある。もちろん、「家」でもいい。丁寧な生活だっていい。「価値」あるいは「価値観」がこの漫画の軸になるテーマだ。
この漫画の「エモさ」に関して言うなら、それは「生活のエモさ」だ。
上述のように、また嘉島唯さんが「生活感」をエモさの正体のひとつとしているように。「エモさ」はグレートな、何か大袈裟な感情よりも、より「毎日」everyday lifeに即した感情なのだろうと思う。
すっきりとした玄関、カーテンから透ける日差し、朝のコーヒー、目玉焼きを焼くフライパン、可愛い柄のクッション。ケトルの湯気、雑誌、卵かけご飯とお味噌汁。
特に説明なく現れる、細い線で描かれた「生活」のイラストが、美しいと感じる。「エモさ」は時に、何か昔の恋(それも異性愛中心の)の思い出を限定的に指しているような感もあるけれど、この漫画はそうではない「エモさ」を感じる。「自分ひとりの部屋」で快適さを追求すること、そして静かに時の流れを感じること。その生活感が、読んでいて心地いい。
徒然なるままにここまで、私が感じる「エモさ」のぎゅっと詰まった、詰まりまくったモノたちを紹介してきたけど、実際この曖昧で微妙な感情なんて人それぞれだし、世の中には無数エモコンテンツが氾濫しているだろう。
でもここまで書いて気付いた、非常に曖昧な感情、「エモさ」の正体をなるべく正確に要素を入れるなら、
①固有名詞、具体性を持った懐古、懐かしむ気持ち
②生活感、日常性、安っぽさ、キッチュなものが醸す雰囲気
③重くないこと。ふとした時に感じ、すぐに忘れるような良さ、なつかしさ。
④受け手の共感性を引き起こす。
このようにまとめてみた。
※未だ研究中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
