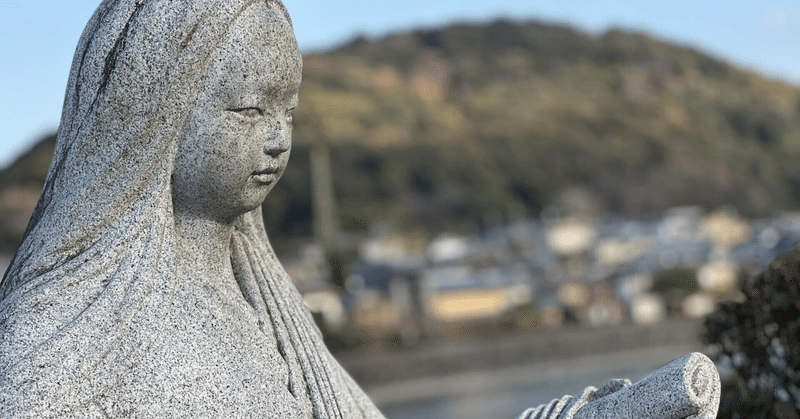
スタンスを『令和源氏物語』に変えたこと
みなさん、こんばんは。
すでにお気づきかと思われますが、表題「紫がたり」のサブですが、『新源氏物語』であったのを『令和源氏物語』に変更致しました。
そもそも私の書きおろした源氏物語は創作部分が多いため、表題を「紫がたり」と改めましたのは以前コラムに書いた通りです。
源氏物語は言わずと知れた悠久の名作、千年以上も語り継がれてきた物語です。
もちろん名だたる研究者や学者さん、訳者の方々がそれぞれの時代にそぐって読みやすく、現代語として連ねてこられたわけで、それらすべてが「新しい源氏物語」であったと私は考えております。
とある時にお酒を飲みながら、こんな話になったわけで、この「令和」だからこそ、私の源氏物語は『令和源氏物語』であるべきだと友人に指摘されました。
「なるほど」
とまぁ、納得した次第で、変更させていただきました。
そして私が以前掲載いたしました落窪物語「昔 あけぼの シンデレラ」も同じ法則で『令和落窪物語』と相成りました。
ちょっとパリッとして、腑に落ちたわけです。
来年は紫式部さまがフィーチャーされ、源氏物語も何度となくやってきたブーム再燃となるでしょう。
私の書く源氏物語も残り80話を切りました。
私の源氏物語は源氏が生涯を閉じる「雲隠」までで一区切りです。
通常の区切りでは、次帖「匂宮」「紅梅」「竹河」までが含まれ、いわゆる『宇治十帖』は、「橋姫」から「夢浮橋」となっております。
さて、賢明な皆様ならばここに大問題が出来することにお気づきでしょう。
今までの法則に従いますと、帖ごとに書いていますので、宇治の恋物語は「匂宮」から始まらなければなりません。
薫の話なのでそれは、ちょっと・・・。
と、いうわけで、宇治のお話は表題変更さることながら、帖名にとらわれない創作全開のお話となります。
約200〜250話ほどになるでしょうか。
表題はまだ未定です。
推敲を重ねて、書き上がった時点で相応しいものを考えたいと思います。
私がこのような大胆な手法(暴挙?)をとりますのは、とある説、宇治の話は紫式部によって書かれたものではない、という主張に著しく同意しているからです。
それまでは歌がふんだんに詠みこまれ、移り変わる季節の息吹までも感じさせた、美しい語りです。
それが宇治のお話ではいささか乏しいと私は感じます。
自然に囲まれて雄大な川の辺に展開される物語ならば、より季節感、それに揺さぶられる情緒があってしかるべきです。
そして紫式部の手ではないとすると腑に落ちる場面があります。
匂宮が浮舟を川の小島に連れ出すあの場面。
源氏が夕顔を伴い昼間から逃避行したあのシーンのオマージュに思われます。
元祖源氏バージョンでは窮屈な身分から逃れた源氏のおちゃめな面がのびのびと、知的な語らいもありますが、宇治編では逢瀬ばかりでよくわかりません。
ご存知の通り、源氏物語は写本によって語り継がれてきた物語です。
加筆されたり、書き換えられたりと、写本の系列によっては違うエピソードもあるのではないか、とも言われております。
ですから宇治の話は写本した賢しらな女房あたりが書き加えたのだという説もあるほどで、そうなりますと私もそれに倣おうかと考えました。
もしかしたら、私のような女房が創作写本して悦に入っていたのかもしれませんね。
時代にそぐって変容する源氏物語。
その寛容な部分が千年以上語り継がれてきた秘密なのかもしれません。
まずは『紫がたり』源氏の生涯、残り80話ほど、しばらくお付き合いくださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
