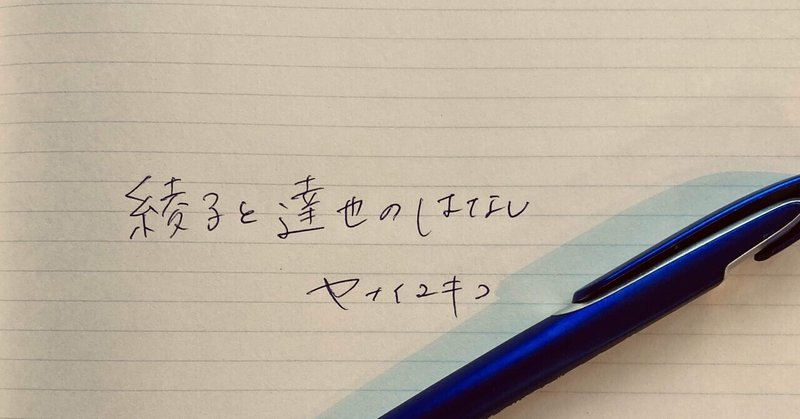
綾子と達也のはなし①|恋は焼きいもから
「綾子(あやこ)さんって、いつもおいしそうな食べ方しますよね」
向かいに座っている達也(たつや)が、今まさに焼きいものひと口目を頬張ろうとする綾子をじっと見つめ、そう言った。すでに勢いがついた綾子の口元はブレーキが効かず、返答するよりも先に、今にも蜜が溢れ出しそうな焼きいもにかぶりついた。とろけるような果肉を口いっぱいに味わいながら「そうかなあ?」と、もごもご答える。一方頭の中は「甘い、濃ゆい、うまい」という焼きいもを賞賛する声が鳴り止まない。視線も達也ではなく、湯気立つ焼きいもの方である。
「バターをのせる選択肢があるって知っていたら、僕も真似したかったのに。もう全部食べてしまってからこれを見させるなんて、綾子さん、罪深いですよ」
綾子と達也は同棲を始めて半年が経とうとしていた。もちろん好き合って一緒に住んでいるが、三つ年上の綾子に対し、達也は未だ敬語が抜けない。「きょうだい間の年功序列が強烈だったもので」というのがその理由らしい。土曜日で仕事も休みだった今日は、二人揃ってスーパーへ行き、一週間分の献立が成り立つであろう量の肉や野菜を次々と買い物カゴに放り込んだ。二つのカゴがいっぱいになる。レジに向かう足が直前で方向を変えた。入店時から買うと決めていた、紅はるかの焼きいもを二本手に取り、スナック菓子の袋の上にちょこんと置く。スーパーの焼きいもは時間をかけてじっくり熱しているからか、どれも甘くて、はずれが少ないのがうれしい。
達也は帰宅してまもなく「僕、腹ごしらえしてから片付けますので」と言って、買ってきたばかりの焼きいもをあっという間に平らげた。そんな中、綾子は買ってきた食材を冷蔵庫や引き出しに手際よく収納し、その合間に加熱しておいたオーブントースターへ焼きいもを入れて温め直す。冷蔵庫から真四角に切れたバターを取り出して小皿にのせ、トースターの上に置いた。焼きいもの温度、バターのやわらかさ、どちらも適度に整って、焼きいもがもともと入っていた茶色いクラフト製の袋に戻す。無糖で氷なしのカフェオレとともにトレーで運び、ちゃぶ台の前に正座して座る。ほかほかの焼きいもを半分に割ると、黄金色に艶めく果肉が「私、おいしいよ」と囁いているようだった。
「こっちの半分あげるよ。バターがまだ白いうちに食べるんだよ。溶ける前に食べる、これ重要」
綾子はそう達也にレクチャーして、ほんのり白くバターが塗られた焼きいもの片割れを差し出す。「半分もくれるんですか!」口ではそう言いながらもうれしそうに手を伸ばした達也はバター目がけて齧りつくと、「綾子さん、天才です」と静かに興奮して、またあっという間に平らげた。
達也は焼きいもに目がない。季節問わず、焼きいもが食べたいという類い稀な男だった。達也が年功序列に厳格な環境で育ったというなら、綾子はそのピラミッドの頂点に君臨する女王様のような立場で育った。綾子の下には、一歳、三歳、五歳と離れた弟が三人いた。ある程度の年齢からは、姉というより保護者のようで、「年下の男は弟にしか見えない」という台詞が彼女の恋愛観を有り有りと示しているようだった。が、同じ職場で後輩の達也がある日、弁当と一緒に焼きいもを持参してきた。さらにそれを、人目を憚らず堂々とオフィスでかぶりついているから、どうにも話しかけずにはいられなかったのだ。
「焼きいも、男の人でめずらしいね」
「そうですか? 僕はそうは思いませんが」
「私の周りの男性陣は、さつまいもを筆頭に、かぼちゃも栗も、どこがおいしいの?って人ばっかり。このおいしさをわかり合えるのはやっぱり女同士しかないと思っているの」
「最近の蜜芋系の紅はるかや安納芋もおいしいですが、シルクスイートは初めて食べた時、あまりのなめらかさに驚きました。だけど、昔ながらのほくほくした、わりと甘味の少ない紅あずまを焼きいもにしたものも好きです、僕は」
それまでなんとも思っていなかった。が、達也の口からすらすら述べられた焼きいも愛をたまたま聞かされた綾子は「こいつは本物だ」と射抜かれて、そのまま恋に落ちた。嘘ではない。
綾子はまだ、先ほどの焼きいもを食べている。
「紅はるか自体がおいしいから、バターがなくてもそれだけで十分スイーツだよね。……あ、そうだ」
キッチンからピンク色の岩塩の入ったミルを手に戻って来た綾子は、ガリガリと焼きいもに塩を振った。
「子どもの頃さ、家の前にゲートボール場があって、その裏が林だったのね」綾子は話し始める。そのゲートボール場には、秋になると枯れ葉がたくさん降ってきて、それを弟たちと集め、焚き火をしたという。綾子の母がそこにアルミホイルで包んださつまいもを何本も入れてくれた。「結局待ちきれなくて、だいたい生焼けの状態で食べちゃっていたけどね」
その焼きいもを待ちわびている間、三、四歳の小さな綾子は愛車の三輪車をひっくり返し、前輪の隙間に小石を挟んでは、手でペダルをくるくる回して石焼きいも屋さんごっこをした。それがなぜ、焼きいも屋を表現していたのか今ではわからないが、小石が車輪から飛び出たら、焼きいもの出来上がり! のような遊びだったはずだ。まだよちよち歩きの弟と、母に抱かれた赤ん坊の次男が写る写真に、三輪車のペダルを得意げに回す、綾子の姿が収められていた。
「焚き火をする時、クリスマスツリーのもみの木みたいな、針葉樹の枯れ枝がよく燃えたんだよね。あれはなんていう木の枝だったのかな」綾子は遠い目をする。
「……たぶん、これじゃないですか?」と、達也は「スギの木 枯れ枝」と検索したスマートフォンの画面を差し出した。
「わあ! そう、これこれ」
約三十年越しの答え合わせは、達也が小学生の時、このスギの枝に火をつけて遊んでいるところをおまわりさんに見つかって、ひどく怒られたという話のおまけつきだった。「火遊びは絶対にダメだ。そして、このスギの木みたいに、トゲトゲした葉はどれもとんでもなく燃えるから気をつけろ」
おまわりさんは小さな達也にそう言って、チャッカマンを回収していったそうな。
「ふふ。なんか人生の格言みたい。一途でいろ。そして、尖った奴と一緒にいるとお前も火傷するから気をつけろ、みたいな」
綾子は塩を挽いた焼きいもをひと口囓った。すでに沁みるほどに甘い紅はるかの糖分がさらに引き立って、身体がビクッとしてしまう。
「綾子さん、またおいしそうな食べ方をしていますね」
達也の眼鏡の奥に、優しくも鋭い目が光っている。
「ひと口食べる?」
と言って、綾子は岩塩のついた焼きいもをスプーンですくって差し出した。達也はしばらく無言で味わった後、ひとつ小さい溜息をついた。
「綾子さん、あなたは天才です」
「本日二回目だね」と言おうとしたその時、達也は綾子の手を取った。焼きいもとスプーンがちゃぶ台の上に落ちて、カタンという音とともに時が止まる。
「綾子さんの、その、ふだんの日を特別な日に変えてしまうような発想と好奇心、行動力に僕はいつも感動してしまいます」
達也の座る方角が綾子にとって逆光で、陰影のついた表情が場の緊張感を際立たせる。鼻筋だけ白く光っている。一直線に伸びたラインが美しいなと思う。
「僕はいつまでも隣で、綾子さんがおいしそうに食べる様子を見ていたい」
「いつまでも」という言葉に綾子の頬は熱くなり、身体の中心にきゅうっと何かが寄り集まってくるような感覚があった。鼓動が早くなった。小刻みに震えているように見える達也から、目が離せなかった。
「いつまでも、おじいちゃんおばあちゃんになっても、二人で焼きいもを食べたい」
綾子は笑った。そんなプロポーズ、世界でたった一人、達也しかできないと、泣きながら笑った。達也はすぐにでも泣いてしまいそうで、唇をぐっと結んで堪えている。
「はい。こちらこそ、よろしくお願いします」
綾子はぺこりと頭を下げて微笑む。それを見て安堵したのか、達也の溜め込んだ涙がひと粒頬を伝った。
ふいに立ち上がった綾子が、ごま塩を持ってきて、半分がさらに三分の一ほどになった焼きいもにパラパラとかけた。
「食べる?」
二人で最後のひと口を頬張る。
「綾子さん、あなたはやっぱり天才です」
一話目は「さつまいも」をテーマに書きました。二話目のテーマは「カレー」で、11月末に更新予定です。よろしくお願いします。
※この小説は「mg. vol.7 さつまいもをめぐる」に掲載しています。「mg.」はこちらの通販で購入できます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
