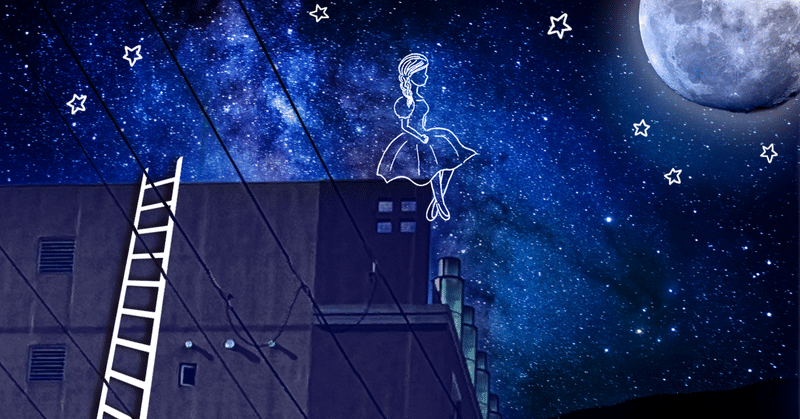
【短編】君が好き
久しぶりに真希とふたりだけで食事をした帰り道、最寄りの駅を降りてから静まり返った深夜の住宅街を真希の家まで並んで歩いた。家々の窓からカーテン越しに灯りがみえる。白く光る街灯がぼんやりと道路に光をおとしている。
夜空を見上げても星なんてひとつも見えない。暗闇になろうとしているのになりきれていないような薄明るい夜空の下を、遠くを走る車の音しか聞こえない深夜の住宅街をふたり並んで歩いた。
ふたりの影と靴音だけがあとを離れずについてくる。モンクレーのダウンを着た真希の栗色の髪が風にそよぐ。
私はふいに真希の手を握りたくなった。そしてしばらくためらった後、右手を真希の方に寄せようとしてやめた。行き場を無くした私の右手は私と真希の間をふわふわと漂ってからチェックのステンカラーコートのポケットの中に収まって、ポケットの中のスマホをぎゅっと握った。
「今日はごめんな。急に呼び出したりして」真希がポツリと言う。
「いいよ。気にせんとって」そして友達なんだからと言葉を継ごうとしてやめた。
真希は大学を卒業して三年ほど働いてから同じ職場の男性と結婚して夫の地元の金沢で暮らしていた。子供はまだいなかった。夫の両親との関係が良好だったのかまでは知らないけれど夫とはうまくいっていると聞いていた。だからひと月前に彼女の口から夫と離婚したと急に聞かされたときは驚いた。
真希は僅か二年で結婚生活に終止符をうった理由を言わなかったし私も訊かなかった。多分私からは訊かない方がいいと思った。それに離婚した理由なんてそのうち分かるだろうし別にどうでもいいことのようにも思えた。どんな事情であれ真希は帰ってきた。私達が昔一緒に過ごしていたこの街に。
「さっきの鴨鍋とお酒美味しかったな」真希はそういいながら微笑んだ。
「金沢にいるときは魚ばっかり食べていたような気がする」そう言いながら真希が私の顔をじっと見つめる。
「わたしと一緒にいれば何処でなにを食べたって美味しいよ」私がそう言うと確かにそうやねと言って真希は笑った。その笑顔をみつめながら真希が高校生のころはどんな表情で笑っていたかを思い出そうとしたけれどやめた。昔はもっと、なんて言うような事を思いたくなかった。
♢♢♢
「もしもひとつだけ願い事が叶うとしたら優希はどんな願い事をする?」
高校生の頃、真希はたびたび私にそう言った。そんな真希が教えてくれる願い事は決まって毎回違っていた。真希は浮気性やなと言って私がそのことをからかうと、真希は浮気性とちゃうしと言い訳をしてバツが悪そうな顔をしながら笑った。
「優希の願い事は何なん?」真希が私にそう訊ねるたびに「好きな人と一緒になりたいっていうこと」と答えた。
「好きな人って誰なん?」といつも真希は私に訊いてきたけれど「いまはいないよ。好きな人が出来たときにその人と一緒になりたいっていう意味だよ」と答えた。そう言うと「そうなんや。優希は今は好きな人はおらんのやね」真希はそう言って微笑んだ。
真希と知り合ったのは高校一年生の時だった。中等部から内部進学で高校に入った私とは違って真希は公立中学から入学してきた生徒だった。そんな真希は内部進学の私に対して最初のうちはよそよそしい振る舞いをみせていた。
真希は小学生の時に父親を亡くしていて母親と二人で暮らしていた。私も中学生で母親を亡くしていて父親と二人で暮らしていたから似たような境遇だった。そしてお互いにそのことを知ってからは急速に仲良くなっていった。そのうちに私達はまるで仲の良い姉妹のようにずっと一緒に過ごすようになった。
真希は良くいえば年の割には自立していたし悪くいえばよそよそしい所があった。私や他の友人達が真希に対して心を開いているほどには真希は私達には心を開いていないように思える時があった。でもそのことを他の友達は気づいていないように見えた。
でも私はきっと真希は誰よりも多くの秘密を心の中に隠していると思っていた。そして、そのときの私は真希の視線からそれが何なのか分かったような気がしていた。それはきっと真希が隠していた色々な秘密の中でもとくに大切な秘密なんだということも多分私は知っている。そう思っていた。
♢♢♢
信号が青に変わった。アスファルトの上に引かれた横断歩道の白線が薄い青色に染まった。
「次の交差点まででいいよ。優希の家は左に曲がらなあかんやろ。私は真っすぐやし」そういって真希は歩き出した。真希の履いているグレーのニューバランスのスニーカーが横断歩道の白線を跨ぎ、白いロングスカートの裾がゆれる。
「せっかくだからもう少し一緒に歩きたい。真希の家の前まで行くよ」そう言いながら私は速足で真希の横に並んだ。
真希は私の顔を見ながら「優希は優しいな。昔から優希がいちばん優しかった」そう呟いた。私はそんなことないよって言おうとしたけれど黙った。
「嫌なことがある度にいつも優希に聞いてもらってた」
そうだね。真希が打ち明けてくれる話をいつも聞いてた。そうすればいつか真希が心の壁の向こうに隠している秘密を打ち明けてくれるような気がしたからだった。
♢♢♢
「他のみんなは絶対に分かってくれないと思ってた。でも優希だけは分かってくれると思ったし、分かってもらいたかった」
真希が心の中に隠していたいくつかの秘密。その中でもきっと一番隠しておきたいと思っている秘密。そしてその秘密は私が隠していた秘密と同じ種類のものかも知れないっていつからかそう思っていた。
お互いの心に秘めていたそれぞれの秘密を真希と確かめ合ったときから私達は付き合いはじめた。誰にも気づかれないように、足音をたてずに近づいてくる猫のようにそっと。
やがて私達は誰にも見つからない場所で普段は服の下に隠している肌をさらけだして、身体を重ね合ってお互いの温もりを確かめあうようになった。真希のすこしだけ汗ばんだ肌に自分の肌を重ね合わせながらお互いの唇を求めあって、ふたりは溶けて混ざり合うようにしてひとつになった。そんなふうに一緒にいるときだけ私達は本当の自分を取り戻せたような気持ちになれた。私達は誰からも祝福されなくても構わないと思ったし、ふたりで一緒にいられたらそれだけで充分だった。
♢♢♢
「生きる意味なんてあるのかな」真希がよく言っていた。
生きるのに意味なんてないよ。たまたま生まれてきて死にたくないから生きているだけだよとその度に私は真希に言った。
「それじゃあつまらないよ。私は何者かになりたい」いつも真希はそう言いながら何かに対して苛立っているように見えることがあった。そんなときの真希は普段よりも積極的に私を求めてきた。私はそんな真希の様子をみながら真希は私の知らない何処かに行こうとしているのかもしれないと思うようになった。そんな日常を過ごしながらも私は残り少なくなった高校生活が終わったあと私達はどうなるのだろうと不安をおぼえるようになった。
高校卒業後の進路を決める時期に真希は東京の大学に入りたいと言いだした。私は地元の女子大学を受験するつもりで準備をしていた。真希も地元の大学に進学すれば離れずに済むと思っていたから真希が東京の大学に進みたいと言ったとき私はショックを受けた。でも真希が東京の大学を希望しているのは複雑な家庭の事情のせいで親元から離れたいからだということも知っていたから引き留めることなんてできなかった。
真希は私とは別れないと言った。それに遠距離恋愛なんて珍しくないよと言った。私はその言葉を信じるしかなかった。私達は四月になって離れ離れになるまでの間は出来るだけ長い時間を一緒に過ごした。そうして四月になって私達は遠く離れた場所で暮らし始めた。
真希は夏休みや冬休みには私達の地元に帰ってきた。私が東京に遊びに行くこともあった。多くのカップルに訪れる倦怠期もなければマンネリを感じることもなかった。会えない時間が長い分より深くお互いを求めあうようになっていた。そう私は思っていた。
真希は大学二回生の夏にサークルの男性の先輩と付き合いはじめた。真希から突然そのことを知らされたときは驚きのあまり何も考えられなくなった。
いつも近くにいるその人のことを自然に好きになったと真希は言った。信じられなかった。高校生のときの誰にも言えずふたりだけで温め続けたあの気持ちは一体何だったんだろうと思った。
初めての失恋だったから受け止め方も何も分からなかったし、失恋の痛手は思ったよりも深く、何もすることが出来なくなってしまい学校もアルバイトも数日間休む羽目になってしまった。
でも仕方ないと思った。むしろそうなるのが自然なんだって思うようにした。そしていつの間にか私もバイト先の男性スタッフのからの求めに応じてごく自然に付き合いはじめた。なんだ、私もそうだったんだと思ったし、自然とそういう風に変わっていくのかもしれないなんていう風にも思った。
それからは私と真希がふたりで会う機会は年に一回位に減っていた。私も彼氏が出来てからは真希よりも彼氏との約束を優先するようになっていた。でも彼氏と一緒に過ごしている時などふいに場違いな服を着て間違えた部屋にいるような、そんな落ち着かない気持ちになることが次第に増えていった。
社会人になり後輩の面倒をみることにも慣れてきた頃、真希が結婚すると聞いた。もういいかげん真希への想いは終わらせていたつもりだった。
真希以外の誰とも付き合わないと決めていたわけではない。男性を拒んだつもりもない。お互いに好意を持っていながらも交際まで発展しなかったこともあったし一夜だけの関係を結ぶこともあった。
でも次第に私の身体は男性の身体を拒むようになっていった。そして真希とお互いの温もりを確かめあったことを思い出して胸が苦しくなることが増えていった。そのたびに私はいまでも真希のことを愛しているんだということを心でも身体でも気づかされることになった。
♢♢♢
「なぁ、私達はこれからもずっと親友やんな」真希の家までつづく緩い上り坂を歩きながら真希がそう言って私の顔をみた。真希も本当は私の気持ちをきっと知っているくせに、そんな風に試すようなことを言う。
「親友だけじゃ嫌やって言ったらどうする」そんな風に返してしまってから、なんでこんな駆け引きめいたやり取りをしてしまうんだろうと自己嫌悪になる。なんでこんな風に中途半端な言葉で誤魔化してしまうのだろう。いまでも真希のことが好きだって言ってしまいたいのに。
「ねえ、もしわたしが昔みたいに真希と愛し合いたいって言ったらどうする」
今更ためらうようなことでもないと思い出来るだけさり気なく聞こえるように言ったつもりだった。そして真希の口から何かしらの言葉が出てくるのを待った。ほんの僅かな間が開いた後、真希は私の言葉には答えようとせずに「ねぇ、ワタシとダンナの間に何があったか訊きたい?」と私の顔を見ずに言った。
「うん、聞きたいけどまた今度」それよりもいま私が言った、昔みたいに真希と愛し合いたいって言ったらどうするという言葉の答えが欲しい。でも真希は何も言わずただ微笑んでいる。
そんな真希の微笑みをしばらく見つめた。微笑んでいる真希の顔はどことなく弱々しくて口元がかすかに震えているように見えた。きっと泣きたいんだと思った。離婚した理由は訊いていないけれどきっと真希だって傷ついている。聞きたいけどまた今度なんて言うべきじゃなかったかもしれない。
それとも真希は私とはもう昔のようにはなれないと思っているから咄嗟に話を逸らしたのだろうか。
「そうか。じゃあ今度会ったときに聞いてな」そう言うと真希は今度は上手に笑って見せた。
それから暫く私達は無言のまま歩いた。そして昔よく二人で時間をつぶした公園の前を通り過ぎると真希が母親と暮らしているマンションが見えてきた。
マンションの前まで来ると、今日は有難うと真希が言った。
「そんな顔をせんといて。わたしは大丈夫やから」そう言うと真希はおどけたような顔をしながら微笑んでみせた。私はそんな真希の様子を見て笑いながら「うん、分かった」と返して、「いつでもいいから連絡ちょうだい。スマホ握りしめて待ってるから」と言いながらも真希は連絡をくれるだろうかなんていうことも思った。
「おやすみ」真希がそう言ってマンションの中に入っていく。私もまたねと言いながら手をふる。真希がもう一度振り返って手を振った。オートロックの玄関の自動ドアが開いて、真希の後ろ姿がベージュ色の灯りに照らされたエントランスに入っていく。真希の姿がエレベーターホールの柱の陰に消えていくのを見届けてから私はもと来た道を戻って自分の家に向かって歩いた。
夜空にはさっきまでは雲に隠れていた月が浮かんでいる。街の明かりに侵食されて濁ったような色の、夜になりきれない夜空に浮かぶ月はどこか頼りなさげで寂し気に見えた。
「真希が好き」そう呟いた。白い息が闇に消えていく。私は真希のことが好きだ。ずっとそう。初めて出会った高校一年生のときからずっと。
「生きる意味なんてあるのかな」そんなことをまだ高校生だった頃に真希はよく言っていた。
生きるのに意味なんてないよ。たまたま生まれてきて死にたくないから生きてるんだよ。その度に私はそんな風に言った。
「でも本当はあのときには生きる意味を見つけていたんだ」私はそう呟いた。
私は真希が好きだ。私が生きていく上でこれ以上の意味なんて必要ない。私はただ真希とずっと一緒にいたい。そう思った。
いまでも願い事がたった一つだけ叶うんだとしたら真希とずっと一緒にいたい。それが私のたったひとつの願い事だった。傍にいれるだけでもいいとさえ思っていた。私と真希の関係はこれから始まるんだ、きっとそうだと寂しさを押し殺すように自分に言い聞かせながら前を向いて歩く。
遠くを走る最終電車の音が聞こえて、風が吹いて公園の木々が騒めいていた。私はいつ真希から電話があってもすぐに気付けるようにポケットの中のスマホを握りながら歩いた。下り坂の向こうには街の夜景が広がり小さな灯りが瞬いている。家々の窓から漏れる明かりがひとつひとつと消えていき、月のひかりだけが街を照らしている。私の吐いた白い息が闇に溶けるようにふっと消えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
