
いまのわたしを形作っている(と思う)個人的な名著7選【小説部門】
何だこの、「要らない本まとめてメルカリで売ります」みたいなサムネ……(売りません)
こんにちはこんばんは、れでぃーすあんどじぇんとるめん。水生です。
突然ですが、わたしの好きな本を紹介したいと思います!!!
本当に突然だな!!!!!!
と言っても、もう、これは「好き」のレベルが常軌を逸している本達、
すなわち、これまで人生で恐らくウン百冊読んできて、その大半は1回かせいぜい3回読んだら「うん、もうわかったわ。面白かった、ありがとう」ってなって二度と手には取られない中で、
何十回、下手をしたら何百回単位で読み返している、お気に入り中の超弩級お気に入り軍団。
最近は二次創作・ファンフィクションばかりでオリジナルを書くことは滅多にしなくなってしまったけれど、
そんなでも一応「おはなし書き」の端くれであるわたしにとって、
多大なる影響を受けた創作の原点であったり、いっそ人生観の一部になっているかも知れなかったりする、
最早わたしの血肉とも言うべき少数精鋭、とっておきの7作品【小説部門】です。
自作を読み返すと、これらの作品と似たシチュエーションとか場面とか文章とかが散見されることがあって(どころかモロに引用していることもある)、
なんかもう、これらの小説を読んでいただいたら、みずくんの書くものは読まなくてもいいだろうというほどの……いいや、回りくどい前置きはこれ以上はよそう。
とにかく、ぼくの小説を読んでくださるくらいなら、いっそこれらを読んでくれ!!!!!
それではひあうぃーご。
※※免責※※
・一部、盛大且つ致命的なネタバレを含みます。
・多分ないはずですが、絶版等により手に入らない場合はご容赦ください。
・好きな本や小説家のくせに、「貶してんのか?」と思われるような表現を含む場合があります。愛しさゆえの憎まれ口ですので大目に見てください。
・注釈は記事の末尾を参照してください。
【戯言シリーズ】

バイブル。
わたしがおはなしを書くようになったのはこのシリーズと出会う2~3年ほど前なのだけれど、中学三年生で出会って大きな衝撃と影響を受けた存在。
まぁ、厨二病思春期ど真ん中にこのシリーズに出会ってしまったら、人生狂うよね……。
ゼロ年代を代表するライトノベルの名作。だと個人的には思っていて、わたしの書く文章のベースは西尾によって作られていると言っても過言ではない。
何なら大学のゼミの発表の題材にも選んだ。ぶっ飛んだ日文学科生だったな……。
内容そのものは、ミステリー、から出発しての、人外バトルもの、であり、
「一人語りの激しい」「たかだか語り手自身の了見を『世界』という誇大な言葉で表したがる」、セカイ系の作品の代表例として文学研究・批評の文脈上では語られることが多くて[1]、
うん、まぁ、それはわたし自身も否定しないというか、「そうですね」という感じなのだけれど、
それでも個人的に、単なるセカイ系の枠組みの中では語り切れない魅力があると思わずにはいられないのは、
「世界」という言葉を使ってこの作品が描いているのが、人間であれば誰しもが一度は抱いたことがあるような、「自らの存在への何か漠然とした(けれど本質的で、ゆえに透明な)不安」であり、
大人になってしまえば素直に口にすることを躊躇してしまうようなそれを、恥ずかしげもなく(厨二病全開で)余すところなく描き切っている、からだと思う。
「お利口さんだったからね。すぐにわかったよ。ここは――僕様ちゃんの生まれてくるべき世界じゃないって」「ああ、間違った、って」
「なぁ、いーちゃん」「生きてることが、つまんねーよ」
「幸せな奴なんか、全員、死んじゃえばいいんだ」
「さっきから――ずっと、助けてくれって言ってんのが、わかんねーのか、この役立たず!」
ね? ね? それこそ中学生か高校生くらいの頃、一度はこういうこと言ったり思ったりしなかった??
何なら今もたまに思ったりしない???
戯言シリーズは、登場人物の設定こそ天才だったり異能だったりのぶっ飛び具合なのだけれど、
そんなぶっ飛んだキャラクター達が口にするのは、びっくりするくらい人間くさい、純粋な「自らの存在への不安」なのだ。そこがいい。
自分の生に一度でも不安や疑念を抱いたことがある人なら、誰でもすっと感情移入できてしまう、させてしまうところがあるのが、このシリーズの最大の魅力であり、当時の若者に支持された[2]理由なのではないかな、と思う。
特に『ネコソギラジカル』の上中下、三部作が白眉だと思うのだけれど。
『クビシメロマンチスト』と『ヒトクイマジカル』も個人的には好き。
当時はノベルスしかなかったので、中学生のお小遣いでは高くて買えなくて、図書館で何回も借りて擦り切れるほど読んだものだけれど、今は文庫になって手に取りやすくなって、いい時代になったよね。
ちなみにみずくん、大学の卒論は〈物語〉シリーズでした。西尾に毒された人生だな。
【つきのふね】

まさかの児童文学!!!!!
と、侮らないで欲しい。侮れない。
初めて出会ったのはやっぱり中学生の頃だったと思うのだけれど、アラサーになった今読んでも、鋭く冷たいナイフで心の一番脆いところを切り裂かれるような、そうしてはっと胸を突かれるような、そんな不可思議なエネルギーのある小説。
ノストラダムスの大予言とか、非行(万引き・売春・薬物乱用)とか、心の病とか、
題材になっているのは「いかにもバブル崩壊後の九十年代後半に書かれましたね」というものばかりなので、例えば今の時代の十代の子達が読んでもピンとこないのかも知れないけれど(何しろスマホはおろか携帯電話すらメジャーではなかった時代の話だ)、
逆に言えば、その頃の世相や雰囲気を知っていて、そういう一つの「時代」の中で、自らの生き方に悩んだり躓いたりしてきたミレニアル世代(1980~1995年頃に生まれた世代)の人達には、「ああ」とどこか懐かしさすら感じさせる世界観だと思うし、
そういう「時代」を背景にして描かれていることは、例えば不確かな将来や人と人との繋がりに対する得体の知れない不安であったり、閉塞的な世界に対して覚える息苦しさだったりするから、そういう部分は、世代を問わずに共感してもらえるのではないかなぁと思う。
このごろあたしは人間ってものにくたびれてしまって、人間をやってるのにも人間づきあいにも疲れてしまって、なんだかしみじみと、植物がうらやましい。
花もうらやましい。
草も木もうらやましい。
食べたり動いたり争ったり学んだりする必要もなく、ただ水を吸いあげて光合成するだけの、シンプルな機能がうらやましい。
出だしからしてこれである。
えええ……? めっちゃわかるわ……わかるでしょ? わからない???
森絵都作品は、他にも『DIVE!!』とか、『カラフル』も好きなんだけれど、
その『カラフル』の文庫版の巻末で、阿川佐和子さんが対談をした時の森絵都氏のコメントが載っていて、
「私ってぜんぜん真面目ではなかったけれど、基本的にはすごく普通の子だったんです。ハズレ方も反抗のしかたも。私の小説も、普通の主人公の普通の心のあり方が普通の読者に受け入れられたのかなと思います」とそこにはある[3]。
はっきり言って、非行や心の病や、『カラフル』に描かれているような自殺の問題なんて、関係ない人にとっては一生無縁のことで、到底「普通」とは言えないと思うのだけれど、
でもそれは、ほんの小さな一線を隔てたすぐ向こう側の、実はとても身近なところに潜んでいる仄暗い闇で、
そういう場所を彷徨いながら、それでもどうにか藻掻いて生きている人達のことも「普通」と言ってやさしく包み込んでしまう、それが森絵都作品の魅力なのだと個人的には思っている。
『つきのふね』はその代表というか、典型のような作品。文庫版の解説で、金原瑞人さんは「それまでしなやかに、のびやかに駆けていた黒豹がいきなりこちらを向いて牙をむいたような」「作者自身ももてあましているとしか思えないくらい強烈ななにかが、恐ろしいくらいに感じられ」る作品だと評していて[4]、もう、全くその通りだな、と思う。
わたしの創作における、通過点ではなく、到達点としての、目標の一つ。
【国境の南、太陽の西】

最初に言っておく。村上春樹は全然好きじゃない。微塵も好きじゃない。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』も『ノルウェイの森』も『スプートニクの恋人』も、めぼしいものは大体手に取ってきたけれど、どれも最後まで読み切れずに挫折した。高校の時に『青が消える』を授業でやった時も「何じゃこりゃ……」と思って終わった。何がいいのかちっともわからない。ハルキストの皆さますまない。
でも、でも、この小説だけは、大学の時に出会って以来、数十回単位で読み返している。そこそこ綺麗な状態の中古で買った文庫本がご覧の通り、ヨレッヨレのボロッボロである。
内容はね、割とありふれた感じの不倫小説なの。
主人公に、初恋(?)の女の子の幼馴染が居て、一度は離れ離れになったふたりが、三十七歳の時に再会して云々という話。その時には主人公はもう結婚していて子供も二人いるのだけれど、彼女との間で揺れ動く、みたいなそういう話。
でも、読めばわかっていただけると思うけれど、凡庸な不倫小説(恋愛小説)ではなくて、
その主題の一つは、作中で言われているところの「吸引力」だと、個人的には思っている。
僕が強く引きつけられるのは、数量化・一般化できる外面的な美しさではなく、その奥の方にあるもっと絶対的な何かなのだ。…(中略)…その何かを、ここでは仮に〈吸引力〉と呼ぶことにしよう。好むと好まざるとにかかわらず、否応なしに人を引き寄せ、吸い込む力だ。
この小説の中では、その「吸引力」が、おおよそ「性(セックス)」という形で表現されてしまっているのが、個人的には唯一残念なのだけれど、
(だから、一般小説なのにかなり露骨な描写があって、あんまり露骨なのでおいおいというか、個人的には結構げんなりしてしまうポイントではある。まぁ、BL小説のエロと同じで、表現としてはわかりやすいと思うのだけれど。世界の村上春樹も安直なことをするなぁと……いやいや。敢えて迂遠ではなくストレートな表現手段を選んだと言いましょうかね! さすがだね春樹さん!!)(怒らないで! 石を投げないで……)
でも、「これは単に恋とか愛などというチープな言葉で表せるようなものだろうか?」という不可思議な惹かれ方をしたことがある人間としては[5]、その途方もない「吸引力」がもたらす瑞々しい揺れ動きと奇妙な不安には、大いに共感というか、妙なリアリティを感じずにはいられないのである。
単に恋愛という言葉では言い表せない、名前の付けられない(オタク的な表現をすれば)「クソデカ感情」や、
それによって何かが損なわれ、失われたり、道を踏み外したりすることへの葛藤というテーマは、
わたしが自らの創作においてあますところなく描き切ってみたいなと思うことの一つで、この小説を作中で引用したり、オマージュのようなシーンを書いたこともある。
この小説が究極だとは思わないけれど、ベクトル的に、「こういう小説を書いてみたいな」と思う小説。
【狭き門】
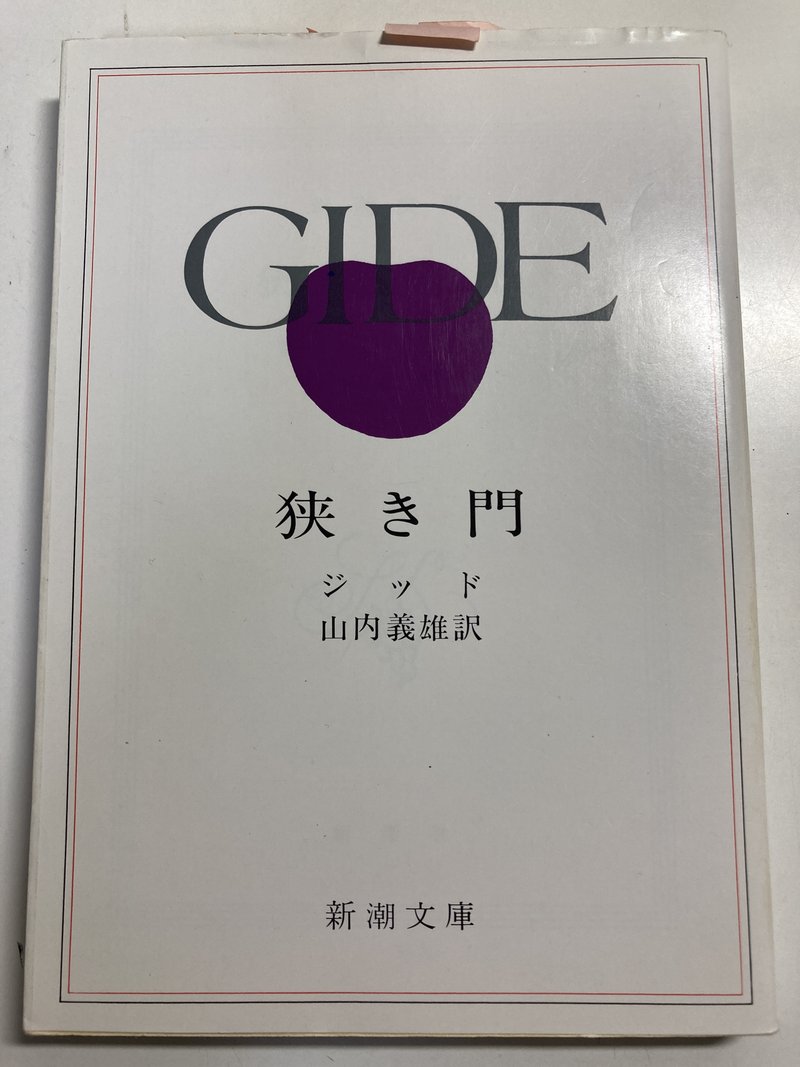
この物語(敢えて物語と言う。作者のジッドは、この作品を「小説(ロマン)」とは区別して「物語(レシ)」と呼んでいた)を初めて手に取ったきっかけは野村美月氏の〈文学少女〉シリーズだったのだけれど、
愛とは何か、愛するとはどういうことなのか、読む度に考えさせられて、未だに答えの出ない作品。
ジッドと、彼の妻であったマドレーヌがモデルである、主人公のジェロームとヒロインのアリサは、若かりし頃から互いに惹かれ合う同士なのだが、敬虔なクリスチャンであり天上の愛を求めて生きるアリサは、ジェロームの求愛を最後まで受け容れようとしない。けれど、彼を思慕する想いを捨て切ることもできず、その狭間を彷徨いながら、最後は一人ひっそりと死んでいく……という、そういう話。
ジェロームとアリサの間には何の障害もなく描かれていて、それでも何故アリサはジェロームと結ばれることを拒もうとするのか、何度読んでも「???」なのだけれど、
(これについて、〈文学少女〉で天野遠子は「よくわからなかったわ。ぼんやりしていて、透明なハルサメを、つるつるじゃなくて、もぐもぐ食べてる感じなの。かんでも、かんでも、味がしなくて……ハルサメが逃げていっちゃうの。お父さん、アリサはどうして、ジェロームと結婚しなかったの? アリサはジェロームのことが好きだったんでしょう? なのに、どうして、一人で神さまのところへ行っちゃったの?」と言っている[6]。凄くよくわかる)
謎だからこそ、何度も読んでしまうし、次のアリサの言葉を読むと、何となくはその心情(信条)がわかるような気がする。
「では、魂は、幸福以上に何を望むというんだろう?」と、わたしは性急に叫んだ。彼女は小声でつぶやいた。
「聖らかさ……」
「清らかさ」ではなく「聖らかさ」という字を当てた山内氏のセンスがいいなぁと思うのよ。
愛よりも、幸福よりも、神に臨みその御前に捧げる「聖らかさ」が魂にとって最も尊いという思想は、理想的過ぎる気もするけれど、わかるなとも思う。「狭き門」を潜り、聖域へと到達する時、人は誰しも孤独でなければならないのかも知れないと。少なくとも、死ぬ時は誰もが独りだ。
この物語には、もう一つ、好きな場面があって、
夜が近づいていた。
「寒くなってきましたわ」彼女は、立ち上がりながらそう言うと、わたしにその腕が取れないほど、ショールでしっかり体をつつんだ。「あなたはあの聖書の一節をおぼえていらっしゃる? ほら、あの気になっていた、そしてはっきりその意味がわからないのではないかとおそれていた――《神は我らのために勝りたるものを備え給いし故に、彼ら約束のものを得ざりき》」
「君はいつもその言葉を信じている?」
「信じなければならないんですもの」
わたしたちは肩を並べて、しばらくは口をきかずに歩いていった。彼女は言った。
「勝りたるもの! ジェローム、あなたそれを考えてみたことがおありになる?」彼女の目からは、たちまち涙があふれ出た。それでもその口は、
「勝りたるもの」と繰り返していた。
わたしたちは、ふたたび、さっき彼女の出てくるのを見た菜園の木戸のところに来ていた。彼女はわたしのほうを振り向いて、
「さようなら!」と言った。「もうここまでにしてちょうだい。さようなら、愛するお友だち。これからあの――《勝りたるもの》がはじまりますの」
世界で最もかなしくてうつくしい別離のシーンだと思っている。
「愛するお友だち」という呼びかけがいいよね……。
【マディソン郡の橋】

これはねー、正直、映画の方がいいのよ。クリント・イーストウッドが監督と主演を務めているのだけれど、何回見ても素敵な映画。
『国境の南、太陽の西』と同じで、これも不倫小説っちゃ不倫小説なのだが、そのストーリーから受ける印象は真逆と言った方がいい。純愛中の純愛小説だと個人的には思っている。
アイオワ州の片田舎で、家族の留守を任されている平凡な主婦フランチェスカのところに、カウボーイの末裔だというカメラマンのロバートが訪ねてきて、4日間だけの短い恋をする、という話。
何がいいって、別れた後もふたりがずっと互いを想い続けていて、最期には同じローズマン・ブリッジのところに遺灰を撒いてくれ(そこで一緒になるから)と言うのがいいのだけれど、
それだけ彼のことを愛していたにもかかわらず、残りの生涯を夫と子供達(家族)に捧げたフランチェスカの生き様もまたうつくしいと思う。
彼のことも、家族のことも、どちらも愛して、その両方を貫いた。しなやかで、うつくしい、究極の生き様。でも、その生き方を貫くにあたっての彼女の心境を思えば、何とかなしい決意がそこにはあっただろうと思わずにはいられない。
ふたりの永遠の別れとなるシーンがね、泣けるのよ。特に映画。
どんな心理的なからくりからか、ふいにすべてがスロー・モーションの映像を見ているように見えた。ロバートの順番がきて、彼は……ゆっくり……ゆっくりハリーを交差点のなかに進めた――彼の長い足がクラッチやアクセルを踏み、右腕が筋肉を浮き上がらせてギアを替えるのが目に浮かんだ――それから左に曲がりはじめた。92号線のカウンシル・ブラフス、ブラック・ヒルズ、北西部方面方向に……ゆっくり……ゆっくり……古いピックアップが向きを変える……トラックはひどくゆっくり向きを変え、その鼻面を西に向けた。
涙と雨と霧を透かして目を凝らすと、かろうじてドアの色褪せた赤ペンキの文字が読めた。〈ワシントン州ベリングハム、キンケイド・フォトグラフィー――〉
曲がるときの視界の悪さを補うため、彼は窓を下ろした。車が曲がりきり、西に向かってスピードを上げながら、彼が窓を上げたとき、その髪が風になびくのが見えた。
〈ああ、そんな――ああ、そんなのひどいわ……だめよ!〉心のなかで彼女は叫んだ。〈間違っていたわ、ロバート、あなたと行かなかったのは間違っていた……でも、わたしは行けない……もう一度説明させて……なぜわたしが行けないのか……もう一度教えてちょうだい……なぜわたしが行くべきなのか〉
すると、ハイウェイの彼方から、彼の声が答えるのが聞こえた。〈この曖昧な世界では、これほど確信のもてることは一度しか起こらない。たとえ何度生まれ変ったとしても、こんなことは二度と起こらないだろう〉
この、最後の「この曖昧な世界では、~」というのは、ロバートが実際にフランチェスカに告げた言葉のリフレインなのだけれど、
「これほど確信のもてる」ような相手と巡り会うことができたら、それはどんなに素晴らしいことだろう、と思うのね。でも、「こんなことは二度と起こらない」。
これを「奇跡」という言葉で表現してしまったら、途端にとてもチープになってしまうのが嫌で嫌でしょうがない。
そんな出逢いと繋がりの物語を、わたしも書けたらいいなぁ、と思う作品。
ロバートの作中作である『Z次元からの墜落』という記事は、運命的な出逢いについて綴った名文中の名文だと思っている。こればっかりは、映画には描かれていない(確かね)。小説じゃないと味わえない文章。
【銀河鉄道の夜】
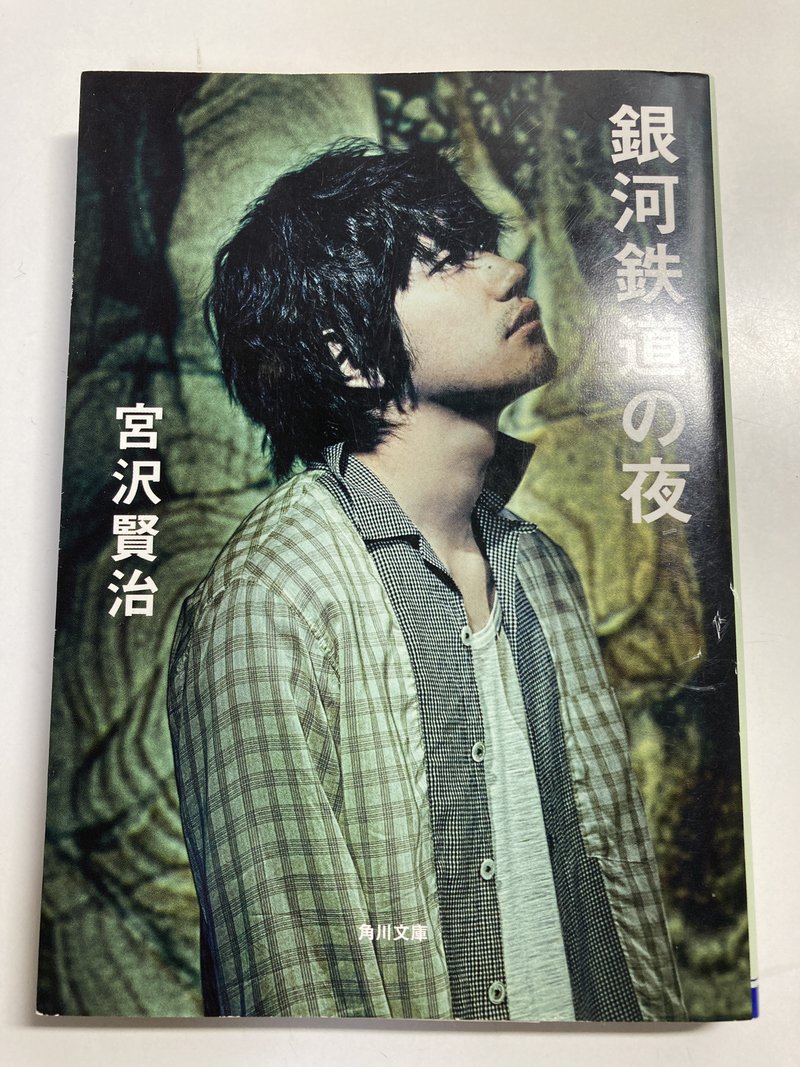
定番だよねー。お決まりだよねー。
『銀河鉄道の夜』という物語が好きだと言った時、一体どれのことを指すのか、遺稿であり、未定稿であって、複数の改稿が施されているこの作品については難しいところがあるけれど、個人的には、第1~4次稿のどれもが『銀河鉄道の夜』であって、その全ての世界観が好き、だと思っている(全部のバージョンを隅から隅まで読んだ訳じゃないけどね)。
作中に出てくる描写のひとつひとつがとても純真で綺麗だというのも好きな理由の一つなのだけれど、この作品が心を掴んで離さないのは、やはりジョバンニとカムパネルラの関係性、ただそこに尽きると思っている。
「カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのさそりのようにほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない。」「うん。僕だってそうだ。」カムパネルラの眼にはきれいな涙がうかんでいました。「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」ジョバンニが云いました。「僕わからない。」カムパネルラがぼんやり云いました。
もうねぇ……。
難しい言葉なんて一個も使ってないのに、何でこう、ありありと情景が浮かぶんだろうか。
ふたりならばどこまでも一緒にいけると無邪気に信じているジョバンニと、そうできたらいいと同じように願いながら、それが叶わないことだと実は気づいているけれど言わずに(言えずに)いるカムパネルラの、コントラストの切なさよ。
この関係性は一言で表せば友情になるのだろうけれど、ただそうとだけ言い切ることを躊躇うような、そんな想いの真っ直ぐさを感じるところがたまらなく好きです。
『狭き門』でアリサがジェロームに言った「愛するお友だち」という呼びかけにも、どこか通じるところがあると思う。
魂が震え合い共鳴するほどでありながら、どうしようもない理由で引き裂かれ、別れ別れになってしまう関係。アリサとジェローム、『マディソン郡の橋』のフランチェスカとロバート、『国境の南、太陽の西』のハジメくんと島本さんと、同じ匂いを感じるふたり。『つきのふね』で微かに予感されているような、人と人との、不確かだけれど心の触れ合うような繋がり。
あるいは、ジョバンニとカムパネルラは、作者の賢治自身と妹のトシさんだとは、散々言われてきたことだけれども[7]。
【愛と死】

これはねー……。
正直、何と語ったらいいのか、わからない作品。
凄くシンプルなんです。もうね、タイトル通り。
小説家の青年・村岡が、彼の友人・野々村の妹である夏子と出会って、恋をして、結婚の約束をするのだけれど、叔父に呼ばれてパリに洋行した村岡の帰国の寸前、流行性感冒によって突然夏子は亡くなってしまう。という、ただそれだけの話。
もう万事用意が出来、ただただあなたのお帰りを待っております。
あなたがお痩せになったそうで気になります。あなたに今病気されたら、私は本当に困ります。自分でも自分がだだっ子になったので閉口しています。
この手紙を御らんになる時はナポリですのね。もうじき船におのりになるのね。本当にとうとう御帰りの日が来たのね。又この前のように私は毎日お祈りしますわ、御航路が平安で、船がおくれませんように。波が静かだったら私のお祈りのせいと思って下さい。波が高かったら、私の情熱の為だと思って戴きたい、これは嘘よ。よき航海であることを毎日お祈りいたしますわ。
うれしい、うれしい日を待っている、あなたのおまえより。
十一月十二日それでは神戸で!!
出国前の会話や、洋行中の手紙の中にある村岡と夏子の言葉は、もう、いっそ稚拙に感じられるくらい、何の捻りもない、あまりに真っ直ぐで甘々な台詞のオンパレードなのだけれど、ゆえに、ただひたすら愛し合う喜びに溢れていて、
その喜びが混じりけなく純粋であればあるほど、あるからこそ、読者を泣かせるための逆ご都合主義じゃないかと思うほど、何の伏線もない突然の夏子の死に、まるで突き放されたようになって、その喪失感に茫然と立ち尽くすような気持ちにさせられる。
それはきっと、自分にとって本当に大切な人が喪われる瞬間というのは、こういう感じなんだろうな、というのを、疑似体験、あるいは追想させるからなのだと個人的には思っている。
かなしいとか、つらいとか、せつないとか、そういうのを全部すっ飛ばして、
まるでその人がこの世から消えてしまった瞬間、自分自身もまた空っぽになってしまう、みたいな。
そういう喪失感を、残酷なくらい純粋に写し取った、切り取った物語。
何でこんなに惹かれるのか、大学卒業の直後くらいに初めて読んで以後、何十回と読み返しても未だにわからない。
マジで何の特別な技巧も感じられないのに、何故か何度も読み返してしまう、本当に不思議な小説です。
おわりに
という訳で、いまのわたしを形作っている(と思う)個人的な名著7選【小説部門】でしたー。
ここのところ、お仕事や推し事や私生活であれこれあって、なかなか「物を書く」ということから遠ざかっていたんですが、せっかくだから年内にもう一発くらい書き物をしておきたくってさ。
需要がないのは知ってる!笑
貴方の、貴方を形作っている本は何ですか?
ただのおすすめ本には興味ありません。貴方の血となり肉となっている本を教えておくれ、愛するお友だち。
おわります。
よい年をお迎えください!
【注釈】
[1]前島賢『セカイ系とは何か』2014年・星海社
[2]宝島社『このライトノベルがすごい! 2006』において、読者投票で1位を獲得している。
[3]森絵都『カラフル』2007年・文藝春秋の巻末、阿川佐和子による「解説」より。
[4]前掲書『つきのふね』の巻末、金原瑞人による「解説」より。
[5]小生による「だいすきだよ、世界。だから、嫌いにならないで。」https://note.com/yumeato1029/n/nb215e2a68510を読んでね。
[6]野村美月『"文学少女"と神に臨む作家(ロマンシェ) 上』2008年・エンターブレイン
[7]山根知子『宮沢賢治 妹トシの拓いた道―「銀河鉄道の夜」へむかって』2003年・朝文社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
