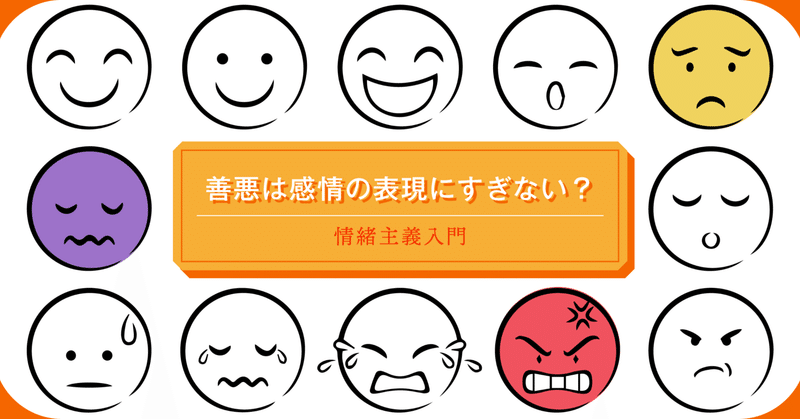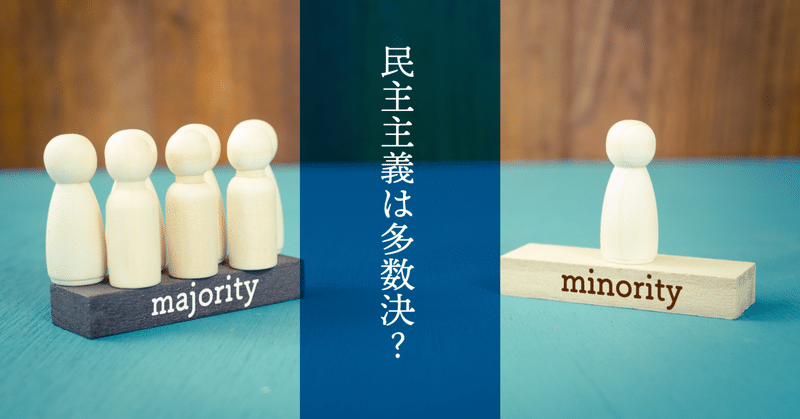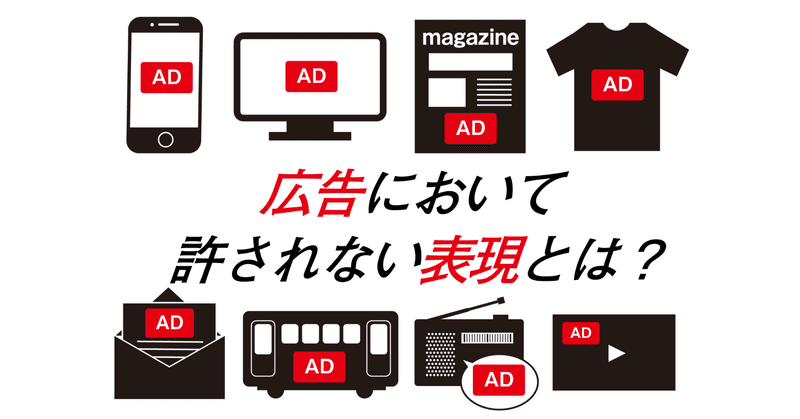記事一覧
広告において許されない表現とは?――虚偽表現・ステレオタイプ表現・性的表現を例に
しばしば、広告の表現が物議をかもすことがある。近年、広告がいわゆる「炎上」の火種になることは珍しくない。それ以前も、誇大広告や子どもを対象とする広告などの問題が消費者から提起されてきた(疋田/亀井/小宮山 1999 p. 66)。
はたして、広告においてどんな表現は許されないだろうか。そして、なぜその表現は許されないのだろうか。この記事ではそのようなことを考えてみたい。
この記事は次のよ
そもそもダブスタって何?――哲学・倫理学から考えるダブル・スタンダード
ネット上で「ダブスタ」という言葉を見かける。誰かの言動に対して「ダブスタだ!」と言い立てる言説は多い。しかしながら、私見では「ダブスタ」という言葉を乱暴に使う言説も少なくない。そこで、この記事では「そもそもダブル・スタンダードとはどのようなことか」を問いなおす。
この記事は次のように進む。Ⅰではダブル・スタンダードの概要を示す。Ⅱでは正義に関する哲学・倫理学の知見の一部をまとめる。Ⅲではダブ