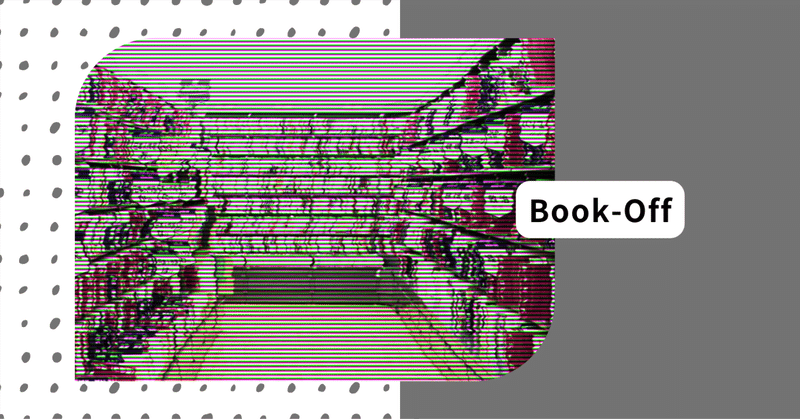
良い意味で客観性の欠けた不器用なスタイル
日本に帰国したのを機に週一で記事を書き始めてから一年が経った。出国する少し前くらいにnoteを始めて、渡航先のオーストラリアでも一年はコンスタントに投稿していたのだけれど、途中で日常の些事に捉われて不定期投稿になっていた。だが今回はもう少し長く続きそうである。
渡豪前に身の回りの物を色々と整理していた際、僕はブックオフに本やら何やら細々としたものをいくつか売りに行った。店のカウンターには二人の若い男性店員がおり、どちらも理系大学のオタクサークルとかにいそうな風貌と喋り方だった。その先輩らしき方が後輩に対してちょっと居た堪れなくなる感じで先輩風を吹かしており、「俺は何を見せられてるんだ」と思った記憶がある。僕は使わなくなった古いiPhoneの査定を待っている間、適当に立ち読みしていた。無駄に三十分くらいが経ち、軽い気持ちで手に取った村上春樹の『アンダーグラウンド』の最初の十数ページを読んでしまった。やがて査定が終了したとの店内放送があってカウンターに呼ばれ、さっきの二人組の後輩の方に対応された。僕をサークルの後輩とでも思っているかのような、ちょっと不自然にフランクな態度と口調だった。その印象が強くて査定結果はよく覚えていない。
それから数年の月日が経ち、僕は最近になってこの『アンダーグラウンド』を買って改めて読んでみた。地下鉄サリン事件の被害者達に行ったインタビューをまとめた本で、エッセイを除けば村上春樹がこれまでに刊行した唯一のノンフィクションである。僕は高校生の時に学校の図書館にあった村上春樹の本を全て読んだのだけど、この『アンダーグラウンド』だけは小説ではなかったので例外的に避けていた。
内容は事件そのものだけについてではなく、それぞれの被害者の仕事や家族などを含めた人生模様についても多く記載されているのが印象的だった。一見は不必要な情報も各自のストーリーに強い現実味をもたらしていた。これは村上春樹の小説家としての独自のアプローチであり、本来のノンフィクションのセオリーからは外れるのだろう。たしか本人もそのことを後書きか前書きで触れていた。
正攻法ではないアプローチのノンフィクションという共通点から、僕は過去に見たテレビのとあるドキュメンタリーを思い出した。『ザ・ノンフィクション』の坂口杏里を密着した回である。番組のディレクターは坂口杏里と同年代の若い女性で、おそらく業界での経験がまだ浅い新人らしかった。彼女は坂口杏里に対して友達に近い感覚で取材しており、かなり主観的な語り口のナレーションを自ら付けていた。おそらく上司なんかには嫌味を言われたのだと想像するが、良い意味で客観性の欠けた不器用なスタイルがこのケースでは功を奏していたと僕は感じた。坂口杏里の人となりをできる限り好意的に伝えようとする人間がメディア側に存在するという事実が、内容そのものの悲惨さを中和していた。
それにしてもここ一ヶ月くらい本ばかり読んでいる。SNSやネットニュースを見まいとするあまり、読書が避難先になっている気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
