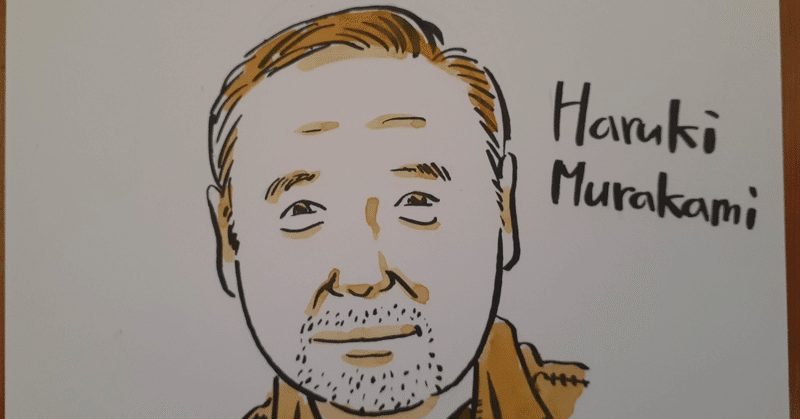
マルホランド×ねじまき鳥
村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』を読みました。
村上さんの長編は、『1Q84』以降と『ノルウェイの森』までを読んでいて(間が読めていない)、次は発表順に『ダンス・ダンス・ダンス』を読むつもりでした。
ところが、先日、noteのコメント欄で二度、ねじまき鳥についてやり取りしたために、この小説が気になってしまったんですね。
コメント欄でやり取りしたのは、「ねじまき鳥は、ディヴィット・リンチ監督の映画『マルホランド・ドライブ』と親和性がある」という話です。去年訪ねた『村上春樹 映画の旅』展の展示に書いてあった意見なのですが。
もう引退なさっているので若い方はご存じないかもしれませんが、ディヴィッド・リンチ監督は鬼才というのか、クセのある映画を撮る方です。クセのある映画は嫌いではないですが、観る時を選ぶので、リンチの映画もとびとびにしか観ていません。
ただ、2001年に公開された『マルホランド・ドライブ』は、好きな映画ベスト10に入るぐらいに、印象深い映画でした。
難解な映画なんですよね。解説サイトもあるみたいですが、「これは解説を読むべきじゃない映画だ」と勝手に思っていて。
例えば、ブルース・ウィリス主演の『シックス・センス』のオチがわからなかった知人がいるのですが、これは絶対、解説を読むべきです。「映画を観れば、オチがわかる」前提の映画ですから。
でも、リンチの映画は、解説を読んで「はあ、なるほど」と思うのではなく、自分なりに考えて、「こういう話なのかな?」と何となくわかればいい…いや、わからなくても、そのわからなさを楽しめばいい作品ではないかと思うのです。
村上さんの小説と似ているかな。村上さんの小説も、読者それぞれ解釈が違っていいはずです。
作り手のリンチや村上さん側も、全員に同じ解釈をしてもらいたいと考えて作品を作っているわけではないでしょう。
といっても、『マルホランド・ドライブ』は、そこまで難解ではない。細かい点は色々謎のままですが、全体像は理解できた気がします(その次に撮られた『インランド・エンパイア』は、「裕木奈江、出番少ないけど、実はかなり重要な役?」ぐらいの感想しか湧かず、わかろうとする意欲さえ持てないほど難解でした)。
*
私の理解では、『マルホランド・ドライブ』は、主人公の夢/幻想/妄想を映像化した場面と、現実(ただし、主人公の主観で歪められている箇所もある)を映像化した場面にわかれています。それぞれの場面には密接な関係があり、現実で果たせなかったことが夢で果たされたり、現実の出来事がグロテスクな形をとって夢に出てきたりします。
また、主人公は女優なので、現実の場面さえも映画的な非現実感が漂います。
そのため、幻想と現実の境目が曖昧になり、最後には、「どこまでが現実とか、そんなことはどうでもいいや。目の前のこのシーンを楽しもう」とか「そもそも、現実ってなに? 現実と幻想の境目なんて本当にあるの?」などと思えてきます。
書いている私自身もよくわからない説明ですが、もう一つの世界が描かれるという点で、村上さんの小説とリンクする部分があるのは理解していただけるかと思います。
私がこれまで読んだ作品でも、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』や最新刊の『街とその不確かな壁』は、マルホランドとかなり近い世界観だと感じました。
でも、『村上春樹 映画の旅』では『世界の終わり』ではなく(『街と…』は発売前だった)、『ねじまき鳥』とマルホランドに親和性があると書いてあった…はず(数ヶ月前のことなので、自分の記憶が信用できない)。
なので、どこがマルホランド的なのだろう? と考えながら、小説を読み始めました。
結論から書くと、確かにリンチの作品を思わせるところのある話だとは思いました。不思議な人たちが次々に登場して、現実か夢幻かわからないことが起きる。ネットで調べたところ、村上さん自身、執筆中に観ていたので、リンチのドラマ『ツインピークス』の影響があるかもしれないと認めていらっしゃいました。
リンチっぽい世界観というだけでなく、赤坂親子のエピソードや、最後の話などには、マルホランドらしさもうかがえる気がしました。特に、赤坂シナモン君はこの物語の裕木奈江か?(二つの世界を繋ぐキーパーソン)とも感じたので、再読する時には、彼の視点を気にかけながら読みたいです。
でも、全体的には、二つの世界の話よりは、この世界で現実に起きている話の方に関心が向かう作品でした。
戦争中やシベリア抑留中の話もそうですが、はじまりからして、夫婦のすれ違いの話ですし。女性の友人に離婚経験者が多いのですが、だいたい「普段と違う生活用品を平然と買ってくる」程度の亀裂から始まっているみたいなんですね。主人公が言うように、物事の本質には関係ないことから。私は、自分の小説を「人はかなしみでしかつながれない」という言葉で締めるぐらいに人と人とはわかり合えないと思っているので、「えっ、その程度で?」と驚いたものですが、一度気になると、すべてが気になってしまうようです。
まあ、主人公もいい人なんですが、鈍感ですよね。妻が電話で心の奥底を打ち明けても、それが妻だとさえ気付けない(私の勝手な解釈です)。妻がこの人との生活に限界を感じたのも、無理はないかな…。
妻の実家の冷え冷えとした雰囲気も、よくわかります。
彼女の父親は役人だった。新潟県のあまり裕福とは言えない農家の次男坊だったのだが、奨学金をもらって東京大学を優秀な成績で卒業し、運輸省のエリート官僚になった。(中略)そういった人物がなりがちなように、ひどくプライドが高く、独善的だった。命令することに馴れ、自分の属している世界の価値観をみじんも疑うところがなかった。彼にとってはヒエラルキーがすべてだった。
母親の方は東京の山の手で何の不足もなく育った高級官僚の娘で、夫の意見に対抗できるような意見も人格も持ちあわせてはいなかった。(中略)彼女はいつも夫の意見を借用した。(中略)彼女の欠点は、そのようなタイプの女性が往々にしてそうであるように、どうしようもないほどの見栄っぱりであることだった。自分の価値観というものを持たないから、他人の尺度や視点を借りてこないことには自分の立っている位置がうまくつかめないのだ。その頭脳を支配しているのは「自分が他人の目にどのように映るか」という、ただそれだけなのだ。
東大卒の官僚と官僚の娘。とても具体的です。昔の話ですが、東大落ちてうちの大学に入った人の中に、「うちは親戚一同東大ばっかりだ」とわざわざ言ったり、東大を受験していない男子を見下したりする謎の一群がいました。なんでこの人たちはこんなに威張った性格なんだろうと不思議でしたが、主人公の妻と同じような家庭環境で育ってきたので、威張って、人を見下すのが当たり前だったのかもしれません(落ちてもなお、東大ブランドにすがっているのがすごい)。
また、仲の良かった男の子は、何が何でも東大! と親に言われ続けてきたので、東大に入れなかった自分を敗残者と見なして精神崩壊寸前でした。その子の親は大卒でさえないのに、東大を絶対視する価値観に染まっているようでした。お母さんもまさに、小説に書かれる妻の母親そっくりの人でした。
そういう記憶があるので、妻の家族が悪として描写されるのがとても腑に落ちました(東大は一つの象徴のようなもので、東大卒=妻の家族的というわけではないですよ、もちろん)。
小説には、過去の悪も登場しますが、肉体的に人を苛む過去の悪に対して、現在の悪は、精神的に人を苛む存在なのか。
主人公が悪と対峙する場面には、マルホランド同様、現実と幻影? が入り混じっています。いくら悪だからって、こんなに簡単に、人を殺めていいのか? とも思うものの、それが現実とは限らない、というのもうまい提示の仕方ですよね。
いずれにしても、一度読んだだけでは、話の意味合いがつかめない作品でもあり、読むたびに読者の受容が変わりそうな作品でもあり…少し間を置いて、また再読したいです。
読んでくださってありがとうございます。コメントや感想をいただけると嬉しいです。
