
デッドエンドの向こうまで
プロローグ
2019年年3月、ロンドン在住のHIV(エイズウイルス)感染患者が、幹細胞移植治療によって病気の症状がほぼなくなり、臨床的にコントロールされる「寛解状態」になった。エイズ根治法の到来も夢ではないと思わせる朗報が世界中をかけめぐ巡った。
志良弘樹(しら ひろき)はそのニュースをネットで読み終わると、報道記事が表示されたコンピュター画面をひらいたまま考えにふけった。なにかが違うと思った。ニュースは二番せんじのような、あるいはフェイクニュースのようなすっきりしない印象を彼にあたえていた。
志良はアルツハイマー型認知症におかされている。頭の中では記憶の鮮明なところとぼやけたようなところが交錯する。先ほど見たニュースがなぜ二番せんじなのかと思いを巡らすうちに、頭の中が霞におおわれたようにはっきりしなくなった。
志良は次に意識を過去に集中しようとした。光と色彩と人々の呼吸感にみちあふれた記憶が、あざやかによみがえって走馬灯のように騒ぎ、志良の記憶は一気に30年近く前に飛んだ。
秘密

広い居間の四隅にある照明のうちの一つがスポットライトのように礼子に向かって真っ直ぐに光を放っていた。
礼子は光に浮かんでソファに両足を乗せて横向きにすわり、まるで何かの訪れを待ちわびるようにベランダに通じるガラス扉の向こうをじっと見つめていた。ほとんど黒色に見える濃いワインカラーの夜会服を着ている。
志良は妻の正装におどろいて、だがすぐに(ああ、そうだった・・)と納得した。彼らは今夜はノザンプ社が日本進出20周年記念を祝って開くパーティーに招待されていたのだ。夫婦はそれぞれの車でマンハッタンのパーティー会場まで行き、そこで落ち合う約束をしていた。志良はそのことをすっかりわすれていた。彼はパーティーのことに気をまわす余裕などない恐ろしい一日を過ごして、こうして妻のいるクイーンズの自宅に帰ってきたのだった。
志良が3年前からひそかに同性愛の関係を持ちつづけてきた相手のアレックス・カーンがエイズの宣告を受けた。彼は今朝ウォールストリートにあるオフィスにかかってきたアレックスの電話でそのことを知った。
「もしもし。ヒロ…」
アレックスはいつものように弘樹をヒロと詰めて志良の名を呼ぶやいなや、電話の向こうでむせび泣いた。あとは言葉にならない。志良はそれがなにを意味するのかを即座に理解した。足下がゆらぐような巨大な不安が彼の上にのしかかって、目の前がすっと暗くなった。こらえて彼は確かめた。
「ポジティブ(陽性)だったんだな」
志良の声はかすれた。
「そうだ・・・」
悲鳴に近い泣き声の合間にアレックスがしぼり出すように返した。アレックスはHIV感染の検査を受けて陽性と宣告され、同時に彼のこれまでの体調不良がエイズ発症によるものであることが確認された。「そうだ」という彼の短い言葉にはその二つの意味が込められていた。
凶変の兆しがあった。
アレックスのひいた風邪がいつまでたってもなおる気配がなく、微熱がつづいた。倦怠感が抜けない、と彼は志良に打ち明けていた。やがて下痢の症状が出た。はなから「エイズ」の3文字が志良の脳裏にこびりついていた。男と女を相手にする二重生活をつづけている限り、いつかはこういう場面に出くわすことがあるかもしれない、と彼はひそかにおそれてきた。
志良は仮に数字にたとえて言えば、六四の割合で男と女に性的な欲望を持ち、またそれと同程度の比率で双方の相手と関係を持ちつづけてきたバイセクシュアルである。
志良の中に深く隠されていた同性愛嗜好は、彼が日本の大学を卒業して、ここアメリカのマサチューセッツの大学に留学している間にあっさりと表に出た。
志良はある夜、大学のコンパの流れで行ったディスコの暗がりで友人らにすすめられるままにマリファナを吸い、気がつくと同行していた学部の若い助教授、ジョン・ヒューズのアパートで彼に股間をまさぐられていた。志良自身でも意外だったのは、おどろいたのはほんの一瞬のでき事で、彼はすんなりと助教授の愛撫を受け入れ、たちまち高まって相手の裸体にしがみついていった。
男と女を同時に愛する志良の二重生活はそのとき以来つづいていて、7年前に礼子と結婚してからも変わっていない。それでも彼は結婚を境に、男色に関してはできる限りむやみな行動をひかえてきた。気の向くままに行きずりの男たちと交渉を持つこともめずらしくなかったそれまでの態度をあらためて、慎重に相手を選ぶことが多くなったのである。
3年前にアレックスと知り合ってからは、志良の行動範囲はさらにせばまって、彼の相手の男はその若い愛人ひとりだけになった。エイズの恐怖が彼の気持ちを委縮させて行ったことももちろんあるが、志良はそんな具合いに自分の欲望を少しは制御できる年齢になっていた。言葉をかえれば志良は、他の相手が目に入らなくなるほどアレックス・カーンにおぼれた。
一方のアレックスは、志良とは違って女にはまったく欲望を感じないタイプのホモセクシュアルである。
志良よりもはるかに若い23歳の彼は、ギリシャ彫刻の端整な肢体に長い金髪と肉感的な赤い唇をつけ加えて生命を吹きこんだ、とでもいうふうな美貌の持ち主だった。ほとんど陳腐な美しさ、と形容してもいいほど古典的にすぎる彼の容貌は、見方によってはあるいは退屈なものでしかなかった。しかし、現代風の価値観に支えられた個性的な美形が入り乱れるニューヨークでは、彼の没個性的な美しさは逆に新鮮にきわだって見えた。そのためにアレックスのまわりには、ホモセクシュアルの男ばかりではなく彼の本性を知らない女たちまでたくさん群がった
アレックスに言い寄る女たちは、間もなく彼の正体を知ってその場を離れた。男たちの場合にはそれとは逆のことが起こった。アレックスは時には何のこだわりもなくあけっ広げに、また時には彼ら同類の人間だけにわかるひそやかな媚びを全身に浮き立たせて男たちの誘惑に応じた。
アレックスはそうやって3年前には志良と関係を結び、同時に他の相手とも交渉を持っていた。それは現在も変わっていない。アレックスは志良と関係を持ちつづける一方で、半ば公然と彼以外の複数の相手とも情交を重ねていた。
エイズ感染の危険を少しも考えていないようなアレックスの気ままな行動に不安をおぼえて、志良は他の男たちとの関係を断ってくれと何度も彼に訴えた。アレックスを介して彼自身がエイズに感染することへの恐怖心ももちろんあった。が、志良はそう口にするとき、本気で若い愛人の身を気づかっていた。
ところがアレックスは、志良の言い分をエイズ禍を盾に取った彼の嫉妬だと決めつけて、少しも取り合わなかった。嫉妬だと言われると志良は返す言葉がなかった。ギリシャ彫刻然としたりりしい青年を、ひとりじめにしてみたい、と彼は心の奥で願うことがよくあった。
3年前、はじめて志良と関係を持とうとするとき、アレックスは彼がエイズウイルスの感染者ではないことを志良に告げていた。一度きちんと血液検査を受けてネガティブ( 陰性)と証明されたという。
「証明書は持ち歩いていないけど…」
アレックスは志良の反応をさぐるように眉間に軽くシワを寄せて彼を見た。
エイズとホモセクシュアルの因果関係があかるみに出て以来、同性愛社会の住人たちのあいだでは、相手と交渉を持つ前にエイズ感染の有無を確認し合うことが当たり前になっていた。
口頭でのやり取りだけでは満足しない者もたくさんいた。彼らは保健所や病院が発行する血液検査の証明書を常に持ち歩いていて、行きずりの相手と関係を結ぶ場合には互いにそれを見せ合うこともめずらしくなかった。
「ぼくも証明書は持ち歩かない主義だ。でも、血液は君と同じように潔白さ。ちゃんと検査も受けているよ」
志良はわざとおどけるような調子でアレックスに返した。そのとき志良の背広の内ポケットには、「ネガティブ(陰性)」と明記された彼自身の血液検査結果の証明書が隠されていた。臆病すぎるほどに用心深い男でありながら、志良はそのときアレックスに
対してとっさにらい落をよそおった。彼の中の欲望の琴線をかき鳴らしている美しい若
者に、疑りぶかい中年男、と見なされることを彼は深くおそれた。
★
アレックスと出会う前、志良が性的関係を持ったはじめての男であるジョン・ヒューズがエイズで死んだ。彼は志良が通う大学の助教授だった。
志良はジョン・ヒューズが発病する前に、すでにエイズ感染の有無を判定する血液検査を受けて陰性と判断されていた。当時は、まともな神経を持つホモセクシュアル
の男たちは、誰もが一度や二度の血液検査を受けているのが普通だった。
志良とジョン・ヒューズの恋愛関係は、助教授がエイズを発症する前にすでに終わっていた。ふたりはその後も友人として親しいつき合いをつづけていたが、性的関係はないため志良は彼からのHIV感染を疑うことはほとんどなかった。それでも身近にいる仲間のエイズ発症は彼に強い衝撃をあたえた。志良はジョン・ヒューズの発病を知るとすぐに、念のために血液検査を受けた。そして再び陰性と診断された。
そのとき以来、彼は関係を持つ相手に対してきわめて用心ぶかくなった。志良が血液検査の証明書を持ち歩くようになり、さらに相手にも同じ書類の提示を求めるようになったのはその頃のことである。

短い秋が過ぎ、摩天楼のあいだに吹きつのるビル風が頬を切るように冷たい季節になっても、アレックスの容態は良くならなかった。不審に思った志良は、彼らの密会場所にもなっているダウンタウンのアレックスのアパートを訪ねたある日、血液検査を受けてみたほうがいいと遠慮がちに彼をうながした。
「血液検査―僕がエイズだとでもいうの? やめてくれよヒロ。前にきちんと検査をして白と出ているんだ。そのあともずっと感染には気をつけてきている。ひどいことを言わないでくれ!」
アレックスは、まったく思いもかけなかったことで侮辱された、とでもいうように激して声をあらげた。
「アレックス。君をうたがっているわけじゃないんだ。ただ万が一ということもある。大事をとった方がいいんじゃないか、とちょっと考えただけだ」
志良はうろたえて返した。
「大丈夫だよ。僕が風邪をひきやすい体質だということはヒロも良く知っているじゃないか。僕の体のことは僕が一番よく知っている。いつもの風邪がちょっとこじれたんだ。こじれた風邪には熱も下痢もつきものさ」
アレックスはさらに言いつのった。無理に笑おうとするために顔がひきつるようにゆがんでいた。彼が志良と同じ不安にとらわれながら、大丈夫、思いすごしだ、と必死に自分に言い聞かせているのはあきらかだった。
アレックスの言葉を信じたわけではないが、志良は彼の言うがままに結論を出させるのを先送りにしてきた。恐ろしいものから目をそらしていたい心理がはたらいていた。またまるでアレックスに合わせるように、思いすごしかもしれない、いや、きっと思いすごしだ、と志良が自分に言い聞かせている部分もあった。
先に不安に耐えきれなくなったのはアレックスだった。血液検査を受けてみる、と彼が自ら口にしたときには、志良には反対する理由もまたその気力もなかった。
葛藤

礼子に声をかけるきっかけがつかめないまま、志良は居間の入り口に棒のようにたたずんでいた。
広い居間の全体には冬の早い夕闇がみるみるうちに忍び入って立ち込め、照明の当たっている礼子とその周辺だけが一段と明るく闇の中に浮かびあがっていった。居間はマンハッタンを拠点にするある劇団が稽古場として使っていたロフトを改装したもので、400平方メートルもの広さがあるのだ。天井の高い広い空間を埋めているのは、離ればなれにぽつんと置かれている2本の観葉植物と、いま礼子がすわっている中央のソファセットと、四方の壁に沿ってほぼ等間隔に置かれている40脚あまりの椅子だけである。
居間の奥の一角には、簡易壁に囲まれたもう一つの空間が隠されていた。そこは礼子専用の部屋である。礼子はその部屋に、もう一組のソファや机や本棚や電話や仮眠用のベッドなどを置いて、自分の書斎代わりに使っている。大きな西洋屏風、といったおもむきのある簡易壁を取りはずすと、居間はさらに広くなる。そこまでがかつては劇団の稽古場だった居間の本来のスペースなのである。居間を二つにへだてている簡易壁は、パーティーがひらかれるたびにかならずとりはずされた。
彼ら夫婦はパーティー好きの礼子の強い希望で、わざわざこのだだっ広い居間のあるアパートを借りているのだった。部屋のぐるりの壁に沿って多くの椅子が並べられているのもパーティーに備えてのことだった。
礼子はブロードウェイの演劇界と深くかかわっていて、舞台俳優や演出家や脚本家やプロモーターやジャーナリストといった、演劇関係の友人知己を招いてしばしばこの居間でホームパーティーをひらく。それはいつも、来るものはこばまない、というスタイルのバカ騒ぎになるので、礼子のパーティーは人気があった。
礼子のパーティー好きは彼女がロンドンに住んでいたころに始まったものである。彼女は日本で大学を卒業すると同時に演劇研究の名目でイギリスに渡り、志良と見合い結婚をするまでずっとそこに住んでいた。
演劇研究とはいうものの、ロンドンでの礼子の生活は学究的なかた苦しいものではなかった。彼女はロンドン市内の演劇学院に形だけの籍を置いて、実際にはウエストエンド界わいの劇場で観劇に明け暮れる毎日を送っていた。その一方で礼子は、素人劇団に所属して彼らの公演活動を手伝ったり、いわゆる呼び屋の仲介に立って駆けずりまわったり、あるいは日英双方の演劇雑誌や新聞にちょっとした記事や評論めいたものを書いたりすることもあった。
夜になると彼女は、演劇関係の仲間を招いて自宅でひんぱんにパーティをひらいた。はじめのうちはそれは、気の合う者どうしが互いに招いたり招かれたりする小さなホームパーティーの一つにすぎなかった。ところが時が経つにつれて礼子の自宅での集まりは人々の人気を呼んで、規模が大きくなり回数も増えていった。
そのころ彼女は一留学生にしては広すぎるほどのりっぱなアパートに住み、パーティーをひらくたびに豊富な飲食物や趣向を用意して客を楽しませた。パーティーといえば、参加者の全員が飲み物や食べ物を持ち寄ってはじめて成立するのが普通だった貧しく若い仲間うちでは、それが評判になって礼子のパーティーはいつも盛りあがった。
礼子のロンドンでの生活は日本の実家からの潤沢な送金でまかなわれていた。資産家の礼子の父親は、娘のイギリス留学には初めは猛反対をした。ところが礼子がほとんど家を飛び出すような形でイギリスに渡ってしまうと、こんどは一転して娘の擁護にまわり、月々多額の仕送りをはじめた。
その習慣は礼子が志良と結婚してからもつづけられている。志良は正確な数字は知らないが、日本から妻に月々送られてくる金が彼の給料をはるかに上回る金額であることは承知していた。実務的な父親が、節税を念頭に置きながらひとり娘に少しづづ財産を分与して行く、という意味もそれにはあるらしかった。
ロンドンで礼子に招かれた客の多くは、後日彼女を別のパーティーや夕食会に招き返した。そこで新たな交友関係ができると、礼子が彼らを自宅のパーティーに招いて次には礼子が招かれる、という具合いに彼女のかかわるパーティーの数も友人の数も急速に増えていった。礼子はそうやって排他的といわれるロンドン演劇界の内部に人脈を築いて、仕事と勉強を兼ねた彼女の演劇活動を有利に進めていった。
志良との結婚を境に礼子の活動の場はロンドンからニューヨークに移った。礼子はそれをきっかけにして、それまでは半ば趣味の域を出なかった彼女の演劇関連の活
動の全てを、仕事に結びつける計画を立てた。礼子はブロードウェイの演劇を日本に持ち込んだり、逆に日本のそれをニューヨークに運んだりするプロモーターとして、本格的に仕事をしていこうと考えたのである。その仕事にはなによりも人脈が大切だった。礼子はロンドンで身につけたパーティー外交の手法をそのまま使ってニューヨークでも動きはじめた。
ロンドンのウエストエンドとニューヨークのブロードウェイは、大西洋をへだてて深いつながりを持っている。そのために礼子は、ニューヨークに移り住んだときにはすでに、ブロードウェイの演劇関係者のあいだに多少のコネクションがあった。ロンドンの友人たちが、礼子のためにブロードウェイの人々にあらかじめ声をかけておいてくれたのである。礼子はそのコネクションを彼女の得意なパーティー外交によってたちまち大きく広げた。
人脈が広がるにつれて礼子の仕事も増えていった。彼女はここ二・三年はブロードウェイの大きな興行主と契約を結んで、アメリカと日本の仲介に立つプロモーターとして定期的に仕事をこなすようになっていた。それはブロードウェイの劇場にかかる全ての出し物を観劇し研究して知りつくす一方で、関係者との絶え間のない会合や接待や裏工作や下見や準備や出張等々を次々にこなしていくことを意味した。そのかたわらで礼子は、ほとんど毎晩のようにひらかれるそこかしこのパーティーや会食にも顔を出し、彼女自身が主催する自宅でのパーティーも計画しなければならなかった。礼子は昼も夜も外出をしていることが多く、彼女が自宅でひらくパーティーの夜以外は、夫婦がそこで顔を合わせる機会はきわめて少なかった
しかしそれは礼子だけに責任のあることではなかった。志良は志良で勝手に生きていて、夜になってもまともに家に帰る日は月に十日もあればよかった。
彼ら夫婦は、そんなふうにお互いが自由気ままに生きていくことを前提に結婚生活をはじめていたのである。
★
「電気、つけてもいいかな・・・」
志良は居間の入り口にたたずんだまま妻に声をかけた。
バネにはじかれたようにふいに大きく頭を振って礼子がこちらを見た。長い豊かな髪が、ばさり、と音がしたかと思えるほどの勢いで振り乱されて彼女の顔にかかった。それがいっせいにゆれて、もう一度ゆれて、やがて止まった。乱れた髪の間にけわしい光を帯びて見開かれている礼子の双眸があった。
「…ごめん…おどろかすつもりじゃなかったんだ」
撃たれたようにすくんでこちらを凝視していた礼子の表情がゆるんで、両肩から力が抜けた。その動きにまぎらせて、彼女は何かの秘密でも隠すようにすばやく感情を押し殺した。妻の表情が、スイッチでも切り替えるようにがらりと変わったことから志良はそのことを悟った。
「―オフィスから直接パーティー会場に行くんじゃなかったの」
抑揚のない冷ややかな声とともに刺すような視線が志良に投げられた。 見開いた切れ長の目と、小鼻を圧縮して盛り上げたような素直な鼻梁と、大きめの唇に引かれた紅が濡れたように光沢を放っている礼子の顔の造作は、意志的で美しい、と見る人は誰もが称賛する。しかし、いま夫を見上げている彼女の顔は、能面のように暗いのっぺりとした印象だけがあって、まったくつかみ所がなかった。
「今夜のパーティー、顔を出すのをよそうかと思うんだ」
志良は入り口の縁に寄りかかって立って、さりげなく顔をそむけて妻の視線を避けた。
「仕事―」
志良はオフィスでやり残した仕事をしばしば自宅に持ち帰る。
「いや」
「具合いでも悪いの」
「そういうのじゃないんだ。ただパーティーに行くのがなんとなくおっくうになった」
志良は歓迎されていない客がはばかりながら敷居をまたぐように、そろりと居間に足を踏み入れた。それから壁際の椅子の一つを引いてそれに腰を下ろした。
「―君が家を出てしまわないうちにそのことを言わなくちゃ、と思ってね。それで急いで帰ってきた」
志良はすべるようにやすやすと嘘をついた。
礼子の表情は変わらなかった。感情をおさえた、あるいはもともと感情など備わっていない人間でもあるかのような冷めた、もの憂い顔つきで夫の動きを見つめている。変わったところはなにもない。彼女はもう長いこと志良とはこんな調子でつき合ってきていた。
礼子には二つの顔がある。一つはパーティーや夕食会などの人だかりの中で彼女が見せる陽気でにぎやかな顔であり、もう一つは今のように夫とふたりきりでいる時に見せる陰うつで不機嫌な顔である。明と暗にはっきりと分かれる礼子の気分は、山の天気のように極端から極端にゆれて変わりやすく、しかも動きが迅速で志良が予測するのは難しかった。
それでも結婚した当初は、礼子はなるべくあかるい浮いた気分を持続させようと彼女なりに努力をしていたような気が志良はする。彼に対する態度にももう少しやわらかいものがあった。礼子はいつからかその努力をやめた。
それがいつ頃のことなのか志良は今ははっきりと思い出すことができない。結婚後しばらくしてある日とつぜん変わったような気もするし、長い時間をかけて徐々に変わっていったような気もする。一つだけはっきりしているのは、結婚してこの方、志良が妻の動向には無関心な男でありつづけたという事実だった。彼の記憶が判然としないのも、まさにそこに原因があった。
志良は「お互いが自由気ままに生きていく」という結婚に際しての妻との約束を、しっかりと守ってきたつもりでいる。普通の夫婦の感覚で考えれば、家庭生活を完全に犠牲にしてしか成立しえない仕事一辺倒の妻の日常を志良が黙認しつづけてきたのも、それがお互いに束縛し合わないという結婚の条件の一つだと彼が考えたからである。
妻の自由を認める代わりに志良は彼の自由も獲得し、結婚生活をはじめてからも独身時代とほとんど変わらない毎日を過ごしてきた。昼間はマンハッタンにある日本系の大手証券会社に籍を置く有能な経営コンサルタントとして働く一方で、夜になると彼はマサチューセツの学生時代からつづく二重生活者として、自由気ままにニューヨークの街を徘徊した。それは彼と同類の仲間たちがひらくパーティーや会食に参加することだったり、ダウンタウンやアップタウンのゲイバーやクラブで、気やすくてしかもエイズ感染のおそれのない相手を探し求めることだったり、そうやって探し求めた相手とホテルや仲間のアパートで交渉を持つことだったりした。
3年前にアレックス・カーンと深い関係になってからは、志良が肉体交渉を持つ相手は彼ひとりだけになった。が、人々が気づかない場所での志良の二重生活は、相も変わらずにつづけられていたのである。
★
「だからあれほど気をつけろと!」
「 ポジティブ(陽性)だったのか」と問う志良に、アレックスが電話の向こうで「そうだ」と返したとき、志良は憤怒をあらわにして叫んでいた。アレックスを介して志良自身も感染しているかもしれない死病への恐怖と、彼の忠告を無視して無茶な行為をつづけた相手への怒りが同時に湧き起こって、志良は体中の血が逆流するかのような恐慌におちいった。彼はつづけてアレックスを罵倒しようとした。しかし志良の言葉はそこなわれ、思考は混乱してただ小きざみに体がふるえた。
「助けてくれヒロ!怖いんだ。とても怖いんだ。お願いだからヒロ、助けてくれ!」
アレックスは悲鳴に近い声で叫んだ。(いまさら何を・・・)と志良は言い返そうとした。しかしやはり声が出せない。アレックスはなおも、助けてくれ、恐ろしいんだ、と叫びつづけ、やがて志良に会いたい、今すぐに会ってくれ、と電話の向こうで哀願した。泣きすがるアレックスを、「こちらから連絡するまで待て」と志良はようやく突き放してガチャリと電話を切った。
アレックスに電話をし返す気はまったくなかった。それどころか志良は、アレックスのことなどどうでもいい、と混乱する頭の中で考えた。― 発病した彼はもうどうあがいても助からない。あいつは忠告を無視して勝手なことばかりをした。自業自得だ― アレ
ックスをあわれむどころか志良の中には怒りだけが残った。
怒りは何の前ぶれもなくふいに消えた。消えた先から波が返すように今度は絶望感が押し寄せた。救いはどこにもなく彼もやがてエイズを発症して死ぬのだ、とまたことさらに考えた。
(まだ俺が感染したと決まったわけじゃない)
志良は気をふるいおこして自分に言い聞かせようとした。彼はエイズウイルスの感染予防には十分に気を配ってきた。アレックスとの交渉のときにも安全を考えて毎回必ずコンドームを用いた。おそらく彼を通しての感染はないはずだ―とけんめいに自分の気持ちを落ちつかせようとする先から、、志良の脳裏には激しい感情にかられて予防具を付けないまま行為を終えたいくつもの夜の記憶がよみがえった。穴に落ちるように彼の心は再び恐怖の底に沈んだ。
アレックスからの電話の後、志良は午前中いっぱいを身もだえるような焦燥感と、怒りと絶望にまみれて過ごした。仕事はまったく手につかなかった。
だが、そんな中で彼はやがて決心した。エイズウイルスに感染しているかどうかが判断される、HIVスクリーニング検査をその日のうちに受けることにしたのである。過去に同じ検査を2回も受けている経験が彼のすばやい決断につながった。
志良は午後一番に仕事場を早退してブルックリンの医療施設に向かった。そこはマンハッタンの仕事場からもまた彼の自宅のあるクイーンズからも離れた場所にある。当時はエイズへの偏見と恐怖と差別が社会に蔓延していた。そうした社会状況の中でスクリーニング検査を受けるのは 、過去に同じ体験をしている志良にとってさえ、決して心やすいものではなかった。
スクリーニング検査では陽性か陰性かの判定結果がその場で出る。結果が陰性と出ればウイルス感染はないと判断されてそこで検分は終わる。逆に陽性と出た場合は、後日再検査が行われる。確認検査と呼ばれる2度目の精査は、スクリーニング検査でたまに出る誤認感染(偽陽性)を排除する目的で実施される。
志良のスクリーニング検査の結果は、あっさりHIV“陽性”と出た。彼はエイズウイルスに感染していると判断されたのである。
検査結果が陽性と告げられたとき、志良はここまでのアレックスとの関係から推測して、確認試験を待つまでもなく自分のHIV感染は真性のものに違いない、と吐いて吸う息でさえ苦しく感じる絶望の底で思った。
★
一週間後、確認検査が行われた。志良自身が予想した通り、結果はそこでも陽性と出た。
そうやって志良弘樹のHIV感染が確定した。
深傷(ふかで)

志良にとってはエイズはあまりにも身近な病気だった。彼はそれまでに、恋人だった助教授のジョン・ヒューズをはじめとする何人もの仲間が、業病に取りつかれて無残に死んでいく様を見とどけてきた。どの仲間の死もまさに「無残な」という形容がふさわしい死に方だった。
死病におかされた者は、誰もがはじめは微熱や下痢や軽い倦怠感などの、一見なんでもないような体の変調を訴えた。普通なら2、3日も静養すれば回復するはずのそれらの症状が、いつも彼らの〝終わり〟の始まりだった。死病は体の奥深くに確実に潜行して肉体をむしばみ、病人はじわじわと衰弱していった。生きたまま肉体が腐って、ぼろぼろに崩れていくのにも似た凄惨な闘病生活が終わりに近づくと、彼らの多くは末期のエイズ患者に特有の痴呆性の精神障害におちいった。何も知らないまま死んでいく者はそれでもまだ幸せな方だった。病人のなかには、しもの世話も自分ではできなくなるほど体が弱っても、依然として正気を保っている者がいた。そういう不運に見まわれた犠牲者は、人間としての尊厳をうしなったまま恥辱にまみれて死んでいかなければならなかった。
しかし、仲間たちの死が悲惨だったのは、彼らが不治の業病に取りつかれたこと自体にあるのではない、と志良は考えていた。彼らの真の不幸は、エイズという病名があきらかになると同時に、ほとんどが身に近しい人々はもちろん肉親にさえ忌みきらわれ見捨てられて、孤独に死を待たなければならない現実にあった。
志良は彼の初めての同性愛相手であるジョン・ヒューズが、エイズで死んだときに早くもそのことを思い知らされた。
ジョン・ヒューズは、ボストンで四代つづいている弁護士一家の三男だった。彼は幼い頃から“天才”とあだ名をつけられていたほど異常に頭の良い男で、ふたりの兄につづいて大学の法学部を卒業した後に、25歳の若さで同じ大学の経済学部の助教授に抜擢された。エイズに発病したときジョン・ヒューズはまだ20歳代の終わりだったが、間もなく教授に昇格すると噂されるほど将来を嘱望されていた。
街でも指折りの名家に生まれた若い天才的な学者は、志良の卒業が間近にせまっていたある日、とつぜん大学をやめて街から姿を消した。
ジョン・ヒューズがエイズにおかされていることを知った彼の父親と、父につづいて弁護士になっているふたりの兄が、ジョン・ヒューズの病名を伏せるように関係者に圧力をかける一方で、大学の上層部にはたらきかけて彼を退職させ、街から遠く離れたニューヨークの病院に送り込んだのである。スキャンダルを恐れての素早い動きだった。
母親だけが息子を見捨てるような男たちのやり方に反対したらしい。が、当時の社会状況の中では結局夫とふたりの息子の決定にしたがうしか方法がなかった。その頃は「同性愛者だけに取りつく」とさえ喧伝された正体不明の業病は、、当事者ばかりではなく世間一般の人々を震撼させ、ホモセクシュアルの人間とエイズ患者への嫌悪感が巷に充満していた。
ジョン・ヒューズが街からいなくなって3ヶ月後に志良は大学を卒業して、ニューヨークのマンハッタンにある今の会社に就職した。ジョン・ヒューズが入院している病院も同じマンハッタンにあった。志良は病院の正確な所在地はもとより彼の病室の部屋番号まで知っていながら、それからさらに半年あまりが過ぎるまで助教授を見舞いに行こうとはしなかった。
死の宣告を受けて孤独に闘病生活を送っているはずのジョン・ヒューズを志良はどこかで恐れていた。いや、ジョン・ヒューズではなく、エイズとエイズ患者を差別し、忌み嫌い、憎んでさえいる世間を彼は恐れた、と言うべきかもしれなかった。ジョン・ヒューズと再びかかわりを持つことで、彼と同類の人間である自分もたちまち断罪されてしまうのでもあるかのような恐怖を、志良はずっと感じつづけていたのである。
志良がはじめてジョン・ヒューズを見舞ったのは、マサチューセッツの仲間だったパット・スペンサーとエミリン・シーガルが、ニューヨークに彼を訪ねて来たときだった。パット・スペンサーは、マサチューセッツの仲間がよく集まる店のディスクジョッキーで、ジョン・ヒューズがもっとも長く関係を持ってきた男だった。行きずりに関係を重ねていくのがめずらしくない彼らの世界にあって、ジョン・ヒューズとパット・スペンサーは、まるで飛び出した二つのブーメランが冒険をつづけていつかは振り出しにもどってくるように、最後にはかならず結ばれている恋人どうしなのだった。
またエミリン・シーガルは、志良の大学の同期性で、彼とともに大学を卒業してボストンの銀行に就職していた。志良はジョン・ヒューズの紹介でエミリン・シーガルと知り合いになった。ふたりは性的な関係を持つことはなかったが、同類の人間どうしの気安さで親しくつき合うようになった。
志良は久しぶりに会ったボストンのふたりの仲間に、ジョン・ヒューズの死期がせまっていると知らされて、彼らとともに病院を訪ねる決心をした。
発病から2年近くを経て、ジョン・ヒューズは変わりはてた姿で病室のベッドに横たわっていた。白いシーツがめくれて外に露出している彼の上半身は、頭も顔も首も肩も両腕も、あらゆる部分が、かび臭い暗室で長い時間をかけてくん製にされた肉塊かなにかのように黒ずんでやせ衰え、小さくしぼんでしまっていた。
志良は病人がジョン・ヒューズその人だとはにわかには信じられなかった。不審に駆られて彼は思わず隣に立っているパット・スペンサーの顔を見た。志良の困惑をたちどころに察したらしいパット・スペンサーは、低いささやくような声で言った。
「間違いない。ジョンだよ。はじめて見る人はみんなびっくりする……」
志良は目の前の病人をぼう然と、しかしありたけの気力をふるいおこして再び見つめた。彼の視線はやがてジョン・ヒューズの顔に吸い寄せられ、それは病人の意志のありかを求めて、ごく自然に彼の両眼に移った。そこにはぽかりとうがたれた二つの穴のような眼窩があった。眼窩の底にある瞳は上の一点を見つめてじっとしていた。しかしそれは何かの想念に没頭している彼の意志が瞳を一点に固着させているのではなく、逆にその束縛から解き放たれた瞳が、死の淵に意味もなくどろりと投げ置かれているにすぎなかった。
「…ジョン―」
志良はここまで一度も彼を見舞いに来なかったことを悔やみながらそっと声をかけた。返事はなかった。
「ジョン―」
彼は声を少し高くして再び呼びかけた。ジョン・ヒューズは呼吸さえ停止したのではないか、と志良がいぶかしがったほどに静ひつにベッドに横たわっている。病人の向こう側の窓外にせまっている隣りのビルのレンガ壁が、志良の悲痛な声音を病室に押し返して反響させたようだった。
「ジョンはもう自分が生きていることさえわからない。苦しみつづけて、今ようやく平和が訪れたんだ。1ヶ月くらい前から意識が混濁しはじめて、すぐになにもわからなくなった。それまではしょっちゅうマサチューセッツの仲間たちのことを思いだしてはなつかしがっていた。君のことも…よく話題にしていた」
パット・スペンサーはまるで遠い思い出でも語るようにしんみりと言いつつ、志良と助教授の顔を交互に見た。病人を避けつづけてきた志良の冷淡を少しも責めようとはしない彼の態度が、志良の中の自責の念を逆にかき立てた。
「もっと早く見舞いに来れば良かった……ここに足を運ぶのが、なぜか怖かった…」
志良がうなだれたとき、それまで黙って彼とパット・スペンサーのやり取りを見つめていたエミリン・シーガルが、なぐさめるような口調で言った。
「しょうがないよ。ジョンの家族だってここには寄りつかなかったんだ。でも君は今ここに来た。ジョンはきっと喜んでいるさ」
「彼の家族は……まったく訪ねてこないの?」
志良はパット・スペンサーとエミリン・シーガルの顔を見くらべるように見た。
ジョン・ヒューズがニューヨークに送られたいきさつから考えて、彼のその後の運命については志良はある程度予想はできた。しかし地元の病院ではなく、遠く離れたニューヨークの病院に入院したのだから、家族は人目を気にしないで彼を見舞うことができたのではないか、とも思った。
「誰も一度も訪ねてこなかった。ジョンの家族は、入院治療費という葬式代を月々払い込んでこの病院に彼を捨てたんだ。預けたのではなく、彼らは確かにジョンをここに捨てた。捨てたのだから、誰もそれを拾い上げる気にはならなかったのだろう」
パット・スペンサーが説明した。相変わらず静かな口調だった。自分の恋人であるジョン・ヒューズの家族に対する憎しみや怨みはすでに消えて、ジョン・ヒューズの運命に自分のそれを重ね合わせて見ているのでもあるかのような、凄惨ななにかが彼の物腰にはただよっている、とその時志良は感じた。それは志良の思いすごしではなかった。パット・スペンサーもそれから2年後にはエイズで死ぬ運命にあったのである。
ジョン・ヒューズは生きる屍(しかばね)と化して、その日からさらに数ヶ月間病院のベッドに横たわっていた。志良はその後はひんぱんに病院に足を運び 、多くの仲間たちとともに彼の最後にも立ちあった。
ジョン・ヒューズの家族は、彼が息を引き取った翌日はじめて病院にやって来た。そこには母親の姿はなく、父親とふたりの兄がいるだけだった。
ジョン・ヒューズの遺体は、まっすぐに火葬場に運ばれて焼き払われることになった。それは家族の強い要請による処置だった。ほとんどがキリスト教徒であるジョン・ヒューズの仲間たちは、その決定に衝撃を受けて普通の形で埋葬しろ、と家族と病院に強く抗議した。しかし、結局それは聞き入れられることはなかった。
キリスト教徒ではない志良は、埋葬と火葬の間にある落差を宗教的な感慨を持って理解することはできなかった。それでも、ジョン・ヒューズの体中に巣食っているエイズウイルスを焼き払う、という名目で行われた火葬が、実は彼の存在や存在した記憶でさえも払拭しつくしたい、と願う父親とふたりの兄の心根の体現であることに気づいたときには、彼は心底ぞっとするものを感じた
★
志良は彼のHIVスクリーニング検査が陽性と知らされたとき、自身がエイズに発病した場合の日本の肉親たちの反応を頭に思い描いた。誰もが驚き、うろたえ、嘆き、志良という人間を身内に持ったことに恥じ入って、固く心を閉ざしていくであろう様がありありと見えた。友人らも彼をあざ笑い唾棄する者がほとんどに違いない。
父と母でさえおそらく彼を許してはくれない、と志良は考えた。小さな田舎町に生まれて東京の一流大学に進学し、そこで大学院を終えた後にアメリカの大学にまで留学した志良を、彼の両親はいつも誇りにしてきた。志良が発病すれば、息子を誇る気持ちが強い分だけ父と母が受ける心の痛手は大きく、それは回復されることがないまま年老いた両親と死病にかかった志良のうちのどちらか一方が近いうちにこの世から消える。そして暗いわだかまりだけが生き残る者の心に宿りつづける、と志良は考えた。彼は暗たんとした気分でそれでもどこかに救いを求めて、ふだんはあまり考えることもなかった日本のなつかしい人々の顔を次々に思い起こしていった。
礼子の顔がふと志良の脳裏に浮かんだ。妻の反応は日本にいる肉親や友人らのそれよりももっと直せつで憎しみにあふれたものだろう、と彼は思った。
礼子は志良がエイズに発病すると同時に、彼がこれまでひた隠しにしてきた彼の同性愛嗜好のことも知る。彼女はおどろき、あきれ、不審と憎悪と侮蔑をあらわにして夫をののしり、ただちに夫婦の縁を切るだろう。仕方のないことだった。彼は結婚に際しても、また結婚生活に入ってからも妻をあざむきつづけてきたのだ。その報いが一気に噴出するありさまを予見しながら、志良は身から出たサビだと自分に言い聞かせてあきらめようとした。しかし、あきらめきれない。胸に空洞をうがたれるような深い寂しさをおぼえた。
その時とつぜん後頭部に電気のコードを押しつけられたような戦慄が志良をおそった。エイズウイルスは志良を介して礼子にもすでに感染している可能性がある、と彼は気づいたのである。
それはまったくふいな感慨だった。彼はそこまで被害者としての自分の身の不運を呪い、自らの痛手を慰めることばかりにかまけきっていて、妻が抱えこんだかもしれない巨大な不幸には少しも気がまわらなかった。
いやな、胸苦しいものが志良の中にじわりと広がった。なにも知らない妻を死病の道連れにしたかもしれないという思いは、彼自身が罹病することを考えるよりももっと息苦しい不安と焦りを志良の中に呼びおこした。それは掛け値のない彼の良心のうずきだった。
引き金

志良は彼の同性愛嗜好を隠ぺいする必要にせまられて、7年前に東京で礼子と見合い結婚をした。
マサチューセッツとニューヨークで二重生活をつづけているあいだに、志良はおびただしい数のバイセクシュルの男たちが、なに食わぬ顔で妻をめとって、無難に世間を渡りあるいているホモセクシュアル社会の事情に通じた。ふつうの人々は、妻帯者というただそれだけの事実にまどわされて、彼らの秘密をあっさりと見すごしてしまうのである。志良もいつかはそうした仲間たちと同じ道を行くつもりでいた。結婚は彼の同性愛嗜好の絶好の隠れみのになるはずだった。
志良は結婚というものを、彼の男色趣味を隠ぺいするための方便であると同時に、自由な男と女が自由なままで共同生活をする約束事であるべきだ、とも考えていた。従って志良は、彼の理想の相手は結婚後も自分の仕事や趣味の追求にいそがしい、独立心の旺盛な女性でなければならない、とひそかに計算していた。
礼子は見合いの日の数日前にわざわざイギリスから帰国して、東京都内のホテルの喫茶室で志良と対面した。型どおりの挨拶が終わった後で、志良は遠いイギリスから見合いに駆けつけてくれてありがとう、と礼子に声をかけた。すると彼女はとつぜんかん高い陽気な声で言い放った。
「あっ、そのことでしたら気にしないでください!もう毎度のことですから!」
志良はおどろいて礼子の顔を見た。
「いけない。私すぐにこんなこと言うからだめなんだ。ごめんなさい」
礼子はあっけに取られている志良に気づいて、あわててつけ加えた。しかし、そうあやまる声もなぜかやけに大きかった。
「全然かまいませんよ。正直に言ってくださったほうが、こっちも気が楽だ」
志良は笑った。あけっ広げに見える彼女の態度に好感を抱いた。
「毎度のことだとおっしゃると、見合いはもうこれまでにもずいぶんと?」
志良は和んでからかう口調になった。
礼子はさすがに困ったような顔をした。恥ずかしそうに少しうつむいて志良をちらと見、やがて思いきった、という風に顔を上げた。
「隠しても仕方がないですね」「今回は17回目です」
「17回!」
志良は思わずアメリカ人のようにひゅーと口笛を吹いた。
「うーん。はじめてあなたのことを聞いたとき、当然見合いの一つや二つは経験していると思いましたけど。それにしても17回目とはねえ」
志良はすっかりリラックスしてしまった。
「ごめんなさい」
「いや、そんなつもりで言ったんじゃないんです。よくぞ我慢した、とむしろ感心しているんです。それとも、よっぽど見合いが好きな人なのかな」
「本当は早く片づきたいんですけど…。何しろこればかりは相手の方の都合もあることですから」
「なるほど。あの、見合いのたびにわざわざロンドンから帰国なさるわけですか」
「そうなんです。向こうに行った同じ年の暮れに始まって、大体1年に2回の割合で帰っています。日本に来て相手の方に会わなければ送金を絶つ、といつも父におどされるものですから」
「そうすると、今回もお父さんにおどされてしぶしぶと・・・ひどい話だなあ」
志良は頭をかいて、わざとがっかりした振りをした。
「そんなにいじめないでください。アメリカのあの有名なH大学を首席で卒業して、ニューヨークのウォール街に勤めていらっしゃる超エリートビジネスマンの志良さんにお会いしてみたい、という気持ちも少しはあったんですから」
その日の面談は、見合いの席らしい厳しゅくな雰囲気は少しも出ないまま、志良と礼子の半ばふざけた、しかしそこかしこに本音を盛りこんだ陽気なやり取りがつづいて終わった。
見合いの翌々日、彼らは赤坂のレストランで再び顔を合わせた。志良が声をかけて、今度はふたりきりで会ったのである。
その日の礼子は見合いの席とは打って変わって物静かだった。ほとんど憂うつな印象さえ与える彼女の極端な変わり方は志良をおどろかせた。あとになってみると、それは明から暗、静から動へと激しくゆれ動く礼子の気性のあらわれにすぎなかったのだが、その時の志良は2日前とはあまりにも違う相手の雰囲気に強くとまどった。
「おとといはとても楽しかった。帰ってあれからご両親に小言を言われませんでしたか」
「どうして?」
礼子はまるで真四角な卵でも見るように志良を見た。
「どうしてって・・つまり――その、あまり見合いの席にふさわしくないことまで僕らがしゃべりすぎたのじゃないかと思って。僕は帰ってから母にずいぶん叱られました。あなたに失礼なことばかり言っていたと」
「うちのほうはもうすっかり私のことをあきらめていますから」
「あきらめている?」
「私がすっかり外国かぶれになってしまって、もうとても日本人とは結婚できないだろう。父も母もいつもそう言って嘆いています」
「いいじゃないですか、日本人と結婚できないのなら外国人とすればいい。そういう意味では僕もあなたと同じです。日本人の顔をした外国人だとよく友人にからかわれますよ。長い間外国に住んでいると誰でもそうなってしまう」
見合いの日のつづきのつもりで志良は陽気にしゃべった。しかし礼子は一向に乗ってこない。彼女は志良の話に耳をかたむけているように見えるのだが、ときどきそれさえ怪しくなって、焦点の定まらないぼんやりした視線を一点に置いてなにかをじっと考えこんでいるような仕草をする。空疎なたよりない印象があった。
次々に出てくる料理にも彼女はほとんど箸をつけなかった。料理が出つくして食後酒が出てくる機会をとらえて、それでも志良は彼の今夜の本題を切りだした。
「見合いはもう今回で終わりにしませんか」
「・・・」
「昨日の今日で唐突に聞こえるかもしれませんが、あなたとならうまくやっていけそうな気がするんです」
礼子は答えなかった。 黙ったままで志良を見返している。その双眸にはおどろきもとまどいも不安も喜びも、要するに何の表情も浮かび出ていなかった。
志良は落ちつかなくなった。彼は見合いの日に礼子が言った言葉をちらりと頭に思い浮かべた。見合い結婚というのは顔のない男と女が夫婦の契りを結ぶような感じがして気味が悪い、と礼子は言ったのである。
「あなたが見合い結婚に対して抵抗感を持っているのはよくわかります。本当のことを言うと、おとといまでは僕もあなたとまったく同じ気持ちでした。月並みな言い方かもしれないけれど、愛情もないのに結婚をするというのは変だといつも思っていました。しかし、あなたに会って考えが変わったんです」
志良はひとつひとつ言葉を区切って、それぞれに実を込めるつもりで強く、しかしゆっくりとしゃべった。
「見合いは即結婚ではなくて、あくまでも出会いの場所なのだと考えればいいんです。僕はおととい北尾礼子さんという女性に出会ったのだと考えています。偶然でもない。自然でもない。少しぎょうぎょうしいところのある出会いであったとは思います。でも出会いであることに変わりはありません。出会って、あなたのことがとても気に入りました。好きだと言ってしまいたいのですが、何しろ見合いでお会いしただけなので、それは言いません。でも―もう言ってしまいました…。結婚してください」
礼子は眠気をけんめいに払いのけようとするように目をしばたたきながら、志良の顔を見ている。じれったくなるほどの間を置いてから彼女はぼそりと言葉を押し出した。
「見合いでも、恋愛でも、結婚には自信がありません。正直に言うと、志良さんはこれまでの見合い相手の人たちとは違うと私も思う。でも結婚となると――」
「僕ではだめですか」
「そういう意味じゃなくて・・・志良さんに迷惑がかかるだけだから」
「迷惑?」
「私は普通の女じゃないんです」
「わかっています。だからあなたと結婚したいんです」
「少しもわかっていません。わかっていたら私と結婚したいなんて言えるはずがない。私は志良さんが考えているような人間じゃない…」
「どういう意味でしょうか。良かったら教えてくれませんか」
「……」
礼子はうつむいた。そのまま押し黙ってしまう。
「あなたが自分を普通の女性ではない、とおっしゃる意味は僕はわかっているつもりです。外国に長く住んでいると、物の見方や考え方が自分でも知らないうちに普通ではなくなっていく。人間が変わってしまう。あなたはそのことを言っているのだと思います。さっきも言いましたように、そういう意味では僕もあなたと同じで普通の男ではありません。僕とあなたは同類の人間なんです」
「私が言っているのはそういうことじゃない」
「じゃ、何ですか。教えてください」
志良はまっすぐに礼子の目の中をのぞき込んだ。礼子はまた押し黙った。やがてふとため息をついた。
「とにかく。私と結婚したら志良さんに迷惑がかかります」
「それはさっき聞きました。迷惑かどうかは結婚してみないとわからないでしょう」
「そういうことじゃないんです」礼子はきっぱりと言い返して、ふいにあかるい声になってつけ加えた。「たとえ結婚できたとしても、私はこまごまと男の人の世話をしたり、いっしょうけんめいに尽くしてあげたりすることもできないと思います。私はそういう女なんです」
礼子が言いたかったのは、要するにこのことなのだと志良は考えた。それならば大いに彼女を説得する自信がある。彼は不毛なやり取りにおちいりかけたそれまでの話題を断ち切ろうとして、大急ぎで話しはじめた。
「そういうことは少しも迷惑ではありません。僕の身のまわりのことだとか、炊事洗濯だとかをやってもらうために結婚相手を探しているわけじゃないんです。僕の身のまわりのことは僕が自分でやります。また食事の世話とか洗濯とか掃除などの家事もあなたひとりに押しつけるつもりはまったくありません。もしもふたりでこなせないなら、パートタイムのメイドを1日に2、3時間も雇えば片がつきます。それぐらいの給料は僕はもらっています」
「つまり、こういうふうに考えてくれればいいんです。僕と結婚してもあなたはそれに束
縛される必要はまったくない。あなたの今の演劇関係の仕事や人づき合いやパーティーもこれまで通りに自由にやっていけばいい。仕事や遊びを含むあなたの個人的な生活には僕はいっさい口出しをしないと約束します」
「ただ、夫婦である以上、お互いに多少の束縛は避けられないと思います。たとえば僕は仕事のつき合いでパーティーだとか夕食会などに招かれることがよくあります。そういう場合は僕のほうのつき合いを優先させてください。そういうときにアメリカで夫婦がいっしょに行動しないのは少し具合いが悪い。もちろんあなたのほうで夫婦同伴のつき合いをしなければならないことがある場合には、僕も同じようにします。それ以外の時間は決してあなたを束縛しない自信が僕にはあります。お互いに今のままで自由にやっていけばいいんです」
「そんなにうまくいくものかしら…」
「うまくいくと思います。うまくいかないのは、夫婦の一方だけが自由で、一方が古い道徳観にしばられて窮屈な生き方をするからですよ。夫婦がふたりそろって本当に自由気ままにやっていけばかならずうまくいくと思います」
志良は礼子がそう望むなら、彼女が共同生活をいやになった時点ですぐに結婚生活を破棄する、という契約書を事前に取り交わしてもいいとさえ申し出た。
「あなたがいやになった場合は?」
礼子はその時すぐに訊き返した。
「その時もやっぱり別れる」
「要するにどちらかがいやになった場合、ということね。公平だわ」
礼子は志良の熱心な話しぶりに触発されたのか、次第に元気を取りもどしていくように見えた。彼がさらに説得をつづけるうちに、双眸に輝きが宿って礼子は志良の言葉の一つ一つに明確に反応するようになった。まるで眠りに落ちていた彼女の中の何かが、目覚めて動き出したのでもあるかのような奇妙な変化だった。
礼子はやがて、強い拒絶を込めて言っていた「私は普通の女ではない」「結婚すれば志良さんに迷惑がかかる」「お互いが自由な夫婦なんて言葉の遊びだ。実際にはあり得ない」、などという類いの言葉を口にしなくなった。それどころか彼女は志良の話が終わったときには、少し考えさせてほしい、と半ば結婚を承諾したようにも取れる口調で言った。
「返事はロンドンで聞きます。2週間後に少し休みが取れるので、ニューヨークからロンドンまで行きます」
その2週間後の週末に、志良は約束通りニューヨークからロンドンに飛んだ。ニューヨーク―ロンドン間は、心理的にもまた物理的にも前者からロサンゼルスに飛ぶのと同じ程度のたやすい旅である。それでも志良が約束を守って、わざわざアメリカからイギリスまで足を運んだことを礼子は素直に喜んだ。それから3ヶ月後に彼らは東京で結婚式を挙げた。
いざない

居間からベランダに通じる大きなガラス扉の向こうに裏庭の高木の頭がゆれていた。
その背景には闇に包まれたあたりのビルの屋根が、どこからともなくやってくる街の光におぼろげに輪郭をあらわしている。
「今夜のパーティーにはノザンプ社の社長も出席するんじゃなかったの。本当にすっぽかしてもいいの」
礼子は相変わらずソファーにすわったまま、ほんの少し上目遣いになる角度で夫を見上げた。
「ああ。いいんだ」
志良は視線を泳がせながらポツンと返した。
今夜のパーティーにはノザンプ社の社長以下の幹部がひとり残らず顔を出すことになっていた。志良の会社は、その大会社から日本市場のリサーチと販売戦略を練る仕事を一任されていて、しかも彼は実質その部門のニューヨーク側の責任者だった。今夜のパーティーは、普通なら少々体調が悪くても押して出席しなければならないほどの重要なものだったのである。しかし今はそんなことはどうでもよかった。
「食事は?」
礼子が訊いた。
「まだだ。君は?」
「パーティー会場に行く途中で軽くすませるつもりだったわ」
「じゃ、どこか外に食べに行こうか」
「・・・・」
礼子の顔にはじめて表情らしきものが浮かんだ。腑に落ちない、と彼女の全身が告げていた。無理もなかった。志良はもう長いあいだ一度もこうして礼子を外に食事に誘ったことなどなかった。
「もっとも…君さえ良ければの話だけど」
志良は遠慮がちにつけ加えた。無言でこちらを見すえている妻に気圧されていた。
「いったいなにがあったの」
礼子は怒ったように志良をにらんだ。今度は志良の方が押し黙る番だった。HIV感染の件はとても口に出せなかった
★
志良はHIVスクリーニング検査で陽性と診断されて医療施設を出たあと、あてどもなくブルックリンの街を歩きまわった。次々に彼の脳裏をよぎる苦しい想念にとらわれて時のたつのも忘れた。ところが妻への思いがふいに脳裏に浮かび、さらにそれが頭の中いっぱいに満ちあふれたとき、彼は文字通り居てもたってもいられない気分になった。志良はきびすを返して地下鉄の駅に至り、クイーンズの自宅を目指して急ぎ電車に乗ったのだった。
だがこうやって妻と実際に顔を合わせてみると、なにをどのように話し、またどんな行動をとればいいのか、志良には身の処し方が皆目わからなかった。それでも彼は、今夜は妻のそばにいて、たとえ氷のように冷えた時間でもかまわないから彼女と同じ空気に触れ、彼女と同じことを感じて見守ってやりたいと強く思った。
窓外の高木の幹に街の明かりが差し当たり、幹の一方には影ができて濃淡のまだら模様がくっきりと浮かび上がっていた。
夜会服姿の礼子は、外の高木の光と影を背景にソファに座って、ひたすら志良の動静を見つめている。外で食事をしようという夫の誘いに、ひどくとまどっているのが見て取れた。
やがて礼子は言った。
「わかったわ―」
なぜ会社のパーティーをすっぽかして外出するのか、という自分の質問には夫からは今は答えが返らない、と彼女は判断したらしかった。
「ありがとう。君は何を食べたい?」
「ひとりならイタリア料理にするつもりだったけど、あなたに合わせる」
「いいんだ。じゃ、イタリア料理にしよう」
「それならこの服を着がえてくる」
礼子は濃いワインカラーのドレスの胸もとに軽く手を触れて、ソファーから立ち上がった。そのまま部屋を出ていく。志良は広い居間にひとり残された。
★
(この部屋から悪夢がはじまった・・・)
礼子が去って、また一段と広くなったように感じられる居間を見まわして志良は思った。彼はエイズの宣告を受けたアレックス・カーンと3年前にここではじめて顔を合わせたのである。アレックスは礼子が自宅を開放してひらいたパーティーの客のひとりだった。
クリスマスが近づいた頃にひらいたそのパーティーに、礼子は80人近い演劇関係の友人知己を招いた。それは来るものは誰でも歓迎する、といういつもの礼子のスタイルの集まりだったために、口コミで「フリー・ブーズ(ただ酒)」の話を耳にした演劇好きの若い連中がどっと詰めかけて、参加者は最終的には150人前後になった。
ブロードウェー界わいのバーやレストランでウェーターとして働きながら、役者修行をしている無数の若者のひとりだったアレックスは、彼が時どき舞台を踏むオフオフブロードウェーのさらにはずれにあたる小劇場の役者仲間に誘われて、その夜の礼子のパーティーに飛び入りで参加していた。彼も彼の仲間もその日まで礼子とは一面識もなかった。めずらしいことではなかった。礼子のパーティーにはそんなふうに彼女が見も知らぬ客が大勢で押しかけて来たりするのである。
アパートにはメインスペースの居間はいうまでもなく、夫婦の寝室や志良の書斎やダイニングキッチンや廊下や、果てはバスルーム前の小さな空間に至るありとあらゆる場所に人があふれていた。夜が更けてくると居間の中央部分はディスコに早変わりして、常時3、40人の客が音楽に合わせて踊りつづけていた。
志良がディスコの人だかりの向こう側にいるアレックス・カーンに気づいたのは、居間にロック音楽ががんがん鳴りひびき、人々の酒量が進んで座がかなり乱れはじめたころのことである。
アレックスは簡易壁が取りはずされて居間とひと続きになった礼子の書斎のスペースの奥にいた。3人の若い女に囲まれて立ち話をしている。つややかに光る彼の長い金髪と、受け口気味にやわらかくふくらんだ赤い唇が遠目にも志良の気を引いた。
「あの青年は誰?」
志良は、居間からダイニングキッチンに抜ける廊下で、友人の演出家と談笑している礼子に訊いた。そこからだと居間の人だかりに視線をさえぎられることなく礼子の書斎が見わたせた。
「あそこで女の子3人と話している男だ。さっきまではいなかったような気がするけど」
「30分ぐらい前に仲間4人と連れだってきた子よ。ショーンの友達らしいわ」
「ショーンの? なんだ、君の友達じゃないのか」
ショーン・ベントリーは悪役専門の舞台俳優である。礼子のパーティーにはかならず顔を出すので志良も親しい。
「あら! 私の友達に決まってるじゃない。友達の友達の友達もそのまた友達も、みーんな私の友達よ。ね、ジェームズ!」
礼子はカクテルグラスを高く掲げて、隣の演出家に体をもたせかけながらかん高い声で叫んだ。それは積み木ががらがらと派手に崩れるのを見るような、放らつで落ち着きのない、しかし志良にとっては見なれている、パーティーでの妻のいつもの顔だった。
志良は妻のそばを離れて居間に入った。どこにでもいる「レディズ・マン(色男)」といった風情で、3人の女と談笑している人ごみの向こうの若者が、彼の気持ちに強くひっかかっていた。
「ヒロ、どの女がそんなに気になるんだ!」
ショーン・ベントリーがふいに志良の耳もとで叫んだ。
「おどかすなよ。アル・カポネの亡霊が出たかと思うじゃないか」
志良は、脇に立ってにこやかに笑っているのがショーンだと気づいて、とっさに言い返していた。悪人面に生まれついた男が、悪役の演技に徹底するうちにいよいよすごみのある怖い顔になっていく、といういささか陳腐なシナリオの筋書きを地で行っているのがショーン・ベントリーである。顔つきとは似ても似つかない、気のやさしい陽気な男だった。
「わかってるよ。アレックスの隣りのあのキューバ娘だろ?皆んなが目をつけてるぜ。ふんどしを締めてかかれ。礼子にはないしょだ。しかし言っておくが、俺もライバルのひとりだぜ!」
アレックスに気を取られて奥の一角を見ていた志良の思わくを勝手に解釈して、ショーン・ベントリーは酔眼でウインクをした。
「彼、アレックスって言うの? いったい何者なの」
「妬くな、やくな。ただの役者の卵だ。それも大根役者のな。あまりにも美男すぎて役者としては大成しないだろうと言われている男だ。美男を逆の言葉に置きかえれば、要するに俺とそっくりのいい奴さ!」
ショーン・ベントリーは志良の背中をポンと叩いておどけた。
ショーンが立ち去るとすぐに、志良は居間の人ごみを縫ってまっすぐにアレックスのいる一角に向かって歩いた。その途中で志良とアレックスの視線が合った。志良の予感は当たった。彼は視線を釘づけにしてこちらを凝視している若者が、ホモセクシュアルであることを直感的に悟っていた。
告白

礼子の行きつけのイタリアンレストランは、表の壁にツタがびっしりとからみついている古いしょう酒な建物の中にあった。
店の中はこじんまりとまとまっていて、暖炉には薪が赤あかと燃えている。その前には前菜をずらりと並べたワゴンテーブルが置かれていて、二人のウエイターが客の注文に応じていた。暖炉の熱のかからない角度にある格子棚には、ワインのボトルが整
然と並べられている。ボトルの一つひとつは火の投げるゆらめきにゆれて、輝こうとして輝かない深い光沢を放っていた。
ほぼ満席の各テーブルには赤と白のテーブルクロスが2枚重ねに交差して掛けられ、絶妙の光量にしぼられた明かりが、三角に垂れ下がっている各テーブルの端のクロスの赤をひときわ鮮やかに浮き立たせていた。優雅な親しみやすい雰囲気が店の隅々にまで染みこんでいる。
志良はその店を知らなかった。
「なかなかいい店だな。ここはよく来るのかい」
志良は食前酒を口に運びながら店内を見まわした。
「ずいぶん通ったわ。ひとりになりたいときは雰囲気が一番ぴったり合う店だから」
「ひとり?」
「そう。こういう店は人数が少なければ少ないほど楽しい」
「ふうん・・・僕はまた君の一番の気に入りの男友達とでも来るのかと思った」
「今夜はそうしているわ」
礼子はさらりと言った。意外な言葉だった。志良はぽかんと彼女の顔を見た。
「―うれしいことを言うね。ぼくが君の一番の気に入りの友達かい」
「食事に誘ってくれたお礼よ」
礼子はぴしゃりと返した。しかし冷めたい感じではなかった。おどけながらおどける気持ちを隠そうとしているような、そんな言い方だった。
「やっぱりね」
志良は妻をまねておどける仕草をした。
「友達と呼ばれるのは気に入らない。やっぱり亭主のほうがいい?」
「いや、友達のほうがよっぽどいいさ。君がぼくを友達と思ってくれているとは知らなかった」
「じゃ、なんだと思ったの」
「やっぱり亭主かな」
「友達でさえない亭主?それとも友達よりも大切な男と誤解されるほうの亭主?」
「誤解されるほうで、しかも友達でさえない亭主」
礼子はふふと小さく含み笑いをした。彼女が今夜はじめて見せた笑顔だった。志良はその笑顔をむしょうになつかしい有難いもののように感じた。
ウエーターが注文を取りにきた。ファーストコースはふたりそろってパスタをたのみ、メインコースは礼子が魚、志良が肉料理を注文した。
「パーティーが流れたから、君は別の用事に出かけてしまうのじゃないかと思った」
「別の用事…どんな?」
「どんなって…外での君のいつもの用事さ。たとえば…誰かに会いに行くとか」
男に会いに、と頭に浮かんだ言葉をすばやく打ち消して、誰かに会いに、と志良は言った。
志良は結婚してこの方、礼子も彼と同様に外にセックスのはけ口を持っているものと思いこんでいた。結局そのことも含めて、彼らはお互いに自由を認め合って生きてきたのだ。そのことに関しては志良は妻を責める資格もなければまたその気も毛頭なかった。それでいながら彼は、礼子の男のことは知りたくない、とそのときとっさに思った。男に会いに、と彼が言えば礼子は外に男がいる事実をあっさりと認めそうな気がした。礼子自身の口からそれを聞かされるのは、今夜に限ってなぜか耐えがたいことのように志良は感じた。
「君が外でひとりきりになることがあるというのは意外だった」
「どういう意味」
「つまり、君は一歩家の外に出たら、いつも大勢の友達に囲まれて陽気に騒ぐのが好きだと思った」
礼子はふとため息のような、鼻で笑うようなかすかな声をもらした。先刻少しほぐれた顔色がたちまち曇って、不機嫌になってしまうのがわかった。
「私は本質的にひとりでいるのが性に合っている人間よ」
「そうは見えない。君はいつもパーティーが好きで友達が好きで――」
「そういうふうに見せるために私がどんなに苦労していると思う?」礼子はふいに声をあらげて志良の言葉をさえぎった。「少しでも気分よく生きるために私がどんな努力をしていると思う?」
最後は食ってかかるような強い調子になった。志良は彼女がすでに酔ったのだと思った。食前酒を飲みほして料理を待つあいだにも、礼子は志良を上回るペースでしき
りにワイングラスを口に運んでいた。
「・・・君がそんな気持ちでいるとは知らなかったんだ。悪かった。あやまるよ」
酔いの勢いを差し引いても礼子の剣幕は志良を充分におどろかせていた。
「あやまることなんかないわ」
礼子は食べかけのパスタにフォークを差し立てて、挑発するように上目づかいに夫を見た。あるかなきかの薄い皮肉な笑いが顔に浮かんでいる。
「本当のことを教えてあげましょうか」
「・・・」
「ほんとは努力も苦労もなにもいらない。一つだけ大きな助けになってくれるものがあるの。それがなんだか知りたい?」
「・・・」
礼子は熱に浮かされたような目つきで夫を見た。志良はそのとき妻が酔っているのではないらしいことに気づいた。礼子の瞳は酔眼と呼ぶにふさわしくもうろうとしていながら、たとえばその曇りの奥にめまぐるしく点滅する光かなにかが隠されているような、居ごこちの悪いせわしないゆらめきを宿していた。
志良は妻のそんな目つきを普段でもしばしば見てきた。彼女の気分が明から暗へ、あるいはその逆へと変化する際に礼子はそんな目つきをするのである。それは礼子自身にも制御できない体質のようなものだと志良は理解していたから、ふだんはほとんど気に留めることはなかった。だがそこでは、酔いの勢いということだけではないなにかが妻の言動の裏にあると気づいて、志良は身構えるようにして彼女の次の言葉を待った。
礼子は熱に浮かされたようなよるべない視線で夫を見すえていた。やがて、あきらめた、と言わんばかりにわざとらしい大きなため息をついた。
「今さら言っても仕方がないわね。あなたは7年間も私と一緒に暮らしていて、これっぽっちもそのことには気づいてくれない人だもの」
礼子の言わんとしているのは男のことだ、と志良はそのとき確信に近い思いを抱いた。その男が妻の大きな生きる支えになっている……。志良は狼狽した。ふいに強い嫉妬心が湧き起こった。妻に男がいることは予測できた。しかし、彼女がそこまで男にのめりこんでいるとは志良は思いもよらなかった。礼子の生きる支えになっている男とはいったい誰なのか……。志良は大急ぎで考えを巡らせた。
演出家のジェームズ・ワイズ、プロモーターのダニエル・シュテーゲル、中国系アメリカ人俳優のロバート・チャン、もうひとりの俳優ロッド・マクマホン、脚本家のマイケル・コーエン、プロデューサーのアンドリュー・レッドスパン……。彼らは礼子のパーティーによく顔を出し、その度にいつも妻と親しげに談笑していた。彼らのうちのひとりが礼子の男だとしても不思議ではない。いや……と志良は思った。男はひとりとは限らない。彼らのうちのふたり、あるいは全員が妻と関係を持っていることも考えられる。だとすると妻の相手は彼らだけでは済まないだろう。たとえばスチュアート・ミラー、ガイ・ロペス、ペペ・アントニオ、フィリップ・サーベイ、ディック・カーペンター……彼らもみんな礼子の気に入りのパーティーの常連たちだ。礼子は連中の一人ひとりとも関係している可能性がある―。
一度思いつくと志良の想像はとめどもなくふくれ上がった。彼はふいに湧きおこった嫉妬に突き動かされて妄想をたくましくし、やがてあることに思い至った。つまり、礼子はたとえこの先エイズウイルスに感染していることが判明しても、志良が先に彼のHIV感染を告白しない限り、彼女自身の感染相手をはっきりと知ることはできないのではないか、と彼は思いついたのである。 礼子が夫以外の複数の男たちとも肉体関係を持っているならば、それは十分にあり得ることだった。むしろその方が自然だった。
志良は一転して、妻の男関係を知りたい、という強い衝動に駆られた。
「礼子、少し立ち入ったことを訊いてもいいかい」
メインコースの料理を食べ終えて、デザートを待つ合い間をとらえて志良は言った。
「そういうのは好きじゃないわ」礼子は返してまたぐいとグラスのワインを飲みほした。
「でも、どうしてもというなら質問によっては答えてもいい」
「ありがとう。君はいつか、ロンドンではパーティーざんまいの暮らしをしていたと話したことがあるけど、どんなパーティーだった?」
「いろいろよ。大きなパーティーもあれば、4、5人が集まってバカ騒ぎをすることもあった。毎日がパーティーみたいなものだったわ」
「セックスはずいぶんした?」
礼子の顔にはっきりそれとわかるとまどいの色が浮かび、それはたちまち怒りのそれに変わった。
「いったいなにが言いたいの」
夫をにらみつけていた礼子は、ワインのボトルをつかんでどくどくと自分のグラスに注ぎ入れた。ボトルを握る手が小きざみにふるえている。聞き捨てにできない、と身構えるのが手に取るようにわかった。
「パーティーの流れで男と女が気軽に行きずりの関係を持つ、というのはニューヨークではよくある話じゃないか。パーティーのほとんどはそのためにあるといってもいいくらいのものだ。ロンドンでもそれは同じかな、とふと思ったんだ」
礼子は再びグラスを口に運んでワインを飲みほした。飲みながらも怒気を込めた視線を夫に投げつづけている。
「私が・・・好きではないことはあなたがよく知っているはずよ」
礼子の言う通りだった。
めずらしく夫婦がそろって家にいる夜や、逆に夫婦が同伴で夕食会やパーティーに出席して連れだって帰宅するような晩に、志良は思いだしたように妻を抱いた。礼子はセックスには淡白な女だった。いや、淡白を通り越して、不感症と形容してもいい奇妙な性癖が彼女にはあった。
礼子はそのとき志良の愛撫にこたえてごく自然に高まるように見えながら、彼が中に押し入る瞬間に必ず凍りついた。まるでおぞ気をふるう、という感じのはっきりとした拒絶反応だった。その戦慄はいつも尾を引いて残り 、彼女は志良が果てるまでついに熱気を回復できずいることが常だった。
「君は僕とのセックスだけが嫌いなのかと思った」
「あなたにはいつも悪いと思っている」
「責めているわけじゃないんだ」
志良は急いで妻の誤解を押し返した。長いあいだ見すごしてきたことに何かが隠されている、と今さらのようにはっきりと気づいた。
「ただ、どうして君がセックスを嫌うのか少し気になる」
「なぜ今ごろになってそんなことを訊くの。結婚してこの方、私のことなんかこれっぽっちも考えてくれなかったくせに!」
礼子は怒鳴り声を低い鋭いオブラートに包んで夫に投げつけた。
「すまなかったと思っている。本当だ」志良は刺すような目でにらみつける妻の視線をまともに受け留めた。「君のことを知りたいんだ。たのむから教えてくれ」
志良はそのとき、腹から妻のことをもっとよく知りたいと思った。知っておかなければならないと思った。たのむ、と彼はある限りの実を込めて再び言った。
長い沈黙があった。やがて志良の気持ちが通じたように礼子が重い口を開いた。
「男に……乱暴されたわ」
「何だって?」
「ロンドンに行ってすぐのことだった。黒と白の獣じみた5人の男に一晩中輪姦(まわ)された。それ以来、セックスも生きることもなにもかも怖くなった」
礼子はまるでそうすることで苦痛を忘れようとでもするように背筋をぐいと伸ばして言いきった。「輪姦(まわ)された」という言い方に彼女のありたけの怒りと怨みと悲しみが込められていた。しかし、声も表情も不思議に波立ってはいない。それがかえって彼女の中の地獄をきわ立たせて、志良は鉄拳でいきなり鼻ずらを殴られたような衝撃を受けた。
彼は息をのんで妻の顔を凝視していた。何か言葉をかけてやらなければ、と志良の中で激しく急き立てるものがあった。しかしどんな慰めの言葉も彼には思いつかなかった。
「だから・・・それ以降、君の相手はこのくだらない男ひとりになってしまったわけだ・・」
志良は深い自嘲をこめて言って、うなだれた。
「それ以後も・・・以前も、私の男はあなたひとり。乱暴されたとき私はバージンだった・・・」
静かに言い返す礼子の目には涙があふれていた。こらえようとして彼女は顔を少し上に向けた。しかし、こらえきれずに、それはいく筋も頬をつたって流れた。
志良はそこが人目につかない場所であったなら、席を立っていって妻を優しく、且つ今の心の力のありったけを込めて強く抱きしめ、いたわってやりたいと思った。同時に彼は自分がそれをしないのは、単に人目が気になるからではなく、彼にはその資格がないからできないのだ、ということにも気づいていた。苦い悔恨と自責の念が志良の中に広がった。
「僕は君と結婚してからも、外でたくさんの関係を持ちつづけてきた。そのことは知っているのかい」
「知りたくはなかったわ」
「いつから知っているんだ」
「いつから?いつからとも知れない遠い昔からよ。あなたは外に女のいる事実を少しも私から隠そうとはしなかった。そのことは評価してあげてもいい」
志良は男たちとの交渉の合い間に関係を持った女の存在を隠すどころか、、むしろ
積極的に妻にそのことを悟らせようとした。だがそれは、礼子が考えているように彼にいさぎよい動機があったからではなかった。志良は彼の男色趣味が妻に知られることをおそれて、関係を持った女にわざわざ自宅に電話を入れさせたり、礼子がそれを読むことを想定して、あからさまな文句を書きつらねた葉書を家に書き送らせたりしたのだった。
「どうしてそのことに腹を立てなかった?」
志良は礼子がどうやら彼の秘密には気づいていないらしいことに内心ほっとしながら訊いた。
「お互いが自由に生きる、という私たちの結婚の約束の中には、セックスのことも含まれると気づいたからよ。少なくともあなたの解釈ではね。もっともそれでなくても、たぶん私はそのことに腹を立てたりはしなかった」
「なぜ・・・」
「あなたが私とのセックスに満足しないことを知っているからよ。そしてその責任は私に―私の体にある。だから許すことにした。あなたが外にはけ口を持つのは当然だと私はいつも自分に言いきかせてきた・・・」
愛、立つ

翌日、志良のオフィスには朝からひっきりなしにアレックス・カーンからの電話が入った。志良はそのたびに応対に出る秘書に言いふくめて、来客や外出中をよそおって一度も彼の電話には出なかった。
アレックスへの怒りは前日にも増して志良の中でふくれ上がっていた。彼のせいで自分ばかりではなく礼子まで死病の犠牲になろうとしている。奴には絶対に会うまい、と志良はかたくなになった。
その日も仕事は一日中まったく手につかなかった。
死病への恐怖と、礼子をそれの罠に引きずり込んだかもしれないことへのやましさと同時に彼女への愛着と、ひんぱんに電話をかけてくるアレックスへの怒りが彼の中で目まぐるしく交錯して、志良は長い年月を一日に凝縮して生きているのでもあるかのような息苦しさを終日おぼえた。
仕事が終わると志良は、同僚たちへの挨拶さえ忘れてオフィスを飛び出し、まっすぐに帰宅した。
礼子は居間の奥の彼女の書斎にいた。
二つの空間をへだてる簡易壁のドアが開け放たれていて、書斎のソファにすわっている礼子の横顔が居間の入り口から見えた。志良は居間に入ろうとして、ふと足を止めて不思議そうに彼女を見やった。礼子はソファに体を深く沈みこませて、足を前に投げ出した姿勢で腰を下ろしているのだが、その様子がまるで軟体動物かなにかのようにぐにゃりとゆがんで見えたのである。
眠っているのか、といぶかしく思いながら志良は居間に足を踏み入れた。そのとた
んに礼子がのけぞるようにして笑い声を上げた。志良はそのときはじめて彼女が電話をしているのだと気づいた。上体を大きく反らして笑う妻の体がこちらに正面向かう形にずれて、左耳に押し当てている受話器が見えたのである。志良がそう気づくのとほぼ同時に、彼女も居間に入ってくる夫を認めた。礼子は笑いつづけながら、「よう」という具合いに片手を上げた。
志良は彼女のムードが、昨夜とは打って変わって上にバカがつくほど陽気になっていることを知った。同時に彼は困惑した。気分屋の妻の性格には慣れているつもりだったが、昨夜のでき事があったばかりなので、彼女のあまりにも屈託のない様子が奇妙な光景に見えたのである。それでいながら志良は、内心でほっとする思いにもまたとらわれていた。 陰うつな妻と対峙するよりも、底ぬけに明るい彼女を見る方が今の志良には有難かった。
礼子は受話器に向かってなにやら話しながらけらけらと笑いつづけている。
志良は広い居間の中央にある、昨夜礼子がスポットライトを浴びてすわっていたソファまで歩いてそこに腰を下ろした。すると彼の動きに合わせるように礼子の笑い声が一段と高くなった。いったいなにがそんなにおかしいのか、夫の動きを目で追いながら、笑いころげる、という感じで礼子はひたすらに笑うのである。電話の相手とよほど滑稽な話をしているらしい。
妻のあけっ広げな笑いにつられて志良も思わず頬をゆるめた。それを見て、礼子は送話口に何かひとこと言ってまた堰を切ったようにおかしがる。どうにも止まらない、というふうな際限のないけたたましい笑いである。
志良はさすがに不安になった。極楽トンボも顔負けのこの気楽さでは、彼女は昨夜のふたりの約束をすっかりわすれてしまっているのではないかと思った。夫婦は今夜は連れ立って外で食事をした後、ブロードウェイの劇場のショーを見に行くことになっているのである。
★
「いったいどういう風の吹き回しなの」
昨夜、礼子との長い息詰まるような会話の後で、志良が劇場でのショー見物を彼女
に提案したとき、礼子は不信感をあらわにして夫の顔を凝視した 。今度こそ志良の真意を聞かずにはおかない、と妻の双眸が無言の圧力をかけていた。
「僕は…これまでの生活をあらためる。君に隠れて勝手放題に生きてきたことをあやまる。この通りだ」志良は深々と頭を下げた。「君ともう一度はじめからやり直したい。7年間の僕らの結婚生活の付けを取り戻したいんだ。その手はじめとして明日はブロードウェイのショーを観に行きたい」
志良は全ての虚飾をかなぐり捨ててありのままの思いを礼子に告げた。
「本気で言っているの」
礼子は煙草の箱に手を伸ばして中から1本を取り出した。指先がかすかにふるえていた。
「本気だ」
志良は妻の目の中を見すえた。
一夜が明けて、今日になっても志良の気持ちは変わらなかった。変わらないどころか彼の心はますます強く礼子に向かって引きつけられ、昨夜の彼自身の言葉を自ら胸中でなぞっては確認し、確認する先からその思いをさらに強くするということをくり返して、妻のことばかりを考えて一日が過ぎた。
ようやく礼子の電話が終わった。しかし受話器を置いてからも彼女はまだくすくすと笑っている。志良はもうそれにはかまわずに訊いた。
「チケットは手に入れてくれたかい」
今夜のショーの入場券は礼子が手配することになっていた。ブロードウェイのことならチケットも含めてなんでも自分に任せてくれればいい、と昨夜礼子が請け合ったので志良も承知したのだが、今夜彼らが見に行くことになっている出し物は、半年先まで予約がいっぱいになっている超人気公演だった。 よほどのツテがない限り当日券の入手は困難なのである。
志良の心配は無用だった。礼子はひょいとソファーから立ちあがった。それからどんとひとつ胸をたたいて威張った。
「もちろん!この礼子サマが声をかければ、いつでもどこの劇場のチケットでもOKに決まっているじゃない!」
その夜ふたりはブロードウェイで評判の高いミュージカルの公演を見たあと、タクシーを拾ってソーホーまで下りた。夫婦はそこで自家製の生ビールを飲ませることで知られるイギリス風のパブに落ち着いた。
「ゆうべはありがとう」
礼子が樽から汲まれたばかりの生ビールのジョッキを高く掲げた。しんみりとした声音だった。
「なにが?」
志良はとぼけた。ふいに夢から覚めて現実に引きもどされたような気分がした。
「やり直そうと言ってくれたこと」
「…やり直せるかな」
「やり直したい」
礼子はきっぱりと言った。
「ありがとう。そう言ってくれると気が楽になる」
「あなただけの責任じゃないから気にしなくてもいい」
「・・・」
「7年前、あなたが結婚という形にしばられずにお互いに自由にやっていこうと言ったとき、私は本当に嬉しかった。願ってもないチャンスだと思った。そういう結婚を私も望んでいたわ」
「ありがとう―」
「そう言ってくれると気が楽になる?」礼子は志良の口調をまねて首を少しかしげて夫をみた。「自分だけがいい子にならないで。あなたはきのうからあやまってばかり。あなたがあやまってばかりいると、私もそうしなくちゃならなくなるわ。だからもういい」
「悪かった」
「ほら、またあやまった。もういい。あなたは十分にあやまった。過ぎたことはもういいの。それよりも私達のこれから先のことを話して」
礼子は両肘をテーブルについて手を組み合わせ、その上にあごを乗せて志良の目の前に顔を押し出した。甘えるように微笑さえ浮かべている。
志良は気が引けた。長い間の夫婦のわだかまりを忘れて、そんな風に無邪気にふる舞える礼子が不思議でもあり、またせつない気分もした。
「わかった。じゃ、過ぎたことはもう言わないし、あやまらない。しかし、一つだけ聞いてほしいことがある」
志良は決意した。この場でエイズの件を話してしまおうと思った。
「ちゃんと聞いているわ」
礼子は夫をうながすように軽くうなずいた。志良の次の言葉が耳に心地よいものであることを信じて疑わない。そんな様子だった。
「なぜ僕が心を入れかえる気になったのか、その理由を話しておきたい」
「聞きたくない!」
礼子はふいに体を起こして、突き放すように言った。
「過ぎたことはもう言わないと、たったいま約束したわ」
「大事なことなんだ。聞いてくれ礼子」
「聞きたくない」
礼子はくり返した。スイッチを切り換えるように彼女の気分が一変した。表情がこわばり、口調がとげとげしくなる。
「あなたの言おうとしているのが楽しい話じゃないことぐらい私にもわかる。 きのうからのあなたの態度を見ていればわかりすぎるくらいにわかる。いやな話はもうたくさん。大事なことはあなたがやり直そうと心に決めたことだわ。その理由なんかどうでもいいの。あなたがやり直そうと言ってくれたおかげで、私もこの先は今までとは違う生き方ができそうな気になっている。だから過ぎたことはもう忘れて。私も忘れる。私も―きっと立ち直る・・・」
礼子は遠くを見るような目つきになった。志良はその先は口をつぐむしかなかった。
破局

アレックス・カーンが志良のオフィスに押しかけてきたのはそれから2ヵ月ほど後のことだった。
志良はその時ちょうど大事な客とのミーティングを終えて、同席した橋本とともに彼らを送り出そうとしてオフィスの入り口に向かって歩いていた。ふいに前方で「待ってください!いったいあなたは誰ですか!」という声が上がってあたりが騒然とした。見ると、オフィスの入り口の脇のデスクカウンターにいるはずの受け付け嬢が、スタッフル
ームの中に駆け入ってこちらに向かって突進しようとする男を制止している。
「放せ!」「待ってください!」という怒声がまた飛び交った。と同時に、近くにいた男のスタッフふたりが、、受付嬢の加勢をしようと彼女のほうに駆け寄った。それを見て志良と並んで歩いていた橋本も思わず足を速める。
橋本につられて2、3歩前に走りかけた志良は、両脇からせまるふたりの男の手を振りほどこうともがいている侵入者が、アレックス・カーンだと気づいた。ぎょっとして志良はその場に立ちすくんだ。ほぼ同時に向こうも志良を認めた。と見えるよりも早く、彼の罵声がオフィス中にとどろいていた。
「ヒロ! 僕にエイズをうつしておいてなぜ逃げるんだ!僕は何もかも知っている。僕の感染源はお前だ! 」
「エイズ」の一語であたりの空気が凍りついた。アレックスを取り押さえようと駆け寄ったふたりの男がギクリとして動きを止めた。それにあわせるように橋本も受付嬢もまたその他のスタッフもいっせいに棒立ちになり、やがて申し合わせたように視線をゆっくりと志良に移した。志良はその場に釘づけになり、身じろぎひとつしないでアレックスを凝視していた。
「卑怯だよ。お前は卑怯なゲス野郎だ。お前が僕にエイズウイルスをうつしたんだ!ヘロイン中毒の女房から病気をもらって、それを僕にもうつしたんだ!」
行く手をふさぐ者がいなくなって自由になったアレックスが、まっすぐに志良に近づいて彼の胸倉をつかんで激しく揺さぶった。
「なんだって――」
志良は我に返った。胸倉にかかるアレックスの腕を思わずぐいとつかんだ。
「お前の女房は、ヘロイン中毒だ。注射針を通してエイズウイルスに感染して、お前がそれを僕にもうつした。だからお前は僕から逃げようとしたんだ。人殺しだよお前は。人殺しのゲス野郎だ」
アレックスは志良の手を振りほどいて、半狂乱になって彼に殴りかかった。やせ衰えた体のどこにそんな力があるのか、と見る者がおどろくほどの勢いだった。
「待て、アレックス。待ってくれ。電話に出なかったのはあやまる。仕事が忙しかったんだ。本当だ。君から逃げたわけじゃない」
志良はアレックスに殴られながらけんめいに弁解した。
「今さらなんだ。お前とお前の女房から病気をうつされたことははっきりしているんだ。お前もお前の女房も人殺しのブタ野郎だ!」
「落ち着いてくれアレックス。言っていることが良くわからないんだ。たのむからもっとちゃんと話してくれ。いったいどういうことなんだ」
「しらばっくれるな。お前は人殺しだ。僕にエイズをうつしておいて逃げようとしたんだ」
アレックスはありったけの憎しみを込めて志良を殴りつづけた。志良は殴られながら必死に彼をなだめようとする。しかし、アレックスは聞き入れない。なおも志良を罵倒し、わめき散らし、暴れまくった。やがて彼は、やせ衰えた体に残っていた力を全て使い果たしたらしく、ずるずると泣き崩れた。
泣きながら苦しげに肩で息をするアレックスを抱き支えて、志良は自分の個室に入った。泣きじゃくるアレックスをなだめすかして、彼はそこであらためて彼の話を聞くことができた。
★
礼子はコカインを常用していた。それはブロードウェイの演劇仲間のあいだではよく知られていることだという。コカインはいつでも気分を盛り上げてハッピーにしてくれるが、すぐには中毒にはならないと言われる。そのためかどうか、コカインをひそかに愛用している演劇仲間はたくさんいる。礼子もそのうちのひとりにすぎなかった。
「いつから彼女は麻薬をやっているんだ」
志良はアレックスにつかみかからんばかりにして身を乗りだした。
「僕が知ったのは3年前のパーティーに顔を出した頃だ。でも彼女はその前からやっていた。それは間違いない。みんなが知っていることだ」
それなら始まりはおそらく礼子がロンドンで男に乱暴されたあたりのことだろうと志良は想像した。苦しい体験を忘れようとして礼子は麻薬に走り、志良と出会った頃にはすでにそれにおぼれていたのかもしれない。明から暗、動から静へと激しくゆれる礼子の不安定な情緒は、麻薬によってもたらされていたと考えれば、見合いの日いらい続いている妻の奇妙な言動がたちまち腑に落ちた。
ところが礼子はコカインでは飽き足らなくなってヘロインにも手を出していた。そのことはアレックスもつい最近まで知らなかった。
アレックスは彼の長い風邪がエイズの徴候ではないかと気づいた直後から、、ホモセクシュアルの仲間を通じて感染源を突きとめようとひそかに動いてきた。彼がニューヨークで暮らした5年の間にコンドームを使わずに交渉を持った相手は志良を含めてたった4人だけである。関係した男は数が知れないくらいに多いが、アレックスはアレックスなりにエイズを恐れて、感染予防には十分に気を配ってきたのだ。従って彼の感染源は当面はその4人にしぼられるが、志良は関係がないと彼は考えた。
アレックスにとっては志良はもっとも信頼のおける愛人だった。彼の身を案じてエイズの感染に気をつけろと言いつづけ、風邪が長引くのを見ると血液検査を受けたほうがいいとまっ先にうながした。そんな男が自分の病気の感染源であるはずがなかった。アレックスは志良を除く3人の男の周囲をひそかに探りはじめた。
ニューヨークの同性愛社会の住人達は横に密接につながっている。情報は次々と集まってきた。3人のうちのふたりは、エイズ検査を何度も受けていて、そのたびに潔白と証明されていることがわかった。残るひとりはニューヨークを出てカリフォルニアに移り住んでいる。そのためにエイズ感染の有無をはっきりと確かめることができない。が、少なくともニューヨークに住んでいた頃には、その男にもエイズ感染の徴候はなかった。しかし、その後も無事でいることが確認されなければ100パーセント安心とは言えなかった。エイズは潜伏期間の長い病気だからである。
アレックスは仲間を介して引きつづき彼についての情報を集めていた。そんなおりに、礼子がコカインに加えてヘロインも使うらしい、という噂がアレックスの耳に入った。彼女があるパーティーで、数人のヘロイン中毒者と注射針を使いまわして麻薬を打っている現場を見た者がいる、というのである。麻薬患者と注射針を使い回せば、エイズ感染の可能性が飛躍的に高くなる。驚愕したアレックスは、礼子の親友で彼の友人でもある舞台俳優のショーン・ベントリーに会って直接に事の真偽をただした。
ショーンははじめ礼子をかばってかたくなにその噂を否定した。アレックスは彼の言葉をいったんは信じた。
ところが、アレックスのHIV血液検査の結果がポジティブ(陽性)と判明したとたんに、彼に対する志良の態度が一変した。態度が冷たくなったばかりではなく、アレックスに会うことも拒み電話にさえ出なくなった。強い不信感にとらわれたアレックスは、もう一度ショーン・ベントリーを訪ねて本当のことを教えてくれとせまった。彼はそこでもやはり礼子をかばって口を割らなかった。しかし、アレックスが自分と志良の関係を洗いざらい話した上で、エイズの宣告を受けている、と告白するとショーン・ベントリーはついに礼子がヘロインの常習者でもあることをはっきりと認めた。
それが今日、アレックスが志良のオフィスに押しかける直前のでき事だったのである。
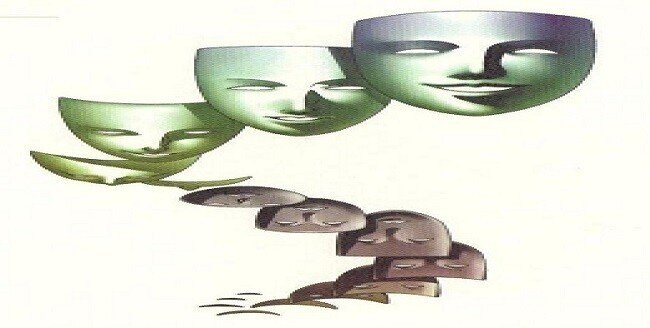
志良の目の前がぼうとかすんだ。
――あなたは7年間も私といっしょに暮らしていて、少しもそのことには気づかない人だもの……。
――少しでも気分良く生きるために私がどんな努力をしていると思う?ほんとは努力も苦労もなんにもいらない。一つだけ私の助けになってくれるものがある。たった一つだけ私の大きな助けになってくれるものが……。
――あなたがやり直そうと言ってくれたおかげで、私もこの先は今までとはちがう生き方ができそうな気がする。だから過ぎたことはもう忘れて。私も忘れる。私も――きっと立ち直る……。
クイーンズのアパートに向かって猛然と車を走らせる志良の頭の中に、礼子の言葉がくり返しよみがえって、エコーを伴ってぐるぐると回りつづけていた。
(俺は礼子の麻薬中毒に7年間も気づかずにいた……そんなばかな…)
志良は頭の中に浮かぶ妻の言葉にさからって、何度も自分に言い聞かせようとした。その先から彼の脳裏には、礼子が夏でも長袖のシャツしか着なかった事実や、セックスの際には必ず部屋を真っ暗にして、裸身を夫の目の前にさらさないようにしていた様子などが鮮明によみがえった。それらの行動は腕の注射針の跡を隠すための妻の懸命の努力だったと考えれば、彼女をヘロインの常習者だと断定したアレックスの話が、収まるべき場所にすとんと収まって見えてくる。
それはさらに、見合いの日の礼子の呆(ぼ)けたあかるい言動や、その翌々日の一転して暗い沈みこんだ顔や、イタリアンレストランでの泣き笑いの表情や、軟体動物のように正体のなかった居間での姿態や無意味な高笑い…といった落差の激しい妻の姿と重なって志良の頭の中に渦巻き、騒ぎ、轟いた。妻の奇怪な行動のすべてが麻薬の影響によるものだった、と志良ははっきりと悟っていた。衝撃が波紋となって頭の中でさらに広がり、志良を錯乱状態に似た異様な気分におとしいれていった。
間もなく、車を運転している、という感覚が志良からぷつりと消えた。対向車が激しく警笛を鳴らしては猛スピードで後方に飛びつづけた。
曲折

ロンドン在住のHIV感染患者が、幹細胞移植治療によって病気の症状がほぼ消失し「寛解状態」になった、というネットニュースを読みおえたあと、志良弘樹はパソコンの画面を開けたまま椅子にすわり、走馬灯のようにあらわれては流れ去る記憶を追いつづけていた。だがいつの間にか、アルツハイマー型認知症の影響で夢うつつの境地に入り込んでいたらしい。パソコンの節電モードが作動して画面が暗転していた。
志良はそのことに気づいて、ほとんど無意識のままキーボードを操作してパソコンの画面を再起動させた。エイズ根治の可能性さえ示す大きなニュースの見出しが、再びパソコンの画面に浮かび上がった。
パソコン画面の向こうには、ベランダに通じる広いガラス戸越しにフロリダ州マイアミの海が広がり、そのさらに向こうにはビスケーン湾を隔ててマイアミ・ビーチのビル群が展望できた。
ことしで71歳になる志良は、3年前にアルツハイマー型認知症と診断されたのを機に、HIV感染者や認知症患者を含むほぼすべての高齢者を一括して受け入れる、マイアミのこの介護施設に入居した。志良のHIV感染が発覚してから30年近い歳月が流れている。
★ ★
アレックス・カーンは、エイズ発症の確認から半年後に故郷の両親に引き取られて終末医療施設に収容された。高校教師だった彼の父と母は、かつてのジョン・ヒューズの一族とは違って、死の床に就いた息子を見捨てることはなかったのである。アレックスは家族に見守られて施設で死んだ。
まるでアレックスの死に呼応するように礼子がエイズを発症した。麻薬乱用からくる体調不良で彼女が病院に収容されたとき、血液検査が行われて彼女のHIV感染が確認された。つまり礼子の症例は、エイズの発症によってウイルス感染が追認された、アレックスのケースと結果的に同じだった。だが彼女の病はそれだけにとどまらなかった。礼子の症状は麻薬のオーバードーズとエイズとが絡んだ合併症だった。そのために病態はきわめて悪く、礼子は入院後は機が墜落するように急速に体調を崩し衰弱していった。
志良は妻の介護に全身全霊をかけて臨んだ。だが、彼女が死ぬまでついに自らのHIV感染の事実を明かすことはなかった。志良の感染源はアレックスなのか礼子なのかはっきりしなかった。また、はっきりさせる手だてもなかった。志良はアレックスからウイルスを受け取ったのかもしれないし、妻が媒介者だったのかもしれない。一方で礼子は、使い回しの注射器から感染したのではなく、アレックスからウイルスを受け取った志良を介して、それを体内に呼び込んだのかもしれなかった。真相は誰にもわからないのである。
確実なのはウイルス感染が明らかになった以上、おそかれ早かれ志良自身もエイズを発症して死ぬということだった。当時はワクチンはおろか、ウイルス感染を防いだりエイズそのものを抑える薬も治療法もほとんど存在しなかった。そのためにエイズ発症の場合はもちろん、その前段階のHIV感染でさえ、死の宣告と同じとみなされることが多かった。
妻への愛に目覚めた志良は、感染源を詮索することで彼女が糾弾される結果にもなりかねない事態を恐れた。エイズを発症した礼子は確実に死に、やがて彼自身もまた病気に屈するのだ。いまさら感染源を特定しても何の益もない、と志良は当時考えた。そうした思考を経て彼は妻との間に余計な波風を立てるべきではない、と結論づけた。 その一方で志良は、実を尽くしてひたむきに礼子を看病した。不眠不休に近い妻への奉仕の日々は、志良自身のHIV感染の事実や、いつ発症してもおかしくない死病への恐怖をさえ、しばしば忘れさせるほどだった。
礼子の日本の家族は、エイズにかかって死の床についた娘の看病と後始末の全てを、志良ひとりに押しつけるような形の対応をした。それはボストンの弁護士一家が、エイズにかかったジョン・ヒューズを見捨てたやり方に似ていた。エイズという病への恐怖心がそこでも人々を支配していた。
それでも礼子の両親は、一度はニューヨークを訪ねて入院中の娘を見舞った。その際に礼子の父親は、入院費用の名目でかなりの現金を志良に渡した。玲子の家族はその後は彼らが高齢であるという理由と、日本と米国が遠距離であることを言い訳に、もう礼子を訪ねることはなかった。その罪悪感もあったのだろう、礼子の父親は二度にわたって多額の金を志良の口座に振り込んだ。一度はまた入院見舞いとして、そして最後は葬儀費用の名目で。
志良は礼子の父親が差し出す金を拒まなかった。礼子の入院費用は高額だった。義父が彼に贈った多額の金は、礼子の療養費と当座の生活資金、さらにいつ志良を襲うかもしれないエイズ発症の危機に備える原資、という意味合いからも彼には有難かった。
礼子の死後、志良はHIV感染者としてエイズ発症の恐怖と闘いながら生き始めた。彼は恐怖と絶望に押しつぶされて自殺を考えたことも何度かあった。だが潜伏期間の半年が過ぎ、10年がやって来て、20年が過ぎても志良はエイズを発症しなかった。
その間にはエイズウイルスの増殖を抑える薬や治療法も発達した。特に抗レトロウイルス薬の開発が進み志良もその恩恵を受けるようになった。エイズウイルスは志良の体中深くに潜んでいつでも彼を殺そうとしているが、治療薬によって増殖を抑えられて身動きができないでいる、というふうになった。
医学界のエイズとの闘いが進展し抗ウイルス薬や治療法が編み出されていくに従って、エイズへの社会の理解が深まりそれに対するむやみな恐怖心や偏見も薄れていった。時の経過とともに多くの事案が志良を勇気付け、生きる動機を形作った。志良は仕事に打ち込みつつ同性愛者の仲間やHIV感染者たちとの交流、協力、助け合いなどにも積極的にかかわるようになり、不幸にもエイズを発症した仲間の介護や援助にも奔走した。
そうやってウイルスに感染したまま長い時間が過ぎた。その期間の薬の進歩は目ざましく、彼は2005、6年頃からはぼ健康な人と変わらない普通の生活を送るようになった。そしてHIV感染にまつわる彼の健康状態は、エイズ発症の危険を懸念するよりも、抗HIV薬の副作用そのものと、ウイルスに長く感染している事実が引き起こす慢性的な合併症のほうがむしろ深刻な問題、というふうにさえなった。
3年前アルツハイマー病と診断されたとき、志良は生への執着が薄らぎ生きるべきか否かと再び激しく葛藤した。結局、生きつづけようと自らを鼓舞した彼は、病人を含むあらゆる境遇の高齢者を受け入れるフロリダ州マイアミの介護ホームに入ることにした。施設入居に必要な多額の費用は、高収入の仕事で得た元手を投資して増やした金や、日本の親の遺産を売却して得た元本、また礼子の父親からの見舞金の残りなどでなんとかまかなうことができた。
エピローグ
「よかったですね」
ふいに志良の耳元であかるい声がした。志良はおどろいて声の方に振りむいた。看護師のジュリア・レンドルが彼の卓上のコンピュターの画面に見入っていた。そこには、ロンドン在住のHIV感染患者が「寛解状態」になった、というニュースがまだ表示されている。
「これってすごいニュースですよね。エイズはもう怖い病気ではなくなりますね」
看護師のジュリアは、認知症の志良がHIV感染者でもあることよく知っていて声をかけたのである。
「ああ。でもそれはフェイクニュースだ。十年以上も前の出来事を蒸し返しているだけさ」
志良は看護師を見上げて微笑し、おだやかな声で言った。
HIV感染者が寛解状態に回復したのは、実は今回が初めてではなかった。2008年にも幹細胞治療によって1人のHIV患者が、ウイルスの検知できない寛解状態になった。「ベルリン患者」とも呼ばれたティモシー・レイ・ブラウンのケースである。彼はHIVに「勝った」世界初のクランケ(患者)として大々的に伝えられた。
志良はふいにそのことを思い出したのだが、そのときちょうど認知症によるゆるい夢幻世界と現実の間を行き来していた彼の脳は、状況の正確な把握ができず、過去の事例と史上2例目の今回のケースとを混同したのだった。
いずれにしてもその歴史的なニュースは、彼にとってはもはやどうでもいいことだった。 エイズという病にほんろうされ続けた志良の後半生は、アルツハイマー型認知症という別の病気によって癒され消滅さえして、彼の心は深い平穏の中にたゆたっていた。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
