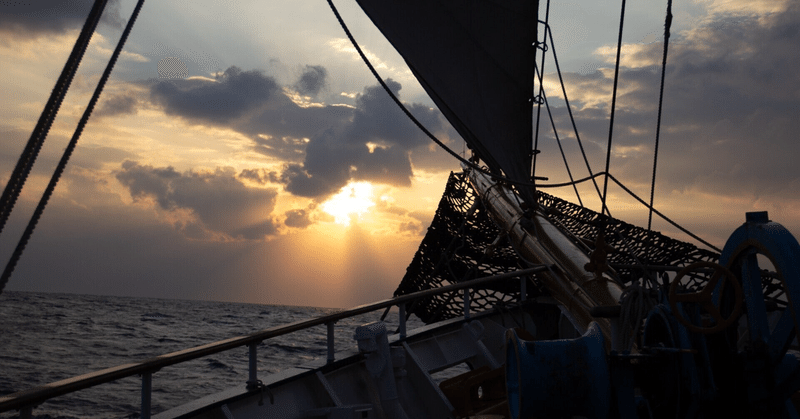
「トライアングル」その7
連載ファンタジー小説
わたしはだれ?
第十九章 長フォラード
翌朝フレイが目を覚ますと、木の扉は開かれており、洞窟の中に朝日が射し込んでいた。
ばぁばたちは、炉のまわりでまだ寝ている。
フレイは肩にかかっていたばぁばの手をそっとはずし、静かに立ち上がって洞窟の入り口までいってみた。崖の下に広がるフラリアの街にも朝の光があたり始めている。けれどもここは死んでしまった街だ。フレイは思わず身震いをした。
「寒いのか?」
ふりむくとアルドが立っていた。
「おまえの生まれた家はあそこだ」
アルドが、鐘楼の隣に建つ小さな家を指さした。
「私の父さんと母さんも・・・海に入っていったの?」
アルドはうなずいた。
「どうして・・・?なにがそんなに憎いの?なにがそんなに恐いの?闇に心をとらわれてしまうなんて、どうして人はそんなに弱いの?ここはとっても美しい国だったのでしょ?」
「たった一人の人間が自滅への道を歩ませることができるのなら、またたった一人の人間がきっかけとなってこれを正すことができる。
長フォラードが、おれらにいったことばだ」
「そのきっかけの手がかりはあるのかい?」
いつのまにおきてきたのか、ばぁばがきいた。
「フレイだ」
「フレイが?そういえば、きのうもこの子のことを希望とかといってたね」
「長フォラードは混乱の中で、ヘブンスのおれらには邪悪な風に操られることなく生きのびることができるだろう、もし最悪のことになったとしても決して希望を捨てるなといったんだ。そしてハメドがいったように、また新しい風の声をきく者が現れるともな」
「それがこの子ということかい?」
うなずきながらアルドはフレイの耳に手をかけた。
そしてその手で髪をかきあげ、両耳をだすと静かに語り始めた。
「おれたちは海に向かって歩く母親の腕からおまえを奪い、あの小さな船に乗せた。長フォラードは船が飛び立つとき、ブルーフェアリーの種をおまえと共に船に入れ、祝福の詞を唱えたんだ。
『聴け、大地が無に帰しても風は歌う 偽りの声を耳にすることなく隠された歌を聴け 年月は再び聞く耳を与える 闇は光 光は闇 光の声を開けろ』
フレイ、風の歌をきいてくれ」
アルドは、フレイをかたく抱きしめた。
「あーあ、これじゃあダフネの本当の名前がわかっても、全て終わりってわけにはいきそうにないな」
ばぁばのうしろに、寝起きでぼさぼさの髪をしたカンタンが腕を組んで立っていた。
「で、おまえたちには、あの亡霊みたいな風に勝つ方法はあるんだろうな?」
「いろいろ試してみた」
「けど、うまくいかないんだな?」
「そうだ。だからこそ、おれたちにはフレイの風の声をきく耳が必要なんだ」
「私はなにをすればいいの?」
アルドが答えようとしたが、ばぁばが止めた。
「みんな起きたみたいだから、その話は朝食をすませてからきかせておくれ」
奥では炉に火がおこされ、サラダッテとハメドが昨夜食べたのと同じかたいパンや干し肉を皿に盛っていた。
「おいおい、またこれかよ。ここには、もうちょっと水気のあるやわらかいものはないのか?」
文句をいっているトンデンじいさんの横で、サラダッテがハメドきいた。
「ここでは何も育たないでしょ?あなたちは食べ物をどうやって手にいれてるの?」
「この街にだれもいなくなった時、おれたちはなにがあっても生き延びるって決めたんだ。水は峡谷の奥の湧水がいきていたから助かったし、食料は街中からをかき集めた。
穀物蔵に貯めてあった小麦を挽きでパンを焼き、肉や魚は保存がきくように干したり、塩漬けにしたんだ。
それも一年たち、二年たちするうちに食い尽くして、今残っているのはわずかな干し肉と小麦だけだ。これも底をつきかけている。フレイが来るのが、もう少しおそかったら、ここから出られないおれたちは飢え死にしてたかもしれないな」
「十二年・・・十二年間も私が来るのを待っていてくれたの?」
思いつめた顔でじっとこの話をきいていたフレイが、か細い声でいった。
「フレイ、君がここに来るにはその年月が必要だったんだよ。だから過ぎてしまった時間のことを嘆かないで。ぼくたちはね、逃がした赤ん坊が、新しい風の声をきく者としてまたもどってきてくれたことがとてもうれしいのだから」
シラードがフレイの頬にそっと手をそえた。
「新しい風の声はどうやったらきこえるの?」
フレイがきいた。
「そうそう、さっき中断した話の続きをきこうじゃじゃないか。あんたたちはいろいろ試したっていったけど、試すあてがなにかあったのかい?」
ばぁばが、アルドを見ている。
「長フォラードは最後の戦いとなる前夜、使いの者をとおしておれたちに手紙をよこした。ブレンド、あれを持ってきてくれ」
ブレンドが、洞窟の奥から出してきた小さな厚紙の筒をばぁばに渡した。
「開けてみてくれ」
「いいのかい?」
うなずくアルドを見て、ばぁばは筒の中から一枚の紙を取り出した。
「【鷲が翼を広げるとき 扉は開く
風を聴く者は 花の上に立ち耳をすませ
大なるトライアングルは 小なるトライアングルに光を与えよ
ブルーフェアリーの花開くとき真実の窓から光が入る
苦しみの中 喜びの声がかくされる
喜びがあれるとき 光は闇を吸い天に放つ】
これは詞だね」
「暗号文さ。これがおれらの手に渡る前に誰かに見られる危険が十分あったから、長フォラードは詞にしたんだ。
これだったらなにを意味してるのか全然わからないだろ?」
カンタンとトンデンじいさんが強くうなずいた。
「おれたちもこの詞の意味を考えていろいろ試してみたが、どれもうまくいかなかった。
だいたい長フォラードは、おれたちのことをだれだと思ってたんだ?
学者か?それとも詩人か?
おれたちは船大工だぞ。船大工にこんなのわかりっこないんだ」
吐きすてるようにアルドがいうと、ばぁばがにやりと笑った。
「さっきシラードが、フレイがここに来るには十二年の年月が必要だったんだっていっただろ?同じことばを私が返すよ」
「どういう意味なんだ?」
ブレンドがきいた。
「この詞を読みとるには、私らもフライといっしょに来る必要があったってことさ。つまり、あんたたちと私らが力を合わせれば暗号も解けるっていうことだよ」
「そうよ、だってサスーラは、そのジャンルの達人ですもの。それに私もね。私たちが手を組めば奇跡もおこるわよ」
奇跡・・・ミラクル・・・。
フレイが、あっと叫んだ。
「おいおい、びっくりさせるなよ。おまえ、なにかわかったのか?」
カンタンがいうと、フレイは首をふった。
「ちがうの、ミラクル、わたしったらミラクルのことすっかり忘れていた。あのこ、たったひとりで飛行船に残ってるわ。どうしよう?ばぁば」
「ミラクルってだれ?」
ブレンドがきいた。
「わたしとばぁばが飼っていたネコよ。一緒に飛行船に乗ってきたの」
「ぼくが連れてきてやるよ」
ブレンドはランダムに乗ってすぐに飛びたっていった。
「さて、あのこがもどってくるまで、もう一度この詞に目をとおそうかね」
ばぁばは、長フォラードが書いた詞を読み始めた。
第二十章 暗号
「このネコの尻尾を見てみろよ」
もどってくるなりブレンドは、シラードにミラクルを見せた。
「へえ、おもしろい。三角の模様がある」
フレイに抱かれたミラクルが、アルドの顔を見てニャーォと鳴いた。
「ふふふ、ミラクルったら、まるでアルドの知り合いみたいね」
「この鳴き方は、案外そうかもしれないよ。
さて、みんなそろったところで始めるとしようかね。まず、この詞を一文ずつに分けて考えてみよう。なにか書くものはないかい?」
ばぁばは、シラードが持ってきた紙に最初の一文を書いた。
「鷲が翼を広げるとき 扉はひらく、か。アルド、フラリアには鷲がいるのかい?」
「いや、いない。だからおれたちは、この鷲っていうのは生きた鷲ではなく、風聴塔に彫られた鷲のレリーフじゃないかと思ったんだ」
「風聴塔?」
「街の中心に建っている塔のことだ。長たちはこの塔にのぼって風の声をきいていたんだ」
「そこに鷲の彫り物があるのかい?」
「ああ、だがここの鷲はみんな翼を閉じていて、広げた奴なんて一つもなかった」
「絵とか敷物とかでもいいから、ほかに鷲の模様がある所はないの?」
サラダッテがきくと、ハメドは肩をすくめた。
「街中をしらみつくしに調べたが、鷲の模様があるのは風聴塔だけだった」
「翼を閉じてるねぇ・・・ちょっとそれを見たいけど、あの気味の悪い風はやってこないかい?」
「あいつはいつも陽が沈むころから夜にかけて来るから、たぶん大丈夫だろう」
そこでミラクルだけを残して、全員がランダムに乗って街に行くことにした。
風聴塔は三角形をした石造りの建物で、街の家々を見下ろすように高く造られていた。
戸のない入り口から中に入ると、そこは二階に通じる階段があるだけのがらんとした部屋で、東西南北の四箇所に窓があり、壁には一面、翼を閉じた鷲と植物のレリーフが彫ってあった。
ばぁばたちが階段をのぼって上に行くと、二階も下の部屋とそっくり同じ造りだった。
「三階もここと同じかい?」
「そうだ。塔の天井に行く階段があるだけで、壁の模様も同じだ」
ばあばの問いにアルドが答えた。
「ふーん・・・」
ばあばは壁に彫られたレリーフを触ったり、叩いてみたりして一つ一つ丹念に調べてみたが、手がかりになるようなものはなにも出てこなかった。
「たしかに鷲は全部翼を閉じてるけど・・・サラダッテは何かわかったかい?」
ばぁばは、窓から身を乗りだしていたサラダッテに声をかけた。
「すごく手の込んだレリーフだけど・・・」
「鷲は翼を閉じてるよな」
サラダッテの続きをトンデンじいさんがしめくくった。
「やっぱりここじゃないのね」
がっかりしているフレイの肩を、カンタンがドンと叩いた。
「なにいってるんだ、まだ始まったばかりなんだぞ。一つだめだったからって、そんなにしょぼくれるなって」
このことばが、その場のふんいきを明るくした。
「そうだね、まだ始めたばかりだ。
アルドたちが他にも鷲がないか調べたっていったけど、もしかしたら見落としがあるかもしれないよ。もう一度調べてみないかい?」
「だったら街をいくつかに区切って、おれたちとばあさんたちがペアになって調べた方がいいな」
ばぁばたちは階段を降りたのに、サラダッテだけは二階に残って天上と床を何度も見ていた。
「サラダッテ、なにしてるんだい?みんな待ってるよ」
一階からばぁばが呼んだ。
「ああ、ごめんなさい。今行くわ」
サラダッテは階段をおりてきたものの、ここでもまた天井と床を交互に見ていた。
「おいサラダッテ、おまえさんは上向いたり下向いたりして、なに見てるんだ?」
「ねえトンデンじいさん、ここって塔の高さの わりには、一階も、二階も、三階もみんな天井が低いと思わない?」
「天井が低い?」
トンデンじいさんも、天井と床を何度も見てみた。
「ああ、たしかに低いけど、おれの推測からすると、これは床を厚くしてるからだな」
「そうね。床が厚いからその分天井が低くなるんだわ。でも・・・どうしてそんなに床を厚くしたのかしら?」
サラダッテは、その場でまた考え込んでしまった。
「おい、もういいかげんにしろって。ほかの連中が外で待ってるんだぞ」
トンデンじいさんがサラダッテを引きずるようにして外に出ると、ばぁばが砂の上に描いた地図を指さしていた。
「サラダッテ、トンデンじいさんも、これを見ておくれ。いいかい?この塔を中心に街を四つに分けて、一区画ずつしっかり調べることにしたよ。まず南東から始めるから、トンデンじいさんはブレンドの、サラダッテはシラードのランダムに乗っておくれ」
それからはペアを組んで、南東の位置に建っている建物や家をしっかり調べてみたけれども、やつぱり鷲の模様はどこにもなかった。
「もうすぐ日が暮れるから、今日は終わりだ」
アルドの合図で、一日目の作業は終わった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
