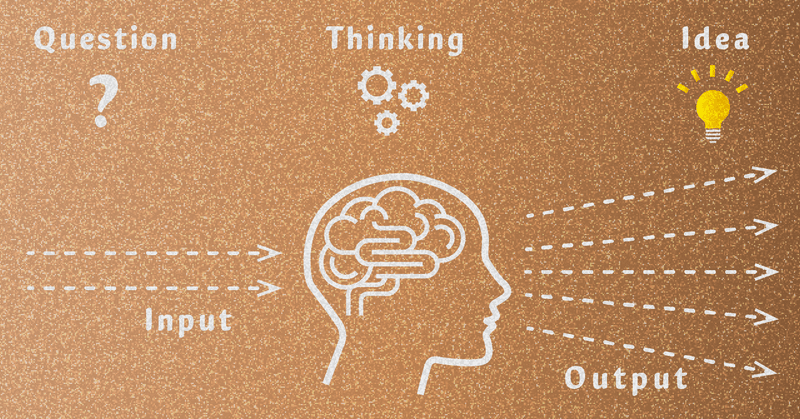
【研究ノート】写真とはなにか
写真についてあれこれと語るうえで、禅問答のように出てくるこの問題。「写真とはなにか」と問われるとき、その答えは「あなたにとって、『写真』とはなにを意味するのか」が求められている。
それは、たとえば自分を映す鏡であったり、もしくは社会を映す窓であったり。総じてその回答は、写真における意義や用途、その役割、想念や感情といった内容に関する回答が返ってくる。
しかし、これは世間一般的な「写真」という誰しもが思い描く媒体の形態を理解している、という前提条件をもって展開されている問いである。
デジタル化が主流となった現代において、写真表現は多様化してきた、と一般的は理解されている。では具体的には何が?と問うたとき、その答えには主に写真、とりわけカメラの機能的な部分が大半を占めている。
高感度、HDR、高解像度、etc。表現が拡張されたのではない。カメラとしての機能が向上したのだ。それによって獲得した写真が、それまでとは違う表現方法となった、というのは得てして撮影者主体ではなく、カメラという装置が主体であり、写真システムの向上によって、「結果的に」それまで撮影することが出来なかった状況や状態を「写真」という形態で表示することが可能となり得たに過ぎない。
また、「写真」とは主にカメラで撮影されることによって獲得する画像データではあるが、「フォトグラム」のようにカメラを使用せずとも暗室作業によって制作された、すなわち写真のプリントプロセスに則って制作されたものもまた、写真として認知されている。
これは、こうして制作されたものが「写真」であるという市民権が与えられ、固有名詞として世間一般的に認知されたことにほかならない。
その一方で、現代において写真と呼ばれてはいるが、写真とは思えない表現が増えている印象を受ける。これは、フォトグラムのように認知されている固有名詞が定まってはおらず、こうした写真的な表現は総じて「写真」と呼ばれていたり、呼んでいたりするためであると私は考えている。
「写真」という多義性のある言葉によってもたらされる、一見すると多様な表現方法。しかし、これは本質的な議論を蔑ろにしてはいないだろうか。
写真とはなにか、これすなわち、写真とはどのようなものを指すのか。そして、それは何と呼ぶに相応しいのか。
写真を理解するためには、いま一度「写真」についてそのあるべき姿を明らかにすることが、デジタル化が主流となった現代において必要とされていると私は感じている。
その写真と呼んできた表現方法の解釈の仕方を拡張しようと写真家やアーティストたちは躍起になって挑み続けてきたのだ。しかし、写真はいつの時代も写真であった。
写真とはなにか、なのではなく、なにが写真なのか。すなわち、なにをもって「写真」と呼ばれるに相応しいのであろうか。写真は写真でなくなり、新たな写真のフェーズへと移行している現代の「写真」は、その行き先を見失ったかのように混沌とした状況に陥っている。それは、写真そのものに意義や概念の拡張を求めようとするがあまり、写真が写真であることの本質的な議論を蔑ろにされてきたことによってもたらされた結果ではなかろうか。
とりわけ写真の生成プロセスは科学技術の発展とともにブラックボックス化され、実際にどのような処理が行われているのか、われわれはその全体像を理解せずとも「写真」と呼ばれる最終成果物を獲得できてしまう。
写真を生成するのはカメラに代表されるアルゴリズムが主体であり、決して人間が主体となって生成してはいない。人間はただそのアルゴリズムを操作しているだけにすぎないのだ。
であるとするならば、そのアルゴリズムを構築できさえすれば、「写真」が生成できるのではなかろうか。私は制作を通じて行っているのはそのアルゴリズムの構築そのものであり、結果として写真となり得ることの証明を実践している。
たとえば私が制作したこの雲のシリーズ。
カメラを用いて撮影したのではなく、アルゴリズムによって作り出されたイメージは、写真としての形態をなしている。果たしてこれは「写真」と呼ばれるに相応しいのであろうか。一般的に「写真」と位置付けられている概念からすれば、この作品は写真であるとはみなされないのかもしれない。
しかし、私はこの作品は「写真」の本質的な概念に即したアルゴリズムに準拠して制作を行っていることから、本作品は紛れもなく「写真」なのである。
それでは、写真であるための必要条件とは何であろうか。制作を通じて本質的な写真のメカニズムを明らかにしていきたい。
よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。
