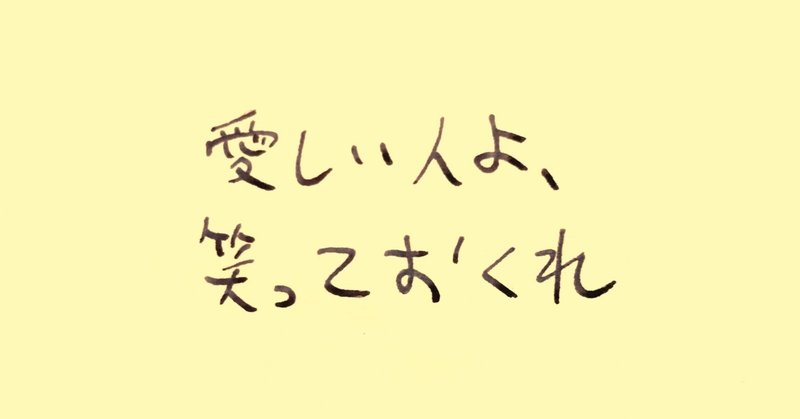
ショートストーリー劇場〜木曜日の恋人〜㊷ 『愛しい人よ、笑っておくれ』
恐ろしい疫病が流行してしまった。
そのウイルスに罹患してしまうと、高熱が出て、激しい倦怠感に襲われ、咳が止まらず肺に炎症をおこしてしまう恐れがあった。重症化しなくとも、場合によっては嗅覚が失われ、それにより味覚が無くなるという症状もあった。でもそれは大分マシな方だった。命を落とすことの次に恐ろしいのは、いや、ある意味じゃそれより恐ろしいことは、その疫病にかかってしまった人から「笑い」が失われてしまうことであった。この疫病に感染した者は皆笑えなくなってしまうのだった。口角を上げることが出来ず、はははと声を発することも出来なくなってしまうのだった。嗅覚や味覚に関しては、時が経てば自然と元に戻っていったが、「笑い」に関して言えば、まだ治癒した人は世界でもほとんどいない。
ここ日本ではいま現在、笑えない人は人口の三分の一に相当する。
電車でも、繁華街でも、真顔で会話をしている人たちが増えたようだ。居酒屋で酒に酔った人々でさえ、ゲラゲラ笑うこともなく、皆真面目な顔をして話している姿を最近はよく見かける。
僕の恋人も、そのように「笑い」を失った一人だった。
「可笑しいでしょ? わたし、エミって名前なのに、クスリとも出来なくなっちゃった」と彼女は真顔で言ってから片方の人差し指で口角を持ち上げた。それは、このウイルスが蔓延して以降、笑いを失った人々が「いま私は笑っています」ということを示すために広まった、世界共通のサインだった。
「これって冗談で言ってるのよ」
「ああ、分かってるよ」と僕は笑ってみせた。
「ねえ、笑うってどういう感じ? わたしもう、忘れちゃったみたい」
僕は彼女の笑顔が好きだった。待ち合わせ場所で、僕を見つけた時に微笑みながら手を振る彼女の顔が好きだった。プレゼントをあげた時に、子供のように嬉しそうに「ありがとう」と笑う彼女の顔が好きだった。だからと言って、笑えなくなってしまった彼女のことが嫌いになったわけではない。真顔で僕に手を振る彼女を見ては、僕がまた、なんとか彼女の笑顔を取り戻してやりたい、と思っているのだ。笑ってくれそうなことならなんだってやった。でも当然、最先端の化学技術を用いても治療出来ない症状を、僕個人がどうにかすることなど出来なかった。
僕は彼女を寄席に連れて行きもした。
「なんだい、蟹ってやつは横に歩くもんだけど、この蟹は縦に歩いてるじゃねえか、ってえと蟹が「すこ~し酔ってますから……」」
真顔で高座を見上げる彼女。噺家自身も例の病を患ったのだろう、滑稽な噺を表情を変えずに淡々と話していた。
寄席を出てすぐ彼女は涙を流した。涙はこんなに出るのに、どうして笑えないんだろう、そう言って彼女は泣いた。収入がまったくなく、月々借金が嵩んでいく気分だと言っていた。
それからしばらくして、ああ、なんということだろう、僕も笑いを失ってしまった。
高熱が出て、何日も咳が止まらず、喉が痛くて食事も、まともに食べられなかった。
二週間ばかり自宅で療養し、笑えないことを除き、症状が治まってから、彼女と再会した。
レストランで向かいあう僕らは、どちらも真顔だった。離婚直前の夫婦が最後に夕食を共にするみたいに、お互い深刻な表情で食事をした。
彼女は両手を使って目尻から口元にかけての皮膚を摘み上げ変な顔をしてみせた。僕の表情になんの変化もないことを見てとって彼女は言った。
「ようこそ」
「思っていたよりも、キツい世界だね、ここは」
「まあね。でもそのうち慣れてくるよ。良いのか悪いのか」
「慣れてくる、か……」
店内にはナット・キング・コールが歌う「スマイル」が流れていた。
笑おう、心が痛む時でも
笑っている限り、人生は悪くないと思えるものさ
これはチャールズ・チャップリンが自身の監督作品『モダン・タイムス』のために書いた曲だ。歌詞はあとから付けられたものだ。誰がつけたのか覚えていないが、たしかそんな内容の歌詞だったと思う。そういえばチャップリンはこんなことも言っていた。
「笑いのない一日は、無駄な一日だ」って。
そうかもしれない。いま僕は『モダン・タイムス』を見ても、少しも笑うことが出来ない。なんて味気ないものだろう。そんなものになんの価値があるのだろう。途端に僕は悲しく、悔しい気持ちになって、寄席の帰り道の彼女みたいに涙を流してしまった。そっと僕の左手に、彼女の右手が重ねられた。顔を上げて彼女を見た。僕は目を見張った。
たしかに僕は見た。あの美しい、僕の大好きな、満面の笑みがそこにあった。
「大丈夫だよ」と彼女は真顔で言った。
「いま僕はね、笑っているんだよ」と僕も真顔で言った。
「うん、分かってるよ」
僕はこの時ほど、彼女と心が通じ合えた時はないような気がした。左手に重ねられた彼女の手に僕はさらに自分の右手を重ねた。
「エミ、僕と結婚してくれないか」
彼女の目が見開いた。それから何度も頷きながら「うん」と答えた。
「一緒に笑いの絶えない家庭を作ろう」と僕は言って人差し指で口角を持ち上げた。
「これ、冗談でいってるんだよ」
「うん、知ってる」
僕たちはしばらく、両手の人差し指でぐいと両方の口角を持ち上げて、真顔で見つめ合った。
いずれ人類は、底知れぬ治癒力で、あるいは、どこかの偉い人が治療法を開発して、再び笑える日を迎えることだろう。街のいたる所に、笑顔と笑い声が戻ってくることだろう。その頃には、笑いのないこの時代が、笑い話になっているはずだ。僕たちはそう信じている。そして、その時に今日という日を、死ぬほど笑いながら、振り返ってやろうと思うのだ。
・曲 Nat King Cole / Smile
SKYWAVE FMで毎週木曜日23時より放送中の番組「Dream Night」内で不定期連載中の「木曜日の恋人」というコーナーで、パーソナリティの東別府夢さんが朗読してくれたおはなしです。
上記は8月17日放送回の朗読原稿です。
僕はいつも、善い物語を書きたい、と思っています。
最後には悪人が必ず成敗される勧善懲悪、という単純なことではありません。
なにをもってして善いと言えるのか、それを言葉で説明するのは難しいです。
たとえば今日みたいに暑い日、あなたは日陰に入り休んでいる。ひゅーっと汗を飛ばす風が吹く。「あー気持ちいいなあ」とあなたはつぶやく。
僕が思う善い物語とは、そんな風のような物語です。
朗読動画も公開中です。よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
