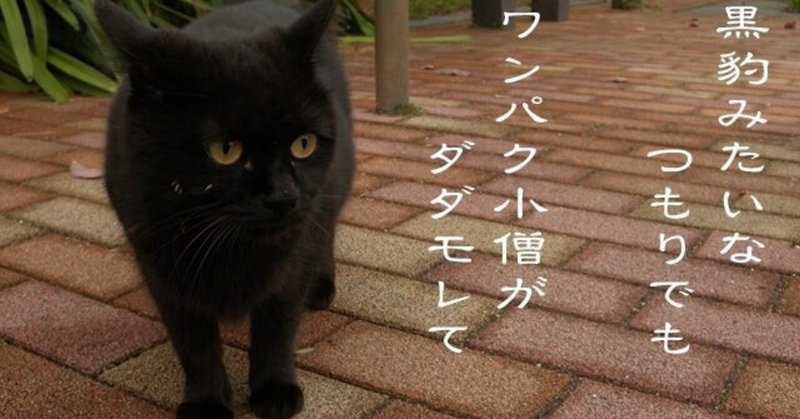
寛容であることの大切さについて2
ヴォルテールの『寛容論』を読み終えました。
寛容であることの意味、不寛容の招く残酷さを痛感します。
『寛容論』は、今もフランス人によく読まれているそうです。本書に関する前回の記事の内容はこちらです。
前回の記事から、寛容論執筆の契機となった「カラス事件」の概要を引用します。
南フランスの都市トゥルーズは、十六世紀来新教徒の勢力の盛んなところで、そのため旧教徒とのあいだに血なまぐさい抗争が繰り返されていた。(中略)
十七世紀からの打ち続く弾圧と迫害により最盛期には二万人を数えたといわれるトゥルーズの新教徒も、十八世紀中頃には市の全人口五万人のうちわずか二百人にまで減少してしまったという。(中公文庫版解説222頁)
そんな中、1762年に起きた「カラス事件」を知ったヴォルテールは、義憤を覚えます。それが契機となって執筆されたのが『寛容論』というわけです。
トゥルーズの新教徒で誠実な商人カラスは、実の息子を殺害したとして、一方的な裁判を経て残酷な処刑によって命を失いました。
ヴォルテールはそれを知り、考証を重ねる中でカラスの無実を確信するに至ります。そして、犠牲者の無実の証明と、未決で拘束されている妻や子女、関係者の救命に奔走するのでした。宮廷までに連なる人脈や古今東西に広がる学識を利用して。
結局、ヴォルテールの真実を追求する著作や、人脈を通じての再審・助命嘆願など、時間をかけた地道な努力・奔走が報われました。
カラス氏のむごたらしい処刑からまる3年を経て、国王が委託するパリの終審裁判所である「宮中訴願審査法廷」による再審が行われ、結審します。
無実が証明され、名誉は回復されました。誤って裁かれた一家の無罪が確定しました。まさにカラス氏の命日である1765年3月9日に。
自分の主人たちを弁護して終始一貫真実を守り通した忠実な召使や、事件に巻き込まれてもカラス氏の無実を訴えて節を曲げなかった、長男の友人ラヴェスも無罪放免、名誉を回復されました。
そして、フランスではその後1789年のフランス革命の「人権宣言」によって信仰の自由が遅ればせながら実ることとなります。
革命に毀誉褒貶はあるとしても、宗教的自由というものは確立されていくわけです。
だが人間の偏見は、宗教的偏見に伴うものではない。19世紀末に、ユダヤ人に対するフランス社会の偏見から、国家機密を外国に漏らしたとして無実の罪を着せられたドレフェス大尉のために文学者エミール・ゾラが敢然と立ちあがり、再度の有罪判決にも屈せず、ついにドレフェスの無実を証明した事実もまた忘れることはできない。(中公文庫版解説250頁)
不寛容が勢力を伸ばして、その度合いが深まるほどに、人間から人間らしさを奪い去り、狂信を蔓延させ、さらにひどくなると、この世に地獄をもたらします。
無知や迷信や偏見など、自由を阻むものを自分の中に持っていないか考え、どうすればそれらを排除して自由を獲得できるかに思いをはせたいです。
おわりに、中公文庫版『寛容論』の帯から引用します。
宗教、国境、民族の相異を超えて「寛容」を賛美した普及の名著
『100分de平和論』(NHK)で高橋源一郎さんが紹介‼
「この本を読まなければならない。いますぐ。世界が壊れてしまう前に。」
※noranekopochiノラ猫ポチさんの画像をお借りしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。記事が気に入っていただけましたら、「スキ」を押してくだされば幸いです。
