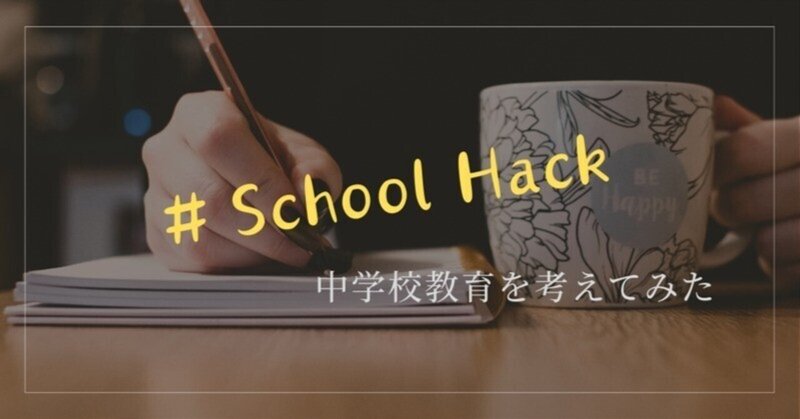
#8)中学校の教育相談期間
中学生がもつ悩みと不安

教育相談期間をGW明けのこの時期に、多くの中学校で設定されています。一般的には、5月、9月、11月、1月のどこかで教育相談を行っている場合が多いようです。長期休み後や、生徒が不安を感じやすい時期に設定されています。
中学生には、日頃は普通にしていても様々な悩みや不安を内在していています。昨日まで普通にしていたように見えたのに、急に学校に来れなくなった。というケースも少なくありませんよね。
中学生がもつ不安や悩みの多くには、次のようなものが考えられます。
⑴学習面・進路面
「授業内容が分からない」「勉強しようと思ってもできない」「勉強する気意欲がわかない」といった悩みです。授業の50分間を過ごすことが苦痛だという生徒もいれば、高校選択にかかわる学校や塾や保護者からのプレッシャーに耐えられないといったことが起因しています。
⑵学校生活面
「先生に対する不満」「友人関係のもつれ」「みんなと一緒への不快感」といった悩みです。主に狭い教室内に閉じ込められて、毎日同じように過ごさなければならないこと、誰かと仲良くしていないと疎外感を感じてしまうことが起因しています。
⑶家庭生活面
「親子関係の不和」「家庭の仕事への深い従事」といった悩みです。保護者の強すぎる教育観や、経済的困窮により保護者が遅くまで仕事をしていることなどが起因しています。
⑷健康面
「心理的・身体的な問題」「自分の容姿」といった悩みです。心理的な不安から頭痛や腹痛を引き起こすことは誰しもが経験したことがあるはずです。また、容姿にコンプレックスをもつことから食事を受け付けなかったり、薬品を過剰に摂取してしまったりすることがあります。
自殺の動機・原因の割合
その原因が本当にそうなのかは分かりませんが、文科省によれば中学生の自殺の動機・原因で多いのは次の通りです。
〇男子中学生
・学校問題31.0%(その内、学業不振10.8%)
・家庭問題19.8%(その内、家族からのしつけ・叱責10.7%)
〇女子中学生
・学校問題38.6%(その内、学友との不和12.3%、学業不振9.2%)
・家庭問題26.0%(その内、親子関係の不和14.9%)
教育相談で担任が心がけること

これまでの情報だけで全てを語れるわけではありませんが、様々なことが複合的に混じり合って、結局「何が原因で自分が悩んでいるのか分からない」と言って学校に足が向かなくなってしまう生徒が年々増えています。
大半の生徒は「いろいろあるがまぁ大丈夫」と割り切るのでしょうが、いつなんどき「まぁ大丈夫」でない状態になってしまうかは予測できるものではありません。そういった意味でも定期的な教育相談の場の設定は不可欠になるわけです。
では、教育相談で担任が心がけるべきことはなんでしょうか?様々な文献にいろいろなことが書かれていますが、私がこれだけは大切にしていたことを紹介します。
⑴よく聴く
⑵聞き(尋ね)すぎない
⑶効かせようとしない
これだけです。
どういうことかと言うと、
⑴よく聴く
みんな大好き「傾聴」です。読んで字の如く、耳と目と心をもって生徒の話をききます。重要なのは、生徒の話を「あ~そういうことね」と思わずに受けることです。先ほど中学生の悩みや不安を分類した通り、生徒の話を聞いていると「その手の話か!」と勝手に頭の中で内容を「分類」してしまいます。すると「こういうアドバイスや、過去のエピソードをしてやればいいな」という回答が浮かんできます。その時点で傾聴失敗ですね。場合によっては話の途中で「それはつまりこういうことだろ?この時はさぁ~、昔こういう生徒がいてさぁ~、俺が子供のころはさぁ~」といって自分の話をし始めて、気が付けば「生徒の話:先生の話=1:9」になってしまうことにもなりかねません。結果としてスッキリするのは、たくさん聞いてもらい、なおかつ良いことをしてやった、と思っている先生の方です。これでは意味がありません。
中途半端にできる(と思っている)先生にありがちな行為です。私にもそういう所が多いので自責の念を込めて…。中学生は言葉を整理して伝えることがまだまだ難しい年代ですが、多少時間がかかっても最後まで自分の口で話をさせることが大切ですね。
⑵聞き(尋ね)すぎない
しっかりと相談に乗ってやろうと思うあまり、とにかく話を聞き出そうと「他にはない?」「家庭は大丈夫?」「友達はどう?」「こんなことが以前あったように見えたけど、あれはどうなの?」「本当に何もないの?」「よく考えてみて?」と尋ね過ぎないことです。とにかく何かを引き出さなければ…と思わずに自然体で臨むべきです。
生徒の立場からすると「本気で困っていることを話す」ことはすごく勇気のいることです。先生には学習面についての不安は言いやすくても、家庭内のことや、まだ微妙な感じの友人関係についての不安は言いにくいものです。しつこく尋ねすぎることで、かえって嫌な過去を思い出させたり、それほど悩んでなかったはずなのに深く悩むことにさせてしまったりする可能性もあります。
また一人の相談時間が伸びてしまい、以降の生徒が待たされることもありがちです。学校では一人の持ち時間は10~15分程度です。保護者面談では時間を気にするけど、生徒だから時間を気にしない、とはいきませんよね。
これもどちらかと言えば、先生の方が「たくさん話をだしてくれた」と満足して終わるケースが多いです。生徒が話そうとするのを少し待つだけでいいと思っています。
ただし「現時点でその生徒との困り感を共有している」場合は、具体的にどんな状況になっているかを詳しく尋ねる必要があります。生徒と情報共有しいるのにも関わらず何も聞かないということは、その問題に関心がないと受けられるかもしれないですから。
⑶効かせようとしない
これは⑴と裏表の関係になりますが、「こうすれば良いよ」という特効薬を簡単に生徒に与えようとしないことです。先生も多様なアイデアを持っているでしょうが、正解がないのが人の悩みです。特効薬などありません。先生は多様なアイデアを持っているからこそ、1人の生徒にアレコレとたくさんの攻略法を授けようとします。ですが、それを実行するのは生徒自身です。具体的なアドバイスを言われるほど「いやそれは分かっているのだが…」と疲れてしまったり、「自分はそれができないダメな奴だ」と自己肯定感を下げてしまったりする生徒も少なくありません。生徒は基本的に先生に対して素直ですから、心の中で「う~ん、疲れてきたなぁ」と思っていても、「そうですね、はい分かりました」と答えがちです。
結局は先生が「良いことを教えてあげることができた」という満足を得るだけになる場合が多いです。
こちらから率先して助言をするよりは「どういう風に改善されたらあなたにとって良いかな?」「先生が力になれることはあるかい?」と言って、生徒が望む未来のためにいくらでも力を貸すよというメッセージを伝え、生徒に思考のイニシアチブを与えることが大切です。
また「重要な問題だと思うから、他の先生に伝えてもいいか?保護者に伝えてもいいか?」と心配と助力を伝えることも必要です。もちろん「他の人には話さないで」という生徒もいますが、その場合は、①生徒には分かったよと言って、学年部職員、生徒指導主事や管理職に秘密ごとにしていることを含めながら情報を共有するか、②これは大切なことだから他の先生や保護者に話さなければならないよとはっきりと伝えるか、で対応します。生徒との人間関係を気にする先生は多いですが、いずれにしても担任で止めておくことは、万が一を防ぐためにやるべきではないです。
教育相談は重要な機会

日頃から生徒とのコミュニケーションをとることが上手な先生も多いと思いますが、整然とした環境下で「1on1」で話をする機会をもつことは非常に重要です。生徒にとって「深刻な話をしても聞いてくれる」という意味合いをもつことができるからです。だからこそ極端な話、時間は1分でもいいけれど一人一人に「勇気をもって話せる場」を提供するのです。
担任の先生も人間ですから、先生視点で、話しやすい生徒、話しにくい生徒、嫌われてるかもと思う生徒などが学級にはいると思います。全員と話すわけですから、精神的にしんどい時間もあるとは思いますが、ぜひそんな先生こそ、これを機会に心を開き、無理せず生徒の話にただただ耳を傾けてみてください。「特にないので大丈夫です」と1分で終わっても「そうか分かったよ。何かあったらいつでも相談してな」と言えばいいのです。
あまり、気を張りすぎずにやっていきましょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
