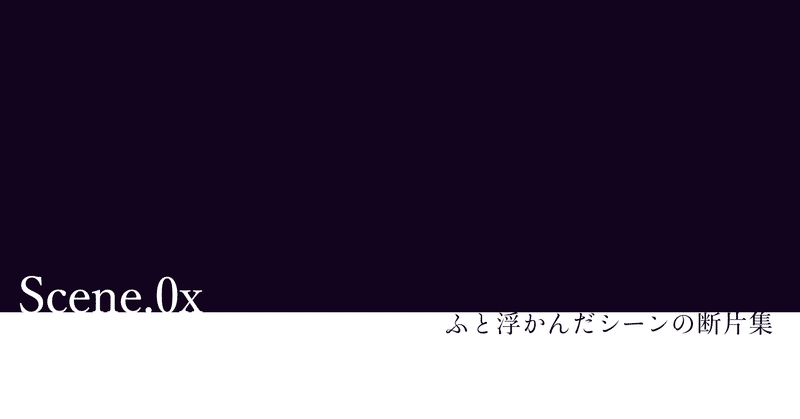
Scene.0x : 静けさの匂いと複合的決断
今日も客は誰もやってこない。エプロンなどしなくてもいいのだが、これを取ってしまったらもう本当に誰も来ないような気がして外さずにいる。カウンターのこちら側で、使ってもいないカップを磨いている。
店にはテレビもラジオもない。ステレオだけを置いている。古いジャズなんかをかけたいが、最も多く来てくれる高齢の女性に「なんだか辛気臭いわ」と言われてから、70年代のソウルミュージックを小さめのボリュームでかけている。
そういえばあの女性もぴたっと来なくなった。亡くなったのだろうか。引っ越したのかもしれないし、家族が引き取ったのかもしれない。養護施設に入ったのかもしれない。
私には妻も子もいないし、狭いアパートとこの店があるだけだ。会社勤め時代の貯金がまだあるのでしばらくは食っていけるが、この店もそうは続かないだろう。
以前住んでいたマンションが、この近くにある。私はこの喫茶店に、朝食を食べに来ていた。休みの土曜か日曜、時には両日来ることもあった。
特に絶品メニューがあるわけではない。トーストと卵とコーヒー。何の変哲も無いモーニングだった。ただ何となくこの店が気に入って、気づくと二、三年通っていた。
マスターは白髪の老人で、品のいい、柔らかい笑顔の男性だった。奥さんと二人で店を切り盛りしていたが、二人ともそれなりに高齢だった。店の客の年齢層も高めで、もちろんコーヒーは美味しいのだが、それよりもマスターや奥さんとの会話、会話のある空気を楽しみに来ていたように思う。
そのマスターが突然亡くなった。脳溢血だったそうだ。朝、奥さんが買い出しから帰ってくると、カウンターの向こうで倒れていたらしい。
奥さんは一人でも店を続けたいと思ったそうだが、自分の思い以上に心は折れてしまっていたようで、マスターの葬儀を終えて店に戻ってきた時、ふっと足腰の力が抜けてその場にへたりこんでしまったらしい。
そうしたことは知らず、私はその日いつものようにモーニングを食べに来た。店は開いていたので普通に入ったが、実際は常連さんが慰問に来たので店に通していただけで、営業はしていなかった。
私がドアを開けるとなんだか妙な空気で、それでも奥さんは「あ」と僕の顔を覚えていてくれて、事情を話してくれた。
「最後にコーヒーでも飲んでいって」と、私を席に通し、いつもはマスターが淹れていたコーヒーを、自分で淹れて私に出してくれた。「お代はいらないから」と。
私は始めて音楽の、爽やかなクラシック音楽のかかっていないこの店で、コーヒーを飲んだ。
「自分で続けるのは難しいけど、できるなら、店はなんとか残したいんだけどね」
奥さんがそう話すのを横で聞いて、私は「私にやらせてくれませんか」と言った。熟慮したというよりは、口を突いて出た言葉だった。
決断というのは、複合的なものだ。この店がなくなってしまうことがそんなにもショックだったとは、自分でも後から気づいたし、歳も40を越えてそれまでの仕事に魅力を感じなくなっていた(というより逃げたかった)のも事実だ。
そういうことはあの日店に入る直前までいろいろと脳内や心内にあって、それが店の中の、日の差し具合とか、静けさとか、奥さんの話すトーンとか、私の体調とか心調とか、コーヒーの匂いとか。そういうもの全てが少しずつ言葉を外に押し出して、最終的に口から出てきたのだろう。
運命的なものを感じていても、それがお客さんに通ずるわけでもない。マスターと奥さんの人柄を愛していた常連さん達の足は段々と遠のき、私の静かな日々が始まった。
何かをしてみなければと思うのだが、私はまだこの静けさを味わっていたいのかもしれない。「しなければ」という一応の言葉が脳内を通り過ぎるだけで、私は特に何も行動に移そうとしない。
いずれは何か起こるし、起こすのだろうが、もう少しこの静寂を味わっていたい。
カラン、とドアがなって、その静寂は崩された。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
