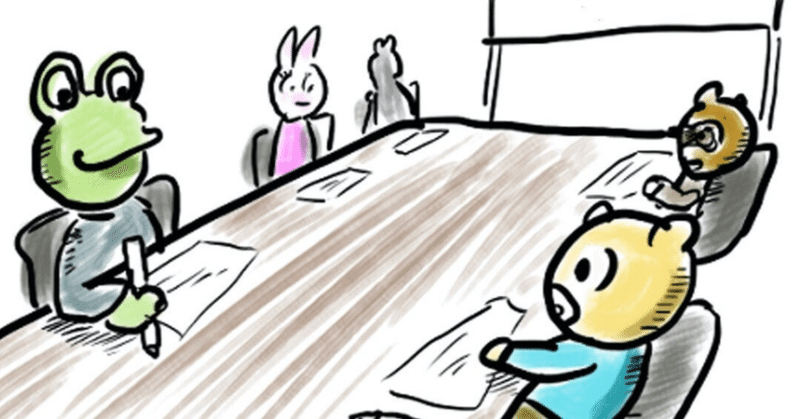
おむつ交換もしたことがない人達が、介護業界のコンサルをしたり枠組みを作っている問題【改悪され続ける介護保険】
こんにちは、アルゴです。
私は現在、どこの組織にも所属しないフリーランス介護福祉士として、いつもnoteや著書で、介護福祉についていろんなお話をしています。
私がいつも執筆する際に心がけているのは、単なる自分の日記にならないように、見てくれた方に有益になるように・・・と思って書いていることです。
日記にならないようにとはいっても、それらは全部、自分の経験則に基づいているのも事実です。
とくに個人事業で行う介護保険外事業というのはSNS以外で情報発信をしている人が少ないものですから、同じように起業を目指している方に役立つよう、自分の経験談を、良いことも失敗したことも織り交ぜることが必要です。
(実際、私自身も同業者の情報がほしいと思っているくらいですからね😓。でもSNS以外で手に入る情報はなかなか無いのです。)
経験則に基づかない情報発信はまるで説得力がない

介護業界に限らず、何かを批判したり問題解決を提案するには、その業界で働いた経験が必要なのだと思います。
じゃないと、説得力がありません。
私自身も、介護福祉業界で働きながら勉強をする中で、各種研修会、著書やYouTube動画などで学びました。
やはり第一線で働いてきた経験のある方の情報発信には、説得力があります。こちらの質問に対しても、『リアル』な返答がかえってきます。
しかし講師や本の著者の中には、大学で介護業界経営について研究している方であったり、経営コンサルの方も多くいます。いずれにしても、介護の資格も持っていない方でしたし、実際に介護の仕事をした経験を持っていない方々です。
そういう方々も一生懸命お仕事に取り組んでいると思いますし、プレゼン資料をとても丁寧に作られていたりするのですが、話の内容がどこか、『机上の空論』にしか聴こえなかったりするのです。
「こんなケア、実際に現場じゃできないよ(笑)」と思うこともしばしば。
私はそういうキレイゴトが嫌いです。
おむつ交換をしたこともない人が、介護業界の枠組みを作る恐ろしさ

過去の介護保険改正で、介護施設の夜間の人員配置が下方修正されたことがありました。
具体的には、見守りロボットや、インカム、離床センサーなどICTをしっかり活用している特養などが対象で、夜勤職員の配置基準が緩和されました。
そして次回2024年の改正で、さらなる緩和がされてしまう恐れがあります。
去年のニュースでは、夜勤だけでなくユニット型の職員配置に関しても緩和される・・・というのが話題になってましたね。
でも介護保険によって国から援助を得て経営している施設ですから、国からの収入が減らされてもどうにもならないし、文句も言えないわけです。
問題なのは、枠組みを決めている人たちは、介護現場に携わっていない・・・介護現場をわかっていない人たちだという事です。
介護のワンオペ業務がどれだけ大変なのかを知らない人・・・他人の排泄物を処理したことのない人たちが、介護現場のルールを決めてしまっているのです。
もし介護や夜勤の仕事をやったことがあるのなら、
「ICTの活用によって夜間の人員を減らしても大丈夫である」
という発想には決してなりませんからね。
国の財源が厳しいのは誰もが承知していると思いますが、それを改善するための介護保険の改正が、人員配置を減らしたり、業務をややこしくして加算を取りづらくさせようとすることなのです。
ケアマネのケアプラン作成料についても介護保険設立当初は、利用者が平等にケアマネジメントを受けられるように・・・という理念の元に、国が10割を負担しているわけです。
今度はそのケアプラン作成料に利用者負担が課されるといいます。国が10割負担する理念があったことは、まるで無かったことのように覆えされています。
この国に福祉制度おいて、この悪い風潮は改善することがあるのでしょうか?個人の力では変えることはできるのでしょうか?
国のしくみだけに頼らない大切さ、介護保険施設や私達にできること

私は複数の介護施設で働いてきましたが、同じ県内・市内の介護保険の中でも、施設によって給料や人員基準、働き方に大きな差がありました。
夜間業務についても、
●同じフロアで介護職2人体制+看護師が常駐
というわりと働きやすい施設もあれば、
●3フロアを介護職2人で見ていた
施設もありました。
しかも皮肉なことに、
過酷な施設ほど給料が悪かったりもします。
①給料が少なくきついからやめる→
②人がいなくなる→
③余計に業務がきつくなる(スタッフ一人一人の負担が増える)→①にもどる
・・・・という負の連鎖です。
逆に良かったと感じていた施設は、職員の働きやすい環境が整っていました。
設計の段階から設備面で導線に配慮し無駄を無くしたり、人員以外の無駄なコストを徹底的にカットしたりして、職員の待遇を良くしていたのです。
国の収入が限られている中でも、施設としてできることはあります。
介護保険以外の事業で収入を増やしたり、無駄な会議やおむつ消費量などを減らしたりしてコストカットしたり・・・です。
「経営者やリーダーなど、上に立つ人達が良ければ良い施設は作れるんだ」と私は感じました。
個人もまたしかりです。
介護を知らない人たちが枠組みを決めている介護業界で働いていくには、一つの働き方だけに頼らず、自分自身を疲弊させないため、いろいろな選択肢を持つことが必要と感じます。
noteや電子書籍などで積極的に情報発信し、介護業界の現状をもっと多くの人に知ってもらうことも大切だと思います。
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
