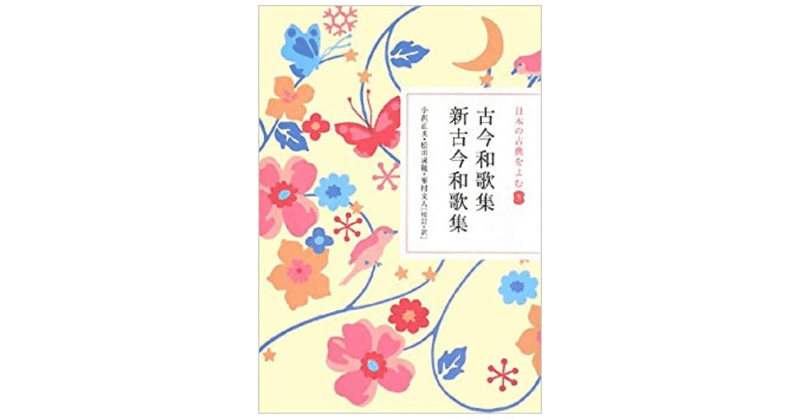
王朝幻想の和歌の世界
『日本の古典をよむ(5) 古今和歌集 新古今和歌集』(翻訳)小沢 正夫 , 松田 成穂 , 峯村 文人
星の数ほどある歌集の中で、ひときわ光彩を放つ二大勅撰和歌集――『古今和歌集』『新古今和歌集』より、秀歌300首余りを厳選して、味わい深い現代語訳とともに収録。紀貫之、小野小町、在原業平、西行法師、藤原定家ら歌人がつむぎ出す、日本語の美の世界を堪能する。
返却期限が来ているので、感想。この本は丁寧に解説されていて分かりやすい入門書。中学生・高校生にもいいと思う。むしろその時代にめぐり会いたかった本かもしれない。『古今集』も『新古今』も季節から始まるので入りやすい。『古今集』は『百人一首』や『伊勢物語』で馴染みある歌が多かった。『新古今集』は後鳥羽上皇のプロデュースということで上皇好みなのかな。塚原邦雄『花月五百年 新古今天才論』のサブ・テキストとして。
『新古今集』の「春上」の並びは、王朝栄華の桃源郷を描き出したというのは、塚本邦雄の説。それは『古今集』に倣い勅撰集として、最期を飾るべき王朝和歌の姿であったという。
み吉野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は来にけり 藤原良経
ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山霞たなびく 後鳥羽院
山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水 式子内親王
三島江や霜もまだ干(ひ)ぬ蘆の葉につのぐむほどの春風ぞ吹く 源通光(みなもとのみちてる)
夕月夜潮満ち来らし難波江(なにはえ)の蘆の若葉を越ゆる白波 藤原秀能(ふじわらひでよし)
岩そそく垂水の上のさ蕨の萌え出づる春になりにけるかな 志貴皇子
なごの海の霞の間よりばながむれば入る日をあらふ沖つ白波 藤原実定
見わたせば山もとかすむ水無瀬川夕べは秋となに思ひけん 後鳥羽院
霞立つ末の松山ほのぼのと波にはるる横雲の空 藤原家隆
春の夜の夢の浮橋とだえにして峰に別るる横雲の空 藤原定家
大空は梅のにほひにかすみつつ曇りも果てぬ春の夜の月 藤原定家
『古今集』の「春歌上」も立春の年明けや雪解けの山から桜の開花まで。桜は「春歌下」で満開となり散っていく桜を最後に夏に移るいく。
やどりして春の山辺に寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散りける 紀貫之『古今集』
また『源氏物語』は「古今集」から引歌として影響を受けながら「新古今集」に影響を与えたとあり、日本の文学の根本には和歌があったのだと思った。
『古今集』には紀貫之や在原業平らの六歌仙の有名な歌が印象深い。
「かきつばた」の「折句」の技法。五七五七七の冒頭に「か・き・つ・ば・た」の文字を入れていく。
唐衣(からころも)きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅(たび)をしぞ思ふ 在原業平
恋歌の小野小町と伊勢(この人は『源氏物語』で取り上げられていた)の女歌。
『新古今集』だと式子内親王と和泉式部。藤原俊成女(としなりのむすめ)後鳥羽上皇が贔屓にした宮内卿。藤原俊成女は藤原俊成の実の娘ではないのだが歌が優れているので養女となった人。塚本邦雄も一目置いていた。
後鳥羽上皇は父の藤原俊成には全幅の信頼を寄せているのだが息子の定家とは反目していた様子。仮名序は定家ではなく信頼を寄せた良経に書かせた。『古今集』(こちらは有名な紀貫之の仮名序)『新古今集』とも仮名序に勅撰集の意義と方針が読める。才能を認めながらも気に食わなかったのは政治的なことなのだろう。塚本邦雄も政治的な西行法師よりも慈円の方に趣を認めた(鎌倉嫌い?)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
