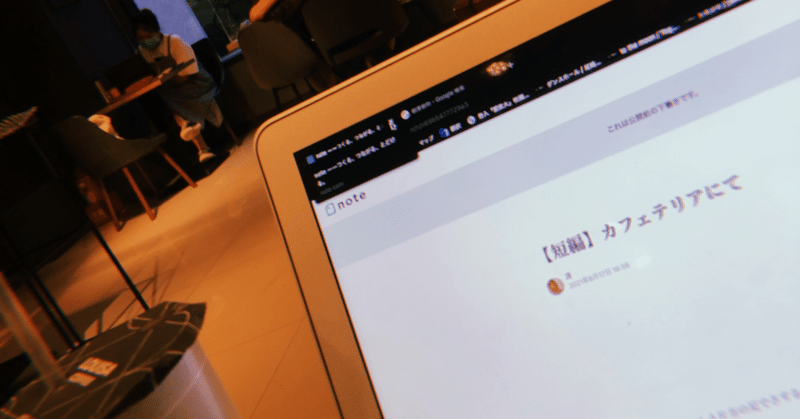
【短編】カフェテリアにて
冷たくなった左足を右の方の足でさする、外はもうすっかり暗くなっていた。
店内は相変わらず人でごった返しており、遠い異国で流行ってる疫病のことなど嘘かのような賑わいだ。
2時間前に頼んだアイスコーヒーも今じゃコーヒー風味の水となっていた。
明るすぎる照明がデスクトップに反射する。
この照明にも、効きすぎた冷房にも早苗はすでにうんざりしていた。
隣の席では暇を持て余した中年女性達が、まるで映画館帰りのお茶会かのように3日前のクルーズ船について語り合ってる。
「人生で一度くらいは世界旅行してみたいと思ってたけど、ああいうことがあると怖くてもう旅行になんか行けやしないわよねぇ」
くだらない、
別に旅行先でもカフェでも狭い一人暮らしの部屋でも変わらない、非日常はいつだって日常と隣り合わせだ。
むしろカフェに強盗が入ってくる方がクルーズ船の中に取り残される確率より高いはずだ。
この店内の客も今日が人生最後の1日かもしれない。
おばさま達の甲高い笑い声に比例するかのようにキーボードを叩く音も大きくなる。
もう家に帰ってしまおうか。
3分の1ほどしか埋まっていない画面を見つめながら考える。
ダメだ、締め切りまでもうあと1週間しかない。今回なんらかの結果を残さなければ今度こそあのど田舎に帰らなければならない。
それに家に帰ったところで六畳一間の空間には何もない。
うーんと声を出しながら背筋を伸ばす。
短編とはいえ、2000文字を余裕で埋めれるほどの出来事は私の日常には起きない。1人暮らしの六畳一間の空間には小さなブラウン管のテレビとリサイクルショップで買った二千円のギターだけ、それも2ヶ月も前に弦が切れてしまったもの。
いっそのことあのクルーズ船に乗っていたら傑作が書けただろうに。
そんな不謹慎なことを考えながら店内を見渡す。
壁にかかったオシャレな時計はちょうど18時を差しており、広いフロアには仕事終わりのOLから親子連れ、商談中らしきサラリーマンの姿も見えた。
階段のある奥の席では若いカップルが観葉植物に隠れて怪しい動きを見せている。
観葉植物もあんなものを隠すために存在してるなんて可哀想に。
それでもあり余る欲と時間と未来を手にしている彼らの方がこの2000字を埋めることができるだろう。
軽いため息と共に再びデスクトップに目をやる。
そもそも自分がなぜ小説家になりたいのか早苗にはよく分かっていなかった。
小さい頃から本は好きだ。学生の頃も暇さえあれば図書館に通い、片っ端から本を読んでいた。卒業する頃には棚の端から端まで全作品を網羅していたほどだ。
だが文字通り青春を読書に注いでいた自分には何にも残らなかった。放課後友達とプリクラを撮りに行ったこともないやつが青春小説なんぞ書けるわけがない。今ならわかる。
いや、それも言い訳なのか。
そんなことを考えていると、文字カウントがやっと1000に達した。
ふっと一息つき、おかわりのコーヒーを頼もうと手を挙げる。
ごった返した店内の端でぼーっと立っていた若い店員が自分に気づき、だるそうに向かってくる。
甘いものも食べようかな。
日替わりケーキはなんだろう、チーズケーキはあるだろうか、そんなことを考えてると店員の動きがピタッと止まった。
だるそうな顔がまるで元カノでも発見したかのようなハッとした表情に変わる。
条件反射で彼の目線の先を追い、入り口へと目をやった
と、同時に店内にパンッ!と破裂音が鳴り響く。
隣の席のおばさまたちが悲鳴をあげる。
目線の先には黒いマスクの人間が2人、1人は右手を高々と挙げていた。
その先には映画で何度となく見た黒い物体が握られている。
なんだ、1000字どころか長編傑作が書けそうじゃないか、
なんて思う余裕は早苗にはなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
