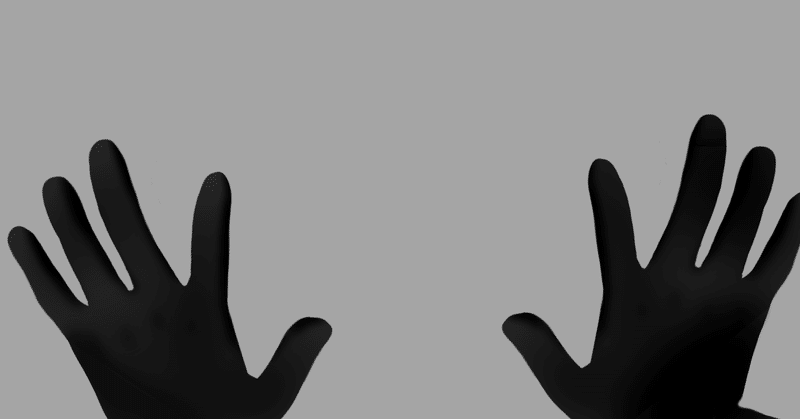
【短編】押し入れのポケット
最近、よく夢を見る。
夢の中の僕はまだ小学校低学年くらいで、いつも押し入れの中にいる。押し入れの外はまだ明るいのか、それとも電気が点いているのか。そこはよくわからないけど、薄く開いた襖の隙間から細い光がスッと差し込んでいて、その光が反射したうっすらとした光が僕の視線の先にある気持ちの悪い布切れを映し出していた。
それは半円っぽい形をしていて、押し入れの壁に縫いつけられたポケットのようにも見えた。不自然に押し入れの壁に張り付いている明らかに古そうな、因縁のありそうな布は、膨らみなんかこれっぽっちも無いにもかかわらず、その上部の口の開いた部分からナニカが出てくるような、そんな気がしていつも僕はそこから目が離せずにいるのだった。
ーーー
ある日、祖父が死んだと母親から電話がかかってきた。
仕事終わりのその足で、僕は電車を何本か乗り継ぎながら数年ぶりに実家へと向かった。
忙しいことを理由に盆暮れ正月と一度も帰省しなかったことに罪悪感を感じないわけではないけれど、実家を出てから今回の祖父の訃報まで実家の側から一度も連絡が無かったことを考えると、罪悪感を感じるということがおかしいような気がしたりもする。自分の家が一般的ではないとは思わないけど、一般的な家庭というのはもっと連絡を頻繁にとるものなのではないのだろうか。なんてことも考えながら電車に揺られ続ける僕の目には、窓に反射する夢の中の僕の面影を残した僕が映り込んでいる。
ふと気がつくと、夢の中の僕の面影を残した僕は、押し入れの壁に張り付いたポケットを見つめている僕と同じ顔で僕をまっすぐに見つめていた。
疲れてる。
窓に映る僕が今現在の僕以外に見えるなんて。
僕は窓から視線を外すとゆっくりと目をつぶった。真っ暗になった視界の中に夢の中の僕が居る。彼は何か言いたそうな顔で僕の方をじっと見つめていた。でも、彼が何を言いたいのかなんて僕にはわからない。僕は瞼の裏の彼からも視線を外すと、ゆっくりと目を開けた。
最寄り駅に着くと父が車で迎えに来てくれていた。助手席に乗り込んだ僕に「元気してたか?」と尋ねた父は、僕が父と会っていない時間以上の時間を過ごしていたんじゃないだろうかと思わせるくらい年老いていた。まだそれほど高齢でもないのにこの老け方。大病でもしているんじゃないだろうか。
「うん。ぼちぼち。父さんは?」
何かあるなら答えてくれるだろうと、あえて突っ込んでは聞かない。
「父さんも、ぼちぼちだな」
本当に何もないのか、それとも僕に心配をかけないようにそう答えたのかわからなかったけど、僕はそれ以上聞かず「そう」と答えただけだった。それから僕たちは何もしゃべらず祖父の家へと向かう。エンジン音と石を踏むタイヤのジャリッという音、そして時折響くウィンカーのカチカチという音をBGMに。
祖父の家に着くと母と祖母が迎えてくれた。
めっきり老け込んでしまった父とは対照的に、母も祖母も僕が家を出た時とそれほど変わった様子は見られない。やっぱり父は体調が良くないのではないだろうか。母に聞いてみようかとも思ったけど、父がすぐそばにいるのでやめておく。また後で二人きりになったタイミングででも聞いてみよう。そんなことを思いながら、母と祖母、父の後に続いて祖父の元へと向かった。
和室に敷かれた布団に横たわる祖父は僕の記憶の中の祖父よりもかなり若かった。でもそれは、仰向けに寝かされていることでシワや弛みが無くなっているのと、死に化粧で血色がよくなっているからだろう。眉間に深く刻まれたシワがそれでも無くなることなく、しっかりとその存在を主張していたのを見て「なんかじいちゃんらしいな」とニンマリしてしまった次の瞬間、僕は顔をこわばらせた。
「ねえ、アレって」
床の間を指さしながら僕は隣にいる母にそう尋ねた。母は何が気になるのかというように不思議そうな顔をしながら首をかしげる。
「あの床の間のさ。掛け軸が飾ってあった場所にあるあの布って……」
「布?掛け軸でしょ?」
僕の指さす方向を見ながら母はそう答える。
「いや、あれはどう見ても掛け軸じゃないでしょ」
「何言ってるのよ。横の間には掛け軸しかかかってないじゃない。どうしたの?疲れてるの?それともおじいちゃんを見て動揺してるの?」
呆れたようにそう答える母の様子からは、母が嘘をついているようには思えない。だとすると僕の目がおかしくなってしまったのだろうか。僕の目には、母が掛け軸だと言い張るモノは夢の中で押し入れの壁に張り付いていたポケットと同じものにしか見えないのだ。
僕は僕を変なものを見るような目で見る母の気配を感じながら、ゆっくりとそのポケットに近付いていく。
やっぱりこれはあのポケットだ。押し入れの中より明るい場所で見ているはずなのに、現実世界での存在感を感じるからかそれは夢の中で見たあのポケットよりもはるかに気味の悪い物体のように感じた。でもどうして。これは夢の中にあったもの。
手が届く距離まで来たところで僕はふと気がついた。夢の中ではぺたんと壁に張り付いていたポケットが少し膨らんでいることに。
夢の中の僕が目が離せなかったポケットは確かにペタンと壁に張り付いていて何かが入っているような感じは全く無かった。でも僕はそのポケットからナニカが出てくるような気がしていた。今僕の目の前にあるポケットは明らかに何かが中に入っている。布の膨らみがそう僕に告げている。でも一体なにが?
その時、袋の中身が暴れ出した。無意識に伸ばしていたらしい僕の右手が視界の端でびくっと跳ねあがるのが見えた。やっぱり何かが入っている? 僕は右手を降ろすと左手でしっかりと手首を掴んで固定し、ゆっくりと母の元まで下がる。母はそんな僕をチラリと見ると「お茶でも飲みましょうか」と言い部屋から出て行った。それに続いて祖母も。僕がその後に続くと僕の後ろに父がついた。
ーーー
通夜、葬式、火葬が終わり、父の運転する車で僕が日常へと帰る途中、ふいに父がこう言った。
「爺さん、ダメだったな。もうちょっとだったのになあ」
ダメだったもなにも、僕がこの場所へと帰ってきたのは祖父が亡くなったという連絡が来たからだ。もうちょっと? 一体何のことだろう? 僕が父の方へ顔を向けると、父は前を向いたままこう続ける。
「やっぱり歳が行き過ぎると体力が無くなっちまうからかな。俺もこないだは戻ってこれたけど次はヤバイかもしれん。お前もこの土地じゃないと戻ってこれないんだから、何かある前にこっちに帰ってきた方がいいぞ」
「父さん、一体何のこと?」
「お前も小学校2年の時、川でおぼれ死……」
父のその言葉を聞いて僕は思い出した。僕は小学校2年生の時、川で遊んでいたときに急に深くなった川底にすっぽりと飲み込まれてしまったことがあった。冷たくて、重たくて。耳からも鼻からも口からも、全ての穴から僕の中に入り込んでくる水を感じながら僕は暗い場所へと沈んで行った。しかしその後、しばらくして僕は押し入れの中で目が覚めた。押し入れの壁にはポケットのような半円型の布が張り付いていて、僕はそこから何かが出てきそうな気がしてずっと目が離せないでいたんだった。
夢でよくみるあの景色は僕が本当に見ていた景色。寝ている間に過去を再生していただけだった。
そしてあの『ナニカが出てくるかもしれない』と目が離せなかったポケットは、僕が出てきたばかりのポケットだったのだ。
ポケットの中のことは覚えていない。
そしてポケットから出てきた僕は一体何者なんだろう。
<了>
良かったらスキ・コメント・フォロー・サポートいただけると嬉しいです。創作の励みになります。
