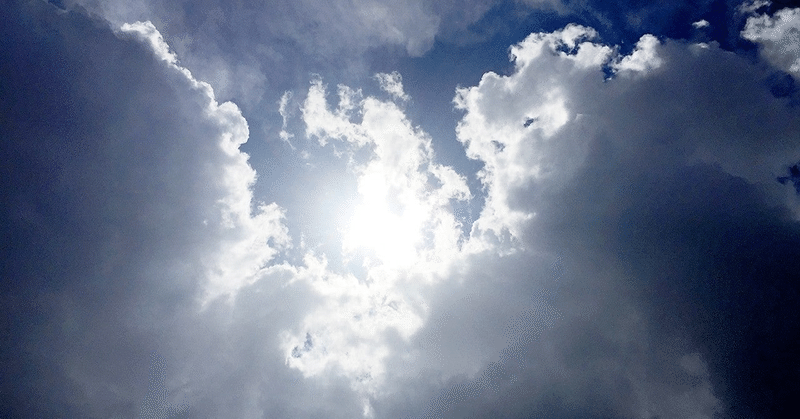
『死ぬ匂い』
子どものころ、おばあが、おじいに自分の匂いを嗅がせていた。
「もうすぐか?」
「あぁもうすぐだ・・・」
おじいはそう言うと泣き出した。
「今までありがとうな・・・」
「わしこそ・・・」
おじいは子どものようにシクシク泣いていた。
おばあは幸せそうに微笑んでいた。
「一政さん、本当にありがとうございました。」
「・・・」
おじいは子どものようにオンオン泣いた。
幼い私には、これがなんのシーンなのかよくわからなかった。
ただ、そのあと、おばあは死んだ。
ずいぶん経ってからおじいに、この時のことを聞いてみたが、おじいは覚えてないと言っていた。
そんなある日、おじいの友達が家に遊びに来ているとき、とんでもなく嫌な匂いがした。匂いは秀さんと呼ばれるおじいの友達からだった。
「おじい、あのおじさんくさい。」
「ん?くさい?」
「うん。変な匂いがする。」
「そうかなぁ?・・・っ! おまえにもわかるのか?!さくら・・・」
「ん?なんのこと?」
「いや・・・なんでもない。」
秀さんというおじさんは、その翌日に亡くなったと聞いた。
少し経って、おじいが私に言った。
「うちの家には、男女関係なく死ぬ匂いのわかるものが時々生まれるらしいんだ。おじいもそうだ・・・おばあの時のことを、さくらは見ていたんだろ? おじいのお父さんの時も、お母さんの時も、この前の秀さんのときも・・・みんなわかってしまうんだ。その匂いが死ぬ匂いだ。さくら。」
「あのくさいのがそうなの?おじい。」
「匂いは人によってちがう。おじいには、桃のような甘ったるい匂いがする。さくらにはどんな匂いがするんだ?」
「どぶのような泥のような塩気のあるくさい匂い・・・」
「そうか。その匂いがする人間は、おそらく次の日に死んでしまう。その匂いがしたら誰にもどうにも止められない。どうすることもできないんだよ。」
「だからおじいは泣いてたの?」
「うん・・・」
「おばあは知ってたの?」
「うん・・・もし・・・おじいから死ぬ匂いがしたら・・・ちゃんと教えてな?」
「うん。おじい、わかった!」
私は中学を卒業すると看護学校へ進学した。そしてそのまま看護師になった。その間、たくさんの死ぬ匂いを嗅いだが、怖くて誰にも言えなかった。もちろん死んでいく本人にも。
看護師になると死ぬ匂いがわかるということは、とても都合が良かった。あまり良いことではないが、先回りして準備ができるし、ある程度、こちら側の覚悟もできる。明日、死ぬことがわかっているのに「治療、がんばりましょうね!」と言うのは心が痛いが、でも「あなたは明日死ぬから治療しなくてもいいのよ。」と言われるよりはマシだろう。そのうち、死ぬ匂いにも慣れてきて、感覚としては他の五感と同じようなものになってきていた。
ある日、仕事を終えて家に帰ると、どこからか死ぬ匂いがする。咄嗟に、おじい?と思い、おじいの部屋行った。
「おじい。元気?」
「どうした?匂いが・・・っ!さくら・・・」
突然、私が血相を変えて部屋に入ってきたので、ある程度は察したのだろう。でも、ちがう・・・おじいじゃない。
では両親? お父さんとお母さんはどこ?
「お父さーん!お母さーん!」
「なにー?どうしたのー?家の中で大声を張り上げてー」
両親は応接間でテレビを見ていた。ちがう・・・お父さんとお母さんからは匂ってない。
えっ!じゃ優?
「お母さん。優は?」
「えっ?優ならまだ部活で帰って来てないわよ。そんなことよりも早く晩御飯食べてよ。片付けが終わらないじゃないの!」
「う、うん。わかったけど・・・」
ちがう・・・優じゃない・・・
えっ?・・・
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
